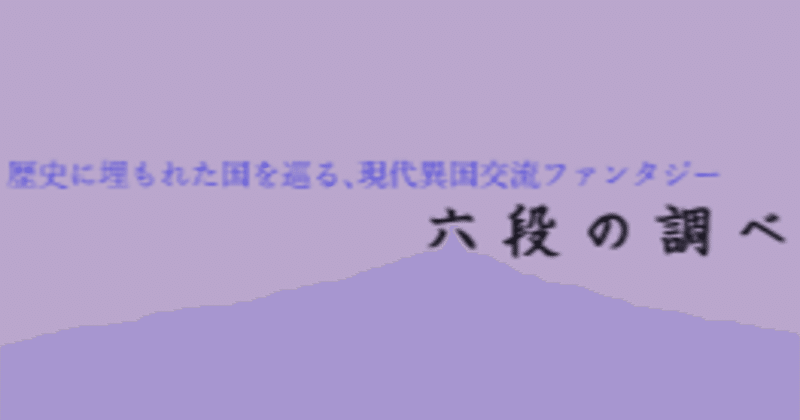
六段の調べ 破 四段 二、憾
前の話へ
序・初段一話へ
「ぼくは、倉橋さんを……倉橋さんの大事なものを……」
北は途切れ途切れに話しだす。倉橋は少し前に突然見舞いの予約を入れ、今日現れたという。
「倉橋さんとは、一回だけテレビで共演したんだよ。しばらく付き合いがあったけど、だんだん疎遠になってね。清隆くんたちから瑞香のことを聞いて、また連絡を取りはじめたんだ」
倉橋が瑞香に縁の深い人だと北が知ったのは、『芽生書』を隠し持っていると家族にも言えず悩んでいた時だった。倉橋のデビューした直後に販売された音楽雑誌のインタビューで、瑞香について仄めかしていたのを見た北は、覚悟を決めてその人に『芽生書』の件を相談した。相手が応じたのがきっかけで交流が始まり、やがてその父である音楽家・菅宗三の裏を聞く。
「菅さんは『サンゼール』――今もときどき上演されている音楽劇とかを作った人で有名だけど、実は瑞香の研究者でもあったんだよね」
若いころに『ノヴェンバー・ステップス』の初演を聴いて、菅は和楽器に興味を持った。そしてたまたま習いに行った箏教室の講師が、日本を度々訪れている瑞香人であった。その縁で菅は瑞香自体にも足を運ぶようになり、いつか再び日本と共存する日を願って資料を集め続けた。そして日本の人々に関心を抱いてもらうべく、資料を基に原稿を記し、実子である倉橋に託した。
菅は人々が少しでも瑞香を知れば、いつかこの国でも再交流に向かう動きが始まると思ったのだろう。しかし書き溜めた原稿を出版することなく、彼は五年前に他界した。そしてそれを受け継ごうとした倉橋の身に、危険が差し迫っていた。倉橋が四辻姫を脅迫したと聞いているか清隆たちに確認してから、北は続ける。
「あれから倉橋さんは、四辻姫さんに命を狙われているとか言っていてね。菅さんの書いた原稿も危ないとかで、ぼくが預かることになったんだけど……」
北は空いた左手で目を拭う。彼は電車で瑞香のものらしき景色を見た直後、何者かに背を押されて落下した。振り向きざまに見た人は、すぐに手から火を出して消えてしまった。
「ここに運ばれてからわかったことだけどね。ぼくの持ってた鞄に、あの原稿はなかった。つまり……ぼくが油断しているすきに、あれを奪われたってことなんだよね」
父の形見ともいえる原稿の紛失に、先ほどまで見舞っていた倉橋は激怒した。北が一方的に言われている形で時間が過ぎていき、面会は長引いてしまった。
語り終えてぐったりとする北を見ながら、彼を突き落としたのは瑞香人か清隆は思考を巡らせる。しかし菅の原稿というのは、四辻姫に危険視されるほどのものだったのか。自分を脅してきた倉橋自身を警戒するならともかく、所持品まで狙うとは。一体何が書かれているのか、自然と清隆の興味は募っていった。
「倉橋殿か……。あの者が伯母――四辻姫様に何を言ったか、北殿はご存知であるか? 私もただ『脅された』としか聞いておらぬのじゃ」
「そこは、ぼくもわからないね」
渋い顔をするシャシャテンの問いに、北は首を振る。四辻姫に噛み付いた倉橋を、シャシャテンは気にしているようだ。
「そなたは倉橋殿と知己であるようじゃが、何か気を付けるべきことはあるか? いや、これから会うことになってのぅ」
「そうだね……。性別については、絶対に聞かないほうがいいかもね」
シャシャテンは首を傾げるもすぐに了承する。そのやり取りから清隆も、倉橋の性別をぱっと見で判断できなかったと思い出した。あの人には何か、深い事情があるのか。
いったん話が落ち着いたところで、信が手にしていた紙袋を持ち上げる。
「よかったらこれ、食べます? あ、腕は大丈夫そうですか?」
「左利きだから気にしなくていいよ。いただこうかな」
信は焼き菓子の詰まった箱を取り出して蓋を開け、ベッド上のテーブルに置いた。個別包装されていないクッキーや小型のパイが、区切りの中で整然と並んでいる。先に北が選び、彼に勧められて清隆たちも一枚ずつ食すことになった。
その後に、美央が紙袋から用意していた見舞い品を取り出した。包みを破って彼女が取り出したのは、これからの時期にも役立ちそうな薄手のストールだ。北はそれを膝に載せるなり、顔を綻ばせた。
「今日はありがとう。ここはいつも以上に退屈だったから、きみたちと話ができてうれしかったよ」
左手で箱の蓋を閉め、北は包帯の巻かれている右腕を見下ろす。彼が骨折したのは、後夜祭で演奏を披露した後だった。
「あの日、みんなは本当に喜んでくれていたのかな……」
北は普段の沈んだ表情に戻って零す。実際に発表を聴いていた清隆は、相変わらず音色は暗かったが悪くなかったと振り返る。しかしそれを言う暇もなく、北は話し続けた。
「ピアニストにとって命ともいえる手が使えなくなるより、胸から落ちて死ねばよかったね……」
腕が治っても、元のように動くかは分からない。演奏の質が落ちて、今まで褒めていた人も心から馬鹿にするかもしれない。北の呟きには、清隆にも刺さるものがあった。吹奏楽をやっていることを嘲笑いながら、ソロを聴くなり反応を変えたかつての同級生が浮かぶ。
北によると、彼の演奏に対する評価は人によって正反対のようだ。ある者は「音が重厚で、聴き応えがある」と言い、ある者は「重々しくて聴くに堪えない」と言う。
「ここまでいろんな意見を持つ人たちが、わかりあうなんてできるのかな。菅さんや倉橋さんの望んでいる日本と瑞香の交流も、難しいんじゃないかな。今まで知らなかった人どうしが仲よくなるとか、無理に決まってるよ――」
思わず清隆は、シャシャテンを見る。彼女は北の話を黙って聞き、面持ちを変えていない。この居候と一年半以上過ごしてきたが、自分たちは互いを理解し合えているだろうか。
約束していた面会終了時刻が近付いていた。ここで長居すれば、また看護師を怒らせかねない。部屋を出ようと清隆が扉に手を伸ばした時、北がぽつりと口を開いた。
「そうだ、倉橋さんは大変なことを考えているから、気をつけたほうがいいよ。特にシャシャテンさんはね……」
「倉橋殿と言うのは、日本では名が高い者なのか?」
病院の外に出るなり、シャシャテンが問いを投げ掛けた。八重崎がそれに答え、倉橋がヴァイオリニストであり、本名・性別共に不明だと明かす。そんな彼女も、菅と倉橋の親子関係は知らなかったと驚く。
清隆の持っていたメモをシャシャテンが覗き込み、待ち合わせている喫茶店はまだか頭を巡らす。
「しかし倉橋殿も奇異じゃのぅ。菅宗三殿の子であるなら、その名も菅何某であろう」
「ひとまずは、あまり突っ込まない方が良いかもしれない」
目的の喫茶店を見つけて足を止め、清隆は念のために忠告する。こちらの詮索で倉橋の心を傷付けてはならない。
店では大勢の人がくつろいでいるテーブルが多数ある中に、倉橋が手を振っていた。外からは見えにくい場所で招き寄せ、清隆たちが丸い卓を囲むように座ってすぐに、倉橋は再び謝った。それから好きな飲み物を頼むよう勧めてくる。
「それにしてもここで会えるとは思いませんでした、六段姫」
全員の飲み物が運ばれた直後、倉橋はさらりと告げる。呼ばれたシャシャテンはカップに手を伸ばしたまま、しばし正体を知る相手を睨んだ。用心されていることも気にしないように、その人は微笑む。
「私、瑞香の王家についてはよく知っている所存ですので――」
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
