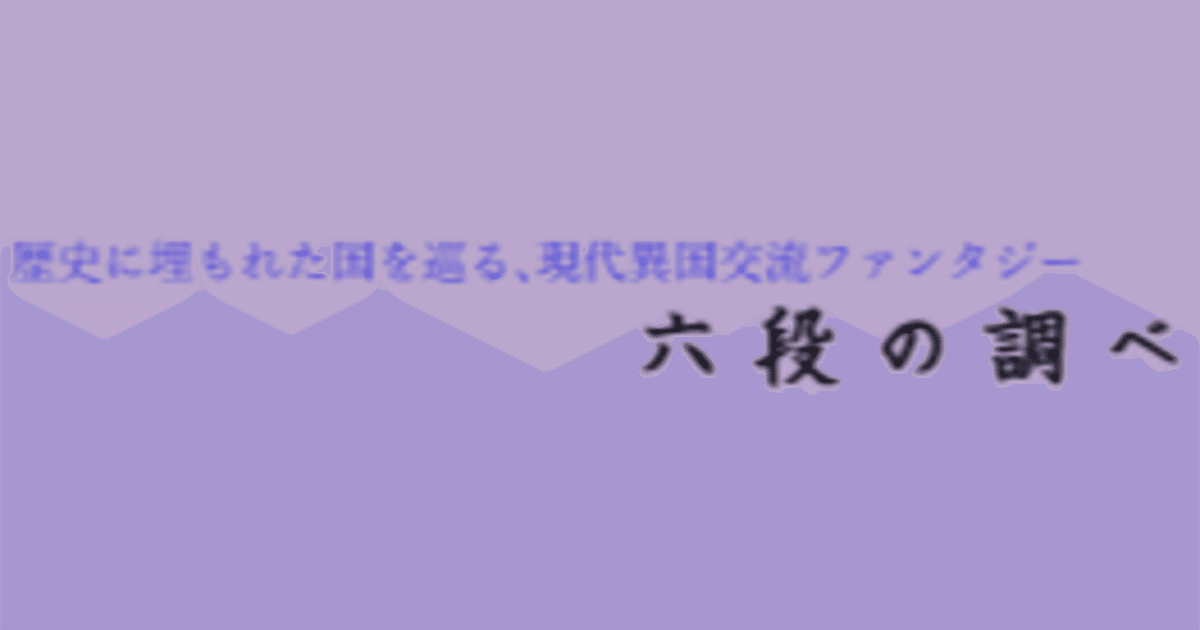
六段の調べ 破 三段 四、諸田寺へ
前の話へ
三段一話へ
序・初段一話へ
山住と約束していた日の夕方、清隆はまず自宅の最寄り駅へ八重崎を迎えに行った。前もって清隆がしていた助言通り、彼女は片手にカーディガンを抱えていた。そこから自宅へ引き返し、居間で山住が来るのを待つ。清隆が冷房を付けた和室からシャシャテンの箏が漏れるのを、八重崎が耳を澄ましていた。そういえば信が箏の手習いに行くと話していたが、あれはどういう風の吹き回しだろうか。
玄関で扉を叩く音がし、清隆は山住を出迎えた。山住は八重崎に軽く名乗り、まず主に挨拶がしたいと真っ先に和室へ入る。シャシャテンは演奏の手を止め、清隆たちを頼むよう従者へ念押ししてきた。
「清隆も八重崎殿も、私にとってはそなたと同じほど大事な者なのじゃよ」
そう話すシャシャテンに、山住は深々と頭を下げる。玄関に赴いてから、彼が手を前に突き出す。その様子に八重崎が不思議そうな顔をしていたが、山住の結界を操る動きと同時に炎が上がったのを見て声を上げた。彼女に瑞香へ行く仕組みを説明し、清隆は町中の風景に入り込む。振り返って八重崎がまだ玄関に残っているのを認めて思わず手を伸ばしたが、彼女は苦笑しながら自力で異国へ足を踏み入れた。
清隆は去年も見たような、左右に店棚の並ぶ大通りに立っていた。それもそのはずで、山住はここが宮部の手習い場もあった、宮城へ続く道だと教える。人々が思い思いに談笑して歩いている様子は、どこか清隆にとって懐かしくもあった。
一方で八重崎は、今回が初めての瑞香訪問だ。まず道を行く人の着物が綺麗だと指摘し、それから通りを見回して感嘆の息を漏らした。山住に連れられて歩いている間も清隆たちから離れ、甘味処や呉服屋、装身具の店など気になった所を覗き込んでいる。
「江戸情緒っていうのかな? こういうのがまだ残っている場所があったんだね」
はしゃいでいるような八重崎の気持ちも、清隆には分からなくもない。自分も一年前は、初めて訪れた瑞香の景色がどれも珍しかった。町娘に声を掛けられもしたと思い出し、今回は隙を見せないようにする。
通りの出入り口となっている門を抜けると、ぽつぽつと茅葺屋根の家々が目立つ代わりに、人の賑わいは少なくなった。次第に自然も増え、小鳥の鳴き声や風の吹く音が目立ってくる。しかし不死鳥の特徴的な声は、どこからも聞こえてこなかった。空を見ても、巨大な鳥が飛んでくることはない。
「いつもなら、不死鳥がよく飛んでいるはずなんだが」
八重崎へ瑞香で尊ばれている鳥について話してから、清隆はまだ彼らが帰ってくる様子はないのか山住に尋ねた。不死鳥が姿を消して半年が経とうとしているが、まだ変わりはないという。
「ここまでとなると、民は胸が潰れる思いのようで……」
人々は災いの前兆だの治世が悪いからだの、行方知れずの理由を推測しては怯えているらしい。山住が話す都の風聞を聞いて、清隆は町中にいた人を思う。彼らも何気ない笑顔の裏で、いつも上空にいた不死鳥の失踪を深く憂いているのではないか。
やがて道も舗装されていない、雑草の目立つ場所へ移った。風が涼しいというよりも冷たくなり、八重崎が上着を羽織る。建物が消えて木々の生い茂る中を進むうちに、真ん中がくぐれるようになっている木造建築を目に捉えた。ここが諸田寺の入り口である山門だと紹介し、山住が清隆たちを寺の中へ導く。石畳を歩きながら、清隆は伽藍を囲む回廊と、その向こうに広がる森を見やる。ここを取り巻く自然は、裏にそびえる医王山のものだと山住が話すのを聞きつつ、平屋建ての講堂へ入った。
玄関には前に日本で見掛けたのと同じ格好をした僧侶がおり、山住に挨拶をした。それに返してから、山住は清隆と八重崎が靴を仕舞ったのを確認して廊下を歩きだす。その後を追って清隆たちが板張りの上を進んでいると、次第に人の話し声が大きくなってきた。どこからか箏の音もして振り返ったが、山住たちに置いて行かれそうですぐ前を向き直る。
山住に案内されたのは、講堂で最も広いとされる部屋だった。火の入っていない行灯が、所々に置かれている。そして既に大勢の人が、真ん中を空けて囲むように座っていた。
「あの人たちは皆、不老不死を望んでいるんですか」
「恐らく、誘われただけでまだ悩んでいる方もいるでしょう。梧桐宗とは縁のない、一介の民も」
清隆の疑問に、山住が小声で返す。ざっと見て五十人は超えているだろう人々の多さに、清隆は驚きを隠せない。同時に、以前八重崎や自分を襲ってきた者も、ここまで人が多ければこちらに目を付けないだろうか考える。
清隆は賢順が来るのを今か今かと待ったが、なかなかその姿は現れなかった。やがて数人の僧侶が行灯に火を入れ、すぐ去っていく。八重崎や山住と会話をして時を過ごしていると、開いていた襖からこれまた多くの人々が入ってきた。先にこの部屋にいた儀礼参加者が、焦ってより前へと詰めていく。清隆たちのいた列も、後方から真ん中へと変わった。急に新しく訪れた人の群れに、清隆は怪訝な顔となる。山住もまた、このような予定があったかと首を傾げていた。
「ほら、何か始まるんじゃない?」
八重崎が指差した部屋の中央には、法衣と頭巾を身に着けた僧侶たちがいた。そして黒い袈裟を着て水冠を被り、両手を合わせながら一人の男が遅れて列に入っていく。
「あの男こそ、筑紫賢順斎でございます」
山住の言葉が、清隆の耳を打つ。どことなく大友にも似た顔立ちで、小さめな瞳を備える垂れ目が印象深い。
弟子たちと揃って座り、賢順が部屋に集まった面々へ顔を向けて、ここに来てくれたことへの感謝を述べる。それから講話と称する語りが始まったが、それは死や老いの恐ろしさを語るというものだった。
死んだら肉体は腐り、野犬や鳥に食われる。あるいは荼毘に付され、惨めな骨や灰と化す。これほど恐ろしく、虚しいものはないのではないか。生きている間に得た喜びや幸せも、死んでしまえば全て忘れてしまい、また二度と味わえなくなる。死は人の全てを一気に奪ってしまうのだ。九相図と呼ばれる絵などを時々見せつつ、僧侶は教えを説いていく。
初めは様子見のつもりで清隆も真面目に聞いていたが、次第に退屈を覚えるようになった。賢順の話には繰り返しが多く、声にも抑揚がない。下手をすれば経とも変わりないように思えて、眠くなる人もいるのではないか。現に隣の八重崎は俯き、完全に寝落ちしている。賢順や弟子たちに近い前の方では、まだ語りに同調して恐れる声を上げる者もいたが、後ろ側は眠っている人が多いように見えた。とても梧桐宗の教えを本気で信じるつもりがあるとは思えない。
「やはり、教えそのものに興味を抱いて訪れた者は限られていると思われます」
山住がそう呟いた時、弟子たちがにわかに動きだした。巻物を手に立ち上がり、低い声を揃えて読経している。
「あれは声明といいます。経を読んでいるようにも聞こえますが、実のところは歌っています」
説明をしながら、山住が八重崎を起こすよう清隆に頼む。袖を何度か引っ張られて何とか目を覚ました八重崎は、突然耳に入ってきた弟子たちの大声に目を丸くしていた。何が起きているのか戸惑う彼女に、山住が声明について教える。寺で僧侶によって歌われる仏教音楽であり、瑞香では日本から伝わってきたという。その歌詞はインドが由来で、ただ聞いただけでは意味も理解できない。この部屋にいる聴衆には、ほとんど何も通じていないだろう。この儀礼で、本当に信者が増えるのか。
僧侶たちが蓮の花弁に見立てた紙を撒き、色とりどりのそれが床に落ちる。部屋全体に太鼓の音が響き、空気を揺らす。一方で旋律らしき旋律もない独特の歌に、八重崎が再び舟を漕ぎ始めた。それを見かねた山住が笑い、いったん退室しようか勧めてきた。目立たないように立ち上がり、膝を曲げながら歩こうとする山住を引き留め、清隆は尋ねる。
「勝手に抜けても良いんですか」
「これほどまでに人がいますからね、誰も気にしないでしょう」
人を掻き分けて進みだした山住を止められず、清隆もその場を離れる。起こした八重崎と共に廊下へ出、案内人に続いて玄関に戻る。
「少し気晴らしをしましょうか。伽藍を案内しますよ」
寺に住んで「修行」をしている信者たちもあの部屋に集っており、人に見つかる可能性はない。前向きに話して外へ出る山住を、清隆たちは追った。
時刻を告げる鐘が下げられた鐘楼、本尊である薬師如来像が祀られている本堂を巡り、回廊の外を出て僧侶や信者たちが寝泊まりする僧坊へ入る。山住は臆さず、賢順の部屋まで清隆たちに紹介した。必要最低限の調度だけがある質素な雰囲気の室内を眺め、この寺の責任者といえる人物の部屋へ勝手に入ったことに、清隆は気まずさを覚える。
隅にあった文机には、手紙の封が置かれていた。思わず清隆はそれに目を落とし、辛うじて賢順宛てであると認める。山住がそれにつられて封を見、眉をひそめた。
「これはよもや……陛下の勅筆では?」
四辻姫の筆跡と似ているという宛名の字を清隆は覗き込むが、それがはっきりと彼女のものかは判断できなかった。シャシャテンのもとに届く文をちゃんと見ておけば良かったと後悔しながら、四辻姫と賢順の関係を考える。やり取りは今この部屋にある文だけで終わっているのか、前から続いていたのか。
山住の配慮で、封は開けられなかった。建物を出、三人で講堂へ戻ろうとする。他愛もない話をしつつ足を進めているうちに、清隆は異変に気が付いた。周囲には草木が生えるだけで、清隆も先ほどまで視界に捉えていたはずの回廊はない。歩いているうちに寺を離れ、山に入ってしまったようだ。
「……まぁ、私たちは梧桐宗に入るつもりでここに来たのではありません。戻ったときにあの話について行けなくても、構わないでしょう」
冷や汗を浮かべる山住に、清隆の不安は一気に強まる。果たしてこの男を案内人にして良かったのだろうか。彼を先頭に山を下りる中、清隆はそんな懸念を抱えていた。だがそれも、無事に講堂へ着いた途端に吹き飛ぶ。建物の一部から煙が上がり、人々が玄関を飛び出している。
山住に止められ、内部で何が起きているかを入って探ることは出来なかった。代わりに逃げた人の騒ぎに耳を澄まし、儀礼の行われていた部屋で火の手が上がったと耳に入れる。置いてあった行灯が倒れでもしたのか、清隆が考えていた時だった。
「あれ、清隆の用事って……?」
思わぬ高めの声がし、清隆はすかさずそちらを見た。逃げてきた人々に混じって、信と美央が扉のそばに立っている。八重崎が彼らに駆け寄り、無事だったか確かめる。二人とも傷はないようだが、なぜここにいるのか。後から来る避難者たちのために場所を空け、清隆たちは話を聞くべく講堂の脇へ移った。
前の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
