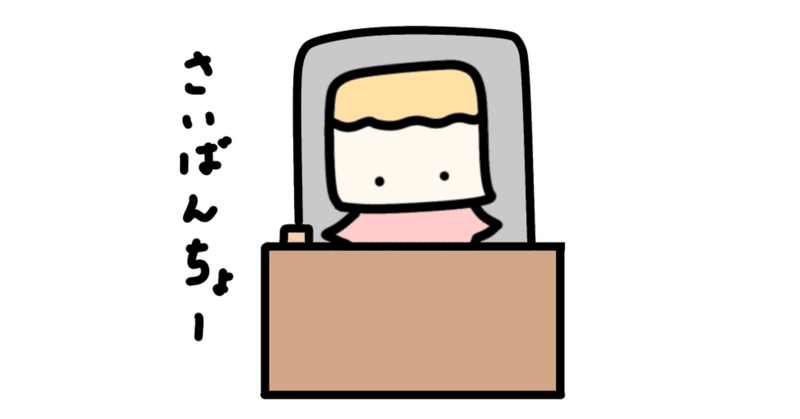
【社会科】授業で判例を使いたい3つの理由
どうも。いかたこです。
中学校で社会科の教員をしています。
今年は初めて中学3年生の授業を担当しています。
1学期の終わりくらいから、本格的に公民が始まりました。
9月中は、憲法を扱っていく予定です。
憲法の授業をつくっていく中で、やっぱり判例ってとても魅力的な教材だなと思いました。
インターネット上にある学習指導案等でも、判例を教材として取り上げているものが多いですね。
今回は、私が憲法の授業において、判例を使いたいと思う3つの理由を紹介したいと思います。
よろしければ、最後までご覧ください。
最後にコラムを付けています!
①大学で法学を専攻していた
1つ目は、とても個人的な理由です。
私は大学で法学を専攻していました。
なので、判例を調べたり読んだりすることに多少慣れています。
大学時代に得た詳細な法の知識は、ほとんど忘れてしまいましたが・・・
ですが、やっぱり自分の専門を活かして授業をしていきたいなと思っています。
②憲法の解釈について学べる
2つ目は、憲法の解釈について学べるということです。
大学時代に、教授と話していたときのことですが、「学校ではあまり憲法の解釈について習わないよね」という話になりました。
もちろん、基本的な知識として、憲法の基本原則やその内容については学習します。
ですが、ただ暗記するだけ、抽象的な理解のままで終わってしまい、それらをどのように解釈していくかについては、あまり扱っていないように思います。
法学を専攻していると言うと、「憲法の条文1つ言ってみて」と、まるで憲法の条文を全て暗記してるんでしょ?と言いたげな態度を取られるのは、このことも要因なのかなと思います・・・
憲法をどのように解釈して、社会での対立を解決していくかは、主権者として重要であると思うので、力を入れていきたいと思っています。
③生徒の考えを拾いやすい
3つ目は、生徒の考えを拾いやすいということです。
憲法の判例を使った授業では、「合憲か違憲か?」という問いを立てます。
このような「AかBか?」という問いの難しさは、問いの結論と異なる考えをどのように拾うかということだと思います。
例えば、有名な判例として、薬事法薬局開設距離制限訴訟があります。
薬事法薬局開設距離制限訴訟
薬局・薬店の開設距離制限(旧薬事法第6条)が、憲法第22条の職業選択の自由に基づく経済活動の自由に反するとして起こされた訴訟。
他の薬局・薬店が近くにある場所に、新しく薬局・薬店を開設することを制限する法律(旧薬事法第6条)が、憲法に保障されている経済活動の自由に反するかどうかという事例です。
これについても、「旧薬事法第6条は合憲か違憲か?」という問いを立て、生徒に判断させます。
実際、最高裁は「違憲である」という判決を出しました。
では、「合憲である」と判断した生徒の考えをどのように拾っていくか。
ここで第一審・第二審の判決を使います。
判例の中には、第一審・第二審において、最高裁判決とは異なる判決が出ているものも多くあります。
これを使えば、最高裁の結論とは異なる考えを拾いやすくなります。
この訴訟でも、第二審(広島高裁)で「合憲である」という判決が出されました。
もちろん、この活動は、具体的な事例を通して考えることが重要であるため、各生徒やグループの出した結論が、最高裁判決と一致したかどうかは重要ではありません。
でも、それは大人の事情です。
生徒からすると、自分たちの考えと最高裁の結論が異なっていると、自分たちの意見は間違っていたのかなと自信をなくしてしまうかもしれません。
そのため、たとえ最高裁判決とは違っても、第一審・第二審の判決と同じであるということは、生徒の考えを拾いやすく、生徒が安心して議論できる環境づくりにつながります。
注意点
判例には、社会で生じた対立がとても詳しく書かれています。
その全てを説明してしまうと、人によっては刺激が強すぎたり、嫌な記憶を思い出したりすることがあります。
何を伝えて、何を伝えないか、生徒の様子を考慮して授業をつくる必要があります。
まとめ
以上が、私が公民の授業で、判例を使いたいと思う3つの理由です。
初めて判例を使った時は、中学3年生には少し難しいかなと思っていました。
ですが、自分たちの意見を交えながら、それぞれの判例について議論してくれました。
社会科が苦手な生徒も、周りの生徒からの解説を受けながら、自分なりの考えを伝えることができていました。
憲法は、国の政治のあり方を決める法であるとともに、国家権力から国民の権力を守るための法でもあります。
そのため、憲法について深く理解していくことは、自分たちの生活を守っていくためにも大切であると思います。
判例を用いることで、生徒の理解を促していけたらと思います。
コラム
先日、2学期の中間テストの範囲を決める話し合いがありました。
思っていたよりもテスト範囲が広くなり、かなり焦りました。(^0^;)
ここ数回の授業は、少しペースを上げて行いましたが、生徒が考える時間が少なくなり、説明の時間が増えてしまいました。
やっぱりたくさん説明するのは、私には合っていないようです。
余裕がないと息苦しさを感じますし、なにより授業が楽しくないですね。
何とかテスト範囲までを終わらせる目処が立ったので、来週からは少し余裕が持てそうです。
さて、授業のタネを考えなくては!
最後までご覧いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
