
走るを言語化することについて語るときに僕の語ること、 #走ラン会 で紹介した書籍3選
昨年のことになるが「走らないランニング会(通称「走ラン会」)」というイベントに参加した。
──
・走る人
・アスリートとして走る人
・走る経営者
・走ることを応援する人
・走ることを撮る人
・走ることを取材する人
・走ることで繋がりを創る人
・箱根駅伝で東京国際大学の躍進を予言していた人
自薦・他薦問わず、上記の方々によるライトニングトーク(以下「LT」と言います)はとても面白かった。お酒も飲まず、ただただ「走る」ことを肴にして。時間を忘れ、イベント会場を出なければならない時間ギリギリまで交流を楽しんだ。
イベントレポートは瀧澤さんのnoteが詳しいので、ご覧ください。
──
恐縮ながら、僕もLTに参加した。
テーマは「走るを言語化することについて」。noteやblogでエッセイを書いたり、短編小説で箱根駅伝を描いてみたり、これまで様々な方法で「走る」ことを表現してきた。
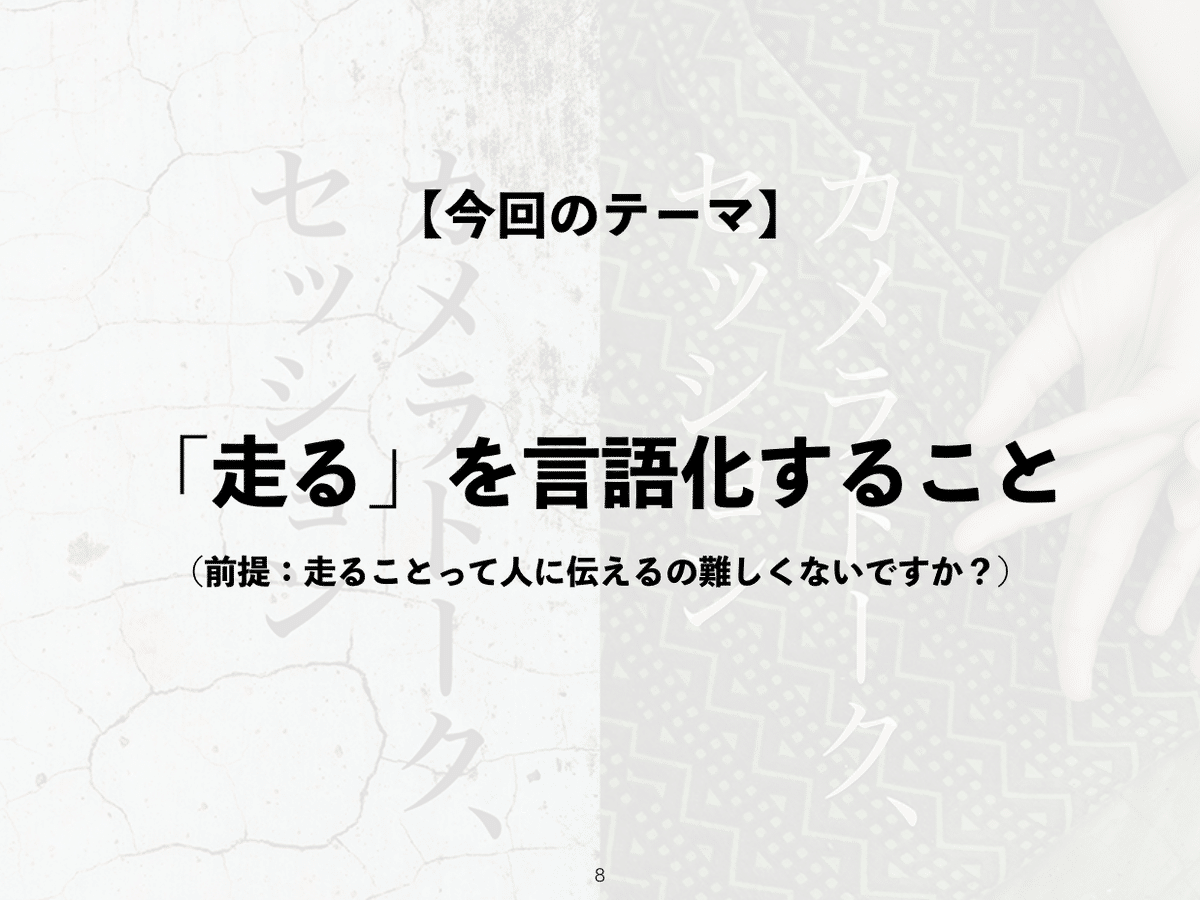
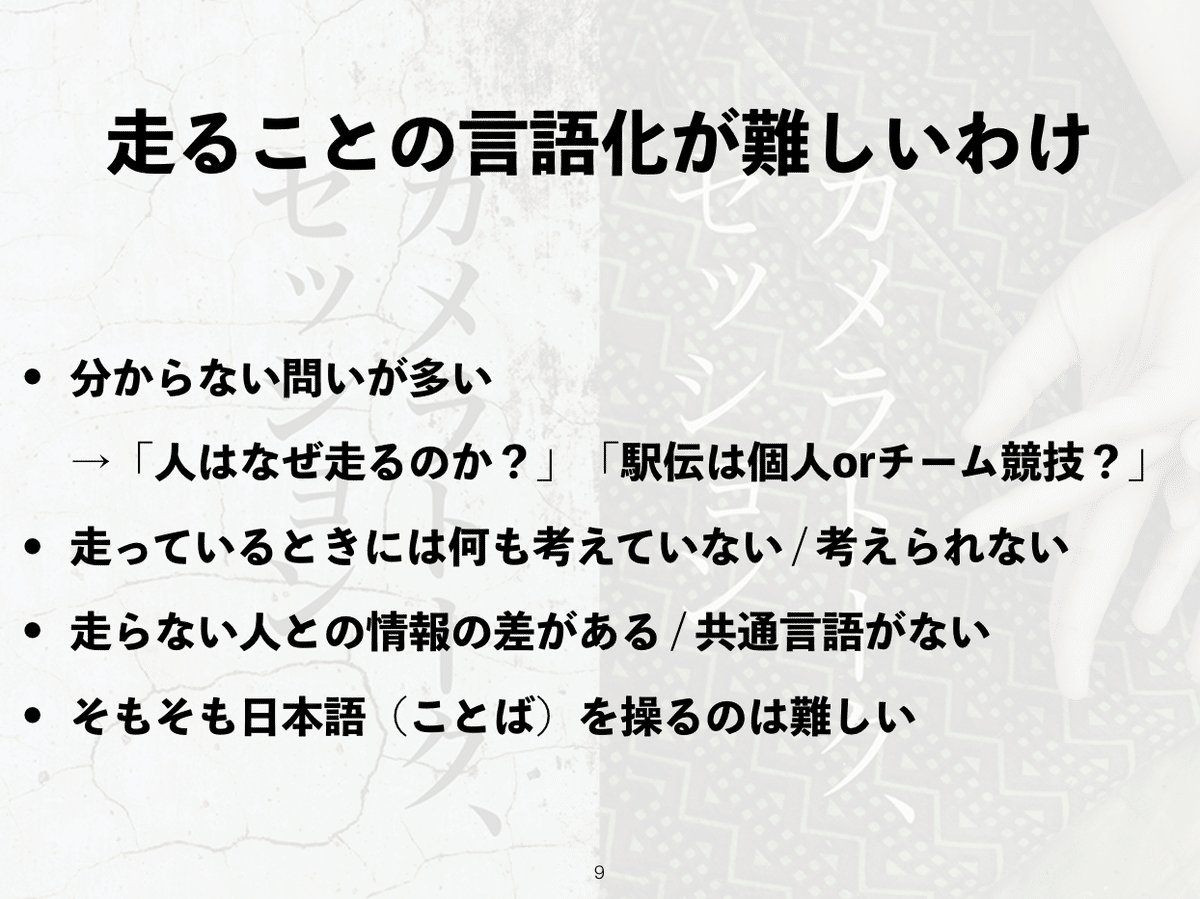
それでも。「走る」を言語化することは難しい。
走るのは一時的な行為ではない。「なぜ息しているの?」「なぜ食事しているの?」と同じくらい、ランナーにとって日常と不可分のものだ。走った距離、時間、天候、体調のことを記したら、他に書くべきものはないように思えてしまう。
人はなぜ走るのか。
そんな問いを投げ掛けられるたび、急ごしらえの答えを返すけれど。いつだってゼロから答えを模索してしまう。僕はなぜ走るのか。スライド作成は最後の最後まで悩んだが、最終的に三人の作家の言葉を拝借した。書籍と共に紹介したい。
──
駅伝は個人種目なのか、チーム種目なのか。堂場瞬一さんによる「チームとしての駅伝」の描き方
堂場瞬一さんの小説『チーム』は、箱根駅伝の学連選抜チームが描かれている。箱根駅伝出場が叶わなかった大学から選抜された選手で構成されている学連選抜は、悪く言えば寄せ集め。そんな彼らがチームになっていく様子が描かれている。(原晋さんが監督を務めた2008年は、学連選抜が脚光を浴びた年だ。リンクも見てほしい)
鍵となる登場人物は、高校時代のチームメイト同士でもある浦と門脇だ。旧知の仲とは言え、浦はキャプテンであり、門脇は補欠。卒業後は陸上を辞める門脇にとって箱根駅伝は「思い出作り」。モチベーションの違う二人の気持ちが結実する瞬間は見応えがあった。
以下は、それぞれが、それぞれの区間を走り出したときの描写だ。(門脇はメンバーの怪我により、繰り上げで箱根5区を任されることになった。浦は10区)
駅舎を通り過ぎると、箱根湯本のささやかな市街地に入る。見物人が多いせいで空気が濃くなり、雪を溶かしてしまうような熱気が渦巻いているのを門脇ははっきりと感じ取った。(中略)歩道は幾重にも連なった人だかりで、溢れんばかりになっていた。押されて痛がっている女の子がいる。おいおい、大丈夫なのか?心配して顔をしかめたが、すぐにそれどころではない、と気を引き締める。誰かが「港学院、頑張れ!」と叫んだ。
違うだろうが。学連選抜。それが今、俺のチームなんだ。港学院のユニフォームは仮の姿だぜ。襷を突き出して見せてやりたくなった。
(堂場瞬一『チーム』P117より引用、太字は私)
橋は中央付近で断層のように少しずれた構造になっており、反対車線は浦が走っている車線よりも数十センチたかくなっている。そこをのろのろと走る車の列から声援が飛んだ。風に吹き飛ばされそうな声だが、確実に耳に届く。「城南!」という叫び声も聞こえた。それは間違いなんじゃないけどな、と浦は腹のなかで苦笑いした。俺は今、城南の選手として走ってるんじゃない。襷を突き出してアピールしてやりたかった。俺たちは学連選抜だ。この二日間のためだけに作られたスペシャルチームだ。
(堂場瞬一『チーム』P269より引用、太字は私)
作家とは、同じような状況 / 同じような感情も、なるべく別の表現をしなければならない。義務というか宿命。「セックスシーンを30種類の表現で書けたら作家になれるわよ」とは、とある海外ドラマのいち台詞。
堂場瞬一さんは、そんな不文律を破り、敢えて全く同じ表現を使用することによって、選手同士が「繋がって」いることを示した。誰からも期待されていない存在だった門脇と、学連選抜のキャプテンとしてチームを作らなければいけなかった浦。そんな二人が、同じ気持ちでレースに臨む姿勢に胸が熱くなる。(ちなみに、このような感情表現は他の8人のランナーには描かれない)
『チーム』に関しては、駅伝を個人種目だと言い続けてチームの輪を乱していた山城の成長も読み応えがある。三浦しをんさんの『風が強く吹いている』と併せて読みたい駅伝小説だ。
──
「走る理由なんて、脇役に語らせておけ」なのか、「脇役だからこそ、走る理由が語れるのか」
倉阪鬼一郎さんの小説『永久のゼッケン』は、病気でランナーの父を亡くした娘が、父の代わりにウルトラマラソン(50kmの部)に臨むことを描いた作品だ。
ランナーは誰しも、最初はランナーではない。だけど真剣に走り始めると、心と身体はランナーのそれになっていく。真剣に取り組めば取り組むほど、身体のどこかは変調をきたす。体力に不安を抱えながら臨むレースもある。そんな初心を思い出させてくれる作品だ。
以下は、小説の終盤で出てきた「名もない脇役たち」の台詞だ。
それほどの歳ではないランナーが二人、こんな会話を交わしていた。
「何のために、朝から夕方まで走ったりしているんだろう?」「しかも、金を払ってな」「ウルトラマラソンなんかに出るやつの気が知れないよ」自嘲気味に言う。
「まあ、でも、何のために生きてるんだとか、何のためにこの世界があるんだとか、解けない疑問はたくあさんあるから」
「長く走っているうちに、そういった難問に肉薄できるんじゃないかっていう感覚にとらわれることはあるよな」
「錯覚だけど」「そう、錯覚」
(倉阪鬼一郎『永久のゼッケン』P243より引用、太字は私)
ずるいなあと思った。笑
ランナーが、うんうんと頭を巡らせている問いを、こんなにもあっさりと、しかも脇役に答えさせるなんて。でも、そうなんだよなと思う。
主人公が走りながら、もっともらしく答えることは簡単だっただろう。だけど脇役が勝手に話し出していることで(主人公に話し掛けているわけではない)、それはとてもリアルだし、それを耳にする主人公の感覚・感触を読者は擬似体験できる。
台詞にある「錯覚」というのは、「そうなのかなあ?」「どうなんかねえ?」というようなニュアンスだと僕は捉えている。走ることをもっともらしく語ることは簡単だ。でもきっと、その人の言葉の裏には、漏れなくクエスチョンマークが付与される。迷いながら、考えながら、あるいは何かを忘れながら、ランナーは今日も走っている。
──
「そうだ、村上さんに聞いてみよう」。メタファーの第一人者が綴る「走る」こと
村上春樹さんのエッセイ『走ることについて語るときに僕の語ること』は、多くのランナーのバイブルだ。僕も例外ではない。
そこで描かれていたウルトラマラソンの過酷さに、僕は当時、心底恐怖した。それでも「いつか僕もウルトラマラソンを走りたい」と決意するのだから不思議なものだ。そのときは、まだフルマラソンさえ経験していなかったのに。
マラソンを走ると、多かれ少なかれ身体は変容する。
多くの場合、変容はネガティブで。「もう絶対に走れない」ところまで追い込まれることさえある。だけど走っているときは必死だ。ネガティブな感覚を吹き飛ばそうと、メンタルで必死に自分自身を鼓舞しようとする。なので実際のところ「キツい」という感覚はあまり憶えていない。「キツかったよなあ?」というレベルまで、リアルさは目減りしている。
そんな前提のもと、村上さんのテキストを読んでほしい。
そのラインを超えて、50キロ地点に近づいてきたあたりで、身体の感じが少し変わったかなという感触があった。脚の筋肉が硬くなり始めているみたいだ。腹も減ったし、喉も渇いた。給水地点があれば、喉が渇いていなくても、必ず水を少しは補給するように心がけていたのだが、それでも脱水は不吉な宿命のように、暗い心を抱えた夜の女王のように、僕のあとを追いかけてきた。微かな不安が脳裏をよぎる。まだ半分も走っていないのに、今からこんなで、本当に100キロを走り通せるのか。
(村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』P146〜147より引用、太字は私)
走っているあいだに、身体のいろんな部分が順番に痛くなっていった。右の腿がひとしきり痛み、それが右の膝に移り、左の太腿に移り……という具合に、ひととおりの身体の部分が入れ替わり立ち替わり、立ち上がってそれぞれの痛みを声高に訴えた。悲鳴を上げ、苦情を申し立てて、窮状を訴え、警告を発した。彼らにとっても、100キロを走るなんていうのは未知の体験だし、みんなそれぞれに言い分はあるのだ。それはよくわかる。しかし何はともあれ、今は耐えて黙々と走り抜くしかない。強い不満を抱え、反旗を翻そうとするラディカルな革命議会をダントンだかロベスピエールだかが弁舌を駆使して説得するみたいに、僕は身体の各部を懸命に説き伏せる。
(村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』P149〜150より引用、太字は私)
一時は沸き立っていた筋肉の革命議会も、今ある状態についていちいち苦情を申し立てることをあきらめたようだった。もう誰もテーブルを叩かず、誰もコップを投げなかった。彼らはその疲弊を、歴史的必然として革命的成果として、ただ黙って需要していた。そして僕は規則的に腕を前後に振り、脚を一歩ずつ前に差し出すだけの自動的な存在と化していた。何も考えない。何も思わない。気がつくと、肉体的苦痛すらほぼ姿を消してしまっている。あるいは事情があって処分できない醜い家具のように、どこか目につかないところに押しやられてしまっている。
(村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』P150〜151より引用、太字は私)
まるで劇場だ。
フランス革命をメタファーに登場させていることから分かるように、淡々と走るランナーの「内側」は、(冗談でなく)たくさんの血が飛び交っているのだ。ファンランでない限り、どんな距離のレースであっても、途中でめちゃくちゃしんどくなる時期がある。数kmで済むこともあれば、数十kmに及ぶこともある。
その過程を経て、しんどさは、ふっと消失する。
楽になるのでなく、村上さんが表現するように、身体が諦めただけなのかもしれない。「抵抗しても無駄だ、出てきなさいよ……」と言わんばかりに、最後の力がぎゅるっと絞られる。
革命はいつか終わる。終わって良い。静かに終わりを迎えたい。
そんな静かなゴールの瞬間を、僕たちランナーは心から楽しみにしている。
──
で、ここまで「走るを言語化することについて」つらつら書いた。だけど、そんな自分を軽々と凌駕する皆さんの言語化の力に、当日は驚いていた。
木幡さんは走ることとご自身の想いを、見事に結実させて人生にまっすぐ臨んでいたし、
森尾さんは走るを支え、走るを見守り、走るを伝えることの魅力を教えてくれたし。
アスリートとして自身の経験を語る須河さんは、何だか、今まで見たことのない表現者 / 求道者みたいな人だった。
僕にとって言語化することは、言語化すること自体が目的みたいなところがあるんだけど(その意図はまたいずれ)、言うまでもなく、多くの人にとって言語化することは「伝える」上での手段だ。彼らの伝える技術はめちゃめちゃ凄いなあと思った。
そして、会場にいた全ての人たちが魅力的だった。「走る」に関わる人に、きっと悪い人はいないのだ。
とても乱暴なまとめになってしまったけれど、僕としては引き続き「走る」を言語化することに挑戦し続けていきたい。会場にいる皆さんに宣言した通り、いつか、「マラソンを巡る小説」を書くのだ!
──
まとめ(紹介したもの)
・[本]堂場瞬一『チーム』
・[本]倉阪鬼一郎『永久のゼッケン』
・[本]村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』
──
最後に。なんと、第2回の #走ラン会 があるそうです!興味がある方は、以下のPeatixからお申し込みください。きっとたくさんの、素敵な「走る」に出会えるはず。
走らずに走る楽しさを共有する!「走らないランニング会 #走ラン会」第2回を募集開始🎽✨2月27日夜@渋谷。
— さえきほのか (@saeki151) January 28, 2020
登壇予定の方がいろんなベクトルから走るを語れる方々で絶対面白い!!!当日話してくださる方も募集してます🖐https://t.co/EASeryB1Wq pic.twitter.com/WpukExdJr6
記事をお読みいただき、ありがとうございます。 サポートいただくのも嬉しいですが、noteを感想付きでシェアいただけるのも感激してしまいます。
