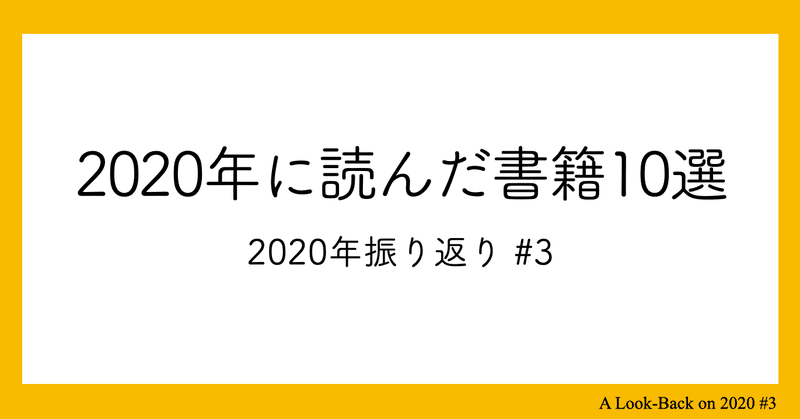
2020年に読んだ書籍10選
もしコロナウィルスがなかったら。
東京五輪は予定通り開催されていただろう。
安倍晋三さんは体調を崩さず首相を続けていただろう。
どの業界もそれなりの好況を維持していたかもしれない。
僕たちは2019年の延長線上で、日常を送れていたに違いない。
from positive to negative.
そんな文脈で2020年が語られることが多い。
でも僕は「大変だったけど、2020年がこんな年で良かったのかもしれない」と不謹慎にも思っている。
Pause for thought.
立ち止まった社会が本質を見つめ直して、様々なことが見直されている。
満員電車で通勤する必要ってあるんだっけ?
この打ち合わせって、本当に対面の必要があるんだっけ?
地域に住んでいる人がイベント参加を諦めざるを得ないのは仕方ないんだっけ?
インバウンド需要に乗っかり、観光に資源集中をしても良いんだっけ?
ワイドショーのコメンテーターの発言って信頼しても良いんだっけ?
今の会社で漫然と仕事を続けていても良いんだっけ?
慌ただしくも、時間は公平にやって来た。
本質に向き合い続けた時間は無駄にはならない。
そしてコロナ禍だからこそ読めた本、響いたテキストがある。
昨年興味を持った哲学、哲学とは本来「知を愛する」行為だと知り、深く思想を辿る読書へと時間を費やした。古典にもたくさん触れた。コロナ禍だからこそ「時間を経て読み継がれてきたもの」の価値の重みに気付いた。
歴史は繰り返す。
知性が軽んじられることなく、未来を前進させる動脈として機能されることを信じたい。
*
ということで、今回のnoteは、2020年に読んだ書籍振り返り、だ。
僕が選んだ書籍10選が、読み手の皆さんに直接役に立つことはないはず。だけどもし何らかの内面的啓発に貢献できたとしたら、本当に嬉しい。2021年に繋がる読書体験になれるかなと。
──
原研哉、阿部雅世『なぜデザインなのか。』
2010年代は、デザインが市民権を得た10年だ。iPhoneが多くの人に手に渡った。無印良品やバルミューダなどデザイン性の高いプロダクトが実際に売れた。僕たちが毎日せっせと触れているSNSは、漏れずにUXに優れたデザインだ。こんなにも良質なデザインに囲まれた時代はなかった。
とここまで書いてナンだが、僕が前述したデザインと、原さんや阿部さんが考えるデザインは全く違う理解のもとで成立した「生き方」だ。「デザインの創造性は問いにかかっている」と話す原さんがこれまで提示してきた問いを、僕は少しでも紐解いて(おこがましくも)継承したいと考えている。
*
宮野真生子、磯野真穂『急に具合が悪くなる』
死が間近に迫った哲学者と、当事者として関わることを選択した人類学者の往復書簡。生きるとは何か、死ぬとは何か。概念としてでなく、フィジカルに死を捉えたテキストは僕の心を物凄く震わせる。
関係性を作り上げるとは、握手をして立ち止まることでも、受け止めることでもなく、運動の中でラインを描き続けながら、共に世界を通り抜け、その動きの中で、互いにとって心地よい言葉や身振りを見つけ出し、それを踏み跡として、次の一歩を踏み出してゆく。そういう知覚の伴った運動なのではないでしょうか。
(宮野真生子、磯野真穂『急に具合が悪くなる』P188〜189より引用、太字は原文より)
どんな時代でも、未来を正しく予見することは不可能で、常に不確定要素が伴うもの。何を選んでも正解とは限らない中で、少なくとも二人のような関係性が成立したことはとても幸せなことだ。
誰だって、突如として死は自分ごとになる。とにかく尊いはずの「いま」を全力で生きたいと思った。
*
宮口幸治『ケーキの切れない非行少年たち』
世の中のマジョリティに決して理解されることのない「非行」。なぜこんな犯罪が起こってしまったのか嘆き、厳罰を求める世論に対して一石を投じる書籍だ。彼らは認知機能に問題があり「近付いてくる人が敵に見える」「誰も自分の話を聞いてくれない」と感じている。
「周囲に気付かれず声をあげられない」で苦しんでいる人が一定数いると著者は主張する。見るもの、聞くものの全てが歪んでいる彼らを救えない社会の側(僕も含む)にあるのだと知った。特定の個人に責任を負わせるのでなく、社会全体で責任を包摂するパラダイムシフトが急務である。
*
マルクス・アウレーリウス『自省録』
時に自己嫌悪に陥るくらいの内省をした、ローマ皇帝のマルクス・アウレリウス。「善き人」であろうとした彼の哲学は、他人に優しく自分に厳しい。
「なんとすべてのものはすみやかに消え失せてしまうことだろう」という刹那を理解しながら、社会を前進させることに人生を賭けた賢帝の思想。当時文書保管は極めて難しかったが、彼のテキストは2,000年以上保持され続けてきた。内省を忘れた僕らの国の「賢者」たちに、彼の爪の垢を煎じて飲ませたい。
*
梅田卓夫他『高校生のための批評入門』
冒頭に「批評とは、世界と自分をより正確に認識しようとする心のはたらき」と記されている。否定や誹謗中傷とは全く違うし、何事も肯定から始めようという流行からは一線を画したクリエイティブな行為だということが分かる。
工業高校の国語教師が編んだアンソロジーには、安部公房、水木しげる、澁澤龍彦、安岡章太郎、カフカ、チャップリンなど時代を超えて読み継がれる名文が選定されている。言葉は知性と感性を磨く。一読の価値あり。
*
カミュ『ペスト』
元々は対ナチス闘争への寓意が描かれた作品。コロナ禍で注目され、多くの人が読み直した名作だ。
「理不尽小説」と形容されるアルベール・カミュが伝えたいことは何だったのだろう。僕は「世の中には期待されているほどの希望もないし、悲観されるほどの絶望もないよ」ということだと解釈している。とりあえず生き延びていけばコロナ禍は終わる。その先には思ったよりも「楽しさ」はないかもしれないが、それでも終わることを信じて、前を向いて進んでいきたい。
*
ジョージ・オーウェル『動物農場』
名作『1984年』を遺したジョージ・オーウェルの、もう一つの代表作。「権力」が肥大化し、歪んでいった先には、滑稽なほど幼稚な社会が生まれてしまう。それはまるで僕らの国のようではないかと胸が苦しくなった。
過去も含めて「なぜこんな愚かな独裁が許されるのだろう」と疑問だった。独り善がりな独裁は論理破綻している脆弱なものに見えるけれど、弱者のインサイトを激しく掴む求心力がある。歴史の見方が変わる一冊だった。
*
髙崎卓馬『表現の技術』
広告に軸足を置きながら、映画の脚本や小説執筆など活躍の場を広げるクリエイティブディレクター・髙崎さんの哲学が余すところなく語られている。「方法論はあくまで方法論。そのままなぞっても強い表現が生まれるわけではない」とも認めながらも、再現性の高い技術を追求している。予定調和や思考停止を拒絶し、人のココロに触れる表現を今なお生み出している。
手を動かそう。違和感に気付こう。多少の知識や経験に安住してはいけない。広告に限らず、世の中にインパクトを残せるアイデアは、考えに考えを重ねた結果生まれるものだ。常に発想できる人間であるべく精進したい。
*
東浩紀『ゲンロン戦記』
雑誌『ゲンロン』や『哲学の誤配』『テーマパーク化する地球』など東さんが関わるテキストを何度も読んだ。東さんが伝える誤配(メッセージが誤った解釈で伝わること、知らせなくても良いことが誤って伝わること)の考え方に深く共感した。世の中に根付いた豊かな文化は、誤配を受け入れる余白が常にあり、効率性や生産性を遥かに超えた価値を生み出している。
「ひとの人生には失敗ぐらいしか後世に伝えるべきものはない」と語る東さん。他責として処理したくなるような失敗を全て背負い込みながら「知の観客」を作ろうと奮闘されている姿は、経営者というよりも修行僧のよう。
*
読書猿『独学大全』
700ページを超えるほどの厚い本が、現時点で11万部以上売れているという。その事実だけで「世の中は、学びへの渇望に溢れている」と分かり希望を持つことができた。
山に登る方法は一つではない。そもそも山に登らないという選択肢だってある。著者は「〜しない」ことも否定しない。それでも「学びたい」という想いを信じ、ひたすら寄り添おうと本書を記したに違いない。この本はビジネス書でなく、哲学書だと僕は思っている。
──
まとめ(紹介した10作品)
・原研哉、阿部雅世『なぜデザインなのか。』
・宮野真生子、磯野真穂『急に具合が悪くなる』
・宮口幸治『ケーキの切れない非行少年たち』
・マルクス・アウレーリウス『自省録』
・梅田卓夫他『高校生のための批評入門』
・カミュ『ペスト』
・ジョージ・オーウェル『動物農場』
・髙崎卓馬『表現の技術』
・東浩紀『ゲンロン戦記』
・読書猿『独学大全』
──
昨年までのエントリは以下をご参照ください。
──
上記書籍について個別に書いたnoteも時間があれば。
記事をお読みいただき、ありがとうございます。 サポートいただくのも嬉しいですが、noteを感想付きでシェアいただけるのも感激してしまいます。
