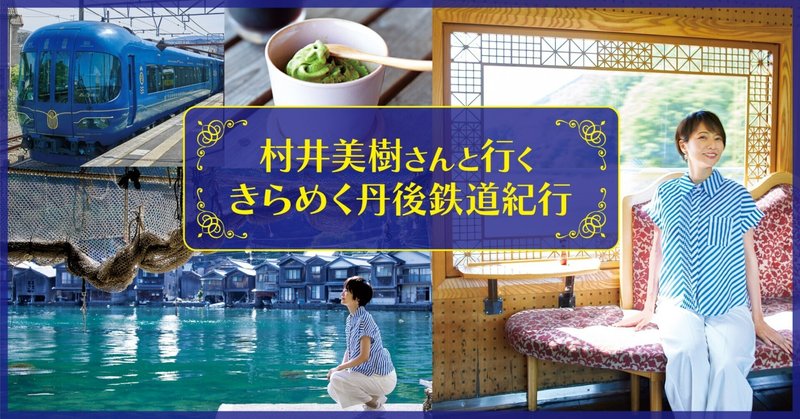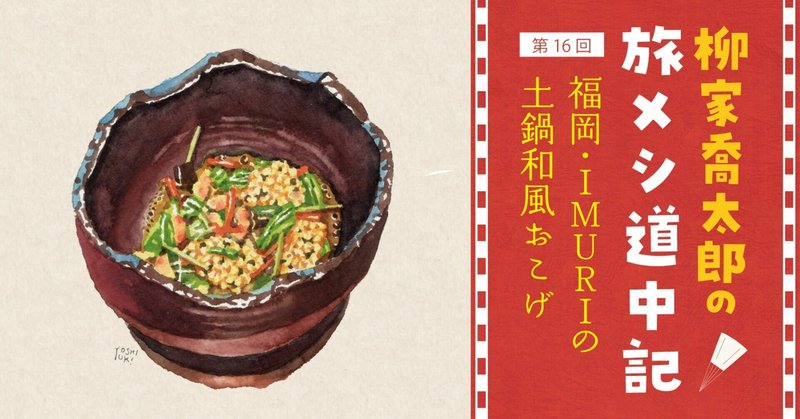ほんのひととき
“旅や本にまつわる読みもの”を日々お届けするウェブマガジンです。月刊誌「ひととき」の人…
最近の記事

東京都指定有形文化財「百段階段」で味わう、妖しくも美しい7つの物語|ホテル雅叙園東京「和のあかり×百段階段2024~妖美なおとぎばなし~」
2015年から夏の恒例催事として行われてきた企画展「和のあかり×百段階段」。9回目を迎えた今年は「妖美なおとぎばなし」をテーマに、粋を凝らした作品が全国から集結。2024年9月23日まで、ここでしか味わえない贅沢な空間が堪能できます。 それでは、めくるめく不思議な物語の世界へとさっそく足を踏み入れてみましょう。 竹取物語はじめに訪れたのは、十畝の間。 林立する竹灯籠と、和紙でつくられたやわらかな月の光が表現するのは、幻想的な「竹取物語」の世界。荒木十畝の描く花鳥画と一体に
マガジン
記事

【MIHO MUSEUM】特別展「奈良大和路のみほとけ ─令和古寺巡礼─」の見どころを、仏像イラストレーターの田中ひろみさんが現地レポート!
滋賀県甲賀市信楽町「MIHO MUSEUM(ミホ ミュージアム)」の夏季特別展「奈良大和路のみほとけ ─令和古寺巡礼─」〔会期2024年7月6日(土)~9月1日(日)〕のプレス内覧会に参加しました。 緑が多くとっても素敵な「MIHO MUSEUM」で、私の大好きな奈良の仏像の数々を拝めるという素晴らしい展覧会です。 記事冒頭の入口ポスターの写真は、大安寺蔵の奈良時代の秘仏・馬頭観音菩薩立像。展示期間は8月6日〜9月1日のため、私が訪れた時はお会いできませんでした。 会場