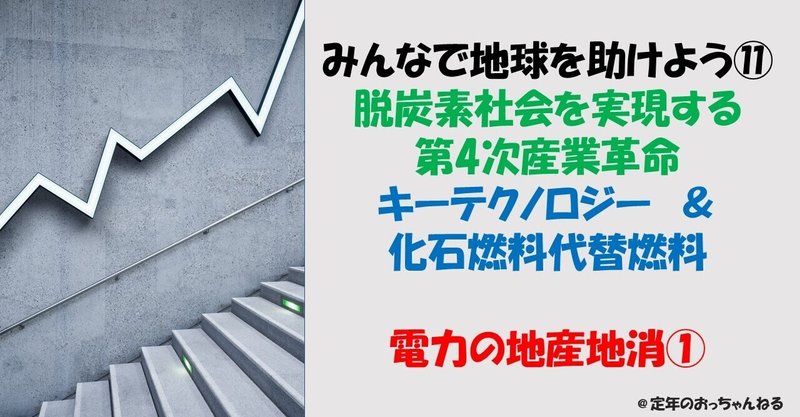
みんなで地球を助けよう⑪:電源構成を変える脱炭素は電力の地産地消が適している⁉

今回からは、水素から離れて電力の地産地消について考えてみましょう。
国際社会の中で仲間づくりが下手で、内向きな国民性、女性の人権に鈍感な国、そんな日本が、未だに戦後の奇跡の復興、1985年のプラザ合意までの成功体験を引きずって脱皮できずにいます。
その成功体験とは、家庭内での明確な男女の役割分担の下、男性は社畜と呼ばれるほど会社のために働き、その間、女性が家庭内で子育てや家事を分担するというジェンダーの役割分担で成り立っていました。
そんな古臭くて、男性が牛耳る社会ではなく、ダイバーシティを実現してみんながイキイキと働ける、そんな社会の実現を政治家も口には出しますが、ことはそう簡単でないことを過去30年以上の歴史が示しています。
✅シルバーポリティクス
若い人に頑張ってもらいたいけれど、そう簡単に政治は変えられないし、行政の縦割りも既得権益者に有利な制度も今日、明日でどうなるものでもありません。

大阪市の行政効率を上げようとする大阪都構想という大阪市規模の投票になるとあれだけの人気に支えられている大阪維新の会であっても、既得権益の前に現状を変えることは拒絶されました。
そうなると、もっと小さな規模でないと「変えることの意思決定はできない」と思うのです。
エネルギーの決定権を国といった大きな単位で考えていたのでは、なかなか先には進みません。
電力、エネルギーこそ地産地消、つまり5万人規模の我がまちの発電所なら自分たちで決められるのではないでしょうか?

多くの方がご存知のとおり、小泉純一郎さんは、政治家を引退した後「脱原発」を訴えて、全国で講演されています。
政治家を辞めた後、自分で勉強して「原発は、使用済み核燃料、核のゴミ処分に10万年先の安全まで保障する必要があり日本に向かない。原子力発電から撤退すべきだ。」と主張されています。
小泉さんは、これまで原子力が担ってきた30%の依存度を太陽光や風力といった再生可能エネルギーで代替すればいい、福島原発の後、一時期は原発なしで日本の電力は賄えていたのだから、脱原発はできると主張されています。
しかし、火力発電所をそのままにしていたのでは、気候変動が先に進んでしまい取り返しがつかなくなります。それはいいのでしょうか?
菅(かん)元首相が言うように全ての水田の上に太陽光パネルを付ければ理屈の上では火力発電を止められるといった寝言はやめにしましょうよ。(稲は光が当たらなくても日陰で育つのでしょうか?)
菅(すが)首相は、日本は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにすると表明したのですから、感情論だけでなく原発の是非を議論しなくてはなりません。
どうやって議論の俎上に載せるか?
✅シュタットベルケをお手本に!

じーじは、エネルギーを地産地消で考えればいいのではないかと思っています。
よくお手本として、ドイツのシュタットベルケが例に出てきます。
地域の「公益会社」と訳されることが多いようですが、地域インフラ供給会社とでも訳す方がしっくりきます。
シュタットベルケは、市内の全電力を賄う市の100%子会社です。
市内のCO2排出削減といった難しい取り組みであっても町のインフラ全体をカバーするシュタットベルケだからこそ「我が町の電力会社」として、市民からの関心と期待に応える具体的な対策が進むそうです。
この会社の規模を5~6万人単位に1社とすれば、いろいろな選択肢を検討して、多様な意思決定が行われ出すのではないかと考えています。
つまり大阪都構想のような大規模な単位になると、どうしても「変わりたくない」という人が多数になってしまいますが、5~6万人規模なら感情論抜きの車座集会だって何度もやれると思うのです。
我が町のエネルギーをどうすべきか、我が町の電気代の将来設計はどうするか、日本の将来を考えた上で結構冷静な話し合いができるのではないかと思っています。
急峻な地形で67%が森林の日本では、太陽光発電の競争力はありません。
夏と冬で風の強さが違う日本では、風力発電も諸外国に比べて競争力がありません。
そんな日本で、安全性が腹落ちできるのならば、小型原子炉を選択する市民集団も出てくるのではないでしょうか?
【3分程度の講演紹介動画2編👆を見れば、シュタットベルケが分かり、フルで見れば専門家⁉】

✅小型原子炉を受け入れる自治体は⁉
SMR(スモール モジュール リアクター:小型原子炉)の開発ベンチャーで米国オレゴン州ポートランドに本社を置くニュースケール社の新型原子力発電施設の採用を米国の35の地域が検討しているように、そんな地域が日本にも必ず出てきます。
米国では、その35の地域の内、2020年10月、2つの町が計画からの撤退を表明しました。
我が町に原子力発電が来るとなると、計画を受け入れる人ばかりでないのは、米国も日本も同じです。
日本では、風力や太陽光発電であっても、景観が嫌だと反対する場合も出てきているので、カーボンニュートラルのハードルがものすごく高いのです。
そういう多様な考えを許容するドイツのように「我が町のことは、我が町で決める」というのが、日本人には向いているのではないでしょうか?
後まで読んでいただき、ありがとうございました。
よろしかったら「スキ」🤍ポッチンをお願いします😊😊
コメントなんかいただけたら、飛び上がって喜んじゃいます😂😂

▼「じーじのボヤキ」孫と祖父シリーズのサイトマップです。
▼じーじの初期投稿4部作のサイトマップを紹介しますね。
▼「じーじは見た!」シリーズのサイトマップは第2弾ができました。
▼じーじの時事川柳シリーズのサイトマップです。お一つ読んでみてくださいな😊
▼Z世代応援団のじーじをよろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
