
インタビューその4:半分死んでいた自分が、編集の仕事で救われた話
イラストレーター&文筆家・陽菜ひよ子です。
今回の記事はインタビュー企画です。わたしのまわりにいる「クリエイティブな活動をしている人」に「仕事や創作」について赤裸々にきき、その人の「クリエイティブのタネ」を見つけよう!という企画の第4回。
今までのインタビューはコチラでごらんになれます。
今回お話を伺ったのは、長野県佐久市と東京を拠点とする編集会社「株式会社バーネット」の代表・高橋修さん。
高橋さんの略歴など。
高橋 修
編集者。1974年、東京都日野市生まれ。
2000年、立教大学文学部心理学科卒業。
幾つかの出版社・編集会社を経て、2018年、株式会社バーネット設立。
株式会社バーネット代表取締役。
元造事務所代表取締役(2010-2017年)。
高橋さんは2018年に佐久に移住し、編集会社・株式会社バーネットを設立。東京と佐久を行き来しながら精力的に本を作っておられます。
今回、佐久×キャンプなフリーマガジン『Lantern』を創刊。

『Lantern』創刊準備号(撮影:宮田雄平)
雑誌の創刊に合わせて制作されたこの動画、素晴らしい!佐久ってこんなにいいとこなんだ!住みたい!
というわけで、今回は高橋さんの数奇な編集人生と「なぜ佐久なのか?」についてお伝えします。
恩人であり業界のお父さん
高橋さんとのお付き合いは、今までのインタビュイーの中で一番長く、はじめてお会いしたときは、わたしは「フツーの主婦」でした。というのも、わたしのデビューのきっかけを作ってくれたのが、ほかならぬ高橋さんだからです。
『やさしい写仏ぬり絵帖』(2006年・ダイヤモンド社)
造事務所・著(編集担当・高橋修) 陽菜雛子・イラスト
そんな高橋さんにインタビューをお願いすると、こころよい返事と共に「僕の人生の重要な局面は、すべて『女性関係の流れ』に従ってます」という、ある意味衝撃的な言葉が返ってきました。
それから「あとは『兄の死』と『師匠に恵まれたこと』かな」とも。

お互い東京在住だった2010年秋に飲んだ時の高橋さん。
高橋さんがかぶっているのは、わたしのつくった帽子。
(2010年11月@池袋・撮影:宮田雄平)
「女性関係の流れ」「お兄さん」「師匠」の3つをキーワードに、高橋さんの編集人生の「核」のようなものを、あぶり出していければ、と思います。
兄がひたすら怖かった少年時代
――――高橋さんって、関西のご出身でしたっけ?たしか西宮?
高橋:ああ、そういう印象あるもしれませんね、両親ともに関西人なので。
西宮は高校の3年間だけなんです。生まれたのは東京の日野市なんですよ。3歳のときに神奈川県厚木市に引っ越して、5歳で東京都文京区本郷、7歳から中学までは文京区千駄木に住んでいました。
――――なるほど、では記憶があるのは文京区時代からですね。はじめてお会いしたころは千駄木にお住まいでしたが、千駄木はなれ親しんだ街だったんですね。ご両親はどんな方たちでしたか?
高橋:父はモーターボート取得のための小さなスクールを経営してましたが、もともとは編集者だったんですよ。母は神戸出身でセンスはよかったかな。僕のなんでもおもしろがるような、好奇心の強さは母ゆずりだと感じますが、母は本は読まない人で。
父の方は編集者だったので、本をすごくたくさん読んでいたんです。あらためて影響を受けていたんだなと感じます。
でも、僕の「人格形成」に多大な影響を与えていたのは、やはり6歳年上の兄だったと思います。
――――お兄さんとは仲が良かったんですか?
高橋:いえ、全然。僕が小2のとき、兄に新潮文庫の『坊っちゃん』を渡されて、読んで感想を言えっていわれたんですよ。
――――新潮文庫って、あの字の細かい大人向けの?小2で?
高橋:そうです。それまで、そこそこ普通に本は読んでましたけど、小2男子にわかるわけないですよね。最初の一文からわかんなかったです。「親ゆずり」も「無鉄砲」も。「損ばかりしている」でやっと少しわかったかな。
そんな難しい本は、はじめて読んだので、全体の3割くらいしか理解できなかったと思います。それでも「読めるんだな」って気づいて。「わからなくても、最後まで読み通せば、全体像はつかめるんだ」ってことがわかったんです。
これが、僕の「本を読むこと」に対する原体験だったと思います。
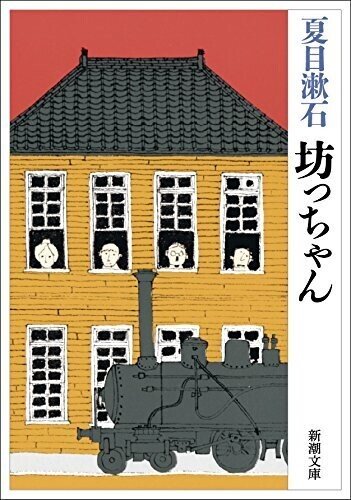
――――上に兄姉がいると、文化的には『お得』ですよね。
高橋:そうですね。兄の影響で知ったことはすごく多かったです。
――――強権的なことも多いですよね。ウチは姉ですが、ジャイアンみたいでしたし。あんたのものはアタシのもの、的な。
高橋:僕なんかは完全に兄の奴隷みたいなもんで。兄の話をし出すとキリがないんですが。
10歳くらいの頃には兄の趣味で洋楽を聴かされて。あるとき千駄木のレンタルレコード店にプリンスのアルバム『パープルレイン』を借りに行け、とメモを渡されたんです。
メモにはPrinceって英語で書いてあって。そんなの小学生に読めるわけないですよね。
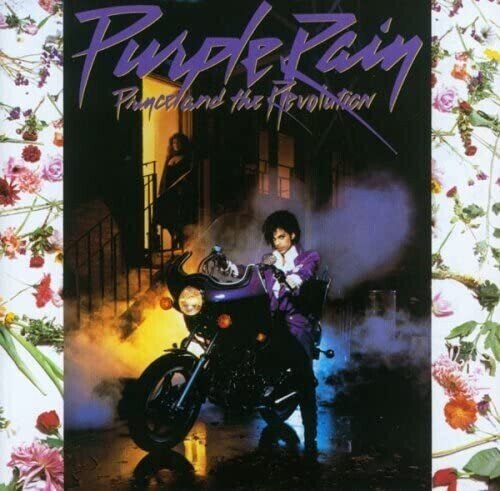
それと、図書館に新譜が入ると、借りたい人が殺到するんで抽選になるんですが、それも並んで借りて来いって言われたりとか。
――――ちょっと待ってください。図書館に新譜?CDとかレコードって、寄贈されたものだとばかり思ってました。新しいのなんて入荷するんですか?
高橋:してましたよ、うちの近くの図書館では。
――――それって文京区だから?すごーい!初めて聞きました!
高橋:確かに文化的には恵まれていたかもしれませんね。
兄にはとにかくいろいろやらされて。アメリカのヒット曲のランキングチャートの変動をグラフにさせられたり、プレイリストを作らされてレコードからテープにダビングしたり。
――――そのあたりは、今の編集のお仕事に生きていそうですが。お兄さんは弟を鍛えようとか、そういう意図があったんでしょうか?
高橋:いや、まったくないです。自分の楽しみのためだったと思います。
あとは、キャッチボールですごい剛速球を硬球で投げられたり、サッカーで至近距離からシュートを決められたり。「背中が凝った」とか言って1時間くらいあんまさせられたり。もうホント兄が怖くて怖くて。
当時は「死んでくれ」と思っていました。
兄の死
高橋:それで、陽菜さんもご存じの通り、その兄が、本当に亡くなってしまったんです。山で遭難して。兄が26歳で、僕が21歳のときです。
――――20代なら、もう割と対等な感じだったのでしょうか?
高橋:そうですね、もう奴隷ではなかったですね。
――――仲はよかったんですか?
高橋:ふつうです。兄は東大生で、僕は立教の大学生で。
最初にお話ししたように僕は西宮の高校を出てるんです。両親が関西人なので、両親はいずれは関西に帰りたいと思っていて。
僕が高校に入った頃、兄は大学生で寮生活、父は代官山で事業をしてたので、母と僕だけ西宮に住んでいたんです。結局バブルで千駄木の家の価格が高騰しすぎて買い手がつかず、関西へ帰ることはあきらめたんですよ。それで僕も東京に戻って進学したんです。
――――お父様が代官山で会社を経営して、お兄様が東大で高橋さんは立教って、すごいお宅ですね。
高橋:兄が亡くなった頃の僕は、すごくしんどかったんです。1995年の1月に阪神大震災があって。高校時代を西宮で過ごした僕には、他人事じゃなくて。実際亡くなった知人もいますし。
3月には地下鉄サリン事件が起きて。我が家は全員たまたま無事でしたが、被害にあってもおかしくなかったんです。千駄木は千代田線(※サリンがまかれた地下鉄の路線)が通ってるんで。
――――震災もオウムも渦中に近いところにいたのは辛いですね。
高橋:その頃、兄は独立して埼玉に住んでたんですが、塾講師のバイト先から連絡があって、兄が授業に来ないんだけど、連絡なしで来ないなんてありえないって。
調べてみると、兄は真冬の富士山に登ったらしいことがわかったんです。もともと単独登山をする人だったので、そのときもひとりで。
捜索願を出して、3月から6月くらいまで、父と車であちこちの警察署に行きました。ヘリも飛んだのかな?結局6月下旬に、雪が溶けて遺体が見つかったんです。
――――それはご両親もがっかりされたでしょうね。
高橋:そうですね、落ち込んでいましたね。
僕も1995年は本当に疲れ切っていて。地震があってオウム、兄の死ときて。生きていく気力がなくなったんです。でも死ぬのも怖くて、ぼんやりしちゃって。
大学も行かなくなって、辞めちゃったんですよ。
兄の死で変わった人生観
――――高橋さんは、知り合った頃はSNSにあまり個人的なことを書かれない方でしたが、唯一お兄さまが亡くなったことは書かれていましたよね。未だ乗り越えることが難しいのかな、と感じています。
高橋:簡単には受け入れられませんでしたね。このとき、人格が変わったんです。喜怒哀楽を超える境地というか、憎いとか殺したいというような、激しい感情がなくなりました。
それで思ったんですよね。人と話したり、怒ったり憎んだりって、生きている間はどんどんした方がいいって。どんなに相手を憎んだところで、死んでしまったら終わりなんだから。
「死んだら終わり」という意味ではないですよ。むしろ「生きてるって貴重」だなと。
――――明石家さんまの「生きてるだけで丸もうけ」みたいですね。
高橋:そうそう。
憎んだりうらやんだりって、マイナスの感情だと言われますが、悪いことじゃないって思うんですよ。だって「生きてるから」できるんですもんね。
だったら、そういう感情を無理におさえ込まなくてもいいのかなと。自分の中にマイナスの感情があることを、認められるようになったんです。
――――「達観」されたんですね。
高橋:そうですね。達観としか言いようがないな。一歩引いてる自分がいたんです。
「喜ばしい」「うれしい」という感情も、どこか別のところから見てるような。浮かれることもなくなりましたし。
たぶん、人格が分裂しないで、その直前でなんとか止まっている状態だったんじゃないかな。俯瞰して見ることで、どうにか自分を保っていられたんです。
女性関係で人生が変わる・その1「ヒモ編」
――――大学をやめて、その後はどうされて?
高橋:すごくつらかったんですけど、元気ない状態がずっと続いたかというと、そういうわけでもなくて。当時付き合ってた彼女とはうまく行っていました。
親のところに帰りたくなくて。親が落ち込んでるところを見たくなくて。ひとり暮らしの彼女のところに転がり込んだんですよ。ヒモですね。
親とはたまに電話する程度で。でも親は、僕が生きてさえいてくれれば、それでいいって思ってたんでしょうね。大学を辞めたことも、何も言われなかったし。
――――彼女の家では何をして過ごしていたんですか?
高橋:掃除や料理してましたよ。ホントヒモ状態で。もう4年生だったんで、彼女は就職活動で忙しかったんです。
僕はヒマで。だからよけいに辛くて。ヒマだと悲しさやむなしさが襲ってくるんですよ。だからこの頃は、現実逃避のために本をすごく読みましたね。何でもよかったから、古本屋さんの10円コーナーで手当たり次第買いあさって。今からすれば、ホントビックリするくらい読みましたよ。
家からスーパーファミコンも持ち込んでやってましたし。「信長の野望」とかね。目の前の現実から逃げられるなら、なんでもよかったんです。

そんな生活が半年続きました。
――――半年たって、何か変わりましたか?
高橋:ここで転機があって。彼女は就職先に出版社を希望していたんです。中堅どころのある出版社でバイトしていたんですが、彼女は持病があって、会社を休みがちだったんですね。
彼女の上司である編集長は体育会系で、ちょっとブラックなことも平気で言う人なんですよ。
――――わかる気がします。編集者って、体力勝負ですしね。
高橋:そうそう、その編集長も「体力がいちばん大事」って言ってました。
で、彼女がある日泣いて帰って来て。編集長に「休むんなら代理を連れて来い」って言われたって言うんですよ。
――――もしかして、それで代わりに?
高橋:そうなんです。彼女はそういうつもりはなかったみたいでしたが、そんな話を聞かされて、今ここにヒマな自分がいるわけで。そりゃ、行くしかないでしょうって話ですよね。
――――それまで、編集者になりたいと思ったことは?
高橋:まったくないです。
――――つまり「女性関係の流れで編集者を目指すことになった」と。
高橋:自分は代理だと思っていたので、最初は編集者を目指すつもりもなかったんです。自分はどうなってもいいって思ってたんで、完全に世間をなめていましたし。
社会復帰をするつもりもなくて。フーテンの寅さんみたいな感じで、適当な格好で行きました。
――――今の高橋さんからは想像できませんね。
高橋:ただね、兄の影響で、年上の人に丁寧に接することは身についていたんですね。だから何となくうまく行って。それと、父の仕事の手伝いをしてたので、電話番もできて、文章を書くのもなんとかできたんです。
当時はまだ編集部にPCがない頃で、でも僕は兄の影響でPCを使えたし、なぜかノートPCを持ってたんですね。中にLotus 1-2-3や一太郎が入ってて。
――――Lotusや一太郎、懐かしい!ノートPCを持っていたのはすごい!高かったですよね、当時のノートって。
高橋:誰かにもらったんですよ。そのPCを編集部に自前でつないで仕事していたんです。
――――それ、傍から見ると、すごく「やる気ある」みたいに見えますね。
高橋:そうだったみたいです。しばらくして、編集長から「代理じゃなくていいから、彼女とは別枠で来い」って言われました。
僕は声も大きいし、兄に鍛えられたお陰で、体育会系で上の人にはとりあえず従うし、「使える」って思われたみたいですね。
でも僕はあんまり仕事したくなかったんで「週1で」って返事してました。
女性関係で人生が変わる・その2「バイト編」
――――彼女はどう思ったんでしょうか。
高橋:複雑な気持ちだったみたいですね。まぁあたりまえですが、これがきっかけでだんだんすれ違っていくんです。彼女は就職活動が佳境に入って来て、もっと忙しくなって、バイトはますます休みがちになって。
僕はだんだん楽しくなって来て、ヒマなんで、行く日数が増えていくんです。最初は週1だったのが、週7になって。土日も帰らなくて、いつも編集部にいるような。
――――のちのワーカホリックな高橋さんへと一直線に突き進んでますね。バイトだという事ですが、お給料はどれくらいもらってたんですか?
高橋:時給900円でしたが、すごいことになってましたよ。編集部にシュラフを持ち込んで、朝5時に起きてタイムカードをガチャ!夜中にガチャ!という感じで、1日20時間くらい働いてました。
単純に考えても月に50万はもらってましたね。お金使わないし、たまる一方でした。
――――すごい!バイトなのに!時給900円でも「編集部の主」になればそんなに行っちゃうんですね。
高橋:そうなんですよね。それでも誰も何も言わなくて。ゆるい時代だったんですね。
それで、僕はこうして社会復帰を果たして、救われたんです。
――――本をつくることで救われたんですね。
高橋:そうですね。その代わり、彼女とは別れてしまいました。
女性関係で人生が変わる・その3「転職&復学編」
――――その後、その会社の社員になられて。
高橋:そうそう、1996年の3月頃に編集長から「社員になるか?」と聞かれまして。一度は断ってるんですよね。
――――それはまたどうして?
高橋:最初に提出していた履歴書に虚偽があったんですよ。代理のつもりだったんで、とりあえず通ればいいや、と思って、本当は大学辞めてるのに「卒業見込み」って書いて提出したんです。
それを伝えて「高卒じゃダメですよね?」と言ったら、編集長に鼻で笑われたんです。「おまえ、それ社長に伝えてこい」って言われて。
社長にも伝えると、ニヤッと笑われて。「高卒だから、(基本給から)マイナス5,000円でいいか?」って言われたんです。それで「社員にしてください」とお願いしました。
学歴なんて、どっちでもよかったんですね。
――――社長も編集長もカッコイイ!高橋さんはもう「編集部になくてはならない人」になってたからですよね。
高橋:そうなのかな?そうだといいですけどね。
その出版社には3年ほどお世話になりました。この体育会系のA編集長は僕の最初の師匠と呼ぶべき人で、たくさんのことを教わりましたよ。
――――その後、転職されたきっかけは何だったんでしょうか?
高橋:いろいろありますが、一番大きいのは、本づくりの現場からじょじょに離されてしまったことです。僕がのちに勤めることになるような編集会社(編集プロダクション)に委託して、出版社の編集者の仕事は「スケジュール」と「お金」の管理だけ、というのがイヤで。
――――なるほど。本づくりが好きな人には物足りないでしょうね。
高橋:あとは、編集部に2歳年上の女性が移動してきて、付き合うようになるんですが、彼女が先に辞めて、別の出版社に転職したんです。それで僕も後を追うように同じ会社に転職しました。といっても社員ではなく業務委託でしたけど。
――――出た!「女性関係で人生が変わる第2弾!」
高橋:あはは、そうですね。それに不安になったんですよ。あまりにも世間を知らなくて、大丈夫かなと。別のところで勝負したくなったんです。
大学に戻って、ちゃんと卒業しようとも考えて。
――――大学って、休学じゃなくて辞めてもまた戻れるものなんですね。
高橋:いや、そんなことはないと思うんですけどね。立教からは辞めてからもたびたび電話があったんですよ。そういう方針のようで。辞めても「休学扱い」になってて、単位は留保していますよと。
僕の場合、ゼミと卒論とフランス語と保健体育の単位が取れればいいので、あと1年で卒業できますよ、とか。再試験は不要ですよ、とか。まぁ、勧誘してくるわけです。
――――復学したい人にとっては願ってもない話ですよね。復学することにしたのは、転職のためですか?
高橋:いや、付き合ってる彼女と結婚しようと思ったんです。地方出身の彼女の父親が、話に聞くとすごく怖い人で。
改めて自分の経歴を振り返ると、大学もちゃんと出てないし中途半端で、絶対許してもらえそうにないなと。
――――でもそのときはちゃんと編集の仕事をされていたわけですもんね。
高橋:彼女のお父さんみたいな人から見れば、出版社なんてわけわかんないし、ヤクザみたいなものなんですよ。
それで、仕事をしながら復学しました。業務委託で辞典を作ってたんです。それが25~26歳の頃ですね。
――――何だかんだと、転職も復学も、女性がらみで決めたんですね。。。
高橋:ホントそうですよね。
大学は無事卒業できて。春になって当時の勤め先から今後の打診を受けたんです。といっても社員に誘われるわけではなく、このまま業務委託を継続という話で。
僕はこういうとき、あんまり人に相談しないんですけど、このときはさすがに迷って、彼女に相談したんです。彼女は僕のことよくわかってるんで。
そしたら彼女が「あなたみたいに飽き性な人は、辞典の仕事は合わないんじゃないか」っていうんです。
「あなたはもっといろんな本を作れた方がいい。無理して続けても、きっとすぐに辞めちゃう」
――――ああ、確かにそうですね。飽き性かどうかは別として、高橋さんに辞典って、わたしもピンと来ないです。
高橋:それで6月頃から転職活動をはじめて。お恥ずかしながら、実は当時の僕は※編集会社ってものをよくわかってなくて、出版社ばかり受けてたんです。
※編集会社=出版社の下請けで本の制作・編集を行う会社。=編集プロダクション。略して編プロという。
彼女が新聞の求人広告で、編集会社である造事務所の求人を見つけてくれたんですよ。彼女はなんかピンときたみたいで「この会社おもしろそう」ってすすめてきて。
僕は最初気が進まなかったんですが、入ってみたら正解で。創業者で当時の社長だったMさんは僕の第2の師匠というべき人ですが、本当にきたえられました。
「世界の神々」がよくわかる本(PHP研究所・2005年)
東 ゆみこ・監修 / 造事務所・監修
造事務所時代に担当した中で、いちばん印象深い本。
ちょうど高橋さんと知り合った頃、売れに売れていて
わたしにとってもこの本はすごく印象深い(ひよ子)
――――そして無事、ご結婚されて。
高橋:そうそう、数年後に彼女の家に挨拶に行ったら、親父さんは高校を中退した、たたき上げの苦労人で、学歴や会社の規模なんて全然気にしてなくて。何だったんだって感じでしたよ。早く言ってくれよって感じですよね。
――――あはは。彼女は、高橋さんが頑張ってるなら、水をさすこともないと思ったんでは?
高橋:まぁ結果的にはよかったですけどね。
社長になり、離婚、そして再婚
――――造事務所では社長にまでのぼりつめて。
高橋:先代のMさんが病気で急死したんです。それで僕が正式に跡を継ぐことになって。
――――それが2010年5月のことですね。社長になって、生活は変わりましたか?
高橋:結婚してからは特に頑張って働いてたんですが、社長になってからはさらにプレッシャーがひどくて。会社のことしか考えられなくなったんですよ。
――――わたしが知り合った頃、2005~2006年頃の高橋さんのワーカホリックぶりもなかなかでしたよね。いつも真っ赤な目をして、いつ寝てるんだろうって感じで。それ以上になってたんですね。
高橋:全く家庭を顧みてなかったですね。それが離婚の原因につながるんですが。
その後、元妻とは2015年に離婚することになったんです。
――――離婚については知らなかったんですが、ピンと来たことがあって。
高橋さんが「最近コーヒーを豆から入れるおいしさに目覚めた」ってFacebookに書かれてて。おやって思ったんです。
男性が趣味嗜好やライフスタイルが変わるのって、絶対女性の影響を受けてるなって。あれ?パートナーが変わった?って。
それまでまったく生活感や家庭の影を見せて来なかったのが、すごく変わられましたよね。
高橋:よく覚えてますね。おっしゃるとおりなんですが。
前の妻と離婚してひとりになって、これはヤバいって思ったんですよ。僕は糸の切れた凧みたいなもんで、過去の経験から、家族がいないとどこかへ飛んで行ってしまうんじゃないかって。
生活力はないくせに、♪包丁一本さらしに巻いて~みたいな、流しの板前みたいに、どこでも生き延びられると思ってるんです。だから逆に、ちゃんと家庭を持たなくてはと焦ったんです。
――――それで今の奥さんと出会われたんですね。
高橋:もともと知り合いだったんですけど、彼女には子どもがいて、子どもが小学校に上がる前に再婚したいと考えていて。こういっては何ですが、お互いに利害が一致したんですね。恋に落ちたのは結婚相手として見るようになってからなんです。
――――大人同士の結婚ってそういうものなのかもしれませんよね。ワーッと盛り上がる気持ちだけでは決められないというか。。。
高橋:そういうものですよね。
「顔の見える本」を作りたい
――――ご結婚されて、佐久に移住された時、本当に驚きました。わたしの中で高橋さんは「都会の人」というイメージだったので。
高橋:子どものことを考えた時に、東京じゃなくていいのかなって思ったんですよ。子どもが自然派な子で、引っ越すことが決まってワクワクしてたしね。
――――それはいいですね。お子さんが環境に合わないとかわいそうですもんね。
高橋:それと、批判ではないのですが、造事務所での本のつくり方に限界を感じたというか、飽きてしまったというのもあります。
――――そんなにつくり方って違うものなんですか?
高橋:造事務所の本って著者がいないことが多いんです。
出版社に企画が通ったら肉付けして、ライターさん数名にテーマに沿った項目案をたくさん考えてもらって、サンプル原稿を書いてもらって、基本のデザインフォーマットを決めて。
たとえば、50項目をそれぞれ4ページで展開すれば200ページ。それくらいのボリュームになれば本が成立するんで、あとは2~3人のライターさんに同じように書いてもらう、という感じです。
こういうやり方だと設計図も書きやすいし、ビジネスとして成立させやすい。型にはめていく面白さもありますしね。
でももっと、著者性、作家性を出せる本をつくりたいと思うようになったんです。著者が自分の書きたいことを書けるような。
――――なるほど、そういう違いがあるんですね。著者(わたし自身含む)としては、ありがたいお話ですね。
江戸川乱歩語辞典(誠文堂新光社・2020年)
荒俣 宏・監修 / 奈落 一騎・著
現在の会社・株式会社バーネットで制作した中で印象深い本
――――ところで、佐久でのお仕事は、フリーマガジン『Lantern』以外にもされているんですか?
高橋:地元の仕事は、思ったよりたくさんありますね。人口10万人くらいで、ちょうどいいんですよ。僕みたいな職業の人があまりいないからね。
――――想像なんですが、今って移住も増えてて、長野にも編集者やライターもそこそこ住んでますよね。でも仕事をするのは東京のメディアと。だから地元の席は空いてた、そこにはまった感じではないかと。
高橋:まさにその通りなんですよ。僕らは生活するからには当然、地元の仕事をしたいと思ったんで。
流された先にあった編集という仕事と家族
――――ここまでご自身の半生を振り返って、どう感じますか?
高橋:僕はホント風来坊で、中学生くらいのときには、自分は銀行員や公務員みたいな仕事はできないってわかってたんです。今思えば、そういう向き不向きを子どもの頃からまわりに理解してもらえていたことは、ありがたかったですね。
もともと、9時から5時みたいな生活は合わないと感じてたし、毎日同じことをするのも無理だし、やりたくないことはやりたくないんで。今みたいな生活が合ってますね。

八ヶ岳と稲穂を眺めながら犬の散歩。3匹はすべて保護犬。
散歩は高橋さんの担当。(撮影:高橋さん)
――――ノビノビと生活されているのが、SNSなどの発信を通じて伝わってきます。家庭も円満で本当に楽しそうです。
高橋:自分のことって自分ではよくわからないものですが、その、自分でもわからない部分を今の妻はすごく理解してくれていて。
妻は電通にもいたことがあり、出版界では雑誌畑の人なんです。そのせいか職業的なカンがすごくよくて、バランス感覚があるんです。彼女の方がパフォーマー的で、僕の方が職人気質な感じかな。
彼女は僕が困っていると、何も言わなくても察してくれて。これは彼女の才能ですね。だから僕もいろいろ相談するようになりました。
――――そういえば、どうして「佐久」だったんですか?
高橋:もともと妻が長野の人で、小諸出身なんです。佐久に決めたのは、僕は山に登るんで、山が近いのと空気が気持ちよかったのと、水がうまかったからです。
――――奥さんが長野出身!ってことは、移住もやっぱり「女性関係の流れで決めた」と。
高橋:そういうことになりますかね。

内山牧場キャンプ場から、荒船山・艫岩と息子さん(3歳)。
(撮影:高橋さん)
佐久×キャンプなフリーマガジン『Lantern』
――――最後になりましたが、佐久×キャンプなフリーマガジン『Lantern』について。制作することになったきっかけは?
高橋:佐久に移住して1年くらい経った2019年に、地元にある創業100年以上の老舗の印刷所から、声をかけていただいたんです。社長から息子さん、つまりその会社の次期社長と一緒に何かできないかと。
僕はすぐに「媒体をつくればいい」と思って妻に相談したら「フリーペーパーがいい」と。彼女はフリーペーパーづくりのプロなので。
それから一年後、つまり去年・2020年ですね。彼女がマーケテイングした結果「テーマはキャンプがいい」と。
――――そうか、奥さんのアイデアなんですね。さすが!
高橋:キャンプは今、ブームですしね。焚火も癒されるって人気ですし。それで印刷所にふたりで提案に行ったんです。
で、ちょうど僕が大河で話題の渋沢栄一(※佐久にもつながりがある)のパンフを作ったりして、市の観光課とつながりがあったんで、観光協会がバックについてくれて。
制作のほとんどは妻がやって、僕はおもに県の助成金の申請をする書類作成などの面倒なことを引き受けました。

『Lantern』創刊準備号(撮影:宮田雄平)
――――これ、素晴らしいですね。オシャレだし面白い。表紙もカッコよくて。何度か「あれ?ウチってL.L.Beanのカタログなんてあったっけ?」って思わず二度見しました。
高橋:おお!それはうれしいですねぇ。
(インタビューの9月時点では)それは創刊準備号で、10月22日に正式な創刊号が出ます。創刊準備号は16ページですが、創刊号は40ページになるので厚みがあって、背表紙に文字が入ります。
――――かなり読みごたえがありますね。楽しみです。
ところで、制作は高橋さんと奥さんで、準備号の巻頭の対談ではお嬢さんが登場して。まさに「家族総出で」つくりあげてますね。
高橋:家族総出。。。ホントそうですよね。
――――お嬢さんの対談、いいですよね。ていうか、お嬢さん、ものすごくしっかりしてますよね。6年生ってこんなに大人でしたっけ?
高橋:うーん、編集上、言葉を整えているからそう見えるのかもしれませんが。確かに年齢よりは少し大人びているのかな。。。
――――お嬢さんの語る、校長先生との交流の話なんて、なんだか上質な童話を読んでいるようで。対談相手のキャンプ場のオーナーさんのお話も、ふたりの会話もすごくいいです。

『Lantern』創刊準備号・巻頭対談ページ(撮影:宮田雄平)
――――このフリーペーパーは、どこで入手できるんですか?
高橋:佐久市内では、佐久平駅をはじめ、あちこちに置かれています。都内だと、アウトドア用品店などですかね。
対談は本当は、〇〇が登場する予定だったんですよ。
――――ええっ!〇〇ってあの〇〇ですか?マジですか?すごい!大物すぎませんか?
高橋:マジなんですよ。コロナで緊急事態宣言になっちゃって、来られなくなったんですけどね。それで急きょ娘が登場したわけなんです。
――――緊急事態宣言が解除されたら来てくれるんですか?次号には?
高橋:創刊号には間に合いませんでしたが、第2号には出てくれるんじゃないかな?創刊号も、誰もが知ってる作家さんなどが協力してくれました。
――――すごい!〇〇の名前はモチロン記事には書いちゃダメですよね。でも、ウズウズするぅ~~~
高橋:なので、これを読んでるみなさんも、期待して待っててください。
『Lantern』創刊に合わせて制作された動画・その2
おまけ:長野県が広すぎる件
わたしの住む愛知県と長野県は実はお隣さんだ。だけど、隣接している部分が狭い上に、我が家のある名古屋市内からすごく遠い。
そもそも長野は広すぎるのだ。隣接する県だけでなんと8つもある。埼玉までお隣さんだとは知らんかった。
わかりやすく図を作ってみた。
この図の真ん中右の方のぺパミントグリーンの部分、群馬との県境に位置するのが佐久市。わたしの住む愛知県は左下にちらっと見える赤い部分。隣とはいえずいぶん遠い。

このインタビュー連載の前の回にご登場いただいた装丁家の宮川先生は戸隠の出身。戸隠は上の方にあるぺパミントグリーンの部分。新潟との県境で、やっぱりウチからは遠い。
我が家は愛知県でも、この図よりずっと左の方で、長野といえば岐阜を超えた先にあるイメージ。松本や乗鞍、諏訪あたりは名古屋からも行きやすい。スキーで白馬もよく行ったけど、意外と遠いのね。。。
長野は広いが世間は狭い。
なんと『Lantern』に、Twitterで交流しているライターMさんがコラムを連載。最初同姓同名かと思ったら、なんとご本人!
世間が狭すぎて、ホント悪いことはできないのだ。

おまけ・2:長野つながり
上記でも触れたけれど、前回の宮川先生は「長野出身で東京在住」。インタビューの中で「自分とは逆に都会から田舎に移住した人もいるのだろう」と話しておられたけれど、今回はまさにその「東京出身で長野に移住した」高橋さん。
狙ったわけではないのだけど、奇しくも、宮川先生へのanswerのような記事になって、感慨深い。
もし、この記事を読んで「面白い」「役に立った」と感じたら、ぜひサポートをお願い致します。頂いたご支援は、今後もこのような記事を書くために、大切に使わせていただきます。
