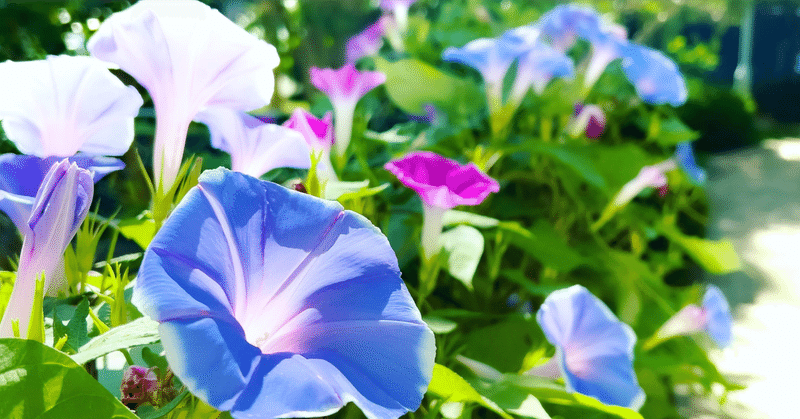
読書会を運営して2年目の私が、本気出して私の読書会の始め方を解説する。
こんにちは😀
ひろゆきだよ。
まえがき
今回、読書会の始め方を解説したい。というのも、読書会の始め方講座のようなものを始めようと思っていて、これを機に自分自身の体験を語りたい。これを読めば、ほぼ始められるくらいのものを目指している。それでは、行ってみよう。
読書会の始め方その1 読書会に行ってみる
読書会を始めようとする人はどんな人だろうか。
私が読書会に行くようになったきっかけは、当時自分のコミュニケーション能力に悩んでいて、ある本を読んだら読書会に通いだしたら克服したという文章を読んだことから始まる。
それは8年前くらいの話だろうか。だいぶ昔の話である。当時GoogleやTwitterで検索して読書会を見つけそこに通っていた。ここでの注意点は水に合わない読書会があることだ。いろいろな読書会に行ってみて、ここは自分に合うと感じるところに行くことをオススメする。
私が行っていたのは自由が丘で開催している読書会ふしぎらだ。純文学の短編小説を読んで、小説そのものの理解を深める内容だった。たぶん、3年くらい通ったのではないか。その読書会に参加するようになって純文学の楽しみ方を知れたと思う。この読書会は素敵だった。
その他、読書会ではないが哲学カフェという場にもよく行った経験がある。問いを立て、いろんな考えを対話する中で、知的興奮を楽しんでいた。読書会よりも哲学カフェの方によく行っていた気がする。ここでの体験から人が集まる場所で自分自身の考えを伝える自信につながっている。
読書会の始め方その2 読書会にした理由
そもそも私は読書会を始めようとして動いていたのではない。正確に言うと社会とつながれるきっかけを探していたのだ。
東京都世田谷区にある地域の交流地点であるタタタハウスに、あるとき通うようになった。タタタハウスのコミュニティカフェに通うのはとても楽しいことだったが、窮屈に感じることもあった。なぜなら、私はこの場ではお客さんとしてでしか振る舞えないからだ。それだと、ただコーヒーを飲んでくつろぐことしかできない。そのとき自分自身でなにか企画を立ち上げようとする。そのときはまだなにをやるのかは決まっていなかった。
いろいろ考えてタタタハウスのいろんな企画にも参加する。そのときに東京都市大学でしあわせなウェルビーイング会議フェスが開催された。私は元々コミュニティに救われた体験があるため、コミュニティを研究する大学のゼミにも興味を持つ。
その会議フェスの中で、尾山台の地図を作ろうというワークショップに参加した。まちのためにどのような地図を作ったらいいのか参加者みんなで考える。そこで、私はまちにあるものではなく、まちにあったらいいなあと思うものを紙に書いた。それは、「読書会」と「哲学カフェ」だった。当時どちらも行っていない状態で、気軽に通える場所で開催していたらいいなと気軽な気持ちだったからだ。
その会議フェスで一発目のワークショップで、それが終わってからも会議フェスは続いたが、私は疲れて帰ってしまった。
帰路に東京都市大学がある尾山台のまちを歩いていると、一軒の本屋さんを見つける。WARPHOLEBOOKSである。この本屋はいまでも大変お世話になっている。この会議フェス帰りにたまたま見つけたのが出会いだった。
本は元々読んでいたので、本屋にふらっと入ってしまった。棚をちらちら見ていると衝撃的な出会いを果たす。ここで「読書会の教室」出会う。これは、ビビっときた。私に読書会をやれという意味だと受け取る。ここから読書会を始めることになった。
読書会の始め方その3 周りの協力を得る
読書会を始める時期にEコミュニティ塾という講座に通っていた。その時期の私は過去にコミュニティに助けられた経験があったため、コミュニティの名前に敏感な時期である。
その講座では、なにか企画を始めるときには一人で始めるのではなく、誰かを誘って始めるように勧めていた。だから、その講座の教えの通りに友人を一人誘って読書会を始める。
会場はタタタハウスにした。コミュニティを大事にしている雰囲気があり、自分に合うと思ったからだ。タタタハウスのゆうだいさんに相談したところ、やってもいいとのことで始められた。
読書会の始め方その4 読書会初期
読書会はまずは仲間と二人だけで、テストプレイをしてみた。二人で10冊以上持ってきたので、たくさん語る。楽しく会を進められたので、このスタイルで始めることにした。
さて、ここで問題なのは集客である。もし参加者が一人も来なかったら、仲間がいるので二人でやればいいのだが、それも寂しい。なので、チラシを作成してタタタハウスに置いてもらったり、タタタハウスに来ているお客さんに声をかけたりと営業活動をしていた。
その成果があったのか、5名の参加者が来てくれた。第一回目として十分ではないか。その後、二か月に一回のペースで読書会を開催している。
その間にあれこれあった。それは別の機会に話そうと思う。
読書会の始め方その5 最近の読書会の状況
読書会を始めて2年目に突入している。2年目になってから、いきなりこの読書会が本気を出し始めた。
たとえば、コラボ企画である。世田谷区にあるフリースクールの学び舎トーカで子ども向けの読書会を企画したり、秋田県金山町の地域おこし協力隊の人と協力して2拠点の読書会を企画したりと大忙しである。
また、WARPHOLEBOOKSの店長から会議のやり方を教えてもらったので、読書会会議も行うようになった。この会議の内容は主に読書会の運営をしている私の読書会に関する悩みを相談する場所となっている。
さらに、読書会のチラシも読書会メンバーによる寄稿を載せている。いったいどんな方がこの文章を読んでくれているかわからない。でも、寄稿を載せるようになってから、チラシを見て参加くださる人が出てくるようになった。十分働いているチラシと言えよう。
読書会の始め方その6 読書会のこれから
これからこの読書会はどうなっていくのだろうか。それは私自身もよくわかっていない。でも、いろんな出会いを通じて変わっていける部分があるといいかなと思う。
今回、このnoteを書くきっかけは、読書会にかかる経費をどこかで稼げないかなと考えたからだ。読書会の経費は主にチラシにかかっている。大きな金額ではないが、続けていくと少し負担に感じるようになってきた。だから、もしかすると読書会を始めたいという人に、読書会の始め方を教えられたなら、その問題を解決できるのではないか。それを試そうとしているところだ。
読書会を始める理由も十人十色だと思う。よき出会いに期待している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
