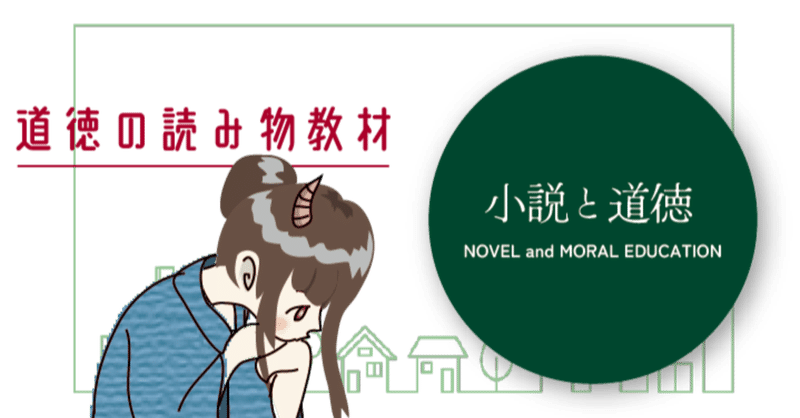
道徳の読み物「死者を嗤う」(中学校:礼儀) (原作:菊池寛「死者を嗤う」)
対象学年:中学校(3年)
内容項目:礼儀 (7)礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動をとること。
教材の種類:菊池寛「死者を嗤う」を部分的に省略・語の置き換えをしたもの
死者を嗤(わら)う
二、三日降り続いた秋雨がやんで、からりと晴れ渡った快い朝であった。
江戸川の近くに住んでいる啓吉(けいきち)は、いつものように十時ごろ家を出て、東五軒町の停留所へ急いだ。彼は雨の日が致命的に嫌であった。だから、こうした秋晴れの朝は、何か良いことが自分を待っているような気がして、なんとなく心がときめくのであった。
彼が、江戸川にかかる小桜橋という小さい橋を渡ろうとした時である。ふと上流を見ると、石切橋と小桜橋との間に架せられている橋を中心に、常には見慣れない異常な情景があるのに気が付いた。橋の上にも堤防にも人が一杯である。そしてすべての群衆は、川中に行われつつある何事かを、一心に注視しているのであった。
啓吉は好奇心の強い男であった。彼はこの光景を見ると、すぐ足を転じて群衆の方へ急いだ。群衆は、岸にあっては堤防に、橋の上では欄干へ、ギシギシと押し詰められている。そしてその数は、刻々と増加して行きつつあるのだ。
群衆に近づいてみると、彼らは銘々に何か喚いているのである。
「そら! また見えた、橋桁に引っかかったよ。」と、欄干に手をかけて川を覗いている子供が、得意になって後方に押しかけている群衆に報告している。
「何ですか。」
啓吉は、自分の隣に居合わせた女に聞いた。
「溺死体ですよ。」と、その女はちょっと眉をしかめるようにして答えた。
啓吉は、奇妙な好奇心に囚われ、かなりの密度をもった群衆の中へ入っていった。まだ自分の前には人がいて、水面を覗き込むことはできなかったが、大抵の様子はわかった。死人は啓吉の立っている岸のすぐ下の水中にあるらしい。そして巡査一人と、役人が二、三人とで、しきりに引き上げにかかっているらしかった。
そのうちに群衆はますます増えていった。千人を超した群衆が、この橋を上流下流、四五十間(約百メートルほど)をぎっしりと詰めかけている。引き上げ作業を目撃している者が、自分の見ている事を後方へ報告している。
「男ですか、女ですか。」
「どうも女らしいですよ。」
「こんな水の浅い川で死ねるのでしょうか。」
「夜通し、入っていると、凍え死ぬのですよ。もう水の中が冷たいですからね。」
すると突然、橋上の群衆や、岸に近い群衆が、「わあ!」と大声を上げた。
「ああ、とうとう引っかけやがった。」と所々で同じような声が起こった。役人が、先に鉤のついた竿で、死体の衣類を引っかけたらしい。
群衆は、以前よりも大声を立てながら騒いでいる。しかし、啓吉は、人間、しかもその生前には、その身だしなみのために絶えざる考慮を払ったにちがいない女性の体が、ゆでだこか何かのように、鉤につるされて公衆の面前、しかも何等の同情も無く、好奇心ばかりで動いている群衆の面前で、引き上げられるということは、その死体に対する侮辱のみではなく、人間全体に対する、ひどい侮辱であるように思われて、憤りと悲しみの混じったある感懐に、囚われずにはいられなかったのである。
すると、突然「パシャッ」と水音がしたかと思うと、群衆は一時に「どっ」と大声を立てて笑った。啓吉は、最初その笑いの意味がわからなかった。が、その意味は周囲の群衆が発する言葉ですぐわかった。
一度水面を離れかけた死体が、鉤の外れたため、再び水中に落ちたからであった。
「しっかりしろ! 馬鹿!」
役人は、また死体に鉤をかける事に成功したらしい。群衆が「今度こそしっかりやれ。」と叫んでいる。
啓吉は、また押しつまされるような気持ちになった。彼は、死体が群衆の見物から一刻も早く逃れる事を望んでいた。すると、また突然水音がしたかと思うと、以前にも倍したような笑い声が起こった。むろん、死体が再び水面に落ちたのである。
この時、彼はふと、二、三年前浅草で見た米国の映画の事を思い出した。それは相手を追いかけまわす喜劇で、勢いあまって湖水に落ちた大柄の俳優を、皆が寄ってたかって救助にかかるのだ。投げ込んだ縄に俳優がつかまる。皆が力いっぱい引き上げるが、俳優が水面から出ると、縄を引いている連中の力が抜けて、俳優は水音高く再び水中に落ち込んでブクブクやる。それを見ると、観客は訳もなく嬉しがった。啓吉も腹を抱えて笑った一人である。
ところが、現在啓吉の目撃している死体引き上げの場面も、この映画の場面とまったく同じではないか。
啓吉は、群衆が笑う心理がわかったようにも思った。が、それでも、啓吉の感情はそれらの笑いを正当視することができなかった。死者を嗤っている群衆を、啓吉の感情はどうしても許さなかったのである。
三度目に死体が、とうとう正確に鉤にかかったらしい。役人は、死体を竿にかけたまま、橋桁から石崖の方へ渡り、石段の方へ、水中の死体を引いてきた。
石段は啓吉から一間(約1.8メートル)も離れぬ所にあった。岸の上にいた巡査は、死体を引き上げるために石段の近くにいた群衆を追い払った。そのために、啓吉の前にいた人々が払いのけられて、啓吉は見物人として絶好の位置を得たのである。
役人は死体に縄をかけたらしく、その縄の一端をつかんで、死体を引きずり上げている。啓吉はその死体を一目見ると、悲痛な心持ちにならざるを得なかった。ギリシアの彫刻で見たある姿態のように、髪を後ろざまに垂れ、白蝋のように白い手を、後へ真っ直ぐに反らしながら、石段を引きずり上げられる死体は、確かに悲壮な見物であった。ことに啓吉は、その女が死後のたしなみとして、男用の股引をはいているのを見た時に悲劇の第五幕目を見たような、深い感銘を受けずにはいられなかった。それは明らかに覚悟の自殺であった。啓吉は暗然として、にじむ涙を押さえながら顔を背けてそこを去った。死体をまざまざと見た見物人は、もう自分たちの好奇心を充分満たしたと見え、思い思いにその場を去りかかっていた。
啓吉も、来合わせた電車に乗った。が、その場面はなかなかに啓吉の頭を去らなかった。啓吉は、最も不幸なる人々が、死後においても、なお晒し者の侮辱を受ける事を憤らずにはいられなかった。
ふと啓吉は、今日見た場面を基礎として、小説を書こうかと思いついた。それは橋の上の群衆が、死者を前にして、盛んに笑っているうちに、あまり多くの人々を載せていた橋が、その重みに耐えずして墜落し、いままで死者を嗤っていた人たちの多くが溺死をするという筋であった。が、よく考えてみると、啓吉自身も、群衆が持っていたような、浮いた好奇心をぜんぜん持っていなかったとは、言われなかったのである。
※菊池寛(1948年没)「死者を嗤う」を、涌井が部分的に省略・語の置き換えをしたものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
