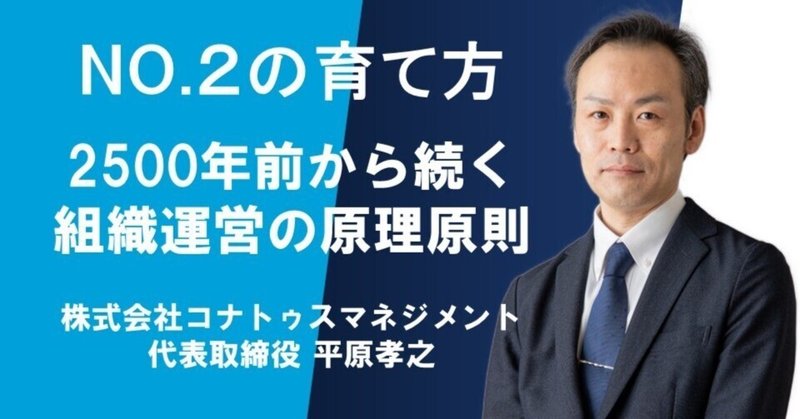
NO.2の育て方 vol.65 2500年前から続く組織運営の原理原則
孫子の兵法は、多くの方がご存じのとおり、今から約2500年前に記された中国の古典的な兵法書です。
その中の計篇という章に登場する、戦争における勝敗を決める要因に五事七計という概念があります。
なぜ孫子の兵法は今も読み継がれるのかという素朴な疑問への答えとして、今回は組織運営の原理原則である五事七計についてお伝えしたいと思います。
※孫子の兵法の本文に、現代経営での事象に置き換えて解説しています。
■五事七計とは
五事とは、自軍の戦力を検討するための五つの基本原則で、道・天・地・将・法という項目からなります。
道:民と君主が気持ちを一つにしているか(ビジョンや理念の合致)
天:天候・季節の利があるか(市場やタイミングの合致)
地:地の利があるか(事業領域)
将:兵を率いる人物が優れているか(ナンバー2の有能さ)
法:組織のルールがしっかりしているか(仕組みや制度の構築)
七計とは、自国と敵国の力量を比べてその優劣を求めるための七つの指針で、主・将・天地・法令・兵衆・士卒・賞罰という項目からなります。
主:どちらの君主の政治が良いか(社風や経営システム)
将:どちらの将軍が有能か(ナンバー2の優劣)
天地:どちらが天の時と地の利を得ているか(市場でのポジション)
法令:どちらの法が公正に執行されているか(秩序や規律などの制度)
兵衆:どちらの軍隊がより強いか(能力の高い人材)
士卒:どちらの兵士がより訓練されているか(人材育成)
賞罰:どちらの賞罰が公正に行われているか(評価制度)
相手と比較して自国が劣っていると判断するのであれば、積極的な交戦は避けて、和睦や他の諸国との合従により牽制するなどの打ち手を考えることになります。
これらの概念は、戦争だけでなく、もちろん現代経営にも応用でき、特に、社長とナンバー2という組織の中で重要な役割を担う人物同士の関係性について考える際に参考になります。
社長とナンバー2は、組織を率いる将であり、主でもあります。そのため、五事では道と将、七計では主と将に注目する必要があります。
まず、道とは、民と君主が気持ちを一つにしていることです。
これは、組織内で社長が打ち出した経営理念やビジョンを社員が共有し、一致団結していることに相当します。
また、社長とナンバー2との関係性においても、ビジョンを基礎として社長とナンバー2が信頼し合い、協力し合えば、組織全体もその影響を受けて士気が高まります。
逆に、社長とナンバー2が対立したり、意見が食い違ったりすれば、派閥を作るなどして組織全体もその影響を受けて分裂や混乱が起こります。そのため、道は組織の成功のために最も重要な要素です。
進むべき方向性を示した経営理念やビジョンがなければ、何によって集団を結び付けるのでしょうか。
ここ数年、パーパスといった理念経営への回帰が叫ばれていますが、孫子の兵法の著者である孫武からすれば「2500年も経ってまだそんなこともしていないのか」とお𠮟りを受けそうです。
次に、将とは、兵を率いる人が優れていることです。これは、組織を率いるナンバー2が有能であることに相当します。
ナンバー2は、孫子の兵法における将の条件である智謀・誠実さ・思いやり・勇気・威厳を備えていなければならず、社長が決めた組織の方向性に基づいて、戦略を立て、実行する責任があります。そのため、将は組織の成果のために必要不可欠な要素です。
一人の人間にできることなど限りがある。孫子の兵法はそう気づいていたのでしょう。
一国の王が敵国に勝つために作戦を練り、戦場で先頭に立ち、練兵した兵を率いて戦い、勝利を収めることなどできないとわかり切っていたのだと思います。
さらに、主とは、どちらの君主の政治が良いかです。
これは、組織を統治する社長の経営が良いかに相当します。社長とナンバー2は、組織の文化や価値観を形成し、組織内外のステークホルダーとの関係を築く役割があります。そのため、主は組織の信頼性や持続性のために重要な要素です。
組織はなんのために存在するのでしょうか。
売上利益を増やし、事業規模を大きくすることだけが目的なのでしょうか。売上利益を確保するのは組織を運営していくための手段でしかないはずです。
少ない人数であっても社員がいて、お客様がいれば、それはもう立派な組織ですから売上利益以外のことも真剣に考えなければ存在意義のない人の集まりでしかないことになってしまうと思います。
最後に、将とは、どちらの将軍が有能かです。これは、組織を指揮するナンバー2の能力が高いかに相当します。
社長とナンバー2は、七計で挙げられた他の項目(天地・法令・兵衆・士卒・賞罰)をうまく活用できるかどうかが問われます。そのため、将は組織の競争力や優位性のために決定的な要素です。
仮に主である社長が優れていても、あらゆる状況や条件を鑑みて、思う通りに物事を進めるというのは難しいと思います。
社長は方向性を示すのが大きな役割であり、その社長には現実に起きる障害を乗り越えて構想を実現してくれる実行役が必要です。
以上のように、孫子の兵法の五事七計は、社長とナンバー2の関係性について考える際に有用なフレームワークです。
社長とナンバー2が五事七計を理解し、それぞれ自分自身や相手と比べて強みや弱みを把握し、補完し合えば、組織はより強くなります。
ーーーーーーーーー
ナンバー2の存在など不要と考える社長も世の中には多いものです。将を持たない社長である主は五事七計を踏まえた経営はできないと私は思います。
一人で経営戦略を考え、現場に命令し、制度を整え、社員を育て、評価する。
言葉で言うのは簡単なことですが、果たして全てできるものでしょうか。少なくとも私には無理です。
ナンバー2育成支援事業などしていると、さまざまなお考えの社長さんのお話を伺う機会がもちろん多いです。
「ウチは従業員数が少ないからナンバー2なんて大袈裟な存在はまだまだ不要だよ」
少人数でも社長一人でやり切れないのが現実だと思いますし、一人で抱え込んで課題に目を背けていないでしょうか。
「社員数は多いけど、自分で全部できてるから問題ない」
本当に全部できているものでしょうか。業績だけは良いことを理由に、社員の本当の声を聞かないようにしたり、課題に目を瞑り、先送りにして自分を正当化していないでしょうか。
孫子の兵法に限りませんが、古典というのは不変の原理原則が存在し、時間と言う洗礼をかいくぐって今に語り継がれているものですから、原理原則を無視したやり方では組織は持続しないのではないかと私は思います。
なぜ2500年前からトップとナンバー2という組織上の役割分担を明確に示した五事七計という考え方が今もなお多くの経営者の心に響くのか。
そうした事実に目を背けてはいけないのではないでしょうか。
ご興味ありましたら孫子の兵法はじめ古典の中に組織運営の不変の原理原則を見つけてみるのも良いかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
ナンバー2育成のノウハウが詰まった「ナンバー2育成ガイドブック」の無料ダウンロードは下記サイトからできます。
自社のナンバー2人材や将来の候補者の育成などのお悩みがありましたら
ぜひお話をお聞かせください。
noteユーザー以外の方のお問い合わせはこちらから↓
