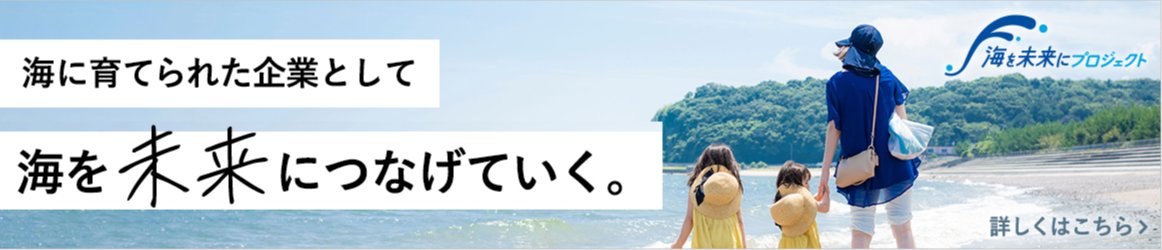空を見れば、魚がどこにいるかわかる。世界初のバードレーダー開発物語
プロローグ|このナブラはふとかぞ!
まるで滝のようなスコールが途切れ始めた。船は雨域から脱出しようとしている。視界は依然閉ざされたまま。時刻は16時を回ろうとしていた。
魚群探知機、スキャニングソナー、潮流計、プロッター・・・ぎっしりと電子機器が並んだブリッジの中で、漁労長、通信局長を中心に数人のスタッフがひとつのレーダーモニターに眼を凝らしていた。
ブラウン管には南東に進路をとる船首の真正面に、厚い雨雲を通して30羽から40羽のカツオドリの一群が捉えられている。
「ヨーソロ4.8マイル」
スコール圏の端、ちぎれ雲のように見えるひとつの輝点を確認する声がする。もう間違いない。
「あと15分、このナブラはふとかぞ!」
マイクを通じて漁労長が船の隅々に届く。ブリッジのスピーカーから持ち場持ち場の「準備よし」という海の男たちの声が間髪入れず跳ね返ってきた。
豪快なカツオの一本釣り、海の遭遇戦が始まる寸前の緊迫した瞬間である。
海の中にいる魚を空から探すレーダーシステム
『魚は海のどこにいるだろう・・・?』
そんな課題を解決する機械として魚群探知機やソナーをこれまで古野電気は開発してきました。しかし、これらの機器は船の周囲しか見ることはできず、広い海の中で魚群を探すためには船を走らせる必要があります。
今回はそんな課題を異なるアプローチで解決したユニークな製品を紹介します。
かつてより、カツオやマグロを狙う漁船の乗組員は交代でアッパーブリッジに立ち、片時も双眼鏡を離さずに血眼になって海面を見ていました。探していたものは"カツオドリの群れ"です。
カツオやマグロといった高速で大型の魚は、獲物である小魚を追い上げ、小魚は海面近くに分厚い魚群を形成します。これをナブラと言います。
そしてその上空には追い上げられた小魚を狙って急降下するカツオドリの一群が集まっています。つまりカツオドリは漁場を知らせる大海原の標識となるのです。

しかし、全周360度、海と空だけの世界で揺れる船の上で遠くの鳥の群れを見つけるというのはどんなに過酷な作業なのでしょうか。当然雨で視界が遮断されたときはどうしようもありませんでした。
そんな従来の漁法を大きく変えたのが1986年(昭和61年)にフルノが世界に先駆けて発売したレーダーシステム「海鳥探知機」です(現在の名称は海鳥レーダー™)。
この製品の開発の背景には海という舞台で様々な開発を行ってきたフルノらしい情景がありました。

※「海鳥」は古野電気株式会社の登録商標です
失敗の中に見えた光明
「レーダー波は相手が金属じゃないとつかまらない、というのが通説でした。ですが魚群探知機を開発したときだって"魚は超音波には映らない"といろんな方から言われたものです。私はこういうものを"円満なる常識"と言って打ち破ってきました。
双眼鏡で水平線を見ている漁師さんの苦労を知っていたら、黙っちゃおれません。フルノには世界一になった船舶用レーダーの基礎技術があるのだから。」
古野電気の創業者である古野清孝氏は当時の取材にこのようなコメントを残しています。
ことの始まりは1985年7月11日、北海道釧路港の岸壁から始まります。2人のエンジニア、箟氏と小林氏がこの海域で荒天用レーダーの実験を行っていました。しかしその実験結果は「他船の探知不十分」と、残念ながら失敗の部類に属するものでした。
しかし一方、レーダーは宙を飛ぶ"かもめ"の姿を捉えていたのです。これが、後の画期的な発明として実を結ぶ「海鳥探知機」開発のスタートでした。
翌年の年明け、とある水産会社の社長と漁労長がフルノ本社を訪れていました。そしてフルノの副社長が会社を案内している際、デスクでレーダーの映像写真を整理していた小林氏のところを通りかかり、"かもめ"が写っている写真を目にしました。
3人は直感的に「これはいける」と感じ、ぜひ実現したいと正月早々から大いに盛り上がったといいます。そして荒天用レーダーの試作機を装備し実験協力していただいていた31日光丸に、海鳥探知の実験を依頼しました。
そして1月27日、実操業中の31日光丸から短い電文が届きます。
当初、船頭も船長も、そして乗組員も皆、このレーダーには期待を寄せてはいませんでした。むしろ、妙な実験を押し付けられた感すらあったようです。
箟氏と小林氏も「使い物にならない」と連絡が入るのではないかと心配していました。
ですが入電文には「商品価値は最高と称賛する・・・・・、船頭」とあったのです。両者が歓喜の声をあげたことは言うまでもありません。

大ヒット製品は船の形をも変えてしまう
この海鳥探知機の登場によって、漁船の装備状況は一変しました。海外まき網船、遠洋カツオ船のメインマストの形状は変わり、スタンド付きの大型双眼鏡がはずされました。そして雨や霧の中でも鳥の探索が可能となり、漁の形そのものを大きく変えてしまったのです。
現在では海鳥探知機は漁船の必須アイテムとなっています。
これまで一定の漁獲量を確保するために必要な航海の期間に2ヶ月かかっていたものが、この海鳥探知機の装備によって効率化され、半分の期間の1ヶ月ですむようになったと現場からも喜びの声があったそうです。
海鳥探知機は、発売直後から大ヒットを続け、1988年2月期、フルノが売り上げ400億円の大台を突破した業績のひとつの大きなテコとなりました。