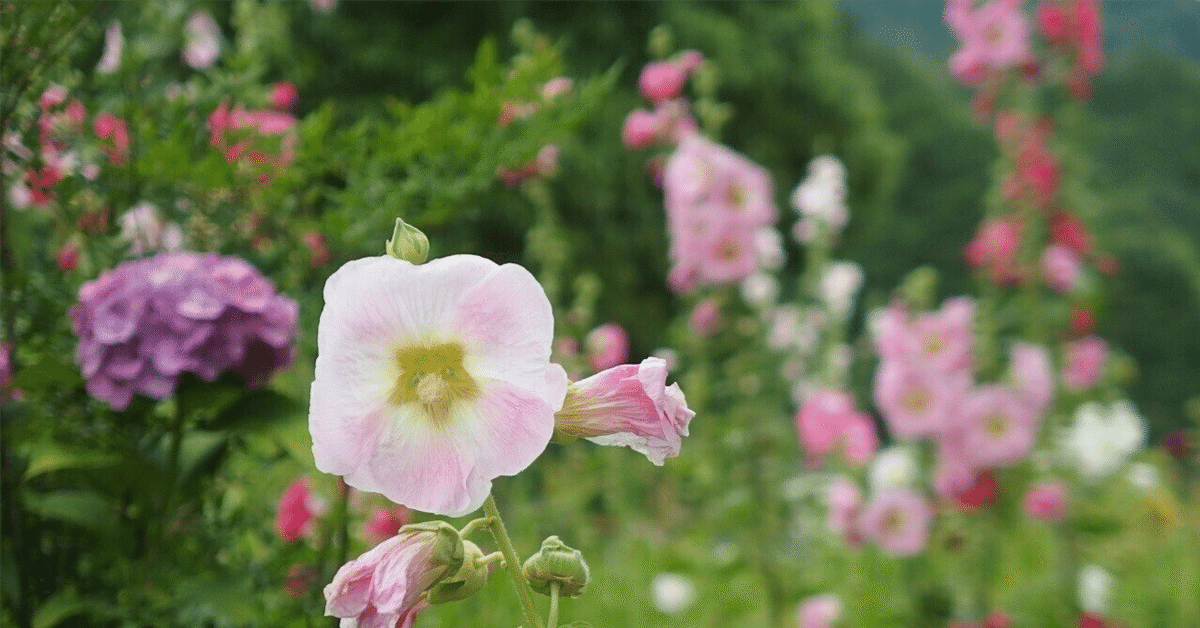
第1章:仮説の提唱者の紹介
<ドナルド・ウィリアムソン博士について>
リン・マーギュリス博士が提唱した連続細胞内共生説によれば、原核生物にα-プロテオバクテリアが、藍藻が、そしてスピヘロータが、その原核生物の体内に取りこまれて、それぞれミトコンドリア、葉緑体、鞭毛といった細胞内小器官(オルガネラ)として共生するようになったという。しかも、ミトコンドリアと葉緑体には、環状二本鎖のDNAが存在し、核とは独立した遺伝システムを有している。つまり、真核生物の祖先は、ミトコンドリアや葉緑体を獲得したと同時に、これらの遺伝子をも取り込んだことになる。こうして、真核生物は、ミトコンドリアを獲得して酸素呼吸と多量のエネルギーの消費が可能になり、植物では、葉緑体の獲得で、光合成による栄養の獲得が可能になったのだという。
対象はいきなり変わるが、海辺に行くと岩礁などによく見かけるフジツボは、卵から生まれた時は遊泳する幼生だが、変態を遂げて堅い殻を持った成体になり、一ヶ所に固着する。両者は知識がなければ、別々の動物にしか思えない。類似点がないからだ。このような個体発生がどのようにして成立したのだろうか。突然変異や遺伝子頻度で説明できるのだろうか。
突拍子もない発想だが、真核生物の祖先がミトコンドリア等の細胞内小器官の源を獲得したように、フジツボが“幼生”を手に入れた、と考えてみるのはどうだろうか。つまり、
“幼生”を手に入れる前:卵 ⇒ 成体のミニチュア ⇒ 成体のフジツボ
“幼生”を手に入れた後:卵 ⇒ 幼生(遊泳できる)⇒ 成体のミニチュア
⇒ 成体のフジツボ
ということである。この考えを提唱したのは、リバプール大学海洋生物学研究所名誉教授のドナルド・ウィリアムソン博士である。
<幼生転移>
博士は、種の異なる動物のみならず、系統の離れた動物同士で、遺伝子の移動があり、幼生の形はその結果獲得できたものではないか、と考えた。フジツボに例えれば、遊泳する子供は元々フジツボとは関係のない別の生物で、フジツボは、生まれた時から一ヶ所に固着する堅い殻を持った生物であったが、この両者の精子と卵が受精して子孫を残せる、いわゆる雑種形成の機会に恵まれ、孵化したときは、遊泳する子供の形をしているが、変態後は固着して生活するフジツボになった、ということになる。遺伝子のレベルで説明すると、フジツボの体内で、幼生の形を作る遺伝子が発現し、その結果幼生の形が作られ、フジツボの幼生世代の姿になったと説明できる。ウィリアムソン博士は、フジツボのような子供と大人の姿形が著しく異なる動物について、成体の世代と幼生の世代という二つの世代が別々の生物に由来しており、この別々の生活史が合体したキメラであると考えた。例えばフジツボでは、
卵 ⇒ 幼生(遊泳できる) ⇒ 成体
元々フジツボの世代(卵) ⇒ 手に入れた“幼生”の世代 (遊泳できる幼生) ⇒ 元々フジツボの世代(成体)
というようになる。フジツボの一生の中で、別々の動物の生活史が出てくるのである。博士は、こうして“幼生”を手に入れた動物は、それぞれが違った進化の道程を歩み、棲家や餌を巡る生存競争から解放されて、新しいニッチを獲得していったのではないか、と考えた。博士は、この幼生獲得の一連の生命現象を幼生転移(larval transfer)と名付けた。
<ウィリアムソン博士の経歴>
博士は、元々は甲殻類、とりわけ、エビ・カニの分類を専門とする研究者であった。幼生の形態形質を丹念に比較し、エビの研究においては、クルマエビやイセエビ等従来から知られていたエビの仲間とは異なるエビを発見し、これをアンフィオニディウム目という新しい目として定めた。カニの研究においては、Dorhyncus thomsoni等の子供であるゾエア幼生を、系統的に近い仲間のゾエア幼生と比較し、成体の形のみを観察した場合とは異なる結果の分類になることを、欧文雑誌に発表した。博士の幼生転移についてのアイディアは、ゾエア幼生の研究に関する論文から始められている。彼の幼生転移についての論文は、このカニ・エビを中心とした甲殻類の幼生の形態比較から始まり、やがて、理論の適用範囲は、ウニやヒトデ等の棘皮動物、トロコフォア幼生を持つゴカイ等の環形動物やアワビ等の軟体動物にまで拡張された。彼は、論文等で発表されている過去の知見そして自身の分類における研究成果を踏まえて理論の可能性を考察するだけに留まらず、自らウニとホヤの卵および精子を受精させ、生まれた雑種がどのような発生をするのか、について実験し、雑種の発生の観察を行った。これについては、彼が1992年に出版した書籍“Larvae and Evolution - Toward a New Zoology - ”に書かれている。しかし、これ以降、彼は遺伝子工学的手法や免疫化学的手法を駆使して実験を発展させることはなく、知識を蓄積し、動物の進化における幼生転移の正当性を主張する論文を発表し続けた。長年にわたり、精力的に持論を展開したが、2016年1月、病を得て昇天した。
<ウィリアムソン博士への評価>
博士の幼生転移の理論は、面白さばかりが先行し、科学的には高校生レベルの戯言、あるいは、彼自身が単に変質的な科学者であるだけ、といった批判が少なくなかった。しかし、彼と同じ研究所に勤務している藻類の研究者であるトレバー・ノートン博士は、E・ヘッケルの業績に匹敵する生物学者である、と博士を評価する。ノートン博士によると、博士は、一言で言えば19世紀にいたような無脊椎動物の専門家であり、免疫化学や分子生物学といった現代的なテクノロジーを駆使することなく、徹底的に実験動物を観察し、動物間の系統関係を重視し、直感的に物事を理解することに優れ、巨視的に物事を見ることができる稀代の生物学者であった、とのことである。
使用文献
細胞の共生進化 リン・マーギュリス著 永井 進訳 学会出版センター 2004年
Larvae and Evolution Donald I Williamson著 CHAPMAN&HALL 1992年
サポートは皆様の自由なご意志に委ねています。
