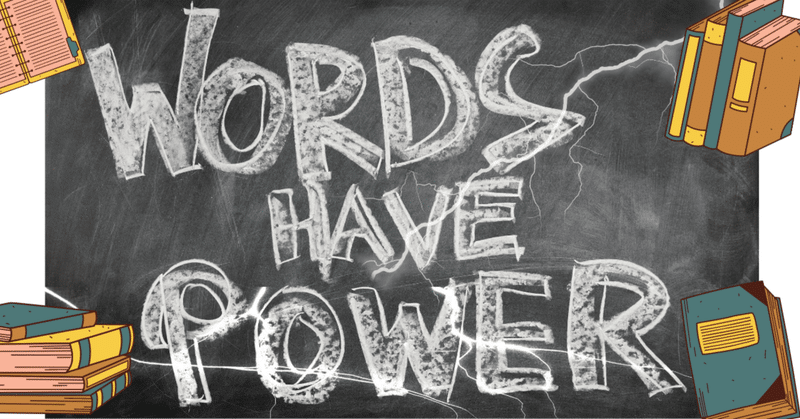
言霊の「呪い」
「推し」、という言葉を素直に使えない。
ご推察の通り、筆者の性格が捻くれているからである。
このnoteを定期的に愛読していただいている傑出した審美眼をお持ちの読者諸賢には改めて解説する必要もないだろうが、どれぐらい性格が歪曲しているかというとセブンイレブンの『カリカリコーン』ぐらい捻れている。

(ちなみにこの『カリカリコーン』ぐらい性格が捻れているという、パンチ力に欠けるショボい比喩を思い付くまでに30分ぐらいかかった。)
筆者は無駄に高慢なプライドと過剰な自意識を抱え込みながら生活しているので、安易に大衆には迎合したくないという生意気な願望があるのだ。いやはや救えないねェ~。
しかしそれにしても最近、急に出現したと思ったらいつの間にか大衆から支持されて市民権を得たものが多すぎやしないだろうか。
「推し」という言葉然り、「ちいかわ」然り、「MBTI診断」然り。さも当たり前かのようにいろいろなメディアで取り上げられたりフィーチャーされたりしてるのを見ると、いつの間にそんなメジャー化したんだ?という疑問が沸いてくる。
まあ単純に僕が流行に疎すぎるのも要因としてあるのだろうが。
僕には昔から流行というか、世の中がよく使用するインターネットスラングみたいなものを忌避したがる傾向があるから、そうなってしまうのも仕方ないのかもしれない。
インターネットの世界には小学生ぐらいの頃から入り浸ってはいたものの、なんだか本能的に所謂ネット用語みたいなもの(「イキる」とか「チー牛」とか)に対しての嫌悪感があって、現実では極力使わないようにしていた。
それでもたまに、臭いものは逆に嗅ぎたくなるみたいなアンビバレントな感情が作用して匿名掲示板みたいなサイトを閲覧してしまうこともあったけど。
そういう経緯があったからかどうかはわからないが、僕の人格はまっすぐ育たず、歪にカリカリコーン化してしまったのだ(ちょっと何を書いているのかわからないと思うが、僕も自分が何を書いているのかわからなくなってきたので安心して欲しい)。
まあネットスラング常用者からすれば「異端者気取り乙w」みたいなことになるのだろうが、そう感じてしまうのは本当なんだから仕方がない。
インターネットヘビーユーザーから異端者気取りだと指摘されかねない事案は他にもある。
それは「彼女」「彼氏」「恋人」などの、恋愛に関する呼称を素直に使えないことだ。
これらの言葉はネットスラングでも何でもないただの公用語だが、哀しいことに筆者の性格がカリカリコーン(腐ったチーズ味)過ぎるがあまりに、これらの言葉を使うことに対してさえ謎の抵抗があるのだ。
自身で使うのはもちろんのこと、あまつさえ自分の親がこういう言葉を言ってるのを聞くとありえないぐらいの悪寒に襲われる。恣意的に吐き気を催して40℃ぐらいの高熱を出したくなる。想像しただけで気持ち悪くなってきた。ヴォエ!!🤮
実際将来的に自分がそういう色事の当事者になり、結婚云々の話まで進んだときに肉親に表面的な部分だけだとしてもそういう話をしなければならないと思うと反吐が、ウッ、オボロロロロロロロロロロロロ!!🤮ハァ……ハァ……。胃酸臭くしてしまって申し訳ない。読者諸賢には今この記事を読んでるスマホかパソコンかの画面に向かってシュッとひと吹きファブリーズでもかけてもらってですね、とりあえず話を進めよう。
親が「早く彼女作って結婚しろ」みたいなことを言ってくるのがどれだけ嫌かというと(結局話進んでない)、羞恥心の度合いで言えば『クレヨンしんちゃん』がよくやる例の体勢で尻の穴を公衆の面前に開示した方がまだマシなぐらい嫌だ。
親とそういう恋愛だの結婚だのの会話をしなければならない状況が発生した時、たとえ極限まで事務的な会話に落とし込めたとしても何か別の選択肢を取ることでその状況を回避出来るなら迷わずそうする。
「親と恋愛や結婚絡みの会話をしたくないなら『クレヨンしんちゃん』がよくやる例の体勢で肛門を限界まで拡張させながら渋谷のスクランブル交差点を闊歩しろ、そうしたら許してやる」と言われれば何の躊躇もなく渋谷スクランブル交差点を半ケツ出しながら渡りきり、デジタルタトゥーを遺すことを選択するだろう。

…………。真面目な話に戻そう。
僕が「彼氏」「彼女」という呼称になんとなく抵抗があるのは別に性差を感じさせるからだとか、時代背景的に「パートナー」という風に呼称を変えた方がいいと思ってるからとかではない。僕はジェンダーの時代の申し子でも何でもないので、そこまで思慮分別があるかのような主張を唱えるつもりはない。
だから別に他人が「彼女」「彼氏」とか言うのは構わないというか、それを許容しなかったら普通に生きていけないから認めざるを得ないんだが、やはり自分がそういう言葉を使うとなると得体の知れない気持ち悪さが生じてしまう。
この気持ち悪さの根源って何なんだろう。男子校で思春期を過ごした弊害だろうか。異性に関する精神的な障壁が生じてしまうのはとりあえず男子校の所為にしとけば良いみたいなとこあるからな(ない)。
日常会話においても素直に「彼氏」とか「彼女」とか使いたくないから、同期の野郎連中とかと会話する時も「お前最近彼女いるのか?」と聞かれたら「いや、『恋慕の情を抱く対象者』はおらんなぁ」とか答えたくなる。
まああまりにも異端過ぎるから流石にそうは言わないけど。ただそのフレーズを発せず「おらんなぁ」と答えるだけ。
若い女性とかと会話する時も「彼氏とかいらっしゃるんですか?」ではなく「あなたが会うと突然テトラポットに登っててっぺん先睨んで宇宙に靴を飛ばしたくなるような存在っていらっしゃいますか?」と聞きたくなる。
「aikoのボーイフレンドの歌詞をなぞらえることでしか『彼氏』という存在を表現出来ない病に罹患しているのか?」と思われる可能性が高いけど。
というかそもそも、そういう会話をする女性相手がいないので杞憂に過ぎないんだが。
いや、でもよくよく考えたら「彼氏いるんですか?」みたいなストレートな質問がご法度なこの時代こそさぁ、逆にそういうワケわかんない聞き方したら許されるんじゃないかみたいなトコあるよな。歌舞伎町のホストとかに積極的に使ってもらって流行らして欲しいわ。セクハラ臭が軽減される(ような気がする)し、もしかしたら画期的な発明してしまったかもしれん。
あと、少し話題が逸れるがそういう性の関連で、卒業必要条件の単位を満たすために大学で性同一障害について学ぶ講義を履修してたことがあるんだけど、そのテキストを家に持って帰った時にそれを見た親が半狂乱になって「これどういうこと!?」と問い詰めてきたのがすごく腹立たしかったのを思い出した。
俺自身はノーマルなタイプだから当事者には該当しないけど、もし仮に俺が性同一障害だったら半狂乱を通り越して発狂したのかよとか、そもそもそういう態度を取ることが渦中で悩んでいる人たちに失礼過ぎるんだよなぁ、と思ったのを覚えている。
きっと子のありのままの姿が自分の希望と合致していないことが許せないんだろう。放任主義の真逆、過干渉の属性を持つ親は子が自分の理想通りの道を歩まないと矯正したがるのだ。
まあしょうがないんだよ、そういう人間なんだから。
俺が中学2年生ぐらいの頃に図書館から伊坂幸太郎の『死神の精度』借りて読んでた時も俺の部屋の机の上に置いてあるその本見つけて「ちょっとアンタこれ死神って何!?なんかヤバいモン読んでるんじゃないでしょうね!?」とかいう見当違いも甚だしいイチャモンつけてきたもんな。
「死神という文言=悪」みたいな、お前の過剰な先入観の方がよっぽど不躾だろうと思ったけど。もう10年以上も前のことだが今でも余裕で怒りが収まらないし、思い出す度に腸が煮えくり返りそうになる。
こういう母親の過干渉エピソードを知人に話すと結構笑われるんだけど、こっちは至って真剣に悩んでいるからなんだか腑に落ちない。まあその場の空気が重くなりすぎないように俺が可能な限り諧謔的な表現で伝えてるっていうのもあるけど。
懇々と説教してる時に平気で爆音の放屁をする(※事実)とか、無駄に深夜3時ぐらいまで起きて録画したドラマとか観てるからバレないように夜更かししてあんなことやこんなことをするのが一苦労だとか、そういう風に茶化していかないとどんどん気分が沈んでいってしまう。ああ嫌だ嫌だ。もう親の話はいいや。
そういえば余談だが、伊坂幸太郎氏の作品に登場する孤高の雰囲気を纏う泥棒「黒澤」という人物も俗語を使わないキャラクターだった気がする。
彼が「やばい」という言葉に対して「やばいって何だ?野梅のことか?」と言ってたのは『ラッシュライフ』だったっけか。結構前に読んだから記憶が曖昧だけど、そのシーンだけ異様に覚えてんのも僕の中に俗語に対する忌避感が深く根付いていることの証左なのだろう。
「陰キャ」、というのもあまり使いたくない俗語のひとつである。正直一番嫌悪感のある俗語かもしれない。自分自身がそれに該当することを認めたくないからだろうか。
カレー沢薫氏による名エッセイ『非リア王』という本があるけれど、その中で氏は「陰キャ」は「非リア充」などの用語に比べて直接的すぎると述べている。
氏曰く、「非リア」とかはただ恋人……いや、その人にとっての恋慕の情を抱く対象者がいないことを意味するだけで、状態を指したものだからまだ秘めたる可能性を感じられるけども、「陰キャ」という言葉は最初から気質が陰気であると断定されてしまって広がりを感じさせないという。
僕はこの考え方に全面的に賛同である。
なんか安易に「陰キャ」って言いたくないんだよな。
多分自分の中に生意気にも「俗世的なものに取り込まれたくない」という欲望があるのだろう。
まったくコイツはプライドだけ一丁前の何も出来ないカスの癖して偉そうなことばっか書きやがってよ(※当noteの筆者は時折、心の闇に潜むもうひとつの人格に自我を乗っ取られるので唐突に自身の文章をセルフ批評することがあります)。
実際「推し」を解説してるWikipedeiaにも「推し」という言葉は「俗語」だって書いてあるしね。
と、ここまでゴチャゴチャほざいてきたが、自身が過去に書いたnote記事を見返してみると結構な頻度でスラング系のワードとか使ってて草生えすぎて森。
まあ世の中には完璧な人間なんていないんだしそういうこともあるわな。
ここで無理矢理オチがついたことにして記事を終了させてもいいのだが、驚愕すべきことに当初書きたかったテーマというか、本題にまだ入れていない(いやスクランブル交差点のくだりとか途中で省略出来る部分いくらでもあっただろ)。
本題に入ろう。
今回の記事で書きたかったのは、タイトルにもあるように「言霊」についてである。
一般的に「言霊」とは、言葉に内在する霊力のことを意味する。古代から、言葉には発した言葉通りの結果が表れる力があると信じられていた。
この「言霊」の概念を最初に教えてくれたのは、僕が小学5年生の時の担任の先生である。
その先生は年齢が50代後半ぐらいの厳格な感じの女性教師、みたいな感じで、普段の生活態度にはもちろんのこと、言葉遣いにも結構厳しかった。
たしかクラスメイト同士が喧嘩をして「ウザい」とか「キモい」とか言い合っていたのを聞きつけた時に、「コラッ、気安くそういう言葉を言うんじゃありません!いいですか、言葉には『言霊』というのがあってですね……」と説法をし始めて、そこで僕は初めて『言霊』という概念を知った。
僕はその時はまだ年端も行かない子どもだったから、幼心にも『言霊』の力というものを強く信じた。
言葉は、人を勇気づけたり励ましたりも出来る反面、容易く傷つけてしまうこともある。
「ありがとう」などの言葉は人を温かい気持ちにするし、その言葉を発する自分自身にも何らかのポジティブな恩恵がある。
しかし、「ウザい」だとか「キモい」だとかいう、否定的で人を傷つけかねない言葉は必ず自分に良くない形で返ってくる。
それが『言霊』の恐ろしさだと先生は説いた。
かなり熱を込めて力説していたのでよく覚えている。
まあ他の生徒は軽く聞き流してたけど。
そんな先生が、「ウザい」とか「キモい」以外にも、生徒が発すると強い拒否反応を示した言葉がある。
それが「かわいそう」という言葉。
先生はとにかく「かわいそう」という言葉を嫌っていた。
「かわいそう」という言葉は、「とにかく上から目線だから」ということである。
多分一番わかりやすい例が、発展途上国とかにいる貧しい子どものことを「かわいそう」って言うのは失礼だからやめろ、みたいなことだ。
これは先生が言ったのかどうか覚えてないけど(なんせまだ子どもだったから)、「かわいそう」というのは「自分じゃなくて良かった」という意味をも内包するし、安全圏からものを言っているような印象がするから使うなっていう趣旨だった気がする。
『ハリー・ポッター』を知ってる人ならわかると思うけど、先生は「かわいそう」という言葉を「穢れた血」ぐらいのセンシティブな言葉だと捉えていた。
僕はその先生の教えがものすごく克明に脳裏に焼き付いている。何故大人になった今でもこのことが印象強く記憶に残っているのかというと、それはおそらく「かわいそう」という言葉が善意で使われる場合がほとんどだからだろう。
大人になるにつれて徐々に気付いていったが、大抵の人間は「かわいそう」という言葉を使う場面に際して、いちいちそんなことは考えていない。
かくいう僕の母親も「かわいそう」を常用する類の人間なんだけど、本人は何の悪気もなくほぼ条件反射的に「かわいそう」を連呼している。
凄惨な事件のニュースなどを見てる時なんかに、被害者に対して「かわいそうだね~」と言う。
母親だけではなく、その他大勢の人間も悲しい出来事の当事者たちに対して「かわいそう」だとよく言う。
もちろん本人は100%の良心に起因する「かわいそう」を発しているつもりなんだろうが、小さい頃に『言霊』の教えを叩き込まれた側からすると、どうしても「あっ、この人は『かわいそう』を言うタイプの人なんだな」というフィルターを通して見てしまう。
言わば「呪い」だ。どれだけ純粋に性格が良い人でも「かわいそう」という言葉を使った時点で、その人は僕の中で勝手に「『かわいそう』を言うタイプの人間」に分類されてしまう。
そのように一元的に人間性を決めつけてしまうのは良くないことだとはわかっている。
「かわいそう」という言葉を発するという事実だけで人間性は判断出来ないし、そこには善意を善意のまま受け取れなくなってしまう危険性があるのも確かだ。
しかし、『言霊』の呪いは強力だ。
だから僕は小学校の頃から「かわいそう」という言葉を言ったことがない。正直「かわいそう」という言葉を使用しないことが果たして善なのか悪なのか、その是非は未だにわかっていないけれど。まだ自分の中ではっきりした答えは出ていない。
使うべきか使わないべきか逡巡してしまうような言葉が、世の中にはたくさんある。
僕の使える言葉が制約される、それが『言霊』の呪いなのだ。
今までも、そしてこれからも、僕は『言霊』という呪いを背負って生きていく。
きっとそういう宿命なのだろう。
最後に、途中で不要な脱線を挟みまくるこの記事をなんとか最後まで読み進められた読者諸賢の驚異的な集中力に敬意を表し、感謝の言葉を述べさせていただく。
ありがとうございました。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

