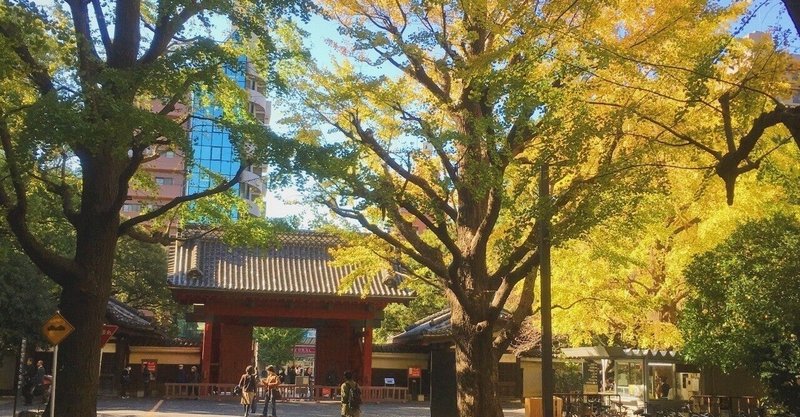
大学院生が自分の研究の価値を高めるためには
大学院生が自分の研究の価値を見出すためにはどうしたらよいのでしょうか?そもそも価値の定義とは?という問題もあるので、答えは1つではないでしょうが、本質的に意味のあるものにできたら研究のモチベーションも上がると思います。
先週、大学院生の研究の意義について思ってることを少し書きましたが、大学でやってる研究で世の中の多くの人たちの役に立つのはとっても難しいことです。
自分の研究に価値を高めるためには
ソフトウェア分野ならまだしも、私たち材料屋はものを作らないといけないわけで、基礎の研究領域で生産や流通、金回りまで考えている学生はいないと思います。
世の中に届かないのならどうすればよいのでしょうか?
そこで大事になるのがものごとの一般化です。自分の研究をもう少し広い分野に生かせるように現象を一般化して考えないといけないと思います。
例えば鉄の研究をしていて新しい現象を見つけたら、それで終わりではなくて、鉄以外の金属でも同じことが言えないか考えてみるわけです。金属でいけたら金属以外にも利用できないか考えます。
おそらくこの行為が考察と呼ばれるものの1つになるのでしょう。
修士の頃は結果が出ればいい、自分は研究者ではないから考察なんて意味がない(頭いい人が考えてくれればいい)と思っていましたが、最近では馬鹿でも考えないといけないんだな~とつくづく思います。
考えないといけないというよりは考察をすることに意義があるということですね。つまり考察をしない研究は先週書いた悪い例:やりました→できましたで終わってる研究なんですよね
やりました(実験)→できました(結果)→ほかのことにも使えそうです(考察)。最低限ここまではやらないとダメですね。でも、こういうことってあまり教えてくれないというか、”考察はするもの”って感じで教えられるのでずっとモヤモヤしていたわけです。
理由なき学習はできないタイプの人間なので、考察はずっと大嫌いでした。最近ではその重要性を認識したので積極的に考察しますが、まだまだ苦手意識は抜けないですね...
周りから評価されるかは置いておいて、自分の研究を本質的に高めるためには全力で考察することが大事だと思います。
実験は世界を切り取る行為
最近実験は世界の一部を切り取る行為だな~と感じています。私たちは科学が発展していろいろなことがわかった気になっていますが、世の中の現象のほとんどはわかっていません。いまだに塩水の性質すらわかってないんですから
私たち人間は世界のすべてを知ることができません。それでも少しずつ理解しようと世界中の研究者・技術者が努力しています。
世界を切り取るとはどういうことでしょうか?
研究対象には無限の条件が影響しており、私たちの手には負えないような気がします。しかしよ~く見てみると実は片手に収まる程度のパラメータを考えるとおおよそ理解できるなんてことはよくあります。
リンゴが木から落ちるのに量子力学的に解く人は多分いないですよね。高校で習う重力加速度を使えばだいたいは理解できます。
科学の歴史には疎いですがお話として、ニュートンがリンゴが落ちるのを見てそれが一般化された結果、物体の運動'という幅広い領域に応用されるようになりました。つまりニュートンは世界の物体の運動をリンゴの落下という視点で切り取ったわけです。
現代のちっぽけな研究からそんな振れ幅の発見は難しいですが、少なくとも一般化することで自分たちの研究分野に対してインパクトを与えられたらうれしいですよね。自分が達成できなくても後輩や周りの研究者が広げてくれれば、それはそれで素晴らしいことだと思います。

自分の研究は世界を切り取る行為、考察は知見を少し広げる行為と思うとなんだか意味あることをやってる気になれます。
このような考え方をすると、どんなにつまらないように見える研究であっても研究者の見ている視点が違えば全然違う価値が見えてくるわけです。
最後に
ダラダラ書いていたらそこそこの文量になってきたので、そろそろまとめたいと思います。
大学院生の研究を価値を高めるためには、自分の研究を少し俯瞰した視点で見て一般化させることな気がします。その手っ取り早い方法が考察することです。(つまり理論に落とし込むということ)
今の大学院は就職予備校みたいな感じがして、こういうマインドは自分で学べ感が強いですが、個人的には正しいかは別としてこういうことを考える時間もまた大事な気がしますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
