「デジタル化」と「IT化」。DXが進まないのはそこだよねって。
枕にかえて
どうも、えんどう @ryosuke_endo です。
わかっているふりをしている人が多いのではないか。少なくとも僕は**「物事を数字で扱うことでしょ、(ドヤ」みたいな顔をすることがデジタル化でありIT化だと考えていた節がある。**
そんな話題を切り出しのは理由があるわけだが、世界有数のリサーチ&アドバイザリーカンパニーであるGartner社が出すプレスリリースは興味をそそるものが多いため、ぜひチェックしてもらいたいと思うのだが、そこへ以下のようなものが追加されていた。
Gartner、世界の人材に関する調査結果を発表 -現在の勤務先にとどまる意向が高いITワーカーはわずか29%
DX(デジタルトランスフォーメーション)だなんだと騒ぎ立てるようになって久しいが、みなさんの就労環境はどれほどまでにデジタル化され、IT化されただろう。
大半がそれほど変わっていないのではないだろうか。
変わったと胸を張れるような人たちもいるだろう。しかし大半の事業者は「DX?なにそれ、おいしいの?」状態なはずだ。実際、以下のアスクルが調査した結果を見れば呆れるほどにバッチリな回答をくれることに満足感を味わえる。
ASKUL事業・リサーチ専門チーム、全国の仕事場におけるニーズを探る「働く人のDXに対する意識と職場のDXへの取り組み」の実態調査
「内容を詳細まで知っているが3%」もいることに驚くが、「内容をある程度まで知っている」まで拡大しても13.1%ほどの認知なのである。つまり、アスクルを利用できる環境を持っている人たちですら、1割強程度の認知しか取れていないのがDXだ。
経済産業省が本格的に動き出したのが2018年であるから、すでに3年は経過している。いや、2000年頃から言われてきたことなのだから20年以上は経過しているのにも関わらず、いまだに浸透すらできていないのだから最早笑うことで許してもらおう。
▶︎ 本質的に目指すべきは「IT化」だと僕は思う
実際、2018年に研究会などを発足した経済産業省だが2020年の12月に出された中間報告で経済産業省が経過観察をしていた企業のうち、95%もの企業はDXにまったく取り組んでいないか取り組み始めた段階だったのである。
どうだろうか。これはもう笑うほかにないのではないか。

デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間報告書『DXレポート2(中間取りまとめ)』を取りまとめました
2.1 DX推進指標の分析結果_経済産業省
そもそも”デジタル化”と”IT化/情報化”との違いから認識をしなければならないわけだが、多くのビジネス現場で辣腕をふるったり汗をかいて走り回っているような人たちからすると、そんなことを考えている暇があったら少しでも数字を上げることを懸命に取り組みたいと考えているのかもしれない。
多くの場合「デジタル」と「IT」の違いも明確に区別がついているわけでもなければ、その二つの言葉に違いがあるとも思わないだろうし、どうでもいいと考えているはずだ。
▷ IT化とは情報を整理して活用する状態をつくるもの
ITはinformation technology の略語で「情報技術」だと訳されることが多い。そのためIT化は情報技術を利用した形に変容させることを指すことを想起するのが一般的だろう。
しかし、名著『コンピュータはなぜ動くのか』の著者、矢沢久雄は自著内でITのことを『情報活用技術』だと翻訳し、ただただコンピュータが導入されるようなことだけを指すのではなく、情報を整理し使いやすくするよう活用することが ITの本質であり、コンピュータを使わなくても実践できるものだと看破している。
コンピュータはなぜ動くのか~知っておきたいハードウエア&ソフトウエアの基礎知識~
つまり、矢沢の文意をそのまま引き継げば、物理的な書類などに積み重ねられている情報をコンピュータにデータとして保存することを指すのがIT化なのではなく、それをどう活用するのかを含めて検討し実際に運用することまでがIT化なのだ。
この定義でいえば、別にコンピュータやWebサービスやツールを利用するでもなく「情報を整理して活用すること」が目指すべき姿なのだ。
上記の矢沢が記した内容を引用すると、物理的に存在する「名刺をあいうえお順に分類し電話や郵送の連絡をする際に参照する」といったこともITしてることになるし、「中元や歳暮を送るかどうかの判断を仕入れ先や販売先などで分類することで区別する」こともITすることになる。
**情報をどう扱い、どう運用するのか。**その結果として、さらに得られた情報をどう利活用するのかを決めることがIT化なのである。
あくまでもコンピュータを導入することやツールを利用することを前提にするのではない。やざわが書いた文章は2003年に出版されたものであるため、今ほどにツールやサービスで埋め尽くされた世界線ではなかったが、非常に示唆的で参考になるものであることは受け止めたい。
▷ “デジタル化”は表現手法を表すもの
ではデジタル化とは何か。
簡単に言ってしまえば表現方法である。digitalとは「整数のような数値によって表現されるということ。」だったり「物質・システムなどの状態を、離散的な数字や文字などで表現する方式。」とされる。
情報を数値などに置き換えて表現する手法の一つということだ。デジタルの対義語はアナログ(analog)で、こちらは相似形のといった意味となる。計数型で表現されるデジタルは二進数で表現し、より細かな再現を図るがアナログの場合は相似形のため情報の粒度が異なるわけだ。
アナログとデジタルで対比されるが、別にアナログが劣位にあるわけではない。あくまで表現手法の違いでしかないのだ。
デジタル化はIT化と対比されることが多いものの、上記してきたようにIT化が情報を整理し活用することを目的にしたものである。「デジタル化」とは、情報をデジタルで表現することを示すものだ。
物理的な情報を二進法で表現するデジタルにすべて置き換えられるものは置き換えてしまおうとする試みがデジタル化であり、ツールを利活用することではない。
たとえば、デジタル教育が盛んに叫ばれ文科省もGIGAスクール構想と銘打ち、一人一台の端末配布が行われている。これはEBE(Evidence Based Education)、根拠に基づいた教育を実施するための必要な前提条件だ。
何をデジタル化するのかといえば、児童生徒がどこで間違えるのか、何なら安易に正解できるのか。どこでつまづき、何を理解し、どんな刺激を与えられたら集中が切れるのかといった行動データを蓄積することであり、その先には個別最適な学習状況を構築することが目的となる。
これまで教員が長年の経験から培ってきた、もしくは先輩教員から施された指導を受けて個別最適っぽい教育をしてきたものを根本から覆すような状態に持っていくことがGIGAスクール構想の目指す姿なのだ。(現状は到底なりえそうにないことは秘密である。)
▷ 根本的にやらなければならないのは整理だろう
僕は自身の就労環境において利用する端末がクソみたいなどうでもいいスペックの端末であることは組織の怠慢であると考えている。
たとえば、軌道ボタンを押してから数分も待機時間が必要となる端末など破棄すべきだし、アプリケーションが業務中にフリーズしてしまうようなメモリやUPUしか積ませてくれないことは業務上の過失だとすら思っている。
IT化だろうがデジタル化だろうが関係なく、家庭用のWebサーフィン程度にしか利用しない想定のスペックPCではなく、業務用で相応のスペックを備えた端末を利用することが前提だ。
それを前提して考えると、そもそもがしなければいけないのは広義の意味であるIT化だろうし、どんな情報をどこまでデジタル化するのかといった整理である。
それを現状はDXだなんだと、本来でいえば20年前からやってきたことを今さらほじくり返しては、しかも行政機関が必死に音頭を取りつつやるようなことに踊らされ、本質的に必要なのか不要なのかも判別がついてもいない状態でツールやサービスを導入した事業者も多いのではないか。
だからこそ、冒頭で記載したような95%もの企業がまったく取り組んでいないか、取り組み始めた段階といった体たらくなのだ。
ひとつ付け加えるならば、デジタル化をしなくても生き残れてしまっている企業があまりにも多いからこそ、あらゆる産業でのIT化が進まなかったのだといえる。
雇用の流動性が叫ばれて久しいが、同時にデジタル化・IT化ができていない企業や組織を駆逐するような状態にでもならない限り、本来的な意味で日本の「でじたるとらんすふぉーめーしょん」とやらは進まないはずだ。
いや、5%もの企業はすでに取り組んでいるのだとすると、それは成果だと捉えるべきなのかもしれない...
…。
ではでは。
えんどう
▶︎ おまけ
▷ 紹介したいnote
情報を丁寧に整理をすることと、それをどう活用していくのか踏まえて丁寧に取捨選択をしている印象だ。こういうことを丁寧に行うからこそ、事業転換とまではいかないまでも業態返還をもたらすほど業務のデジタル化が行えるのだ、と非常に参考になるnoteである。
まさに、である。僕もこれを読んだ時には少々面を喰らった印象を受けたものの、ある程度は予想通りな内容もあった。どこかといえば米国企業と日本企業におけるアジャイルの原則とアプローチのページだ。結局はどこに向けて仕事をするのかって話なんだろうと思うが開きがあるものだ。
戦略なき戦術で無意味なDXが生まれる、“やみくもDX”にご注意を
やみくもDXを行っている組織は数多くあるのだろう。なぜなら、しっかりと浸透しているのなら、ここまで困っていないだろうからだ。各事業者ごとにオリジナル仕様の業務管理システムを入れていたりすることも大きな問題だと僕は思う。自社仕様ってそこまで価値ないだろうに。
▷ 本noteに関連する紹介したい書籍
デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂
落合陽一が宇野常寛と共に著したすばらしい書籍だと僕は思っている。なぜなら、大半が意味のわからない語句によって埋め尽くされているからだ。(言い過ぎであることは認める)ただ、社会認識なんてのは時代によって変わる。メガネは時代が時代なら障害だ。
▷ 著者のTwitterアカウント
僕の主な生息SNSはTwitterで、日々、意識ひくい系の投稿を繰り返している。気になる人はぜひ以下から覗いてみて欲しい。何ならフォローしてくれると毎日書いているnoteの更新情報をお届けする。
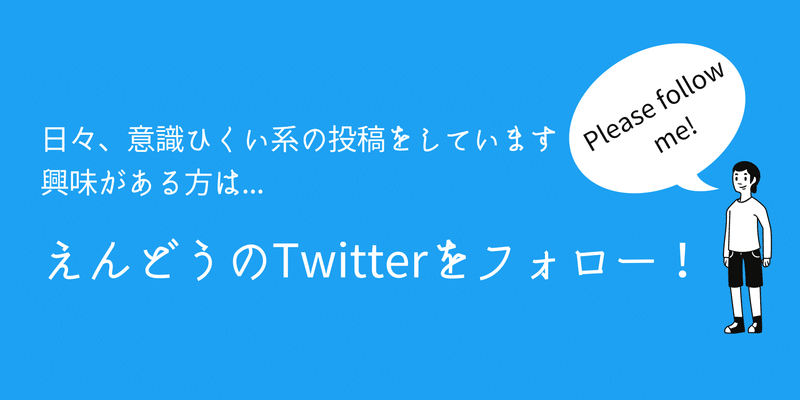
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
