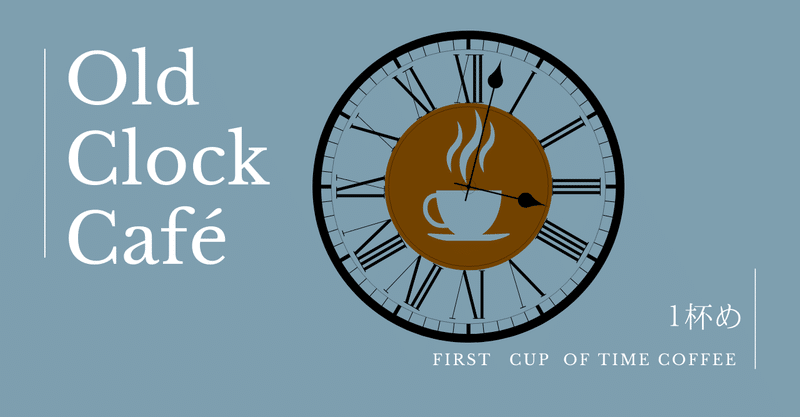
小説『オールド・クロック・カフェ』 #1杯め「ピンクの空」(2)
前回のストーリーは、こちらから、どうぞ。
<あらすじ>
京の八坂の塔近くにある『オールド・クロック・カフェ』には、さまざまな柱時計が飾られている。時計に選ばれた客にだけ出される「時のコーヒー」は、時のはざまに置いてきた「忘れ物」を思い出させてくれるという。亜希は時計に選ばれた3番目の客。白い柱時計が示した時刻は4時38分。亜希はその時刻にどんな「忘れ物」をしてきたのだろう。
* * tick tack * *
ミルで丁寧に豆を挽く音が静かな店内に響く。微かにコーヒーの香りが店内に漂いはじめた頃合いで、ミックスサンドが運ばれてきた。
そういえば、サンドイッチにも流行があったな。少し前には玉子サンドが雑誌で特集されていたけれど、今はフルーツサンドがデパ地下に並んでいる。でも、亜希はサンドイッチといえばミックスサンドだと思っている。きれいな二等辺三角形に切りそろえられたミックスサンドをひとつ、つまんでほおばりながら、通り庭に目をやる。マスタードがいい具合に鼻に抜ける。御影石の手水が配された庭では、今が季節とばかりに連翹と雪柳がひと群れ、右に左にさわさわと振り子のように風にゆらされていた。
4時38分。いや16時38分だろうか。亜希にはその時刻にまるで心当たりがない。私はそこに、何を忘れてきたのだろう。どうして忘れてしまったのだろう。
朝からクライアントの要望や文句に押し潰されそうになりながら、ただぺこぺこと頭を下げてばかりいた。上司の不手際の尻ぬぐいもする。後輩の面倒もみる。時間に追われるだけの日常。それに何の疑問ももたずにいた。時間に追われていることが、働いていることへの実感につながっていたから。
でも。このカフェに入ったときから、時間に追われるのとは真逆な感覚に包まれていた。こんなにもたくさんの時計があるのに。みな規則正しく時を刻んでいるのに。追われるのではなく、時の揺りかごにゆられて、ゆるやかな時間の流れに身をゆだねているような。不思議な感覚に満たされていた。
亜希は柱時計をひとつひとつ、いとおしむように目で追う。
通り庭では紋白蝶がひらひらと遊んでいた。
「お待たせしました。12番の時のコーヒーです」
ぼーん、ぼーん、ぼーん。白い柱時計がうれしそうに時を打つ。
湯気とともに立ちあがる香りが鼻から胸へと広がる。淹れたてのコーヒー特有のスモーキーで馥郁たる香り。丁寧にドリップされたことの証しだ。亜希はためらいがちにひと口すする。ほろ苦い中に広がる甘みがあり、ナッツのような香ばしさもあって、味が重奏になっている。「時のコーヒー」という、いわくつきであることを忘れるくらいふつうに美味しい。豆の種類を訊いてみようかと思って、やめた。きっとそんなものは関係ないのだ。
三口めを舌の上で転がすように味わうとやがて、亜希はゆっくりと時の彼方へとまどろんだ。
* * Time Coffee * *
まず意識の深淵に浮かびあがったのは、ポニーテールの後ろ姿だった。頭の高い位置でゴム留めした毛先に少しくせのある黒髪の束が、肩のあたりでせわしなく左右にゆれている。水色のフレンチスリーブのTシャツを着て学習机に座っている背が見える。机の端に筆洗が置かれ、左手でパレットを持っている。転がっている絵の具のチューブ。徐々に画像が鮮明になる。
突然、耳をつんざくほどの蝉時雨が降ってきて、目の前がぱっとクリアになった。映画のフィルムが回り出した感覚に似ていた。
あれは小学4年生の私だ。夏休みも残りわずかになったころ、宿題の絵を描いていた。「家族の思い出」みたいな課題だったから、2年前の夏、最後に家族で出かけた海の光景を描いた。
それは亜希にとって、家族で過ごしたかけがえのない思い出だった。
盆を過ぎたある日、日本海の海水浴場に1泊2日で出かけた。その前日、仕事から帰宅するなり父は、「竹野海岸の保養所の予約がとれたから、明日は朝早く出発するぞ」と意気揚々と告げた。姉と私は歓声をあげた。「お母さーん、水着、水着」とはしゃぎまわる。亜希は小学2年生、姉の早希は5年生。二人とも子どもだったから、そのときの母の反応には無頓着だった。夫から前触れもなく突然の予定を切り出されたら、戸惑い、うろたえ、苛立つであろうことは、大人になった今ならわかる。おそらく母は夫に文句を並べ立てたはずだ。でも、父はいつものごとく「いやー、ちょうどキャンセルが出てラッキーだったよ」などと、母の感情を無視するようなことを言ったのだと推測がつく。それでも、亜希の記憶の中の母は、車の中でも笑っていたから、娘たちのよろこぶ様子にじぶんの感情をしまい込んだのだろう。
盆が過ぎ海水浴客も減った海は、時折、高い波をあげる。
父が笑う。姉が笑う。母も笑っていた。つられて亜希も笑う。セルフタイマーをセットして、海を背景に顔を寄せ合って写真を撮った。4人ともこれ以上ないほどの笑顔。家族4人で過ごした最後のしあわせな記録だ。
その年、秋から冬へと季節がうつろう頃、父は家を出て行った。
テニスの部活に行っていた中学生の姉の早希が、「暑い、暑い」と言いながら階段をバタバタと派手な足音を立てながらのぼってくる。階段前の亜希の部屋にひょいっと顔をのぞかせた。
「何してるん?」
「夏休みの宿題の絵を描いてる」
ぼそぼそとしゃべる亜希の声は、シャワーのように降ってくる蝉の声にかき消されがちだ。
「もう、蝉がやかましすぎ。窓しめて、クーラー入れなよ」
「絵を描いてたの? 見せて」
姉は制服のまま部屋に入ってきて、描きかけの亜希の絵を取りあげる。砂浜で家族4人が笑っている絵だ。背景には海と空が広がる。
「えー、空がピンクなんて、ありえない」
「お母さーん。ちょっと見てよ。亜希の絵、おかしいよ」
その日、なぜ、母がいたのかは思い出せない。シングルマザーになる前から母は会計事務所で働いていた。常識がものさしの人だから、会計の仕事は向いていたと思う。家事もてきぱきとこなし、いつも忙しそうだった。その日は遅い夏休みでも取っていたのかもしれない。
「もう、何よ。帰って来るなり、にぎやかね」
パタパタと階段をのぼるスリッパの音がして、母が部屋に入ってきた。
「ほら、亜希の絵、見て」
姉が画用紙の端を両手でもって、くるりと振り返って母に見せる。
「空がピンクなんよ」
母はぴくりと眉をあげ、まじまじと絵を見た。
母は良くも悪くも常識人だった。母にとっては常識がすべての基準であり、そこから外れているものは認められない。父がある日突然、会社勤めを止めて絵描きになると宣言したことも大きかったのだと思う。クリエイティブなものを「まっとうではないもの」とレッテルを貼って嫌悪した。
「亜希、どうして空がピンクやの? 空は水色で雲は白でしょ」
小学生にとって、親は神様と同列といってもいい。とくに母親の言うことは絶対である。亜希はとまどった。なぜピンクになったのか。理由はあるといえばあった。でも、それを口下手な亜希にはどう説明すればいいのかわからなかったし、母の意見に抗う勇気もなく、ただうつむくしかなかった。「ああ、また失敗した」と唇をかんだ。
はじめは海も空も水色で塗っていた。けれど、それでは、どこからが海で、どこからが空なのかがわからなくなってしまう。同じ水色で空と海を描き分けるほどの技量は、小学生の亜希にはなかった。困り果て、子どもの単純さで海と空の境に線を引くことを思いついた。後から思えば、濃い青で引けばよかったのだ。
でも、青ではなくピンクを選んだ。
亜希はそのときの自分の感情を思い出した。父も笑っている。母も笑っている。家族みんなの笑顔を描くとしあわせな気分になって、明るい色を足したくなってしまった。
白が多めの淡いピンクをパレットの上で作って、水をふくませた筆に取り水平線にそっと塗った。すると、先に塗っていた空の水色とにじんで、所どころ、ほのかに薄紫になった。その偶然の色が、亜希には魔法の色のように思えた。海と空を分けるだけのつもりが、もっともっと、とピンクを塗る手が止まらなくなった。結局、空のほとんどにピンクをにじませた。できあがった空はピンクと薄紫と水色がまばらに溶け合って、亜希は我ながら美しく描けたと思ったのに。
それを‥‥。姉と母に全否定されてしまった。
亜希はいつも姉がうらやましかった。母の口からはふた言めには決まって「お姉ちゃんのように」という言葉が冠につく。「お姉ちゃんのようにしなさい」とか、「どうして、お姉ちゃんのようにできないの」とか。勉強もスポーツも何ごともそつなくこなす姉は、常識のレールを踏み外すこともなく、母の自慢の娘だった。亜希も母に認めてもらいたかった。
「空がピンクに見えるなんて。目に異常があったらたいへんやから、眼医者さんに行こか」
母にそんなふうに心配されるほど、ピンクの空はおかしなことなんだ。
うまく描けたかもしれない。お母さんにほめてもらえるかも。
さっきまで胸のうちでふくらんでいた、ふわふわとした淡い期待が、急速にしぼんでいくのがわかった。
――失敗した。失敗した。また、失敗した。
――どうして私はお姉ちゃんのようにできないの。
――どうして私はほめてもらえないの。
「早希、あんた、明日は部活ないでしょ。亜希の空を描き直すのを手伝ってやって」
「えー、明日はプールに行こうと思ってたのに。もう、しょうがないな」
「亜希、午前中にちゃっちゃと仕上げちゃうよ」
窓の傍の樫の木にとまった蝉が、渾身の鳴き声を轟かせる。亜希はたくさんの言葉を吞み込んだまま、力なくうなずくことしかできなかった。
その時だった。
ぼーん、ぼーん、ぼーん。
何かを告げるかのように柱時計の音が響いた。蝉の声が遠ざかり、画面がレンズを閉じるようにフェイドアウトしていく。代わりに浮かび上がった白い時計は、4時38分を示していた。
(to be continued)
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
