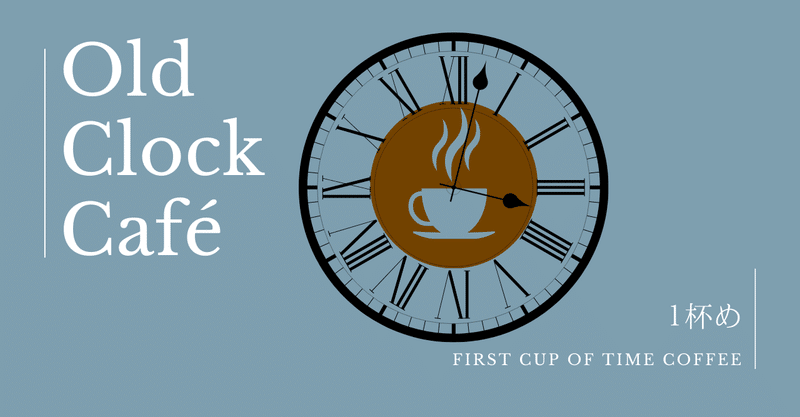
小説『オールド・クロック・カフェ』 #1杯め「ピンクの空」(1)
その店は、八坂の塔へと続く坂道の途中を右に折れた細い路地にある。古い民家を必要最低限だけ改装したような店で、入り口の格子戸はいつも開いていた。両脇の板塀の足元は竹矢来で覆われていて、格子戸の向こうには猫の額ほどの前庭があり、春になると山吹が軒先でゆれる。格子戸の前に木製の椅子が置かれ、その背もたれにメニューをいくつか書いた緑の黒板が立て掛けられていなければ、そこをカフェと気づく人はいないだろう。
そのメニューが変わっていて、黒板には、こんなふうに書かれている。
Old Clock Cafe
6時25分のコーヒー ‥‥500円
7時36分のカフェオレ ‥‥550円
10時17分の紅茶 ‥‥500円
14時48分のココア ‥‥550円
15時33分の自家製クロックムッシュ‥‥350円
なぜメニューに時刻がついているのかはわからない。そこにどんな秘密があって、何を意味しているのかも。ときどき、この風変わりな黒板メニューに目を止めて、開け放たれた格子戸から中を訝し気に覗きこむ人がいる。
いらっしゃいませ。ようこそ、オールド・クロック・カフェへ。
あなたが、今日のお客様です。
* welcome *
店舗コーディネーターの亜希は、朝から外回りで足が悲鳴をあげていた。小指がヒールに擦れて、たぶん中で赤く腫れあがっている。おまけにこの辺りはどこもかしこも坂道ばかりで、必然的にヒールの中でつま先へと圧がかかる。ヒールを脱ぎ捨てて裸足で歩きたい衝動に駆られていた。次のアポイントまでは小一時間ほどある。それまでに昼を済ませておきたい。足も限界だ。小指の痛みが頭まで響く。辛うじて背筋は伸ばしているけれど、おそらく体は不自然に左右に揺れているにちがいない。産寧坂まで行けば店はいくらでもある。でも、これ以上、坂道をのぼれる気がしなかった。
左に細い路地がある。ちらりと覗くと、まっすぐ延びている路地の中ほどに椅子がひとつ置かれていて、黒い板のようなものが座面に立て掛けてあるように見えた。黒板メニューはカフェの定番だから、あそこはカフェかもしれない。違っていても、坂をのぼるよりはいい。亜希は路地に入った。
椅子の上に置かれていたのは、思ったとおり黒板だった。
『Old Clock Cafe』とある。良かった。カフェであたりだった。けれど、そこに書かれているメニューには首をかしげた。それに、門の格子戸は開いているけれど暖簾も看板もない。どう見ても、町並みに溶け込み静かに佇んでいる民家にしか見えない。でも、亜希はもう一歩も歩きたくなかった。まちがっていたら、すみませんと謝ればいい。女も27歳ともなれば妙な度胸がつく。門をくぐり、前庭を通り引き戸を開けた。
ガラスの嵌った杉板の格子戸を引くと、からからと乾いた心地よい音がした。扉を開けると、ぼーんぼーんと柱時計が深く沈んだ声で時を打った。
「いらっしゃいませ」
カウンターで眼鏡をかけて本を読んでいた若い女性が、ぴょんと立ちあがる。20代前半ぐらいだろうか。髪をトップでだんごに結っていて、白いスタンドカラーのシャツに黒のカフェエプロンをつけている。眼鏡をはずして微笑むと、えくぼが浮き出て、たちまちあどけない顔になる。古びた店の雰囲気とちぐはぐな印象が、なぜか亜希をほっとさせた。
店は京町家を改装した造りで、床は磨きこまれて黒光りしている土間だ。入口の真向かいに同じ格子戸がある。おそらく戸の向こうは通り庭だろう。前庭と通り庭に面して窓が切られていて、そこから射しこむ陽光にほんのりと包まれ店内はよい加減に明るい。
丁寧にこしらえられ、丁寧に使われてきた町家だということがわかる。
店に入ってまず驚くのは、壁という壁に所狭しと掛かっている柱時計や振り子時計だった。いったい全部でいくつあるのか。あるものは2時25分を指し、あるものは7時16分を指していて、ばらばらの時刻を刻んでいる。けれど不思議なことに、あのカチッカチッと規則正しく時を刻む音がうるさくも耳障りでもないのだ。それぞれが、めいめいに音を鳴らしているはずなのに不思議と調和してひとつの音楽を奏でていた。
たいていは飴色の鈍い光沢をはなつ木製だが、中には青銅や真鍮製の時計もあった。凝った装飾がついているもの、美しい曲線が印象的な意匠のものや鳩時計もある。まるで時計の森に迷い込んだようだった。
そのみごとさに圧倒され、亜希は口をあんぐりと開けたまま、壁から壁へとゆっくりと嘗めるように首を回す。驚きのあまり声もでない。
「すごいですね」
ようやく深い吐息とともに漏らしたのが、そのひと言だった。我ながらもう少し気の利いたことは言えないのかと思ったけれど、感嘆以外の言葉が見つからなかった。
「そうでしょう。ここは祖父がやってた店なんです。祖父は振り子時計や柱時計が好きで。東寺の弘法市を覗いては、骨董品を集めてたみたいです」
「骨董品いうても、値打ち物はひとつもありません。ガラクタばっかりです。でも、『それがええんや』って祖父は言うんです」
「お好きな席に、どうぞ」
にっこり微笑んで、檸檬を浮かべたピッチャーの水をグラスに注ぎながら、亜希をうながす。
カウンターの他にテーブル席が3つ。前庭の窓際と通り庭の窓側にひとつずつ、部屋の中央にひとつある。亜希は通り庭の窓側のテーブルに座った。
メニューと水が亜希の前に置かれた途端、柱時計のひとつが鳴った。
「ふふ、気にいられたようですね」
あどけない笑顔をほころばせて、彼女がいう。
「えっ? 何に?」
亜希が思わず見あげる。
「えーっと。今、鳴ったのは12番やから。あの白い時計があなたのことを気にいったみたいです」
「時計が私のことを気にいる? それって、どういうこと?」
女性は盆を胸に抱え、アールヌーヴォー調の優美な植物模様がついた白い柱時計を振り返る。それからゆっくり向きなおると、亜希の目を見つめた。
「信じるかどうかは、お客様しだいなんですけど。時計はいつも鳴るわけではありません。それに、私じしん体験したことがないので、本当かどうかもわからないんです。でも」
「祖父がいうには、時計が、時のはざまに置いてきた忘れ物に気づかせてくれるそうです」
女性店員、いや今は店主なのだろうか。彼女は時計をひとつひとつ確かめるように視線を滑らせる。
「忘れ物‥‥ですか」
「何か心当たりはありますか?」
忘れ物なんて思い返せばいくらでもありそうで、どれが該当するのかがわからない。
「あ、そういえば。祖父は、『本人も気づいていないから、忘れ物なんや』と言ってました。そのうえ『時計は気まぐれやさかい、気にいったお客じゃないとあかん』とも」
「気づいてない忘れ物‥‥ますます、わからないわ。それに、あなたの話だと、時計が客を選ぶっていうこと?」
にわかには信じがたい話に亜希はとまどう。ひょっとして、とんでもない店に入ってしまったのだろうか。でも、目の前の娘の視線はまっすぐに澄んでいて、からかっているようには見えなかった。それに。
これだけアンティークの時計が掛けられていれば、多少なりとも妖しい雰囲気が漂っていてもおかしくない。ところが、どういうわけか、この店にはそうした違和感が微塵もなく、どの時計もそこが本来の居場所であるかのようにしっくりと落ち着いていた。窓辺で踊る陽の光がやわらかく、亜希は格子戸を開けたときから、この静謐な空気感に懐かしさまで覚えていた。
「祖父が入院して、店を継いで3カ月になるんですが。今みたいに、時間でもないのに柱時計が鳴ったのは、お客様でまだやっと3人目です」
「ひとりめのお客様は、バカなことを言うな、と怒って出て行かれました。ふたりめのご夫人はずいぶん悩まれたのですが、『時のコーヒー』をご注文になられました」
「あ、時のコーヒーというのはですね。祖父が時計に番号をつけていまして。カウンターの向こうに小抽斗がたくさんついた箪笥があるんですけど。見えますか? 鳴った時計と同じ番号の抽斗に入っている豆を挽いて作るコーヒーを『時のコーヒー』と呼んでます」
「それって、ふつうのコーヒーとどう違うの?」
「そこ、気になりますよね」
「私も実は気になって。お客様のいないときに、1番から順に試し飲みしてみたんです。けっこうドキドキしながら。私の忘れ物って何だろう?って。32番まで全部試したんですけど。何も起こりませんでした。どれもふつうの美味しい豆のコーヒーとわかっただけ。時計が鳴らないと、奇跡は起きないみたいです」
「せやから、味は保証します。それに、変なものが入っていないことも」
えくぼをきゅっと縮めて、あわてて付け足す。
「ふたりめのご夫人は、時のコーヒーをひと口すすられると寝てしもて。15分ぐらいして目を覚まされました。冷めてしまったコーヒーを取りかえてお出しすると、遠い目をして何かを考えるようにゆっくりとお飲みになられ、『ありがとう。忘れ物を思い出したわ』と言って出て行かれました」
「コーヒーを飲んだのに寝たの? コーヒーって眠気を覚ますものじゃなかったけ?」
亜希は単純な疑問を口にする。いつも会議など頭をシャキッとさせなければいけないとき缶コーヒーに頼る。
「コーヒーの覚醒効果は飲んでから効きはじめるまでに長くて30分ぐらいかかるそうです。せやから、パワーナップを取る前にコーヒーを飲むと、すっきり目覚められていいみたいですよ」
「ご夫人が眠られてしまったのは、たぶん、時のコーヒーのせいやと思います。確信はありませんけど」
盆をカフェエプロンの前に提げて、女性は顔をかしげる。
「そうね。この椅子に座っているだけで、眠ってしまいそうだわ」
ゴブラン織の生地が張られた椅子は、背もたれも深く、座面もちょうどよいやわらかさで疲れた体をふわりと包んでくれる。カフェの椅子としては贅沢な造りといえる。亜希はヒールから踵を開放し、つま先に靴をひっかけながら椅子に身をゆだねていた。おそらく、それに気づいたのだろう。
「よろしければ、壁際のラックにある足置きをお使いください」
足もとを覗くと、壁とテーブルの間にマガジンラックがあり、そこに小さな畳が立て掛けられていた。ああ、これはうれしい。畳を足もとに置いてヒールを脱いだ。
「足が限界だったから、うれしい心遣いだわ」
「それも祖父のアイデアなんです。お気に召していただけて、よかった。
『カフェはお客様が疲れた体と心をひと休みさせるところやさかい、何時間でも居ていただけるようにせんとな』というのが祖父の口癖でした」
女性は少し上気した顔をほころばせ、ふわりと微笑む。
「ところで、ご注文はどうされますか」
「時のコーヒーは、無理にはお薦めしません。通常のコーヒーでも紅茶でも。お好きなものをご注文ください」
「ひとつ、訊いてもいいかしら」
「なんでしょう?」
女性が小首をかしげる。彼女のチャーミングな癖のようだ。
「メニューに書かれている時刻には、何か意味があるの?」
最初から一番気になっていたことを尋ねる。
「意味は‥‥わからないんです。意味があるか、ないかも」
「適当に書いてるって、こと?」
「うーん。どうでしょう? これは祖父が書いたものなんです。店を継ぐときに気になったから尋ねてみました。祖父は『おお、あれな。おもしろいやろ』といって、いたずらっぽく笑っただけで教えてくれなかったんです」
「だから、わかりません。祖父は昔からいたずら好きというか。なんでも楽しむ人だったので。意味があるのか、気まぐれで書いただけなのか」
きっとその時のおじい様との会話を思い出したのだろう。女性は、くすっと笑った。
「でも、何かの暗号みたいでしょ。お客様のいらっしゃらないときに、その時刻の意味を考えたりしてます」
いたずらっぽい目をして言う。
「そうそう。忘れるところでした。白い時計が指している時刻が、お客様の忘れ物と関係があるそうですよ。これも祖父の話なので、どこまで信ぴょう性があるかはわかりませんが」
白い優美な柱時計は、4時38分を指している。その時刻に私は何を忘れて来たのだろう。亜希は無性に知りたくなった。
「じゃあ、ミックスサンドと時のコーヒーを」
「かしこまりました。時のコーヒーは豆から挽くので、少々お時間がかかりますけど大丈夫ですか? サンドイッチを先にお持ちしますね。どうぞおくつろぎになって、お待ちください」
(to be continued)
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
