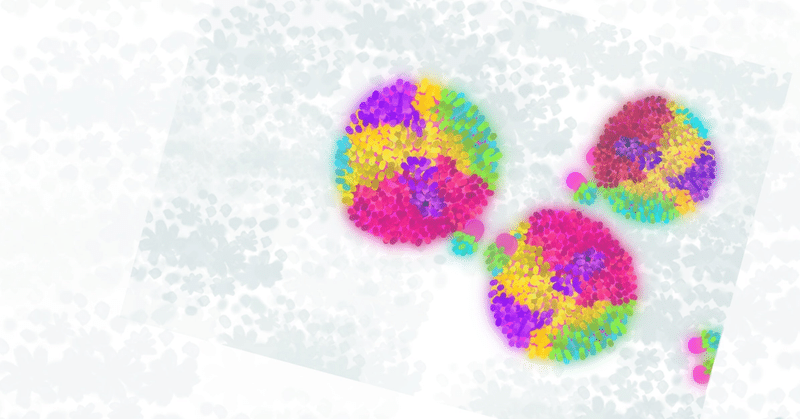
今日の発見🔍 道具の偉大さ
うどん県OTのだんです。
日々の臨床現場の中で見つけたことや再確認したことなどをまとめていく「今日の発見🔍」シリーズです。
主に経験則なので、エビデンスなどがあるわけではありませんのであしからず。
道具の偉大さ
今日は脳梗塞で左片麻痺になられた発症から間もない方との発見です。
患者さんはBADタイプ(Branch Atheromatous Disease:BAD)でした。
BADタイプとは動脈の分枝部の入り口周辺が狭窄・閉塞する梗塞
発症から数日かけて徐々に脳梗塞の範囲が広がり進行することが多い
そのため、初回介入時は左手の動きにくさがありましたが、まだ指折りもできるしグー・パーもできる状況でした。
しかし、翌日訪室すると「来てくれた!手が動かないの!!」と。
手関節以遠で随意性は失われ、手指は全く動かなくなっていました・・・。
指先から感覚を入れ、手指を動かしていくと追従してくれる反応が!
「よし!行ける!」と思って動かしてもらうと動かない・・・。
力は入っているようだが、どう動かしたらいいのかわからないような印象。
そこで、お手玉の登場!
私:「これ握れる?」
患:「握れるよ!」
私・患:「あれ???」
そうなんです。
握れちゃったんです。
その後はお手玉がなくてもグー・パーが可能に。
さらに翌日訪室すると随意性も発揮できるし、分離性も出現してました!
患者さんに聞くと、あの後頑張って動かしてくれていたそうです。
考えてみた
感覚入力によって随意性は確認できていましたがそれをうまく発揮できていない印象。
患者さんは力を入れてくれるけど、力の入れるところが違うような印象。
患者さんも力は入れてるけど、よくわからないと。
随意的なコントロールが難しいのであれば、対象操作の中でこそ随意性が発揮できるかも。
対象物が手の中におさまり、その抵抗感に対して出力をコントロールする。
明確な感覚情報が必要だったんですね。
手の中の感覚情報は重要ですね。
あらためて勉強です📚
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
