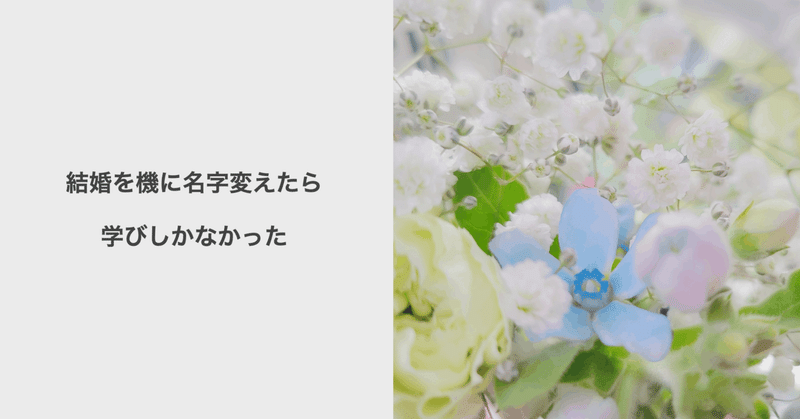
結婚を機に名字変えたら学びしかなかった
結婚を機に名字を変えた。
こう言うと、たぶん半数くらいの人は「えっ、なんで?」と驚くだろうし、逆に残り半分の人は「当たり前じゃないか」と思うだろう。
そう、前者はおそらく男性で、後者は女性である。ちなみに男友達の「えっ、なんで?」に続く第二声ベスト1位は今のところ、「婿養子になったの?」だ。(「マスオさん的な?」と畳み掛けてくる人もいるが、フグタマスオはまったくもって婿養子ではない。)
日本では、結婚を機に夫が名字を変更することは一般的ではない。家父長制的な価値観がいまだ社会に蔓延し続け、選択的夫婦別姓すら認められていないこの国は、事あるごとにジェンダー後進国と揶揄される。そして、女性の社会進出、男性の育児参加、女性のリーダーや政治家の割合、あらゆる面においてそれは事実だ。
改姓に関して言うと、少し前にドラえもんの広告の内容が議論を呼んだこともあった。名字が、というよりは、のび太側との対比において、男性の僕が見ても、確かにこれはどうなのかと感じる面はある。素敵な王子様と結ばれてハッピーエンドといったディズニーのストーリーなどもよく槍玉に挙げられるが、昔ながらの物語の多くで、今の時代の価値観とのズレが見受けられるようになってきている。
僕が妻の姓を選択した理由はひとつではない。たとえば、僕の旧姓より妻の姓の方が、桁が2つ違うくらい「レア度」が高かったから。僕は3人兄妹の長男で、妻は2人姉妹の次女。僕の妹の一人は結婚し夫の姓になっており、もう一人の妹はあいにく結婚の気配がない。父方の従兄弟も女性だけで、皆結婚し、父の名字を残せるかどうかは僕に託されていた。が、それは妻も同様で、最近姉が結婚し、近い親戚で名字を継いでいけるのは妻だけとなった。
お互い自分に名字の存続が託されているとなれば、「レア度」が高い方の姓を残したい気にもなる。さらにその気に拍車をかけたのが、妻の姓の出自だ。どうやら飛騨高山地方、白川郷あたりにあるという。世界遺産で有名な、古き良き日本の風景と文化が残る、あの白川郷だ。その地域の生まれで、江戸の相撲界隈で活躍した白真弓肥太右エ門という巨漢の力士(江戸時代にも関わらず身長が208cmあったという伝説が残っている)を輩出した家系らしく、妻の父も背が高い。
しかも、である。僕と妻が仲よくなったきっかけは、共通の趣味である登山で、それこそ飛騨地方にそびえる北アルプスの山々は、僕と妻の思い出の場所だ。そんな地域にゆかりのある名字と聞いて、ますます僕の気持ちは固まっていった。

などと言いつつも、やはり一番の理由は夫の姓に妻が合わせるという、この国の慣習に疑問を感じたからだ。選択的夫婦別姓制度の誕生を待つのもさすがに限界となり、かといって夫の姓に揃えるのは、なんだか現状に泣き寝入りするかのようで嫌だった。国の方針に異を唱える姿勢をしっかり表明する上でも、妻の姓にしようと思ったわけだ。
とはいえ本音を言うと、その思いにも裏があり、一度きりの人生、名字が変わるなどという貴重な経験ができるチャンスはまたとない。行使できる権利は行使しておくに越したことはないという関西人気質丸出しだったことは否めない。いずれにせよ、自分で実際に体験してみないことには、本質的には何もわからないままだ。だからこそ、身を持って経験してみたい。その思いだけは確かだった。


さて、ここまでやや「意識高い」とも捉えられかねない話をしてきたかもしれない。しかし当然ながら、スーパー平凡人生のど真ん中を歩んできた僕が、最初からこんなGenZ感ある今風な考えを持ち合わせていたはずもない。そのきっかけとなった出来事はふたつあり、ひとつは先ほど趣味と紹介した登山によく一緒に行く、山仲間との会話だった。
数年前、山からの帰りの車内で、その山仲間が同じく山に登る彼女といよいよ籍を入れるという話になり、「俺、名字が○○(彼女の姓)になるんだよね〜」と言ってきたのだ。正直、初めてそれを聞いたときは、「えっ、どうして? なんか事情があるのかな? でも面と向かって聞きづらいな・・」と思ったのを覚えている。当時の僕にとって、夫が妻の姓を選ぶというのは"普通じゃない"ことで、その発言に困惑したのは事実だ。結局、そのときは深く聞けず終いだったのだが、後々の会話の中で、特に深い理由はなく、妻(女性)を尊重し、夫婦で話し合った結果だったということがわかった。ちなみにその友人曰く「嫁」という言い方にも抵抗があり、必ず「妻」と紹介するように心がけているという。なんてカッコいいんだ。そういう価値観に触れたのが初めてだったこともあり、僕の中で彼の選択は、とても印象に残るものとなった。
もうひとつの出来事というのが、今働いているI&COという会社での取り組みを通じた学びだ。
I&COには、仕事に向き合う上での7つの行動指針・原理原則のようなもの(MAXIMSと呼ばれている)があるのだが、アメリカで起きたBlack Lives Matterの一連のムーブメントを受け、新たに8つめの理念として「Be just. Do right.(善く生きる)」が追加されることとなった。
さらに、こうしたメッセージを発信するだけでなく、人種的憎悪・偏見・体系的人種差別・周縁化されたグループの抑圧に対抗すべく、I&COの社員一人ひとりが、学び、議論し、行動を起こしていくためのインターナルプロジェクトが立ち上がった。黒人差別問題に限らず、広く様々な人権問題について、理解を深め、議論し合う機会を定期的に設けており、その中のテーマのひとつが、男女のジェンダー格差だった。
この手の議論をしていく中で毎回のように考えさせられるのが、課題をいかに自分ごととして捉え、感じ、考えられるかが重要だということだ。そして、実体験の有無がそこに大きな影響を及ぼしている。僕は身体的にも、また、性的指向や性自認の面でも男性として生まれ育ち、そのことによる目に見えない社会的恩恵を知らず知らずのうちに享受しながらこれまで生きてきた。当事者であれば当然のように感じている不平等・不利益にまったく触れることなく、理解できないまま、無意識のバイアスに取り巻かれ、今の自分が形成されているということを痛感させられることとなった。
百聞は一見にしかずという言葉があるが、百見は一経験にしかず、だとも思う。そんなわけで、今後こうした経験の機会があるたびに、なるべく自ら進んでそれを体験し、価値観を深めてみたいと考えるようになっていった。
そんなプライベートと仕事、両面での出来事が相まって、今回、結婚を機に名字を変えてみることにした。別に名字を変えたところで、女性が抱える課題への理解が一気に深まるわけでもないだろうが、そうした課題と向き合う上での最初の小さなステップとして、わずかなりとも意味があるように思えたからだ。
実際、名字を変えてみて感じた、言語化するのが難しい「感触」はたくさんあった。夫が妻の姓にするとなると、男性からは十中八九「婿養子?」と聞かれる(あるいは僕がかつてそうであったように、急にそっとされる)のがこの国の現状だということもわかった。実際は養子縁組とか婿入りとか、そういうお家が絡んだ堅苦しい話は一切なく、既婚者ならご存知だと思うが、婚姻届の名字を選ぶ欄で、夫の姓・妻の姓という項目のどちらにチェックを付けるかだけの簡単な作業だ。「えっ、これだけでいいの?」とさえ思える小さな選択のひとつにすぎないし、取り立てて何か窓口の人に聞かれるわけでもない。
一方で、名字を変更したことに伴う手続きは多岐に渡り、とにかく面倒だ。女性からすれば「何を今さらそんなことを」と思われるかもしれないが、こうしたことをひとつひとつ経験していくことが、制度のあり方について理解を深めていく大事なプロセスのように僕には感じられた。たとえば、マイナンバーカードの名字変更は、婚姻届けを提出してから14日以内に行わなければならないという鬼ルールがあることも今回初めて知った。当然そのことを知ったときにはすでに14日を大幅にオーバーしており、思わず頭を抱え天を仰いだわけだが、本人が変更手続きを行う場合、必要なものはマイナンバーカードだけでよく、つまり婚姻届を提出したその場その足で変更を行えば、スーパースムーズに手続きを行うことができたわけだ。が、役所の人も含め、そんなことを誰も教えてはくれない。入籍前に婚姻届の書類を役所の窓口で受け取ったときに、なんで説明してくれなかったんだと悲しい気持ちになったわけだが、お役所絡みの残念すぎるUX(顧客体験)について語り出すと枚挙にいとまがないのでこの辺にしておくことにする。
かくして本名は変わることになったのだが、多くの女性同様、仕事上は今も旧姓の通り名で生活している。なんの思い入れもなかった旧姓だが、30年以上連れ添った仲だからか、なじみがあるのはもちろん事実で、ECサイトなどの入力欄でも、特に事情がない限り、旧姓を使用し続けている。このnoteのアカウント名だって旧姓のままだ。それでも特に問題なく暮らしていけるわけだが、この「特に事情がない限り」というのがやっかいで、場合によっては本名で記入しておかないと何らかの場面で不都合が発生してしまう落とし穴も日常生活には存在する。なので毎回名字を記載する際に、今回は本名でないといけないか、あるいは通り名でもよいのか、判断を行うワンステップが必ず挟まり、その都度これまでにはなかった小さな煩わしさを感じてしまう。
また、今はまだ夫婦ふたりだけの家庭だが、いずれ子どもが生まれた暁には、妻の姓が子どもの姓になるということでもある。出席番号の並びも、体操服のゼッケンも、当然ながら妻の姓になるわけだ。まだまったく実感が湧かないが、僕にとってそのことが我が子の認知にどういう影響を及ぼすのか、今からとても興味深いところだ。
心なしか、自分のアイデンティティみたいなものも、少し揺らぎ始めたように感じている。慣れ親しんだこれまでの名字が違うものに取って変わったことで、いったい自分は何者なのか、その根っこのような部分がなくなってしまったかのような、不思議な感じだ。自分の生まれ持った姓を失い、かといって妻の姓にも完全には染まりきれず、どっちつかずの状態の僕は、今後の自分の人生を何と名前のついた箱に溜めていけばいいのか、よくわからなくなっている。これまた言語化しづらい、奇妙な感覚だ。芸能人の芸名なんかも同じようなものなのだろうか。なんだか「千と千尋の神隠し」みたいだ。
先ほども書いたように、名字を変えたところで、だから何だという話かもしれない。ただ、小さなことにせよ、今回取ることができた姿勢が、今後の自分にとって少なからず何かしらの意味をもたらしてくれることを願っている。女性からは「何をその程度のことで、ドヤ顔でnoteなんか書いてるの!」とお叱りを受けるかもしれないが、一方で僕にとってはとても新鮮で、貴重な経験ができているということは確かだ。
先日、友人の披露宴に招かれた際、本名、つまり妻の姓が円卓に書かれた席次表を受け取った。そのときに感じたポジティブな違和感は、今後もしばらく続いていくことになるのだろう。今回のことをきっかけに、いずれは子育てや教育、夫婦それぞれのキャリアプランの面においても、様々なことに挑戦し、経験を積み重ねていければと思う。最後に、というほどでもないことだが、ハンコ文化なんて面倒なもの、早くなくなればいいとずっと思っていた僕が、今は新しい姓で作り直した印鑑を使いたくてたまらない、そんなワクワクする日々がこれからの僕を待ち受けてくれている。
▼ この記事を書いた人
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
