
【前編】『Z世代』の高校生・大学生の意識について
こんにちは。
ここ最近『Z世代』というワードがメディアなどで度々取り上げられています。
こういった話題は主にビジネスや社会動向といった分野で扱われる傾向にありますが、教育関係者の中では広報担当の方などが敏感に反応するのではないでしょうか。
私も企業の方から「今のトレンドは“チル”なので、そういった雰囲気にするといいですよ」といった具合に提案をいただくこともありました。
学生からも「つぶまんさん、それエモいっすね」と言われた時にどう反応すればいいか困るときがあります😅
その時は『あぁ~…そうですね(そうね)👌』と軽く受け流してしまいましたが。。。
調べてみたら今はこういった意味で使われているんですね。

■調査のきっかけ

Z世代と呼ばれる、彼ら・彼女らは物心ついた時からスマホがありSNSや動画による独特の情報発信と拡散力を持っており、
素人の高校生が翌日からインフルエンサーになる。といったことは今や当たり前の世の中でしょう。
そして、「流行だけでなく消費の担い手」としても期待されるZ世代との関係はビジネス界でも重要とされているようです。
一方で、『Z世代』と呼ばれる彼ら・彼女らが所属する場所はアルバイト先などを除き、家庭以外で言えば学校や大学となります。
それらを踏まえ教育界は、彼ら・彼女らの意識を知っておくべきではないだろうかと思いました。
そして、調べていくうちに進路意識はもちろんのこと「価値観やトレンド」などを知らずして大学等における教育や募集活動も成り立たないのでは、と考えるきっかけになりました🤔
はじめに、これらをまとめるきっかけになった書籍をご紹介いたします。
では、早速現況などを探っていきましょう。
■Z世代の特徴
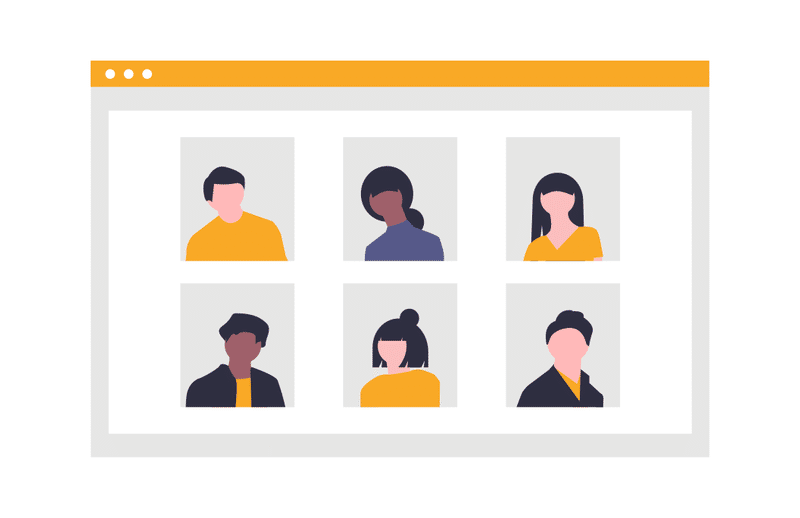
結論から言えば、
今のZ世代と呼ばれる高校生や大学生は
①「社会貢献意識」が高く
②「学歴に捉われずやりたいことをやる」
と思っている反面、
③「自分は社会を変えることはできない」
④「日本と自身の未来は明るくない」
と考えているようです。これらからは
『情熱的に見えて、実はリアリスト』というクレバーな一面を持ち合わせていることが考えられます。
日経デザインでは、Z世代を以下のように呼んでいます。
1996年~2010年生まれの「Z世代」と呼ばれる世代は、デジタルネイティブといわれ、1981年~1995年生まれの「ミレニアル世代」のさらに先をいき、生まれながらの「デジタルトランスフォーメーション(DX)世代」とも呼ばれています。
また、Z世代の特徴の一つに
『社会貢献意識が高い』こともあげられています。
Z世代会議が2018年に行った調査では「社会に貢献する活動に取り組みたい」と答えた16歳~21歳は29.7%。ミレニアル世代の29~35歳は19.3%となっており、その差は10ポイントあります。
社会問題への関心の高さは、震災やインターネットで世界中のあらゆる情報へアクセスできる時代に育ってきたからと考えれられています。
その一方で、内閣府「平成26年版 子ども・若者白書」にある日本を含めた7カ国の満13~29歳の若者を対象とした意識調査では「自分は社会を変えられると思うか?」という質問に対しては世界と比べると低い傾向にあります。

これらの結果から、
〇『社会貢献に役立つことがしたい』
と考えながらも
〇『自分では社会を変えられない』
といったクレバーな一面(達観性)があることが伺えるのではないでしょうか。
(確かに今の高校生は達観した考えを持っている子が多いなと思います🤔)
この理由にもインターネットの普及があるでしょう。
生まれながらにして当たり前にインターネットが存在していたこと、そしてSNSの爆発的普及によって多様な情報がすぐ手に入るようになりました。
ただ、この調査は世界と日本との状況も比べており、単純に国内のミレニアル世代と比較すれば社会貢献意識は高いといえるでしょう。
■ソーシャルメディアによる影響

ビジネスブレイクスルー大学の斉藤教授は「世界的に見てもZ世代はソーシャルメディアの影響が大きく、小さいころから多様な人とつながり、緊密に交流をしている」と述べています。
また、斉藤先生のゼミによるWEBサイト「JOIN THE DOTS」では『SNSの利用頻度』を下図のグラフの通りまとめていました(このサイトはZ世代を知るに重要な情報が網羅されていました)。

利用頻度として「毎日利用している」が高いことに加えて、SNSアプリも巧みに使い分けているようです。

<SNS統計は表面的な数字のみ。2019年の首都圏大学生の共通認識>
〇LINEは「連絡網」として定着。部活などグループ利用はLINEかSlack。
〇Instaは「日常シェアSNS」として浸透。特に女性の利用率は非常に多い。
〇Twitterは「今を検索するツール」として浸透。日常的な投稿は一部の利用者に限定。
〇Facebookは「社会人と交流するツール」。ただし利用者は少なく、ガチ勢が中心。
この傾向は首都圏に限らず、今や全国の若者にも当てはまるのではないでしょうか。
「情報教育」が学校教育の中に取り入れられてから随分久しいですが、情報リテラシーは十分ではないとも言われています。
しかし、これは今回の「トイレットペーパーの品薄」といったフェイクニュースがあったように我々も同様と言えるのではないでしょうか。
他方で、コロナウイルスの影響によってオンライン授業が大学や小中高において導入が進めらたことで、今後さらに情報リテラシーに関する教育が必要になり、それに比例し知識も高まっていくことが考えられます。
実際に大学ではオンライン授業におけるプライバシーやセキュリティーの強化が急ピッチで進められています。
といったように、ここまでまとめてきましたがこれ以上進むと長くなってしまうため一旦ここで終えたいと思います🙇♂️
中編では、進路意識調査から見えた「学歴に捉われずやりたいことをやる」と思っている実態とその背景について調査し、
後編では、高等教育機関が行うべき「Z世代へのアプローチ」について考察していきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
Twitterもやっています。@tsubuman8
ご相談があればお気軽にDMを✉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
