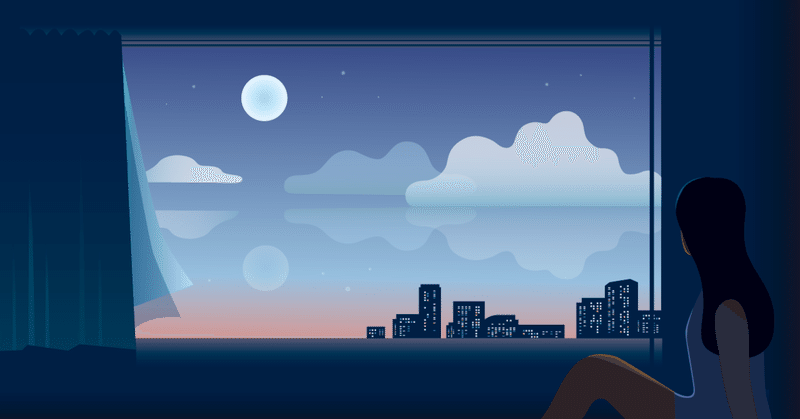
ビロードの掟 第39夜
【中編小説】
このお話は、全部で43話ある中の四十番目の物語です。
◆前回の物語
第七章 ビロードの掟(5)
「この世界では現実世界よりもずっと時間がゆっくり流れてる。私はこの場所で同時並行に進む別の時空間を見たわ」
凛太郎は優里と並ぶようにして、どこかわからない奇妙な道を歩いている。生ぬるい風があたりを包んでいた。
「別の時空間?」
「うん。まるでミニシアターを見ているかのようにパッパッパッて形式が切り替わるの。その中には思わず目を背けたくなるような世界もあった」
今も流れるように周囲の映像が切り替わっている。これは凛太郎からしてみるとどの時間軸なのかはわからないが、おそらくある程度の規則性が存在しているに違いない。
「目を背けたくなる、か」
「そう。……ねえ、覚えてる?昨年のちょうど2月ごろに中国で未知のウイルスが流行していたことを」
「去年の2月ごろか……」凛太郎が過去の出来事を思い巡らしてみると、確かにそんなことがあったような気がした。
それまでにもSERS、MERS、豚インフルエンザなど様々な病気がその年ごとに流行っていたので、その一種だろうなと当時考えていた気がする。
「政府がほんの少し対応を間違ったせいで、もう一つの並行世界ではそのウイルスが蔓延してしまった。そのせいで、人々は半永久的にマスクをつけることになる」
「半永久的に?マスクを?」マスクなんて、冬の時期に花粉症の人がつけるというイメージしかない。
「そう。見えない恐怖に、日夜脅かされることになるのよ。ほんの少しの歯車を違えただけで、わからないものね」
渋谷で見た優里も、そういえばマスクをつけていた。あの時の優里の表情はどこか悲しげで、何かを訴えかけるような瞳をしていた。
あれは彼女が言うように「心のないただの容れ物」だったのかもしれないし、もしかしたらもう一つの並行世界がなんらかの理由で繋がって見せた幻影かもしれない。今となっては真実はわからないままだ。
「ねえ、リンくん。私ね、ずっとこの世界にいる中で様々な人たちの行動を見ていたの。もちろん全てではなくて断片的だけどね。その上で、気がついたことがあるんだけど」
「何?」
「私に関わりのある映像も時には流れて、中には前の職場の同僚や取引先の人たちもいた。そこで彼らは彼らなりの葛藤を抱えていた」
優里が職場の人間関係に思い悩んでいた時の出来事が、一瞬でフラッシュバックした。これはもしかしたら、この世界が凛太郎に対して与えた影響かもしれない。
「私の上司も、取引先のお偉いさんも、リンくんの上司も。きっと彼らは自分の世界に囚われ続けていたんだね。その人たちはその人たちで自分なりの物差しがあって、それを必死で握り締めながら生きている。いつか私のことを邪険にしたクラスの女の子たちも」
彼女はふっと笑い、その瞬間肩の力が抜けたように見えた。
「でもそれってね、仕方ないことだと思う。むしろその人たちに私たちの物差しを合わせてはダメなんだよ。みんな、それぞれの違う世界に生きてるんだから」
ふと凛太郎は優里の顔をそっと伺うと、どこか達観したような清々しい顔をしていた。
「受け入れられないものは、自分からそっと身を引けばいい。本当に大切な人が誰かということだけ、わかっていればいい」
ああ、そうか。俺がかつて大好きだった女の子は、もうどこにもいないんだなと感じた。今目の前にいるのは、昔よりも強くなった一人の女性だった。黒猫のあとをついていくと、やがて出口が見えた。
出口の前には、最初ここを訪れたときに案内してくれた男の子が立っていた。
「遠いところ、ご足労いただきましてありがとうございました。後藤優里さん、元の世界に戻られるんですね。戻った後も、幸多き人生であることを」
しっかり青年が優里の瞳を捉えて言葉を発した。次いで視線を凛太郎に移すと、青年の目には鈍い光が宿った。
「それから、相田凜太郎さん。袖振り合うも多生の縁という言葉もあります。あなたとはいつか遥か彼方で再びお会いするような気がします。その時はどうぞ、お手柔らかにお願いします」
のび太くんに似た青年は温和な表情を浮かべ、軽い調子で礼をした。改めて見ると、どこかで見たような顔である気がする。訳が分からないまま凜太郎は優里と並んで扉を抜けた。
気がつけば、二人は手をつないでいる。
そのまま眩い光に包まれて、凛太郎と優里はもう一つの世界に別れを告げた。
<第40夜へ続く>
↓現在、毎日小説を投稿してます。
末筆ながら、応援いただけますと嬉しいです。いただいたご支援に関しましては、新たな本や映画を見たり次の旅の準備に備えるために使いたいと思います。
