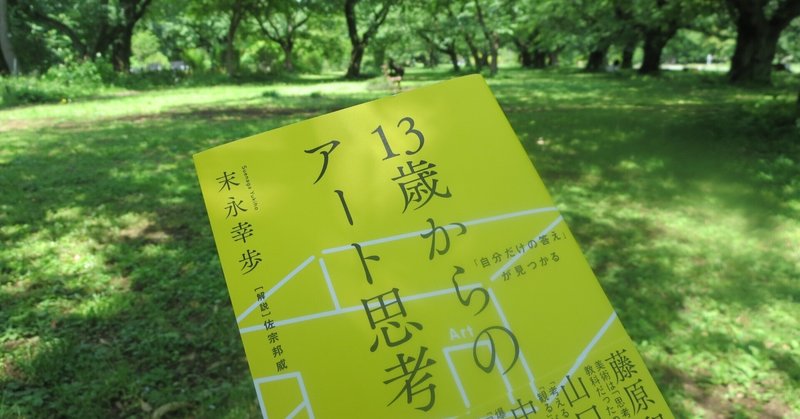
ココロと社会をつなげる「アート思考」
いままでの時代は、自分の本音よりも社会の評価が大事だったけれども…
これからの時代は、社会の評価よりも自分の本音が大事になってきている。
昨今では、AIの進化のスピードが速く、そんな片鱗もみえるようになってきました。生産性はAIに任せて、創造性を人間が担当しよう、みたいな?流れともいえるのかな。
そんななか、noteでも記事をかかれている方に超絶オススメされて読んでみた『13歳からのアート思考』。今日は書籍の紹介です❣
1.📖『13歳からのアート思考』の紹介
面白い本でした!この本は、「紙の本」として購入するのがオススメ。というのも、目次もカラフルで気分があがります♪さらに、絵画や写真が挿入されているので、あえてじっくり手に取って眺めたい。この本の特徴は、美術やアートとは何かの問いかけ、そして自分なりの視点で眺めるレッスンになっているのですが、これからの”生き方”についてのヒントが盛り沢山であることです。この手の情報は、普通の教育課程ではなかなか学べない内面との向き合い方についてのレッスンでもあります。ビジネス本に強い出版社であるダイヤモンド社だけあって「ビジネスでも使える、成果が出せる」みたいなテイはとっていますが、それにとどまらないさらに広い視野での示唆が素晴らしいです。
本題の「授業」に入る前の、プロローグからオリエンテーションまでで、結構ハマります。ネタバレしない程度に書くと、アート思考を構成する3つの要素は、「表現の花」「興味のタネ」「探求の根」。「表現」が、社会にむけて見せる部分だとすると、「興味のタネ・探求の根」が個人の内面、心や感情や意識の活動にあたるでしょうか。
空間的にも時間的にもこの植物(※「アートという植物」)の大部分を占めるのは、目に見える「表現の花」ではなく、地表に顔を出さない「探求の根」の部分です。
アートにとって本質的なのは、作品が生み出されるまでの過程のほうなのです。
そして筆者は世の中には、”アーティスト”と”花職人”がいると指摘します。花職人は、「表現の花」「興味のタネ」「探求の根」の揃ったアーティストと異なり、タネや根のない花だけを作る人を指します。花職人は「他人の定めたゴール」に向かって手を動かす人を指すのだそうです。
「アーティスト」と「花職人」は、花を生み出しているとき点で、外見的にはよく似ていますが、本質的には全く異なっています。
「興味のタネ」を自分のなかに見つけ、「探求の根」をじっくりと伸ばし、あるときに独自の「表現の花」を咲かせる人――それが正真正銘のアーティストです。
「アーティスト」と「花職人」との違い。ここだけでも、渾身のメッセージが込められています。まるで、現代の一般的な職業観に対して大きな疑問符を突き付けているようです。経済合理性を追求し、社会に適応して、組織の目標を達成するために日々頑張る社会人や企業人は、「花職人」の話、耳が痛くないでしょうか。
そのほかにも、この本文に入る前のところだけでも、心動かされるような本質論が、美しく見事に言語化されています。こんな美術の先生に学べる中学生・高校生は恵まれていますねぇ。。こういう本が世に出ているだけでも、私たちは幸せなのかもしれませんが。
書籍は冒頭だけで夢中になってしまいますが、本文の授業(クラス)も、「そうか!そういうことだったんだ💡」といった知識としての面白さももちろんですが、「なるほど、こういう視点・・」と感性がうごきまくる驚きの展開。実際身近な人数名にオススメしてしまった(ご購入いただいたよう)のですが、一読の価値ありです。
2.「私的アート思考」noteマガジンの紹介
この『13歳からのアート思考』本をオススメくださった有美さんの「私的アート思考」noteマガジンはこちらから読めます👇 こちらのマガジンも是非👍✨
自分が社会科学系の出身で、社会に出てからも周囲には近いバックグラウンドの人が多かったので、アートをお仕事にしている方がどのように学び志し、今も作品に向き合っているのか、どのエピソードもひとつひとつが新鮮で興味が尽きないnoteマガジン記事でした。
3.これからのアーティストの役割
世の中全体が、今まで社会への数字的貢献など「経済合理性」を追求してきました。けれども、今はAIの登場と急激な進化によって、合理性については人間ではなくてAIにお任せしたほうがスムーズだし得意なのではないか?ということを人々は薄々感じ始めているのではないかと思うのです。
すると、人間に残されたのは「自分らしさ」「本当の自分の求める道を心のままに行く」「自分の感情や意識」「本質の追求」「自分自身の表現」みたいな部分になってくるのではないでしょうか。

表現の花を咲かせる過程でとことん自分の本質に向き合ってきた「アート思考」。これはまさに今の社会で最も求められている重要な視点の1つなのではないでしょうか。世の中全体、どんな職業や立場の人でもアート思考を求められる流れの中、花職人ではない、「興味のタネ」から「探求の根」をのばし「表現の花」を咲かせてアーティストとして活動されてきた方の存在意義はますます大きくなるのでは?生み出された作品のみならず、アーティストの方々の存在自身や過去の経ががインスピレーションの波紋を静かに広げ、皆が感化されていく、みたいなイメージが浮かびます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
