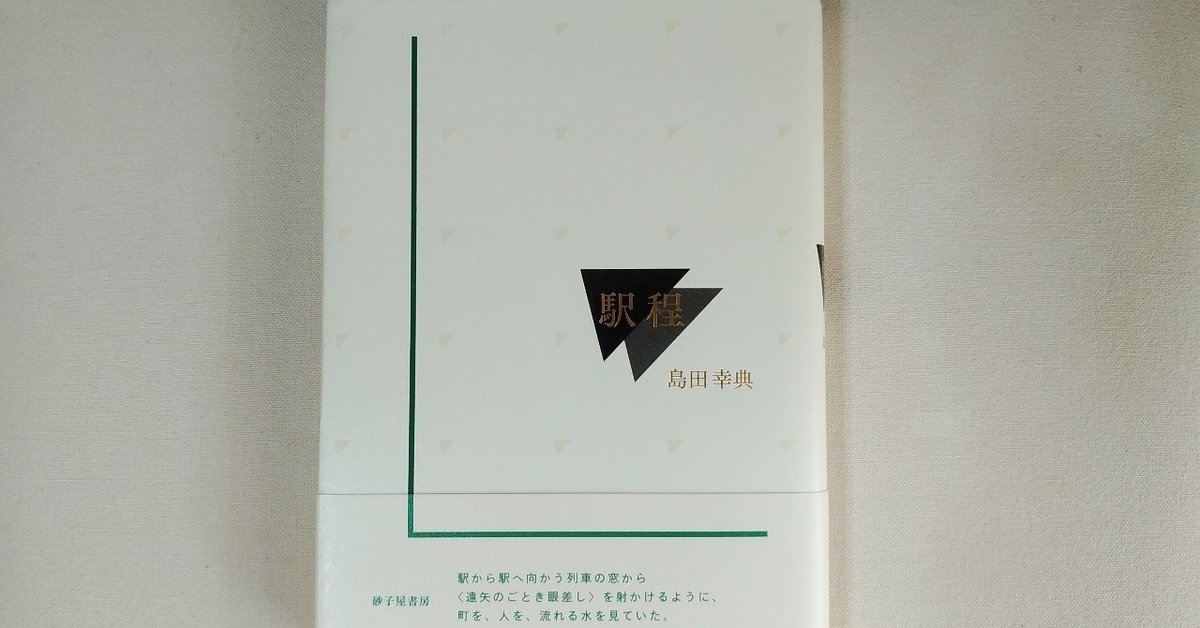
『駅程』島田幸典
第二歌集 605首
近代短歌の写実の良さと詞の端正さを、現在最も保っている歌人が島田幸典だと思う。繊細な観察眼が一巻を通して光る。中頃に留学中の歌の章があるのだが、やはり日本の事物を詠った歌の方が魅力がある。詞にはらまれる湿度や光量の問題だろうか。引用の[ ]内は詞書。
人の世の用に仕えるレグホンが隈なく白き羽根をしば搏(う)つ
卵を取るためだけに飼われているレグホン。人間からしたら卵を産むマシンのようなもの。しかし鳥は生きている。「隈なく白き羽根」を持つ生きた存在なのだと再認識させられる。
曇る日に圧されて咲ける木蓮の白さにひとは身を開きけり
性愛の歌と読んだ。曇り日の空気の圧のようなものに圧されて花弁を開く花のように女性が身体を開く。木蓮の白さと相まって官能的だ。
[ハドリアヌスの防壁]帝国の北辺にして兵舎遺り就中共同便所遺りき
ローマ帝国の北辺は今のイギリスにある。ローマ時代の防壁が残り、兵舎が残り、さらに共同便所が残っている。今は石の遺跡が残るのみだが、かつては生身の兵士が犇めき合っていたのだ。
聖人の受苦を束ぬる絵硝子は寄する西日に色を与えつ
教会のステンドグラスは多く、聖人の人生を描いている。文字が読めない、中世の農民たちへの説明のためと聞く。聖人の人生はイエスを始め、受難の人生であることがしばしばだ。その苦しみを描いたステンドグラスに夕日が射す時、夕日にガラスの色が加えられる。光がガラスに色を与えるのではなく、ガラスが光に色を与えるという把握がいいと思った。
拾わんと伸ばせる指をかなぶんが思わぬ力もちて摑みぬ
かなぶんを掴もうとしたら、思わぬ強い力で自分の指を掴み返してきた。一瞬の驚きを歌にする。もしかしたら、作者は死んだカナブンと思って拾い捨てようとしたのかもしれない。そうであれば一層強い驚きであったろう。
姫烏頭(ひめうず)の白花見んと屈みたるこころにからだ余れり人は
姫烏頭の小さな白い花。下向きに咲いているので、花をよく見ようとしたら屈むことになる。その小さな物に寄せる心に、折り曲げた身体は大き過ぎるのだ。
神学部欠くる国立大学に樟の葉陰はひとを容れたり
国立大学だから、特定の神を学ぶことはできない。神学部も仏教学部も無い。元々無いのだからそれでいいのだ、欠けているわけではない。しかし、欠けている、と捉えるとどこか不全感がある。そしてその不全感は樟の葉陰にいるような涼しさとなって作者に感じられるのだ。
杉林ふかく分け入る県道にありし集落は名のみ残せり
県道には標識として集落の名前があるのだろう。しかしもはやその集落は無い。地名として残っているだけで、人はいないのだ。鬱蒼とした杉林と、かつてそこにいた人々とを思う。
言葉ひとつひとつ捥(も)ぎとりしそののちをついにカチンの森の静けさ
カチンの森事件は第二次世界大戦中にポーランド人将校らがソビエト軍に大量虐殺され、その死体が隠蔽された事件。アンジェイ・ワイダが2007年に映画化したことで話題となった。言葉一つを捥ぎ取った後に訪れる怖ろしいまでの沈黙。その言葉とは何だろう。非常に不穏な雰囲気のある歌。
[弘道館]扁額に「藝に游ぶ」と記すあり肯いてなお辛苦のごとし
水戸の弘道館の扁額はHPでも見ることができる。『論語』の一節から取られており、意味は「文武にこりかたまらず悠々と芸をきわめる」とのこと。芸とは「儀礼・音楽・弓術・馬術・習字・算数」の六芸。その通りと肯きつつも、大変なことだ、辛苦のようだと作者は思うのである。
砂子屋書房 2015年10月 3000円+税
