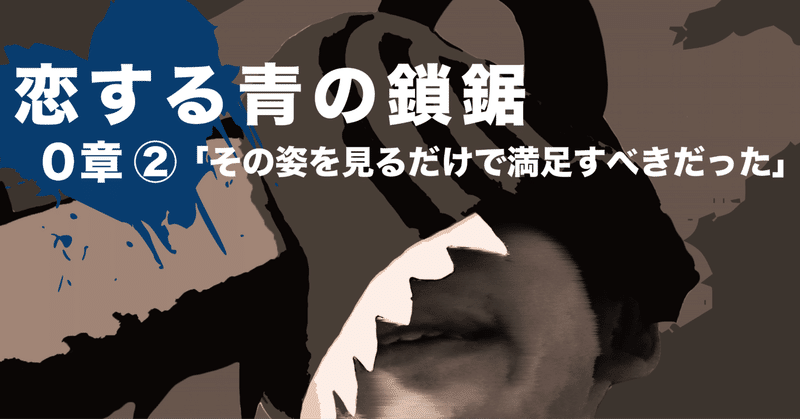
【恋愛私小説】恋する青の鎖鋸 0章②「その姿を見るだけで満足すべきだった」
前回↓
デート当日。ユウキとは駅の改札で待ち合わせた。駅からしばらく北へ歩き続けて、少し前時代的な商店街を抜けると、小江戸の町並みが視界いっぱいに広がった。流石は川越が観光地として誇る景色だ。伝統的な蔵造りの家屋が道の両脇に立ち並び、行き交う人々をレトロな風情に誘う。背の低い建物の中で一際目立つのは「時の鐘」と呼ばれる鐘楼。雲ひとつない晴天に向かって突き出されたシンボルがあまりにも様になっていたので、二人して携帯のカメラのシャッターを切った。
「あれ食べたい!」
彼女が指さした先にあったのは、近年川越名物と銘打たれるおさつチップ。大胆にもさつまいもを縦方向にスライスして揚げた一品。トッピングに「塩バター」「タルタル」「バーベキュー」など数種類あるディップソースを選ぶことで、味変を楽しむことができる。お札のようなサイズ感で無理やりプラスチックカップに突き刺さったようなビジュアルもまた若者受けするのだろうと、自分のことを棚に上げて思った。
日曜の昼時ということもあり、行き交う人々に気を使いながら食べ歩きをするのに少し苦労したが、ユウキの満足げな表情が可愛かったからよしとしよう。
食べ終えて要らなくなったカップを、備え付けのゴミ箱に捨てて歩き出す。
半歩先をいく彼女の手は相変わらず綺麗だった。幼少の頃からピアノを弾いてきたというその指先は細長く、洗練された努力の証だ。
対して自分の手はあまりにも不格好だ。妙に丸みを帯びた大きい掌に、伸び切らない芋虫のように中途半端に太い指が連なる。
一度彼女とふざけて掌をあわせたことがあったが、指の長さが一関節分違ったときはかなりショックだった。
互いに不慣れながらも、以前クリスマスにでかけた時はずっと手を繋いでいたような気がする。
あの楽しかった頃を取り戻さなければ。そう思った時にはすでに彼女の手を握っていた。
その瞬間、ユウキの体が少しだけこわばったように感じた。
「手繋ぐの嫌だ?」
「そんなことないよー」
その返答に安堵することができなかった。以前なら心地良かった彼女の握力が今は感じられない。俺に委ねられたその手の消極的な態度が、彼女の心境を物語っているようだ。繋がれた指先に滲む汗がひどく鬱陶しく思える。
この温もりは一方通行だ。
自動販売機で財布を取り出して以降、手を繋ぐことはもうなかった。
繋ぐ前と後とで二人の間に流れる空気が一変した。一見変わらない雰囲気の裏で、どこか絶対的な一線を引かれたような。そのあとはもう、引き攣る顔に笑顔を張り付けるので精一杯だった。
縁結びの神社と名高い神社にも訪れた。入り口に現れた国内最大級だという大鳥居は、赤が褪せて橙黄色になりかけている。くぐって境内へ入ると有名な「鯛みくじ」がすぐ目に入った。鯛の形を象った張り子の尻尾におみくじが入っている。それが大量に敷き詰められたカゴから、備え付けの釣り竿を使って釣り上げるのだ。 はしゃいで鯛みくじを釣り上げる彼女を、無意識に動画に収めた。その笑顔は無理して作り上げているものではないだろうか。楽しいはずの時間を素直に飲み込めない。
行きたかった場所を大体巡り終えて、あてもなく歩いていると彼女が切り出した。
「明日は学校だから、早めに帰りたいかも」
その言葉を否定する気にもなれず、すぐに帰路についた。
「またね」とユウキを先に見送ったあと、気づけば自分の最寄駅に着いていた。
電車のドアが空いた瞬間、急激に孤独感に襲われた。改札へ向かう人々の流れに背いて、ホームのベンチに座り込む。
瞼を閉じれば、今日の彼女をすぐに思い出せる。控えめな口元も、やりはじめの拙いメイクも、しばらく切っていないという、心地よい色合いの茶髪も、服の隙間から覗く、透き通るようなうなじも。そのすべてが愛おしい。 共に過ごせなかった時間の分、緩やかに大人になっていた彼女。
その姿を見るだけで満足すべきだった。
本当はもっと一緒にいたい。
満たされたはずの寂しさが、絶え間なく溢れ出してくる。
今日は楽しかったと噛みしめるよりも、次に会えるのはいつだろうという不安が止まらない。
身勝手な寂寞の渦に呑まれていく。
本当はどう思っているの?まだ好きでいてくれている?俺に触れられるのも嫌?
会えない時間が愛を蝕む。
続く。(次回、0章ラストです!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
