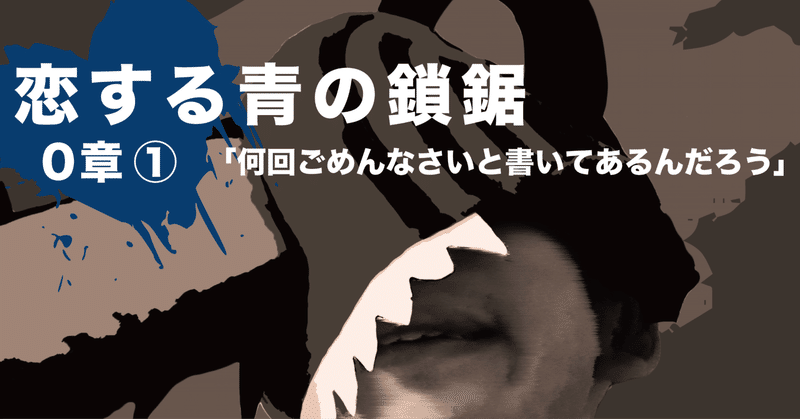
【恋愛私小説】恋する青の鎖鋸 0章①「何回ごめんなさいと書いてあるんだろう」
プロローグ
「恋愛に夢見てない人がいい」
躊躇いなく、彼女が言い放つ。
自分にとって好きな人であり、好きだった人であり、鮮烈で唯一だった貴女。
今はもう貴女に向ける感情が何なのか、何であるべきか分からず、ただ「かけがえのない」としか形容できなくなってしまった。
彼女と別れたあとの帰路で身勝手にこぼす。
「じゃあ俺は違うね」
恋愛に夢しか抱けないのだから。
※この作品は現大学三年生である筆者の高校〜大学三年の恋愛模様を描いたノンフィクション私小説です。
プライバシーの保護のため、登場人物の名前・設定等は多少変更を加えています。
0章
初めて付き合ったユウキとは高校から初心者として入部した吹奏楽部で出会った。高校二年のGWあたりに急激に仲良くなり、連休の半分以上を二人で過ごした。二〇一九年五月二日。二人で出かけた帰り際に「好きです」と不慣れでたどたどしくも伝えた。「私達らしいね」と微笑みながら受け入れてくれた彼女との交際が、その時から始まった。
お互いに始めての恋人で、何もかもが手探りだった。奥手で不器用さ故の一喜一憂が当時は煩わしくもあったが、それこそが愛おしい時間だったと今は思う。「週二回は一緒に下校する」というルールを決めて、登校している時からその時間を待ち遠しく思うこともしばしば。そんな曖昧で心地よい幸せはしばらく続いた。……コロナ禍までは。
会えない時間が愛を育むとはよく言ったものだ。
世界規模のパンデミックが巻き起こる中、世のカップルたちがどのように過ごしていたかは知らないが、少なくとも俺たちの関係はゆるやかに停頓していった。通話で声を聞くことも、ラインで言葉を交わすことも次第になくなっていった。
二〇二〇年五月二日。彼女の影すら日常に感じなくなった頃、付き合って一年を迎えた。緊急事態宣言による外出禁止期間中であったため、会うことは当然叶わないだろうが、通話くらいはしたいと思っていた。ユウキの声で自分への好意を確かめたかったのだ。
『付き合ってもう一年経ったね』
『そういえばそうかー』
『声聞きたいからさ、電話しない?』
『今日、微熱で体調悪いから無理だ、、ごめん』
返信がきた瞬間、心臓と右足の土踏まずのあたりが締め付けられるような感覚に襲われた。まるで内側から鷲掴みにされたような鮮烈な痛みだった。
そうか、あっけなく断られたのか。遅れてようやく状況を理解する。熱なら仕方ないと言い聞かせるより前に感じたこの痛みは一体何なのか。さらに遅れて頬を伝う涙で、ようやくそれが寂しさだと自覚した。
一ヶ月後、感染者数の減少により、少しずつ登校が許されるようになった。久しぶりに見たユウキの顔からはうまく表情が読み取れなかった。顔の大半を覆うマスクのせいか、言葉も視線もしばらく交わさなかったからか。屈託なく笑い合っていた以前の距離感も温度感も思い出せないまま、蔓延る重い空気を吸い込んでは、ため息として吐き出すしかなかった。
吹奏楽部の集大成である定期演奏会も、吹奏楽コンクールも、コロナ禍の煽りを受けて中止の決定がなされた。真剣に楽器と向き合い、仲間とともに音を磨き続けた日々の末に訪れるはずだった未来。理不尽に奪われたステージは、部活の活動意義と士気を喪失させるには十分だった。
まともに演奏の機会も設けられないまま引退が決まった時、すすり泣く同学年の部員たちとともに立ち尽くしているはずの自分の胸中にあったのは「受験勉強ができる!」だ。休校期間中はゲームに溺れて全く手をつけなかったくせに、我ながら都合のいい思考回路をしている。皮肉なことに、元々勤勉だった彼女とはそこで思考が一致し、将来のためという大義名分を得た沈黙がしばらく続いた。
「不要不急の外出を控えるように」と政府が強制力のない曖昧な呼びかけをするようになった頃、何度かカラオケや家で遊ばないかと誘った。世間と同じく曖昧になっていた自分たちの関係を、確かめたかったからだ。しかし、親が看護師ということもあり、徹底した感染対策を行うユウキが取り合ってくれるはずもなかった。
十一月。気づけば迎えた自分の誕生日にユウキがプレゼントをくれるなど、微塵も期待していなかった。もはや形骸化したと思い込んでいた二人での下校の別れ際、
「誕生日おめでとう!」
ありふれた祝いの言葉を嬉々として告げながらギフトバッグを差し出す彼女。夢のように思える眼の前の光景が現実だと気づいた途端、モノクロに染まり切っていた視界が一気に色づいてゆく。
「ありがとう……」
喜びと驚きで声が震えて、うまくお礼を紡げなかった気がする。
「渡したからね! 中身はお楽しみ!」
そう告げて颯爽と自分の帰路につく彼女の背中を、あっけらかんとしばらく見つめていた。
我に返った自分の胸は、しばらく幸せで鳴り止まなかった。
一月の共通テストの日と彼女の誕生日が同じだったため『入試とか色々落ち着いたらたくさん遊びに行こう?』とLINEで呼びかけると「OK」と彼女の好きなキャラクターのスタンプが返ってきた。
その了解を噛み締めて、入試と戦った。ストレスと気候の変化によって持病の皮膚炎がかなり悪化した。少し擦れば剥がれ落ちてしまうような肌が、自らを映し出しているようだった。孤独、不安、炎症、暗澹。常に全身を覆う激痛が何故か分からぬまま、消耗されていく自己を必死に繋ぎ止めながら。憔悴と怠慢を抱き続けて、二月の入試最終日程まで走りきった。
結果は思いの外上出来だった。私立大の中でもGMARCH、ましてや早慶など一般的に高学歴と呼ばれるような大学群こそ受験しなかったものの、一般入試で受験した大学は軒並み合格。第一志望の大学のみ補欠合格で今一歩及ばなかったが、後に繰り上げ合格の通知を受け、見事全勝という幕引きとなった。進路が決定した安堵より、これでユウキと遊びに行けるという喜びのほうが勝った。
しかし、気づけば卒業式すら過ぎ去っていた。受験終了と共に今更高校の近くに引っ越しをするなどこちらも忙しかったが、彼女の方は別段と忙しなかった。指定校推薦で大学受験を終えていたユウキは、持ち前の勤勉さで大学に入学する前にと、教習所、アルバイトと矢継ぎ早に新しいことを始めていた。
「すべきこと」をこなしていく彼女に会いたいと割って入るほど、身勝手なことはしたくない。そう思っていたのも束の間で、卒業式を迎えた途端に暇を持て余すようになってしまった俺が過ごしたのは「虚無」だった。
受験の反動で未だに痛む身体を起こす気にもなれず、ゲームに明け暮れる日々。ブルーライトと夜闇に包まれる中で、曜日や時間間隔さえ薄れていった。友人と遊びに出かけることもあったが、それもほんの数回に留まった。交友関係をあまり広げようとしない性格を、この時ばかりは憎んだ。まるであの休校期間に戻ったかのような寂しさに憤りすら感じた。
曖昧に流れていく時間に叫び続ける。
たくさん苦しんだ。本当はいつだって時間を共にしたいくらい好きで好きでたまらない。それなのに、一人で、我慢して、妥協して、その上で進路と向き合って、全勝をもぎ取った。ならば少しくらい報われてもいいんじゃないか?少しくらい彼女に甘えたってお釣りが来るくらい頑張ったよ。それなのにどうして向き合ってくれない?共に過ごしてくれない?
行き場のない苦しみを糧に、ようやく誘い文句を絞り出した。
『ほんと今更で忙しいかもしんないけどさ、空いてる日ない? 二人で会いたいというか遊びたい』
『ごめんなさい。本当にごめん。今頑張らないと四月になったら更に忙しくなって免許取れなくなっちゃうから、やりきりたい。遊びたいのも分かるし、ずっと会ってないのも分かってるし申し訳ないって思ってる。四月休み絶対作るから……本当にごめんなさい。』
何回ごめんなさいと書いてあるのだろう。
他人事のようにトーク画面を眺める自分がいた事に驚いた。そんなことを考えても、会えない現実は変わらないというのに。彼女に何度も謝罪を言わせてしまったという申し訳なさよりも「ごめんなさい」という言葉の響きばかりが頭にこびりついて離れなかった。
『いーんだよ 意味があって忙しいならそりゃ仕方ないし』
これが紛れもない本心であればよかったのにと、自らを軽蔑しながら送信ボタンに触れた。
四月中旬。
『入学式どうだったー?』『ガイダンス疲れた……』
始まってしまった大学生活の様子を二人で送り合う。そんな日々の中でも無意識に心の内が囁き続ける。
さみしい、辛い、怖い、会いたい。
やはり彼女と会わなければ、この不安は拭えないだろう。
彼女が運転免許を取得したという報告を機に、改めて二人で会えないかと誘った。
互いに授業やアルバイトがない日をなんとか見つけ、ようやく一日デートの約束をするに至った。
行き先は川越。二人ともいったことがなかったのと、遠出をしすぎてもしなさすぎても嫌だとのことで、ちょうどいい距離感と旅感を味わえる場所として選んだ。
前日はまるで修学旅行の夜のごとく一人ではしゃいでいた。相手のことを考えて胸が高鳴るのはいつぶりだろう。
続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
