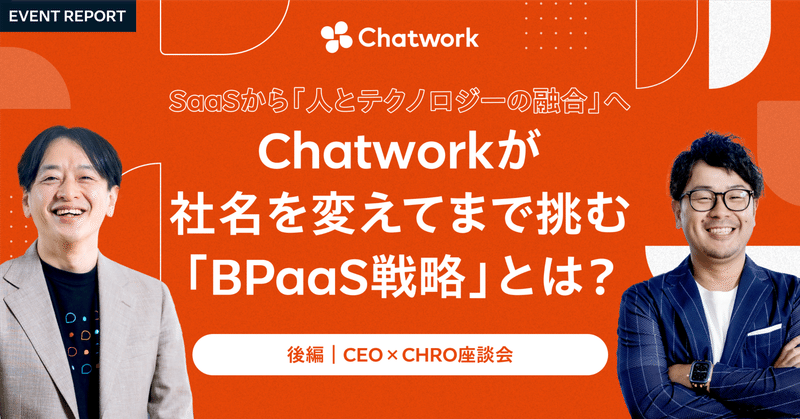
【後編|CEO×CHRO座談会】SaaSから「人とテクノロジーの融合」へ。Chatworkが社名を変えてまで挑む「BPaaS戦略」とは?
みなさん、こんにちは!Chatwork採用広報の大澤です。
前回、2024年2月27日に開催したイベント「SaaSから「人とテクノロジーの融合」へ。Chatworkが社名を変えてまで挑む「BPaaS戦略」とは?」の前編として、CEOの山本から今回掲げた戦略や背景についてお話しするパートをお届けしました。
本記事は後編として、「BPaaS戦略の誕生秘話」や「事業拡大フェーズにおける組織戦略」などを語り合った、CEOの山本とCHROの鳶本による座談会パートをお届けしたいと思います。
このnoteは2024年2月27日に実施したイベントのレポート記事です。体制や情報はイベント当時のものであり、現在と異なる場合があります。
登壇者紹介
代表取締役CEO
山本 正喜
電気通信大学情報工学科卒業。大学在学中に兄と共に、EC studio(現Chatwork株式会社)を2000年に創業。以来、CTOとして多数のサービス開発に携わり、Chatworkを開発。2011年3月にクラウド型ビジネスチャット「Chatwork」の提供開始。2018年6月、当社の代表取締役CEOに就任。
上級執行役員CHRO
鳶本 真章
大手自動車メーカーにてマーケティング領域に従事した後、京都大学大学院でのMBA取得を経て、大手外資系コンサルティングファームへ。その後、複数のベンチャー企業での経営支援を経て、2018年に株式会社トリドールホールディングスに入社し、同グループ全体の組織・人事戦略をリード。2019年より、同グループ執行役員CHRO兼経営戦略本部長に就任。2023年10月、Chatwork株式会社上級執行役員CHROに就任。
こちらも併せてご覧いただくと、より理解を深めていただけるかと思います。
本イベントのアーカイブ動画も公開しています。当日の雰囲気も含め、動画でご覧になりたい方はぜひご視聴ください。
それでは本編をどうぞ!
後編:CEO×CHRO座談会
初公開!BPaaS戦略の誕生秘話

司会:鳶本さんから自己紹介をお願いできますでしょうか。
鳶本:僕は今CHROを務めていますが、元々はマーケティングや経営戦略の分野にずっといました。一方で実は昔、父が中小企業を経営していて、周囲の環境としても中小企業が身近にたくさんあり、中小企業が元気になることが日本を元気にするんだという確信がありました。そんなタイミングでChatworkと出会い、そのミッションに惹かれて参画し、今に至ります。
司会:お二人には「BPaaS戦略の誕生秘話」と「中小企業 No.1 BPaaSカンパニーになるための組織づくり」という2つのテーマについてお話しいただきます。まず、BPaaSという着想に至ったきっかけや経緯を教えてください。
山本:BPaaSという言葉自体を使い始めたのは2022年の頭ぐらいですね。「Chatwork」を立ち上げて以降、ずっとビジネスチャット事業を伸ばすことに注力していたんです。その中で、競合他社が出てくるにつれ、「Chatwork」は中小企業に強いというポジショニングが明確になってきました。
中小企業を回ってみると、まだまだ紙やFAXが主流で、DXの余地が大きいと感じました。そこで、SaaSを使えばDXが進むんじゃないかと考えたんです。でも実際は、ITへの習熟度や、DXを進める人材不足がボトルネックになっていることがわかりました。
そこで行き着いたのが、「ならば自分たちがSaaSの運用代行をしよう」ということ。でもそれだけだと十分ではない。もっと深く業務を理解し、業務プロセス自体を巻き取って最適化したものを提供する。そうすればお客様はチャット経由で最先端のDXを享受できる。そういうコンセプトを探っていたら、"BPaaS"というものにたどり着いたんです。
参考:
これは中小企業にこそ必要だと確信しました。中小企業のDXは参入障壁が高く、競合もあまりいない。でも可能性は大きい。時間が掛かってもやるべきだと。そこでBPaaSをオープンに打ち出すことで、一緒にやりたい人材や企業を引き寄せようと考えました。
SaaSは成熟してきて新規参入が難しくなる一方、BPaaSは新しく開拓の余地がある市場になると思っています。テクノロジーだけでは解決できない中小企業の非効率な部分を、人とテクノロジーの融合で変えていく。それが社会に大きなインパクトを与えるんじゃないかと考えています。

司会:*43.1万社という圧倒的な顧客基盤があったからこそ、中小企業の課題が見えてきて、BPaaSというソリューションに至ったんですね。
BPaaS事業で他社と差別化できるポイントを教えてほしいという質問もいただいています。
*2023年12月末時点
山本:BPaaSという領域で言えば、大手コンサルティングファームが強力なプレイヤーです。ただ彼らは大企業向けで、中小企業は対象になっていません。非効率でなかなか難しいからです。逆に言えば、中小企業のBPaaS市場に、今のところ競合はいないということです。
一方、隣接領域のBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の会社は数多くあります。が、BPOとBPaaSの違いは先ほど説明した通りです。われわれはSaaSも含めて、DX済みの効率的な業務プロセスをワンストップで提供します。

今はまだBPOに近いオペレーションですが、2〜3年かけてノウハウを蓄積し、標準化・パッケージ化していきます。そうすれば圧倒的な低価格と高品質で、あらゆる業務領域をカバーできるはずです。従来のBPOとは全く違うものになると考えています。
鳶本:人とテクノロジーの融合というのがキーワードですよね。人の力も大事にしつつ、そこにテクノロジーを掛け合わせることでBPOからBPaaSへと進化させ、ユーザー価値と効率性を高めていく。皆さんには、その先にある世界観にご期待いただきたいです。
山本:DXというと自前のIT人材を揃えて内製化するイメージがありますが、それが難しいのが中小企業の実情です。大企業にはバックオフィス業務を担う本社機能があるけれど、中小企業にはない。だからこそわれわれが「中小企業の本社機能」となり、バックオフィス周りを一手に引き受ける。経営企画、人事、総務、経理、法務、情シス、果ては採用まで。そうやって中小企業は本業に集中でき、生産性と働きがいの向上につながる。われわれのミッションにも直結すると思っています。
司会:なるほど。BPaaSの可能性は、どんなところにあると思いますか?
鳶本:2つの観点があります。1つは、Chatworkのコーポレートミッションである「働くをもっと楽しく、創造的に」を体現できること。BPaaSによって創出される雇用を通じて、より多くの人が働く楽しさや充実感を得られるはずです。
もう1つは、チャレンジングな事業であること。新しい課題にどんどん挑戦し、それを通じて社員の成長と会社の成長をダイレクトに結び付けられる。事業としてすごくエキサイティングだなと。
実は、正喜さんと初めて話したとき、まだBPaaSという言葉は出ていなかったんです。でも「Chatwork」事業そのものに可能性を感じていて、2ヶ月後にBPaaSの話を聞いたときは本当にワクワクしました。ミッション思考で純粋に社会課題に向き合う姿勢が、僕には魅力的に映りましたね。
司会:BPaaSは高い参入障壁とブラックオーシャンだからこその難しさもあると思います。なぜそこにチャレンジしようと思ったのか、また成功の鍵はどこにあるのでしょうか。
山本:まず、中小企業に強いポジションにあるからこそ、戦略的にも大きな意味があります。日本経済の中心は中小企業ですからね。その課題解決に挑めるのはわれわれくらいしかいない。難易度は高いけれど、誰かがやらないと社会は良くならない。
これから我々が、中小企業BPaaSの先行事例となる必要はある状況ですが、ビジネスモデルとしては大手コンサルティングファームなどが証明済みなので、価値はあるはずです。単純なBPOでは効率も利益も出ない。BPaaSで本気でやらないといけない。そのためには業界知識と、DXの技術的対応力、そしてオペレーションの標準化・効率化が重要です。
まだ誰もやれていないことに挑戦するので、どうしても自分たちだけの力では足りない。だからこそオープンに打ち出して、志ある仲間を集めながらチャレンジしていくしかないんです。最初の一歩が踏み出せたのは、そうやって共感してくれる人と資金が集まったからだと思います。
僕らのような「テックカンパニー」としては、技術面は何とかなるだろうと。問題は人の部分で、そこはチームでカバーしていきたい。例えば人事面では鳶本さんに参画いただいたことが大きいですね。
面白いのは、BPaaSがミッションから演繹的に導かれた事業だということ。事業ありきでミッションを考えるのではなく、ミッションを起点に事業を組み立てていける。そこにブレがないことが、事業を生み出すうえで一番大事なんだと実感しています。
だから社内でも「われわれはチャットの会社じゃない。働き方を変える会社なんだ」と言い続けています。ビジネスチャットは今のフェーズにおける最適解であって、BPaaSもその先の通過点に過ぎません。テクノロジーと人の融合によってコーポレートミッションの「働くをもっと楽しく、創造的に」を体現する会社でありたい。中小企業に留まらず、いずれは大企業や個人事業主、さらにはグローバルにも広げていきたいですね。
「中小企業No.1 BPaaSカンパニー」へ、事業拡大していくための組織のあり方
司会:ここからは、その実現に向けた組織づくりの話に移りたいと思います。
「変化の過程で大事にしていることは何か」「進化のために取り組んでいる課題は何か」といった質問をいただいていますが、いかがでしょうか。
鳶本:人事としては、事業成長を先回りして環境を整備することが重要だと考えています。将来どういう組織能力が必要かを見据え、今から採用や育成の方針を立てておく。
今の事業フェーズに必要なスキルと、将来必要になるスキルは往々にして異なります。その違いを意識しながら、最適なタイミングで最適な人材を獲得・育成していくのが人事の腕の見せ所ですね。
大事なのはミッションとのベクトル合わせです。ただ画一的ではなく、その方向性の中で多様な個性が発揮される環境を作ること。ゴルフで言えばフェアウェイを外さず、その中で思い切りショットを打てるようなイメージです。そこが外れると組織は遠心力に引っ張られ、一体感が失われてしまう。
それを防ぐには、変化を先読みし、常に求心力を高めておくこと。事業の先を読み、必要な組織・人材を予測して備えていく。そこが組織戦略の肝だと思います。
山本:組織の話で言えば、ビジネスチャット中心だった時代から、BPaaSを含むグループ経営の時代に移行しつつあります。僕自身、学生起業からここまでは経験済みですが、グループ運営は初めてのチャレンジ。ミッションや価値観を維持しつつ、事業特性に合わせて柔軟に組織を設計していく。ガバナンスの在り方など、試行錯誤の連続ですね。
組織の拡大に合わせて、経営体制の刷新も行いました。ある意味当然のことなのですが、必要とされる役割やスキルはフェーズによって変わるんです。創業期のメンバーには別の役割に移ってもらい、組織づくりに長けた人を迎え入れる。こうしたサクセッションプランは簡単ではありませんが、皆で何年も前から覚悟を決めていたことなんです。
これからも常に変化を恐れず、適材適所と任期を意識しながら、経営体制を進化させ続けたいですね。

役割はあくまで役割。「社長だから偉い」ではなく、その時々で最適な人にバトンタッチしていく。例えば起業家でも、ある程度会社が軌道に乗ったら経営者の座を譲って、また新しいことにチャレンジする。そんな生き方もアリだと思うんです。そういう意識を組織に根付かせていければと思っています。
司会:DX人材の獲得など、具体的な人材戦略についても教えてください。
鳶本:DX人材の確保には、2つの考え方があると思います。1つは、本当にDX人材を集めること。2つ目は、そうでなくてもできる状態を作っていくこと。まずは、私たちがやっていることの魅力を伝え、新しいことにチャレンジしたい環境を整備することが大事だと思っています。DX人材の定義も、コーディングができる人というような捉え方だけでなく、事業とプロセスを楽しんで自分なりに新しいものを作りたいという定義に変わってくるんじゃないかなと考えています。
なのでわれわれとしては、そのあたりをしっかり定義して、適切なアプローチをすることが重要になってくると思います。
山本:誰でもできるようにしていかないと、本当の意味でのDX人材確保は難しい。事業戦略上、クリティカルなので、ボトルネックにならないよう、しっかりと取り組んでいきます。「Chatwork」のブランド認知は追い風になるので、それを生かしつつ、多様な人材が活躍できる環境を整えていく。採用だけでなく、育成・定着といった観点も大事にしていきたいですね。
そして採用だけでなく、教育もすごく大事だと思っています。個人のペースに合わせて、段階的にステップアップできる仕組みが理想です。そういった、採用・育成・定着までを含めての人材確保だと思っています。
司会:教育体制という面で考えた時に、最も重要なマインドセットは何だと思いますか?
鳶本:今はまだ手探りですが、一人ひとりのペースに合わせて、会社の成長戦略と共に具体的に落とし込み、着実にスキルを積み上げることができる体制を作ることが重要だと考えています。組織の成長と個人の成長を同期させるのは難しい課題ですが、腰を据えて取り組んでいます。
山本:日本の教育は受け身になりがちだと言われていますが、仕事に求められるのは主体性です。自ら学び、アウトプットし、社会に価値を提供する。その体験を通じて、もっと成長したいというモチベーションが生まれる。そのサイクルを、小さくても良いから回していくことが大切だと思っています。当社のミッションである「働くをもっと楽しく、創造的に」を、お客様に提供するだけでなく、自分たちで体現する存在でありたいと思っています。
型にはまるのではなく、それぞれのペースで、楽しみながらステップアップしていける。そんな働き方を実現したいですね。
BPaaSのこれから
司会:最後に、「中長期的に見たBPaaS」についてご質問をいただきました。お客様がITを使いこなせるようになれば、Chatworkは要らなくなるのでは?とのことですが、どのようにお考えでしょうか。
山本:私としてはニーズはなくならないと考えています。なぜなら、われわれが持つスケールメリットが大きいからです。
SaaSの調達コストを下げ、高度なインテグレーションを実現し、専門的なオペレーションを組み合わせる。そういったことを個社ではなかなかできません。だからこそアウトソーシングするわけで、私たちはお客様と伴走し続ける存在でありたい。もちろん、自社で完結したいという企業があっても良いと思います。しかし、基本的にお客様は付加価値の高いコア業務に特化し、それ以外は得意な人に任せる。そんな世界観を作っていきたいと思っています。
司会:ありがとうございました。最後に、登壇者のお二人から一言ずつコメントをいただきたいと思います。鳶本さん、正喜さん、よろしくお願いします。
鳶本:われわれはBPaaSを新たな一歩として、ミッションの実現に邁進していきます。より多くの方とこの世界観を共有できれば嬉しいです。引き続き応援していただければと思います。
山本:Chatworkが社名を変えてまで、新しい技術とビジネスモデルで、中小企業のDXという大きな課題に挑戦していること。ぜひ覚えておいていただければと思います。この挑戦に、何かしら関わっていただけるご縁があれば嬉しいです。引き続き、われわれの動向にご注目ください。
終わりに
いかがでしたでしょうか?山本と鳶本がお話ししたように、Chatworkは世の中の課題と本気で向き合い、「働くをもっと楽しく、創造的に」を実現していくためにkubellグループとして新たな一歩を踏み出します。新たなフェーズを迎える今、事業を拡大していくとても面白いフェーズにあると自負していますので、ぜひ今後の発信もお楽しみに!
kubell特設サイト
We are hiring!!
Chatworkでは一緒に働いてくれる仲間を募集しています。少しでも興味を持ってくれた方は、ぜひご応募ください。
キャリア登録やメルマガ登録もお気軽にどうぞ!
