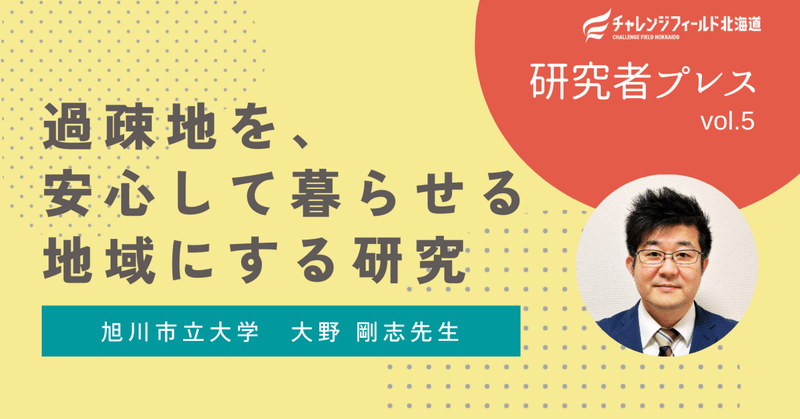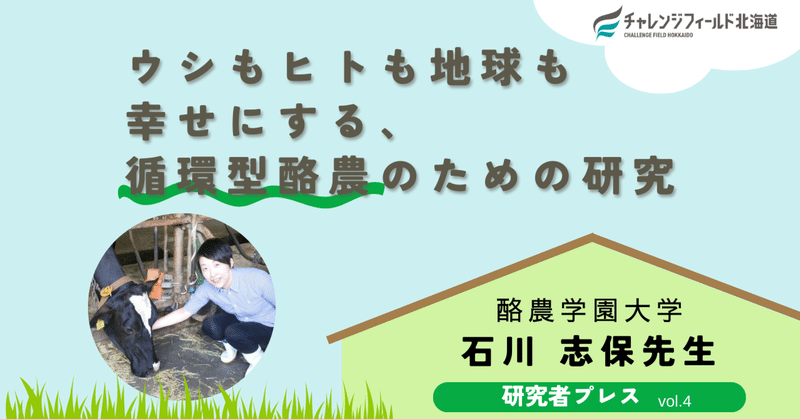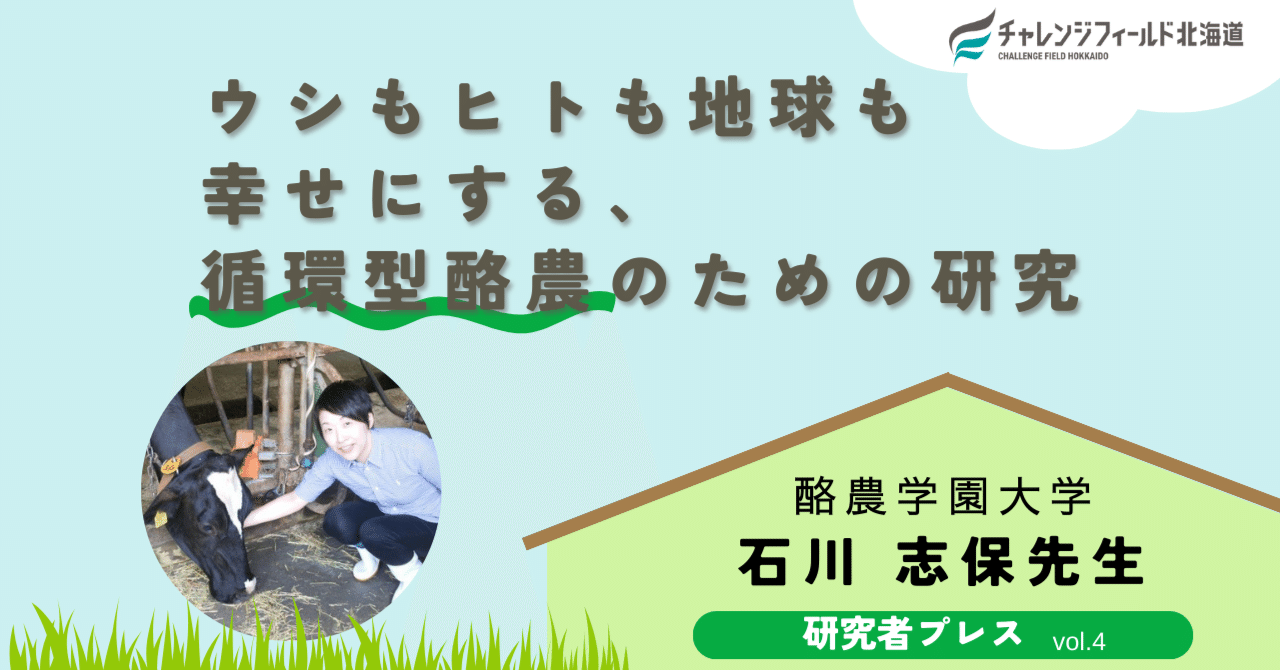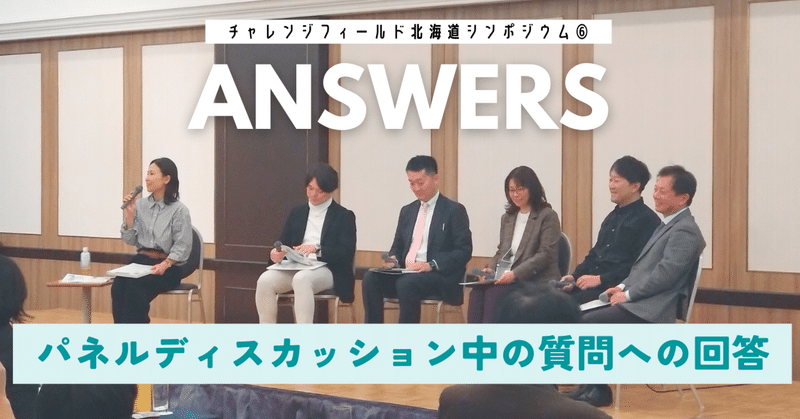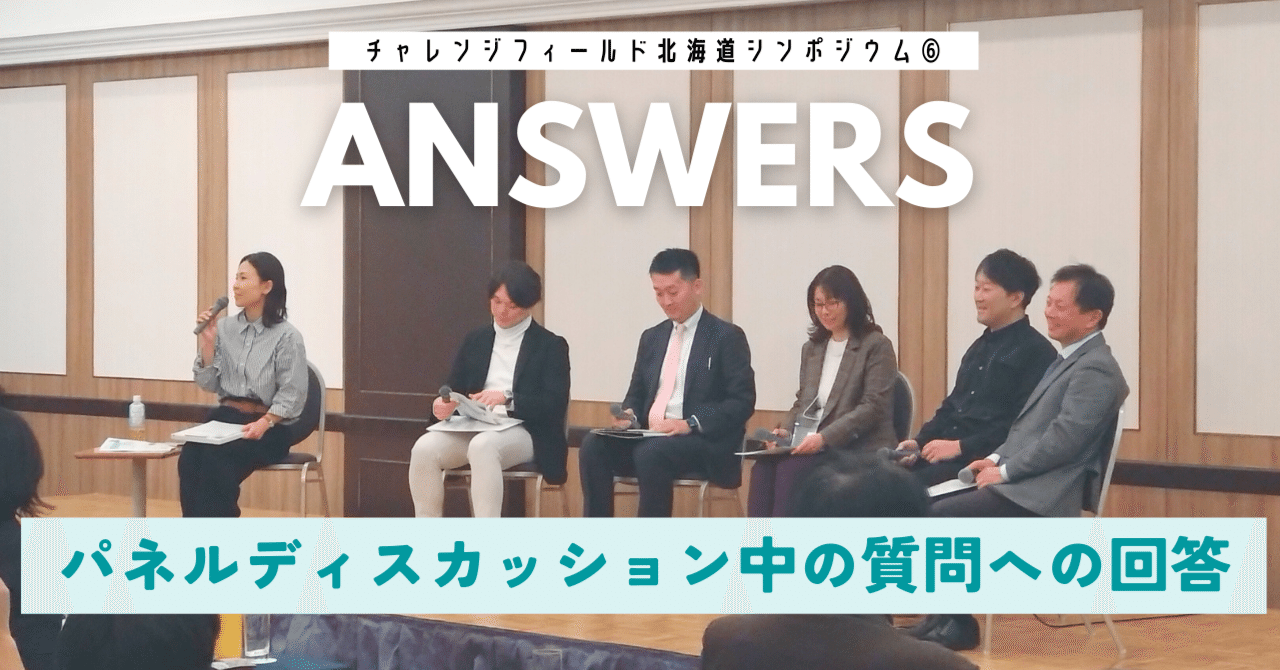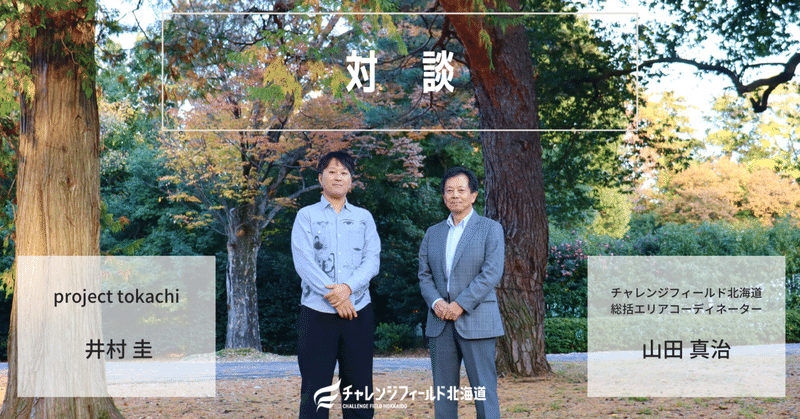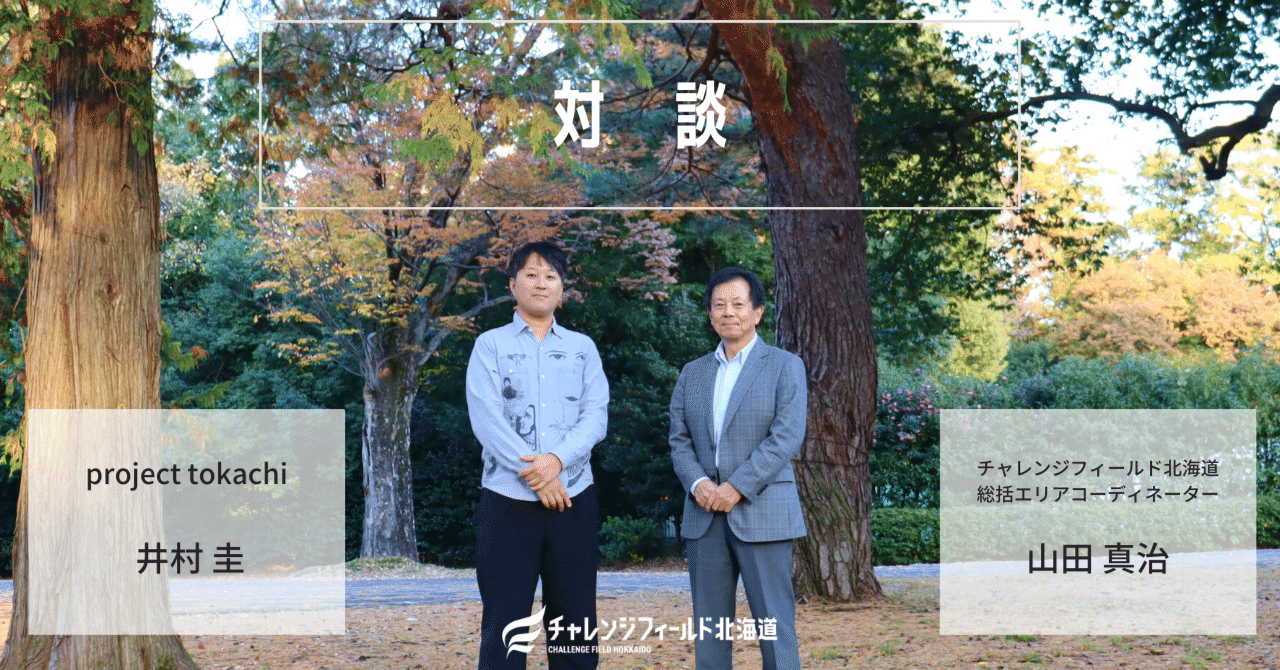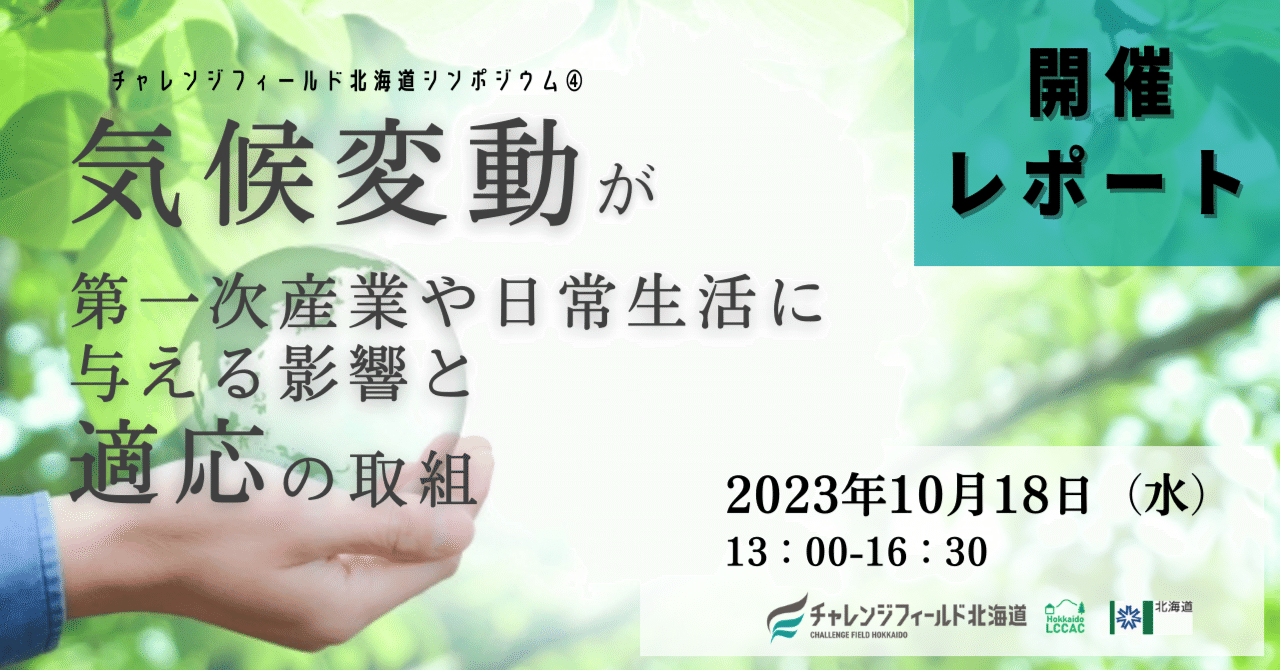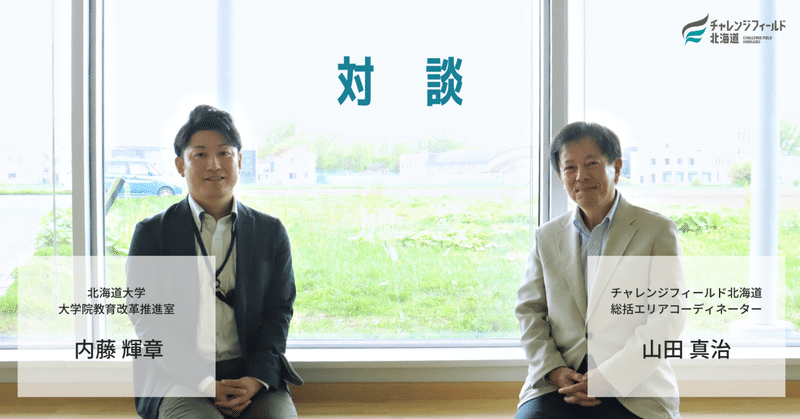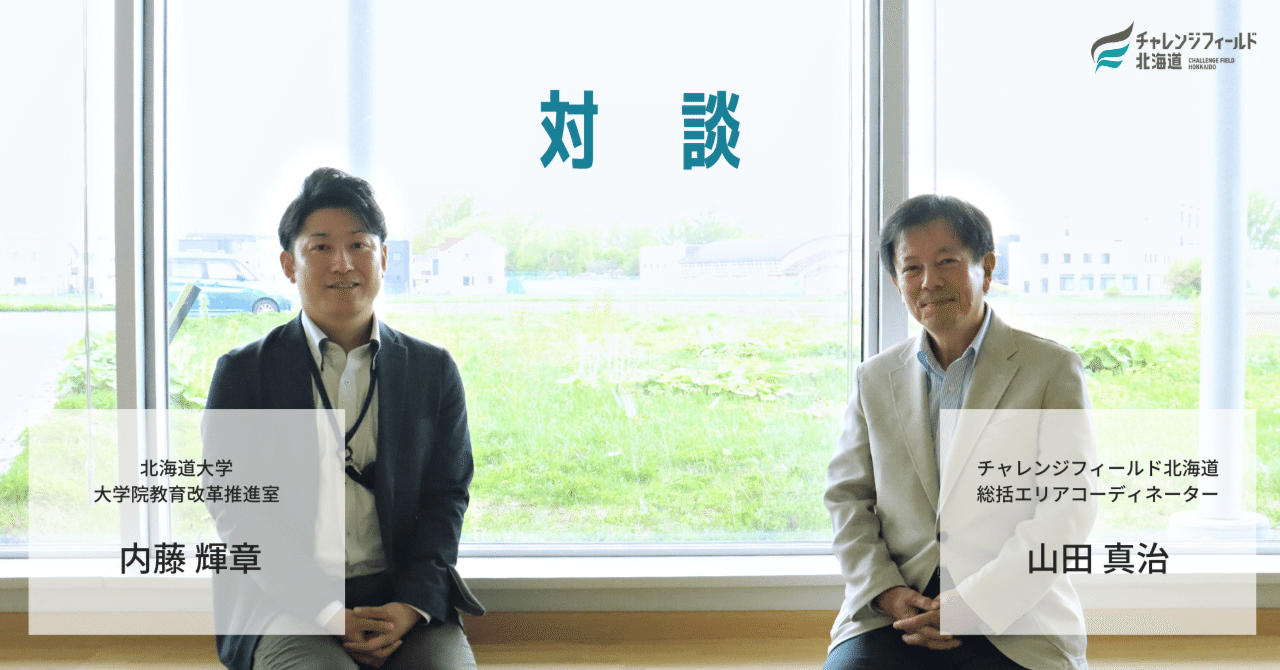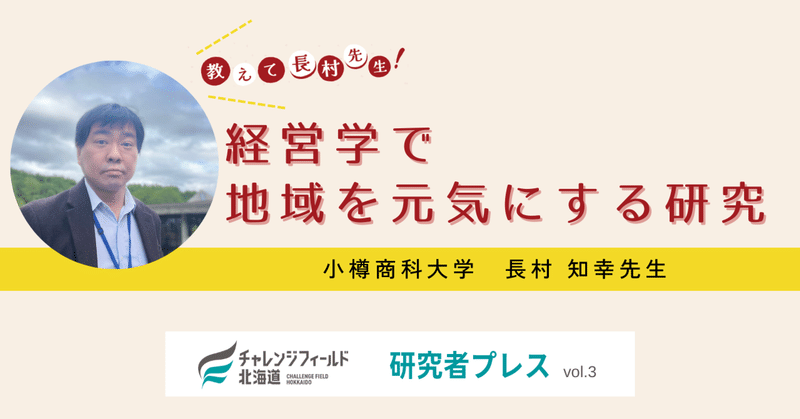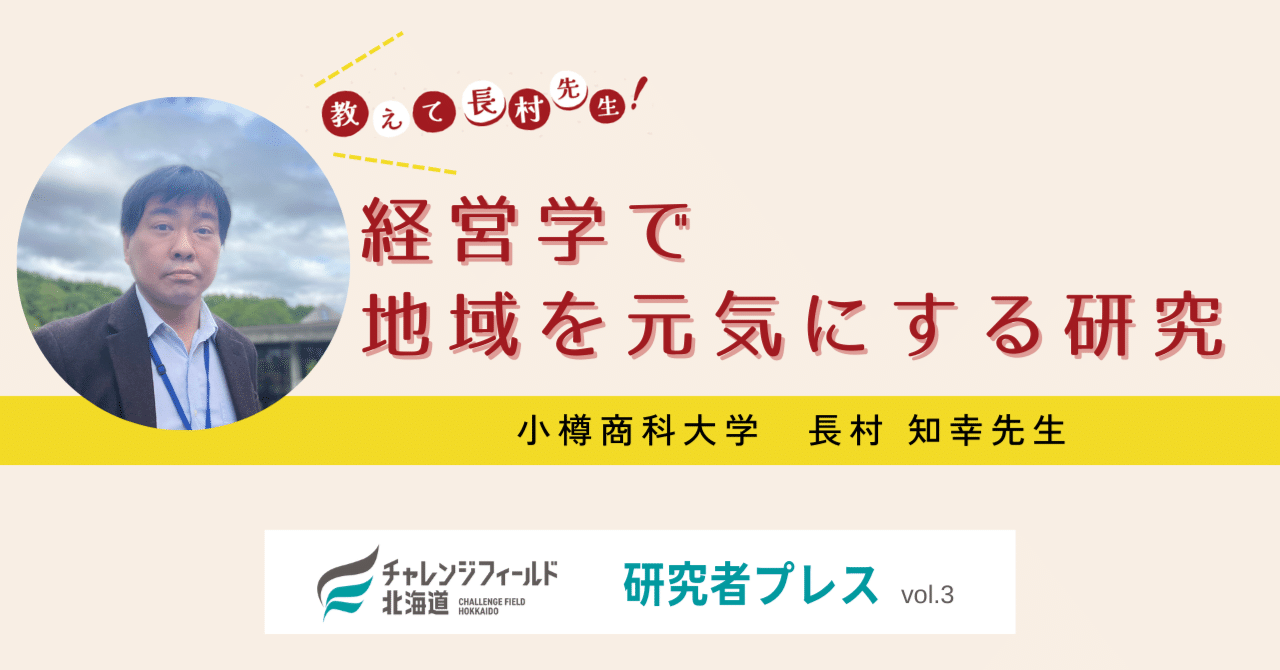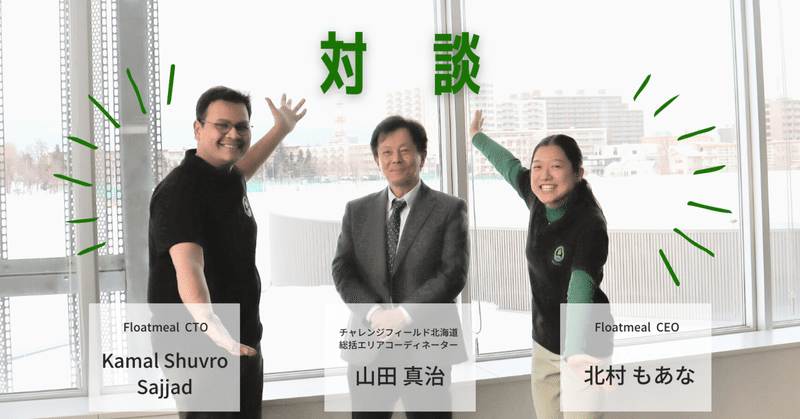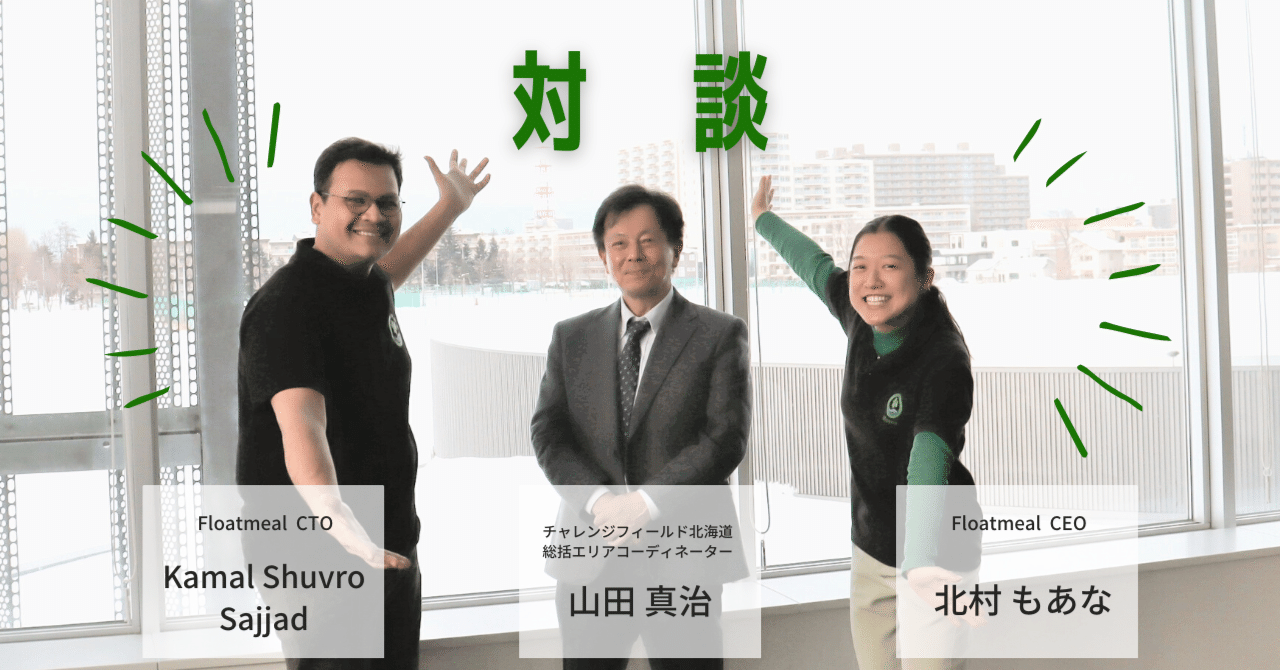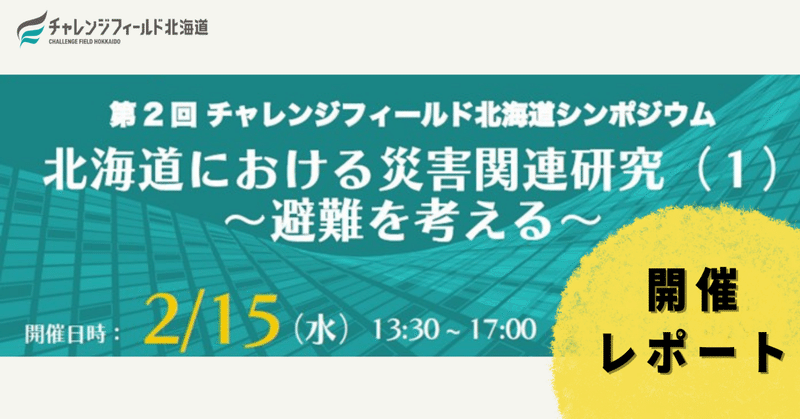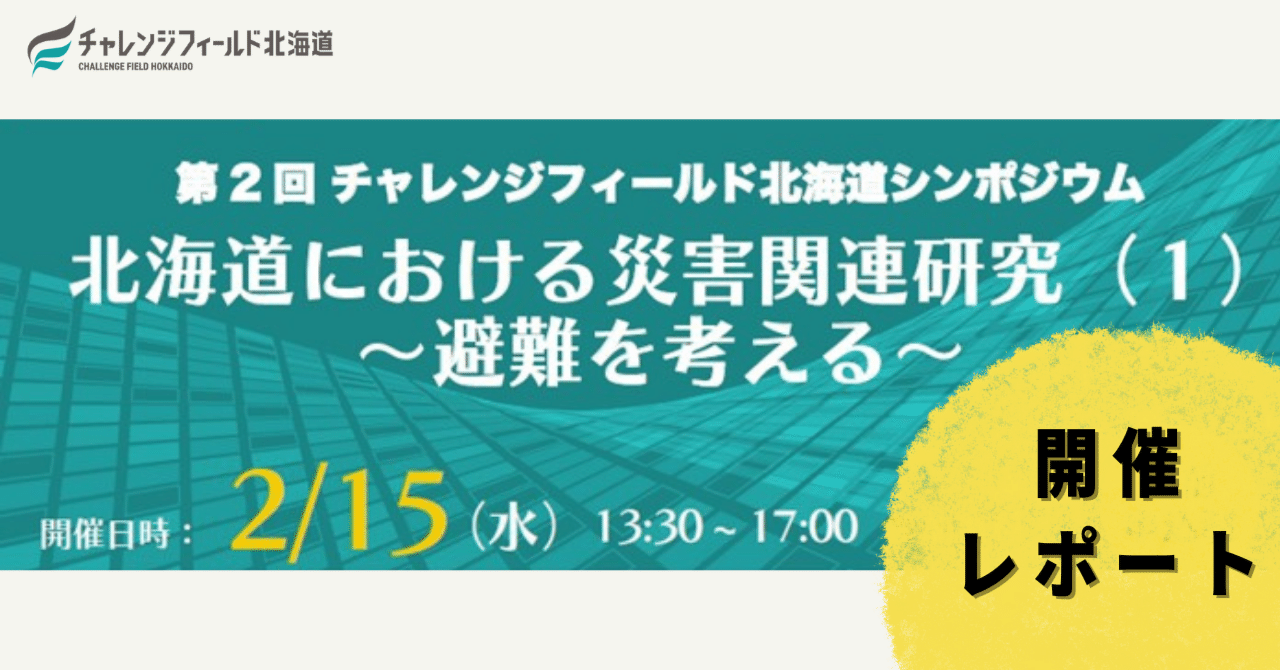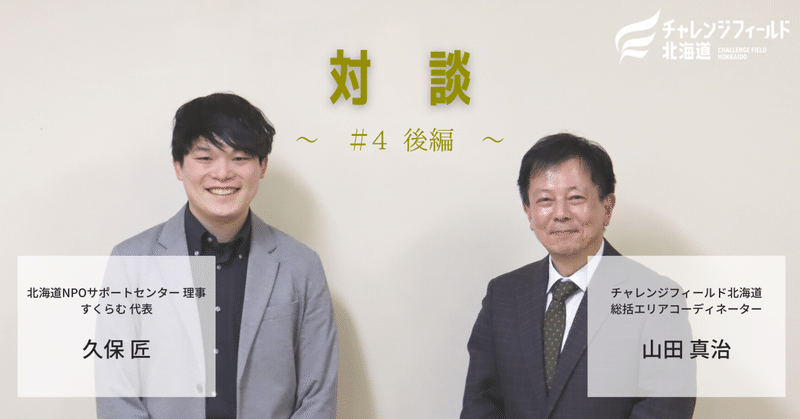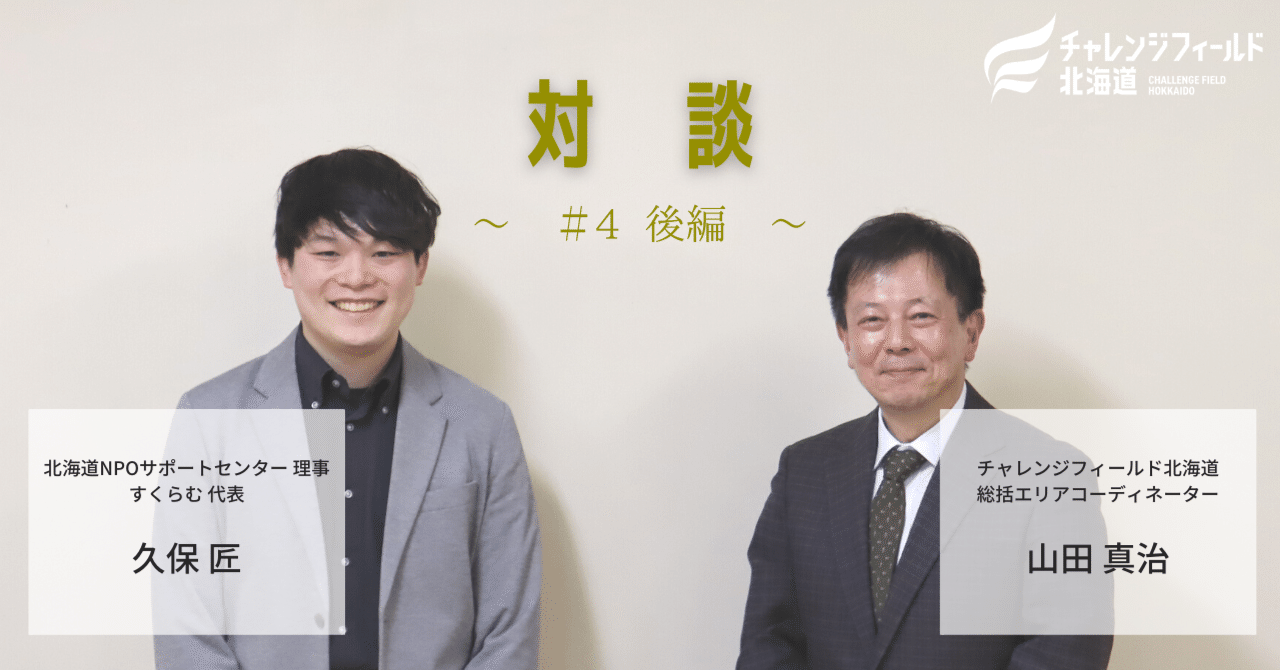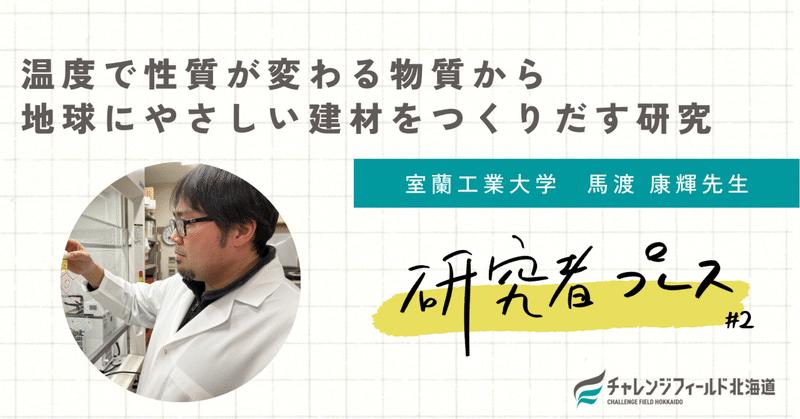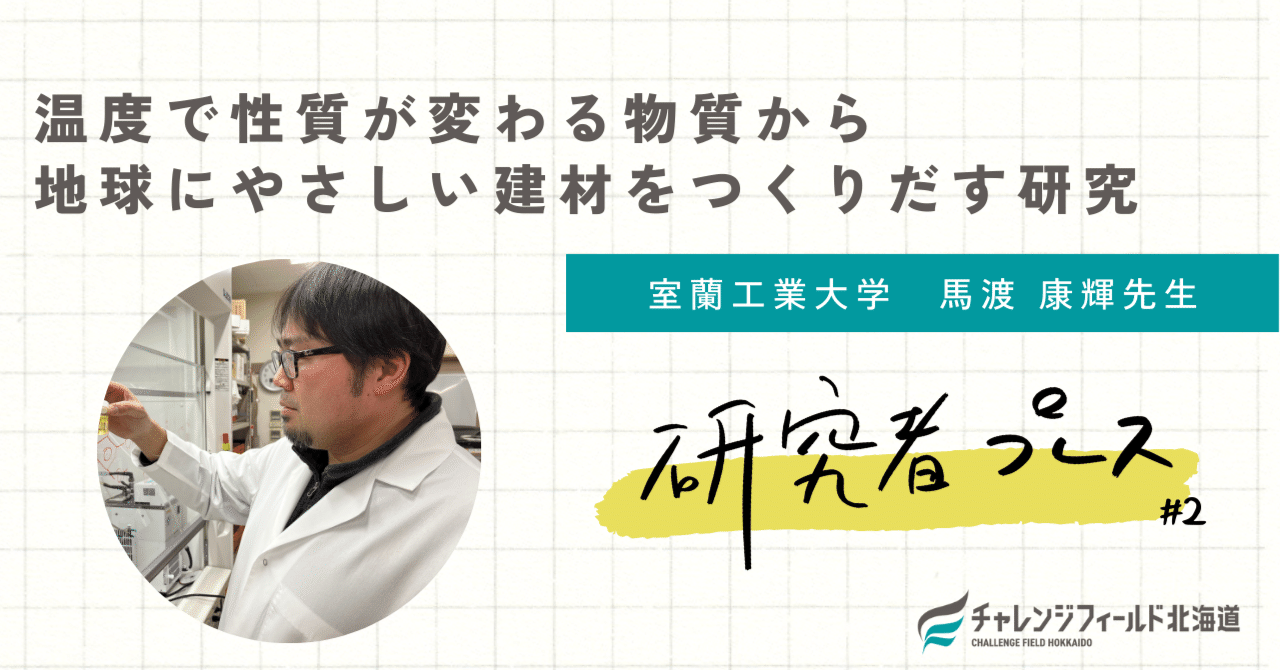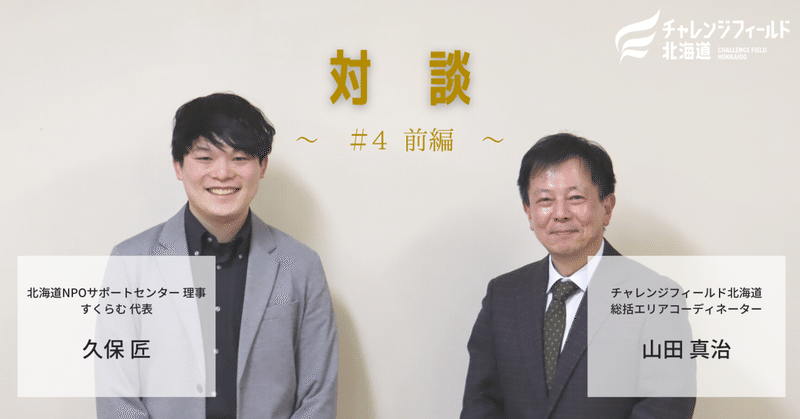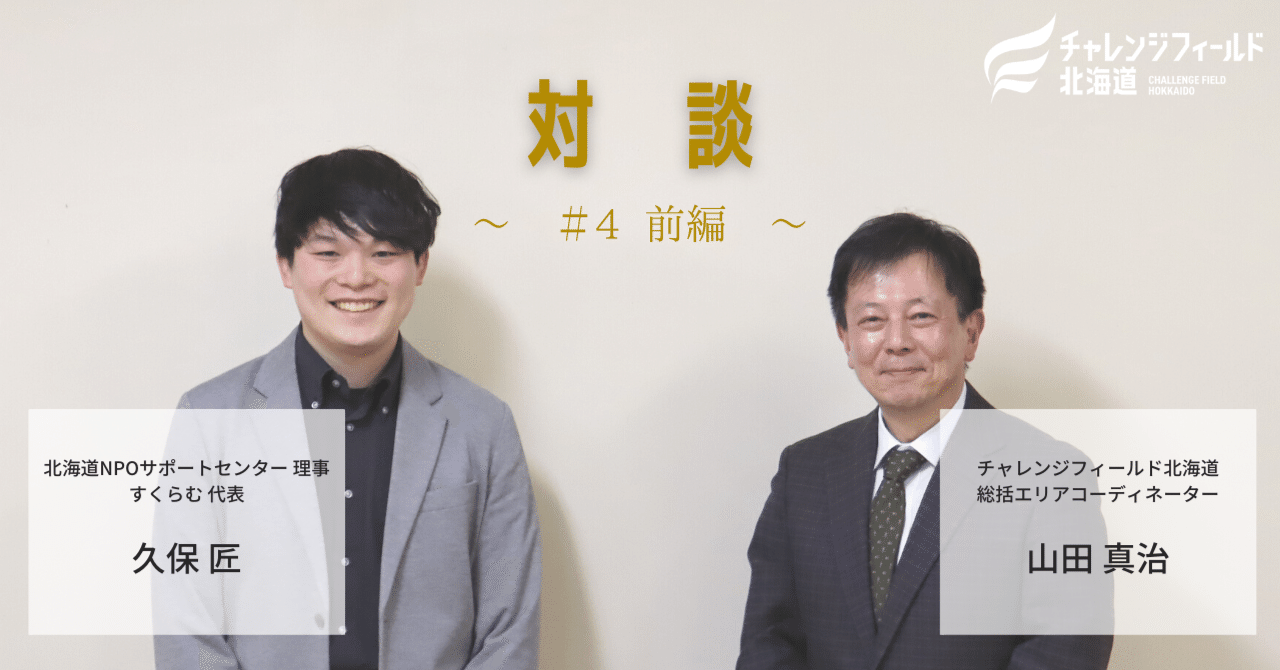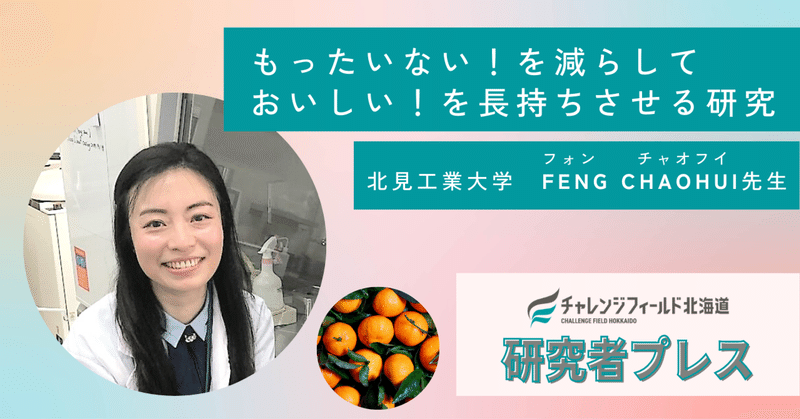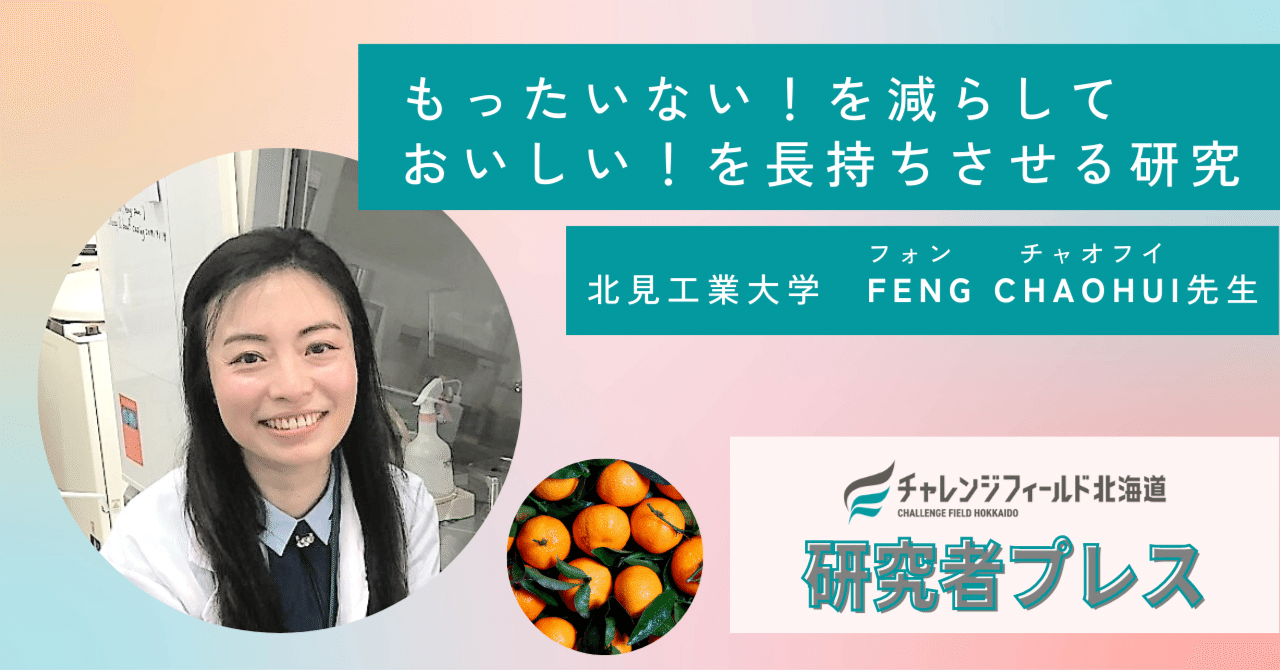最近の記事
マガジン
記事

【開催レポート:チャレンジフィールド北海道シンポジウム#4】気候変動が道内の第一次産業や道民の日常生活に与える影響と適応の取組
チャレンジフィールド北海道では、「チャレンジフィールド北海道シンポジウム」と題し、北海道内のさまざまな課題に対して関係者同士をつなぎ、イノベーションを創発するための場づくりを令和4年度から開始しました。 第4回目はテーマを「気候変動と道内の第一次産業や生活に与える影響」として、10月18日にオンライン配信にて開催し、196人の皆様にご参加いただきました。たくさんの方に視聴いただき、ありがとうございました。 1.開催の経緯近年、道内においても、台風の接近や上陸、連続する真夏