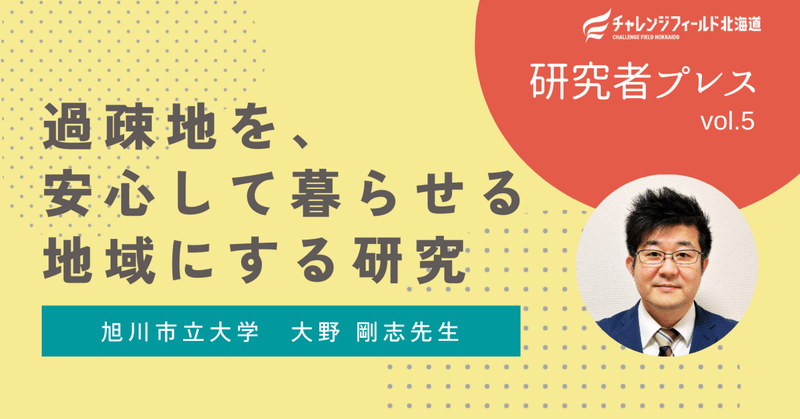
過疎地を、安心して暮らせる地域にする研究【チャレンジフィールド北海道 研究者プレス#5】
チャレンジフィールド北海道イチオシの先生を紹介する【研究者プレス】。研究はもちろんのこと、研究者ご自身の魅力もわかりやすく伝え、さまざまな人や組織との橋渡しをしていきたいと思います。第5弾は、旭川市立大学の大野 剛志(おおの たけし)先生です。

日本全国津々浦々、人の営みのあるところには課題が付きものです。少子高齢化、青壮年労働力の流出、農林漁業の後継者不足の問題にあえぐ「過疎地」、来街者の減少にみられる求心力の低下だけではなく、町内会などのコミュニティ活動が停滞しがちな「市街地」、震災によってこれまで築いてきたコミュニティが分断され再構築が求められている「被災地」 。それぞれに悩みを抱える地域を訪れ、住民からの信頼を得て、彼らの本心を聞き、「誰もが安心して暮らせる地域社会(コミュニティ)のあり方」を模索してきたのが、旭川市立大学の大野剛志先生です。20年以上にわたり、実態調査を重ね理論化をすすめる地域社会学の実証研究のスタイルで、住民と共に道内各地で地域づくりの実践に取り組み、いくつもの地域を再生へと導いています。

地域社会学の「地域」は3つある
―ご専門の「地域社会学」とはどんな学問ですか。
社会学の一分野で、社会学の理論を用いて「地域」を多角的に分析する学問です。地域の課題を発見して、住民をはじめとする関係者とともに、解決策を考えていきます。私の研究テーマは「地域で安心して暮らす」、主な研究対象は「過疎地」です。現地での聴き取り調査を通して、住民の生活実態を知り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会(コミュニティ)のあり方を研究しています。

―「地域づくり」「地域おこし」など、「地域」という言葉はよく見聞きしますが、地域社会学における「地域」とは何ですか。
ひとくちに「地域」といいますが、3つのとらえ方をしています。まず、いわゆる「エリア」。地形や行政などの条件により区画された土地であり、個人の生活圏といえます。これは、地理的・歴史学的なとらえ方ですね。エリア内(範域)には、自然環境や文化など、その土地独特の風土があります。
次は、より社会学的なとらえ方で「コミュニティ」。日本語では「生活共同体」といいますが、血縁ではなく地縁の人間関係です。向こう三軒両隣といわれてきたような「人と人とのつながり」と、町内会のような「生活互助の仕組み」から成っています。
そして、心理学的なとらえ方で「We-feeling(われわれ感情)」。地元への愛着や誇りなど、その地域への帰属意識ですね。
地域社会学では、「エリア」という土地、「コミュニティ」という人間関係、「We-feeling」という感情の3つの観点から「地域」をとらえ、研究しています。
北海道は、過疎化・少子化・高齢化・人口減少に伴うコミュニティの危機という四重苦に陥っている市町村が少なくありません。札幌・旭川・函館をはじめとする都市部に人口が集中する一方、地方の郡部では過疎化がさらに進んでいます。
道内の過疎地域は152市町村(過疎地域自立促進特別措置法に基づく道内の過疎地域指定)で全体の84.9%(2022年4月1日現在)を占めるまでに至っています。「平成31年度(2019年度)北海道集落実態調査」によると、道内の限界集落(註1)は28.5%(2019年4月1日現在)に達し、限界自治体は6自治体にのぼります。それゆえ、道内の多くのまちで今まさにコミュニティの再生が求められているのです。
註1 限界集落とは、高齢化が進み、65歳以上の人口が50%以上を占める地域のこと。地域産業の担い手が不足し、冠婚葬祭などの相互扶助など社会的共同生活にも支障をきたす。環境社会学者の大野晃氏(高知大学名誉教授)が提唱した概念である。限界集落の定義には「量的規定(高齢者比率)」と「質的規定(集落における社会的共同生活の実態)」の2つの規定がある。集落の限界性を判定するためには量的規定のみならず質的規定に関わる確かな実態把握が必要なことから、北海道庁は限界集落という用語はあえて用いずに、「65歳以上の割合が50%以上の集落」と定義している。
―コミュニティの再生にはどのような手法がありますか。
地域の課題によって解決策はさまざまです。ただ、かつて地域活性化の鍵といわれた「よそ者、若者、ばか者」の「よそ者」、つまり新規参入者がブレークスルーをもたらすことは多いかもしれません。たとえば、空知エリアの長沼町は、過疎化・少子化・高齢化に悩んでいました。そんななか、ある移住者の発案により、地元民が体験農業という既存の農業の枠を超えた新たなビジネスに挑戦します。それが、農業と観光を融合した「グリーン・ツーリズム」です。いまでは、長沼町における農業経営の柱のひとつともなっています。
また、上川エリアの下川町は、過疎化・少子化・高齢化により、林業の後継者不足に悩まされていました。危機感を覚えた下川町森林組合は、1990年代から町外にも人材を求め始めます。それが功を奏して、林業がやりたい!と東京から移住者がやってきました。いま、下川町は循環型森林経営をうたい、さまざまなビジネスを展開していますが、地元の魅力を上手に発信しているから、ますます注目度が上がっていますね。
長沼町も下川町も、キーパーソンは新規参入者です。しかし、意欲ある優秀な人が移住してきたから、コミュニティが再生したわけではありません。地元の人たちが危機意識をもって、来る者を拒まずに受け入れることで、移住者がもつ発想やスキルに触発され、集落全体に移住者の技術やノウハウが伝播していったのです。我がまちの課題を協働で解決する実践によって地域が活気づいたのだと思います。
「限界集落」が息を吹き返した
―移住者が来ないと、地域の活性化は難しいですか。
移住者がいないと地域が活性しないわけではありません。たとえば、上川エリアの幌加内町母子里(もしり) 集落。2013年の調査時点では19世帯35人、そのうち移住者は2人でした。年齢構成は15歳未満の子どもは2人、15歳から64歳の生産年齢人口は北海道全体の平均値の半分ほど、逆に、65歳以上の高齢者人口は2倍以上。集落の消滅を危惧した北海道庁が、調査に乗り出します。北海道庁の依頼を受け、私は、地域社会学の専門家として、住民の聴き取り調査と集落の構造分析を担当しました。
調査で明らかになったのは、コミュニティが生きていること。いわゆる限界集落において、なぜコミュニティが維持されていたのか——。それは、他出子(註2)のサポートがほとんど期待できないからです。日本の家族研究では、実家のもしものときには、他出子が支えると考えられてきました。ところが、母子里集落は、救急車を呼んでも到着までに1時間はかかります。親がSOSを出しても、遠距離にいる他出子が駆けつけられるのは4、5時間後ということも。それならば、隣近所に助けを求めて、車で名寄市立病院に連れて行ってもらうほうが早い。そんな地理的な事情もあり、日頃から隣近所との関係性を非常に大事にしているわけです。
註2 他出子(たしゅつし)とは、集落から転出し別世帯をもった子どものこと。

―「遠くの親戚より近くの他人」ですね。
そのとおりです。親密な近所づきあい、積極的な自治会活動への参加がないと、母子里集落では生活が充足できないと言っても過言ではありません。
また、隣近所との良好な関係は、地元への愛着や帰属意識の源泉ともなっているようでした。集落全体を家族のように感じている人が多く、まさに「地域家族」ともいえる関係性が構築されていました。じつに9割近くの人たちが「母子里に住み続けたい」と話してくれたのです。深刻な過疎化・少子化・高齢化にもかかわらず、隣近所で支え合う互助の仕組みを維持することで、集落全体で安心した共同生活を成り立たせている母子里集落は、限界集落ではないと、私は結論づけました。
―とはいえ、人口が減り続けると、住み続けるのも厳しそうです。
住み続けるためには何が必要なのか。それを考えるために、住民座談会が開かれました。対話を重ねながら、住民たちは母子里集落の魅力を再発見していきます。魅力のひとつが、雪と寒さ。マイナス41.2℃の日本最低気温の記録をもつ母子里では11月末には雪が積もり、ゴールデンウィークを過ぎてようやく解ける雪は、冬の暮らしを困難にします。しかし、母子里という土地の特性でもあり、見方を変えれば、ほかの地域にはない魅力となるのです。実際、母子里の雪に魅せられて、スキーがしたいと移住してきた住民、写真を撮りにくる来訪者がいます。
さらに多くの人たちに母子里を知り、好きになってもらおうと、住民たちが考案したのが、「母子里と出会う旅−◯◯−」という地域活性化イベントです。「◯◯」には、春夏秋冬いずれかの季節を入れ、四季折々の母子里を楽しんでもらいます。ターゲットは、都市部に暮らす子育て世代。まずは交流人口(註3)を増やし、将来的には移住や定住につなげるという狙いもありました。私は地域づくりの専門家として、こうしたコンセプトづくりのアドバイザーを務めました。ポイントは、企画発案から当日の運営まで全て住民の手づくりであることです。母子里の集落住民と母子里に研究施設を置く北海道大学雨龍研究林のスタッフ、そして私たち旭川市立大学の教職員で、「母子里と出会う旅実行委員会」を結成し、有志による協働方式で当イベントを運営しています。地域の人たちが顔をつきあわせて、あれやこれやと話しながら取り組む過程こそが、地域づくりだと、私は考えています。母子里集落の成功は、地域住民が自ら考え、行動したことにあるのです。
註3 「交流人口」とは、通勤・通学・観光・買い物などで、地域を訪れる人たち。一過的な関わり方であるために地域との結びつきはあまり強くはない。また、その地域に居住している人たちを「定住人口」、当該地域に継続的に関わりをもつ人たちを「関係人口」という。
地域づくりの鍵は「人づくり」にあり
―過疎地に「移住者を増やす」は難しそうですが、「ファンをつくる」はできそうな気がしてきます。
地域が過疎化する背景には、産業や教育、福祉の脆弱さがあります。仕事がない、学校がない、医療施設がない、子育て支援がない……だから、人は都市部へと出ていくわけですね。そこに移住者を呼び込んでも定着はしません。まずは、安心して暮らすための土台を磐石にするべきです。これからの地域づくりには「移住施策」だけではなく、「定住施策」「出産・子育て施策」が重要になると考えています。この3本の矢がそろっている地域は強く、東川町のように移住者・定住者を増やせるのです。
ただ、定住人口の増加を目指さなくてもいいのかもしれません。現地調査でお世話になった厚真町役場の方が、「交流人口は定住人口・移住人口に必ずしも結びつかなくてもいい。定期的に訪問してくれる関係人口が一定数いれば、地域は活気づくし、復興にもつながる」と話してくれました。とても重要な指摘で、地域づくりの鍵は関係人口をつくれるか否かだと考えています。

【出典】総務省ホームページ「地域への新しい入口『関係人口』ポータルサイト」より画像引用
―どのように関係人口をつくればいいですか。
関係人口になる可能性を秘めているのが、学生です。旭川市立大学は教育目標として、「市民と協働して地域課題に取り組む」「地域社会に貢献する」ことを掲げています。授業での学びを、地域での実践に生かそうというわけです。私が担当する地域密着型授業「コミュニティ調査実習」では、本学コミュニティ福祉学科の2年次必修授業として学生40名が毎年厚真町で合宿を組み、年間を通し地域活性化の研究をしています。事前視察、聴き取り調査、事例研究、現地報告会の学習過程のなかで学生たちが定期的に厚真町に通います。正課のカリキュラムであることから学生が「定期的」かつ「継続的」に地域に関わることが可能です。学生は地域の生きた社会と触れる学びの機会となりますが、住民は大学生の調査分析結果を自治体の行政計画やまちづくり計画の見直し改善に活用できる点で、地域にとっては大学生という「関係人口」の獲得となります。
こうした正課授業のほか課外活動でも、被災地応援ボランティアサークルCROSSを設けて、学生たちにはどんどんフィールドワークに出てもらいます。地域・学生・大学の三方がともに相乗効果をもつ「三方よし」の関係性を構築維持することが、本学の伝統となり、地域との信頼関係が続いていくと思うのです。
「地域づくりの処方箋」には、産業技術が不可欠なことも
―フィールド調査を通して感じている課題は?
私たちは地域社会学の知見に基づき、地域の課題を析出することで、それを乗り越えるための地域再生の処方箋はつくれます。コミュニティの結束や充足度に価値を置いている地域には地域社会学の方法論はよく効きますが、暮らしの土台となる産業の発展を求める地域では効果が弱まることも。というのは、私たちには産業に結びつく技術を持ち得ていないからです。たとえば、農村地帯の調査では、農家の人に「もっと生産力を上げる方法を教えてほしい」と要望を受けることがあります。でも、私は農業技術をもちあわせていません。正直に伝えると「使えないやつだなあ」と呆れられます。地域社会学の範疇を超えた技術やノウハウが必要なとき、どうするのか。そこが課題ですね。
―これからの目標は?
私たちにない技術をもつ研究者や企業と協働できる仕組みがあればいいなと考えています。たとえば、「この地域にはこんな課題がある」「この人がこんな技術をもっている」といった私たち社会学研究者が得ている情報や知見、そして地域社会学に基づく地域活性化・地域再生の処方箋を、工学系の産業技術の力と結びつけることができれば、地元企業の活性化の面でもさらに地域に貢献できると思うのです。

--------
大野先生の原点は、ふるさとの青森県野辺地町にあります。高校生のころに、過疎化により地元の産業が衰退していくさまを目の当たりにしたとき、問題意識をもちながらも、自分の力では解決できないと思っていたといいます。旭川大学(現 旭川市立大学)で社会学と出会い、地域の問題にアプローチする方法を知り、研究へとのめりこんでいきました。
とりわけ印象に残ったのは、「私たちには産業に結びつく技術を持ち得ていない」という大野先生の悩み。地域社会学の専門家が、産業技術に精通している必要はないはずです。しかし、地域に深く関わり続けてきたからこその実感であり、その言葉は重いと感じました。過疎化の深刻な地域こそ、暮らしの土台となる産業とその発展が不可欠なのだから。大野先生によると、これからの地域研究には、地域づくりの成功事例に学び、地域ごとの処方箋による課題解決が必要といいますから、産業技術をもった人たちとの協働はますます重要になっていくのだと思います。地域ニーズと研究シーズを結んできた「チャレンジフィールド北海道」も、さらにチャレンジしていかなければならないと、決意を新たにしたのでした。
[大野先生プロフィール]
大野 剛志(おおの たけし)
旭川市立大学 保健福祉学部コミュニティ福祉学科 教授
旭川市立大学 地域連携研究センター 所長
出身地は青森県野辺地町。地元の産業が衰退していくのを肌で感じ、過疎化に関心をもつ。旭川大学経済学部に入学、指導教授(教育社会学)の影響により社会学を専攻。地域研究にアプローチする。同大学院にて修士(地域政策学)を取得。北海道大学大学院文学研究科人間システム科学専攻社会システム科学講座(社会学講座)の博士課程を修了。博士(文学)学位取得。2008年、旭川大学(現 旭川市立大学)に着任、2021年より教授。
■連絡先:oonotks@live.asahikawa-u.ac.jp

■研究者プレスダウンロード版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
