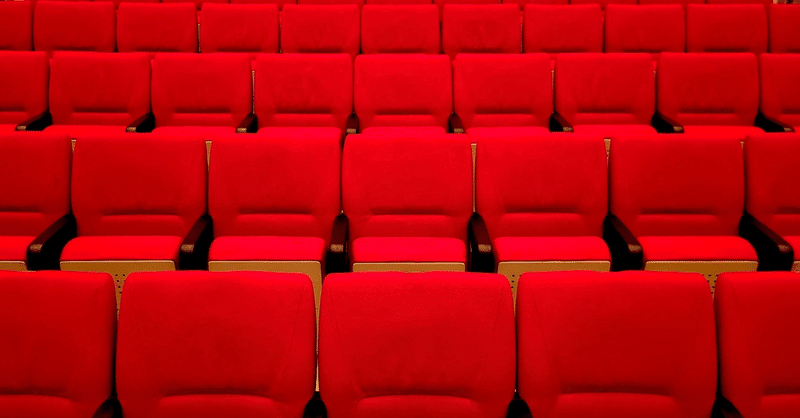
ずっと続いてほしかったエンドロール。
わたしの好きなドラマ、「カルテット」。
夢がかないそうで叶わない。
いつまでこんなことやってるんだっていう
想いにも駆られながらも、夢にピリオドを
打つことを止めにした彼らが好きだった。
一緒に下る坂を下ろうぜみたいな。
四重奏楽団カルテットを組んだ男女4人の
物語。
脚本の坂元裕二さん好きな人には馴染み
すぎているぐらいの
台詞だけど。
泣きながらご飯食べたことがある人は、生きていけます。
っていうのがある。
主人公のマキさん(松たか子)が、いろいろありすぎた
人生のために、仲間にも嘘をつかなければならなかった
かつ丼頬張るすずめちゃん(満島ひかり)に言うのだ。
かつ丼を、すすりながらほお張る。
喉の奥のしょっぱさまでつれてきてくれそうな、
すずめちゃんのかつ丼。
でも、食べたら即エネルギーになってくれそうで。
目の前にいる、マキさんが放ってくれたその言葉もろともすずめちゃんが、どんぶりごと食べちゃうんじゃないかっていうぐらいの、あの破れかぶれな食べっぷりがすきだった。
同じような体験をわたしもした。
何年も前、わたしは大好きだった人を失って。
そう書くとずっと付き合っていたひとを失ったように聞こえるけど。
失ったことで好きだったことに気づいた彼がいた。
クリスマスイブだった。
横浜の黄金町の映画館で追悼上演会があったので、その映画館を訪れていた。
好きだった人が出演していた映画だった。
わたしの若かった頃の支えになってくれた
父親のような人だった。
その映画『一万年後、…。』の時間軸は、
タイトル通り現代じゃなくて。
平成時代が遠い昔のことになっていて、
いまや日本は存在しないようなずっと
先の先の時代を描いていた。
一万年前に生きていた映画監督の男が、
未来の甥と姪に電波の狂いのせいで、
出会ってしまう。
でも、出会う場所は、まるで昭和の
ど真ん中を象徴するようなちゃぶ台の
あるお茶の間だったりして。
予定調和はどこにもない。
つまり「あの世」を描いているのだけれど。
そこには、いろいろな不可能ばかりがつまっているはずなのに、既視感に支えられているせいか、こっちのアンテナもゆるやかにあやしくなってくることが心地よかった。
映画を見ていてちゃんとシーンのひとつひとつに裏切られて、どこに連れて行かれるかわからない体験も久しぶりで。
映画の中で「彼岸」からやってきた
映画監督を演じているスクリーンの中の彼。
いま、ほんとうに彼はこっち「此岸」にはいなくて。
時々そのことがあまりにリアルすぎて、
戸惑った。
最後の場面は「ゴンドラの唄」だった。
♪いのちみじかしこいせよおとめ。
その歌はなんとなく知っていたけれど、
ちゃんと聞いたことがなかった。
最後の場面はもう映画は終わってエンドロールが流れた後のシーンだった。
その歌が、初めから「ゴンドラの唄」だとわからないぐらいの、電波の乱れの中に隠れていて、ずっと耳をすませていると、やがてそれがあの歌のメロディーに時間をかけてむすばれてゆく。そんな演出だった。
なにもないスクリーン上で音だけが存在感をもって、響いてゆく。
それも歌声は、とてもお年を召した方のご婦人たちの懸命な歌声で、それを聞いているだけで不覚にもなみだしてしまった。
だんだんとチューニングがあっていなかったものが、そろりそろりとひとつの鍵穴みたいなところにおちて、やがてぴたりとあってゆく。
このことは人が出会って別れてゆくときそのものみたいで、ほんとうに途方に暮れた。
映画を見終わった後の余韻があまりに濃密すぎて一瞬、このままあの人がいない世界で生きていくのはつまらないなって思った。
その映画館に住んでしまいたいぐらいそこを
離れるのがいやだった。
扉を開けて、映画の空気を纏っていた外にでた。
フライヤーを幾つか手にした。
ほんとに観たかったわけじゃない。
ちゃんと生きてゆくための、お守りのような
フライヤーだったのかもしれない。
階段を降りきって、外に出た。
まだ陽は暮れる前で。
ひとりのどこか南米系のおじさんが、何かを
そこで売っていた。
そこで立ち止まっているのはわたしひとり
だった。
「美味しいよ、ブラジルのパンだよ」
夕方には似合わないような明るいそんな
声がした。
ずっと映画館にいたので、会話するのは
そのブラジルから来たらしいおじさんが
はじめてだった。
生身の声を耳に感じていた。
わたしは涙目になったままだった。
恥ずかしいなって思いながらも、買いますって言っていた。
まるっこい、焼き菓子のようにみえたそれは
ポンデケージョというブラジル生まれのパン
だった。
たくさん買うことにした。
沢山、買ってくれたからってまたおまけで
その丸い、プチシューみたいなパンを紙の
袋に入れてくれた。
おじさんはニコニコしていた。
わたしはめそめそしていた。
ありがとございますって優しい日本語で
答えてくれて、振り返ると笑顔のまま手を
振ってくれた。
袋から伝わってくるちいさなパンたちの
温かさ。
わたしはひとつだけを食べてみたくなって
静かに口にした。
ほんのり塩味だった。
あっさりとしたチーズ味。
甘いのかなって思っていたから、舌が
裏切られたけど、その食感が涙腺をゆさぶった。
わたしは泣きながらブラジルのパンを
食べていた。
とつぜん死んじゃったのか、あの人はって
思いながら
泣きながら食べていた。
泣きながら食べるって思ったよりも
つらいんだなって。
ポンデケージョのあのさりげない塩味。
あの塩味は、今思い出すとそれはちょっと
甘美に蘇ってくる。
『一万年後』でもいいから、会いたい。
なんとか生きてるよ、ありがとうって
いまは彼に伝えたい。
いつも、笑える方向を目指しています! 面白いもの書いてゆきますね😊
