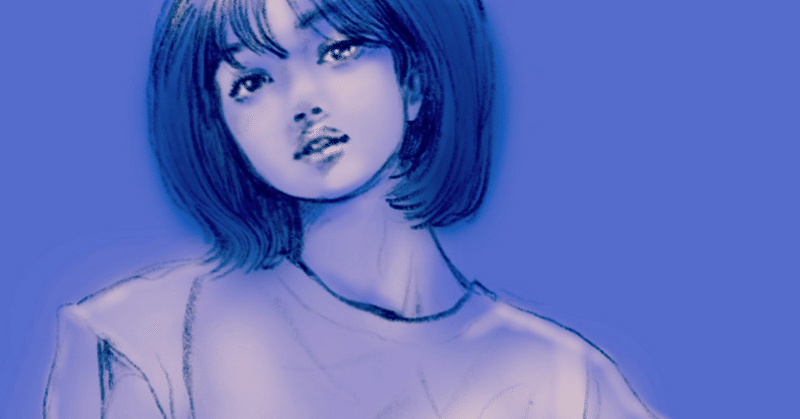
好きになってくれる人なんて、永遠にいないと想っていた。
文芸部って聞くとだっせーってずっと思ってた。
ボール蹴ってる方がましじゃね?とか思ってた。
青春は密ですからって言葉はまだなかったけれど
そっちのほうが尊いとさえ思っていた栞。
身体に汗をかくのと脳の中に汗をかくのは身体の
ほうがえらいと思っていた。
栞はあまり他人のことに関心のない学生生活を送って
いたし。
自分のことに興味がある人間なんてこのクラスのどこかに
いるんじゃろか? って思いながら乾いた高校生を
やっていた。
キーボードの上に指を置いて、横に横に立ち現れてくる文字を
みていると、なんだか打っているそばから、その文字達は
どんどん左から右へと流れて消えてしまうような感覚に陥るん
だよ。
それは文芸部の伊藤君の言葉だった。
それがいいのかどうなのかまだわからないけれど消えてゆく、
からっぽ感にすくわれる事も時折あるんだよな。
って。
栞にとって文芸というジャンルは伊藤君から始まった。
<紙には天と地がある。地に向かっては重力が働く。その重力に
沿ったり、耐えたりあるいは押し戻したりしながら字をつづって
いく。そこには自ずと自制や自省が生じる>
伊藤君が好きな書家の石川九楊さんの言葉を新聞の切り抜きで
知った。
その文章を読んでいるとき、こんなにも横書きに慣れてしまった
にもかかわらず、こぶしひとつぶんぐらいの爽快感を栞は憶えた。
そして昔ならっていた書道の時間を思い出したりしていた。
筆と半紙のあのもどかしい関係が甦ってきて、半ば苦い思いに
駆られる。
それは好きになり始めた伊藤君との関係性に似ていて、薄ら笑い
したくなるほどだ。
墨をふくんだ筆が半紙の上で、どうにもままならなかったのは、
そこに生まれた重力のせいだったのだと、今更ながら気づく。
抗うなにかがあると、なにかを無防備に突破することがためらわれ
たり、あぐねたりするこころの動きがたちまち腕から指へそして
筆へと伝わってきて、半紙の上で掻き乱されてしまう。
わかりあえたとおもったせつな、それはまぼろしだったような。
まぼろしだからいつまでもあこがれがあるような、
なんだかもやもやしたものを抱えたままのような。
放課後の文芸部室に栞は招かれた。
伊藤君とふたり、音楽部から聞こえてくるへたくそな
マイルス・デイヴィスのトランペットを聞きながら、ふたりで
笑っていた。
人の努力を笑った後はちょっと苦い思いになるなって
伊藤君が言って、ふたりで笑うのをやめた。
こういうこところが伊藤君が文芸部を選んだゆえんかも
しれんとか想いながら。
音楽を聴いていると、耳の中をかすめたメロディは重なり
あうように音を連ねながら、たちまちどこかへと消えてゆく。
消えてゆくけれど、それはなくなってしまったわけじゃない
ところが、音の凄みかなって思う。
下手なマイルス・デイビスのトランペットを聞きながら栞と
伊藤君は手をつないだ。
心なしか冷たい手だった。
栞は高校を卒業してからもうずいぶんと時間が経ったことを
まるでじぶんのことじゃないように思い出していた。
文芸となんら関係のない人生を栞は送っていると苦笑した。
しろかくろかきめられない感じが、年を重ねてとても増えた
感じがする。
若い頃のあの好き嫌い観のその輪郭が薄らいでいる。
縦書きの重力とあらがうその葛藤の時間の撓みも魅力だし、
またたくまに流れて行ってしまう横書きの風通しのよさも
すきだなって思うこのごろ。
たとえば横の人、縦のひと。
伊藤君の好きだった石川九楊さんのことばを知って自分の頭の
中に、横の引き出しと縦のひきだしがふたつ増えた。
記憶のなかのいろんな人たちをそっと入れておく箱が、できた
みたいで、すこしばかり栞は愉快だった。
🖊 🖊 🖊 🖊
今日もぎりぎりにシロクマ文芸部のお題に挑戦しています。
小牧幸助さんいつも企画をありがとうございます。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
みなさま残暑お見舞い申し上げます。
どうぞご自愛くださいませ。
いつも、笑える方向を目指しています! 面白いもの書いてゆきますね😊
