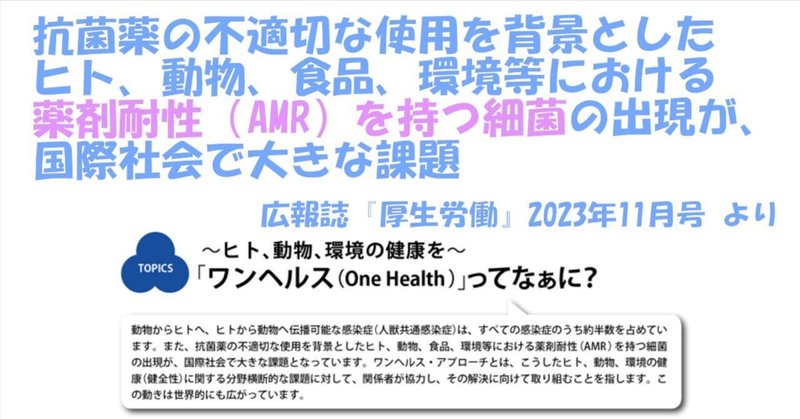
メディアが報じ始めた「薬剤耐性」の不自然さ
中国で、小児を中心に呼吸器感染症が増加していると報じられています。WHO は11月23日に中国当局と電話会談を実施し、「既知の病原体による呼吸器感染症によるものとして矛盾はない」との見解を発表。テレビなどでは中国からの情報を伝えるニュースの中で、「薬剤耐性」という言葉を使い始めました。これまではあまり耳にすることはありませんでしたが、パンデミック条約やIHR改正について調べている中で、いずれ出てくるだろうと思っていた言葉です。
中国で感染拡大している肺炎
11月24日付で、厚労省は各自治体に向けて下記の事務連絡をしています。
厚労省 令和5年11月24日付 事務連絡
中華人民共和国における小児の呼吸器感染症の増加について(周知)
今般、中華人民共和国(以下「中国」という。)において小児の呼吸器感染症が増加していることが報告されています。原因としては、季節性インフルエンザウイルス、肺炎マイコプラズマ、RS ウイルス、アデノウイルス等が報告されており、未知又は新たな病原体は確認されていません。
参考資料1として、WHOの見解が書かれたページが示されています。
Administration of Disease Control and Prevention, in which the requested data were provided, indicating an increase in outpatient consultations and hospital admissions of children due to Mycoplasma pneumoniae pneumonia since May, and RSV, adenovirus and influenza virus since October.
電話会談で得られたデータは、「5月以降はマイコプラズマ 肺炎、10月以降はRSV、アデノウイルス、インフルエンザウイルスによる小児の外来診療や入院が増加している」ことを示していたとのこと。
厚労省検疫所のサイトに、日本語訳がありました。
参考資料3として、北京市衛生健康委員会のサイトが示されています。
下記の部分に注目します。
为何2023年感染症状偏重?
支原体肺炎在儿科的呼吸道疾病中比较多发,一般高发于秋冬季,3-5年为一个小高峰,2023年是一个感染“大年”,支原体的病原可能有一些基因的变异,对阿奇霉素有一定抗药性,相对来说症状就偏重。2022年的支原体感染表现可能只是咳嗽,但2023年的病株容易特别快引起肺部的感染。
「なぜ2023年は感染症状が深刻なのか?」という項目には、下記の5点が書かれています。
・マイコプラズマ肺炎は、小児の呼吸器疾患の中では比較的多く、通常は秋から冬に多く発症する。
・3 ~ 5 年ごとに小さなピークがあり、2023 年は感染が多くなる年である。
・マイコプラズマの病原体には、いくつかの遺伝子変異がある可能性がある。
・アジスロマイシン(抗生物質)に対する薬剤耐性があると、相対的に症状は重篤となる。
・2022 年のマイコプラズマ感染症の症状は咳のみだったといえるが、2023 年のマイコプラズマ株は肺感染症を引き起こしやすい可能性がある。
「2022年的支原体感染表现可能只是咳嗽,但2023年的病株容易特别快引起肺部的感染。」の部分は、前の文とはつながっていません。
なので、薬剤耐性の話は一般的な説明であり、2023年に肺感染症を引き起こしやすい理由として書かれたものではないと読み取れます。
下記は、国立感染症研究所が11月24日に発信した情報です。
なお、中国においては、これまで肺炎マイコプラズマのうちマクロライド系抗菌薬に耐性を示すものの割合が高いことが知られており、北京市CDCによると、2023年に報告されている肺炎マイコプラズマにおいても、遺伝子変異により、アジスロマイシンに対して一定の薬剤耐性を持つ可能性が指摘されている。
この部分の参考資料は、厚労省が示したものと同じ北京市衛生健康委員会のページです。
やはり、薬剤耐性を持つ「可能性が指摘されている」と書かれているだけです。
大手メディアの取り上げ方
マイコプラズマが原因の細菌性疾患は、症状が比較的軽く、発症しても歩けるほどであることから「歩く肺炎」と呼ばれているそうです。けれども、「“歩く肺炎”激しい咳が4週間」などと見出しに使うと、なんだか恐ろしい病気のように感じます。
「歩く肺炎」というのは、英語の「walking pneumonia」を訳したようですが、他のメディアにあった「歩ける肺炎」の方がしっくりくると思いました。
WHOの情報では「5月以降はマイコプラズマ 肺炎、10月以降はRSV、アデノウイルス、インフルエンザウイルスによる小児の外来診療や入院が増加している」とのことでした。コロナ以前は、複数のウイルスが同時に流行することはあまりなかったと言われています。たとえば、秋にRSウイルスが流行していても、冬になってインフルエンザウイルスが出現するとRSウイルスの方は終息するなど、「ウイルス干渉」の研究が行われてきました。
それが、コロナ以降は変わってきているようです。ですから、RSV、アデノウイルス、インフルエンザウイルスの同時流行の要因などにも注目すべきだと思うのですが、テレビではなぜかマイコプラズマ肺炎に絞っています。
下記には、TBS「Nスタ」(12月7日)で取り上げた内容がまとめられています。下記のページでは、動画も見ることができます。
“歩く肺炎”と呼ばれるマイコプラズマ肺炎が世界的にも流行してきている説明から始まり、マイコプラズマ肺炎はどのような感染症かという説明に続きます。
終盤、解説していた医師は、「各国で増えていることを考えると、日本でも増えてきてもおかしくない。そして、中国のマイコプラズマの中でも『耐性菌』、抗生物質が効かない菌が増えているということも、より詳しいデータが知りたい」と締めくくりました。
それまでの話では、耐性菌には触れていませんでしたが、急に出てきたのです。しかも、「可能性がある」ではなく「増えている」と言っています。
するとコメンテーターは、下記のようにまとめます。
やはり「公衆衛生」という言葉のあり方だと思ってます。日本だけでなく、世界中でパブリックヘルス、みんなの健康をどうやって考えるか、ということを考えていかないといけないんだなということを、感染症を聞きながら本当に感じることですよね。
唐突に、「みんなの健康」の話になった印象です。このコーナーはちょうど見ていたのですが、なんだか「自分の言葉」ではない感じで「言わされている」感がありました。
もし医師が言うように「耐性菌」が増えているデータがあるなら、それを示してから、このような流れになるならわかりますが、とても不自然な感じでした。
下記はテレ朝ニュース(12月1日)から。
先月26日、国家衛生健康委員会・報道官は「はやっているのは主にインフルエンザです。ほかにマイコプラズマ肺炎など呼吸器系の疾患が同時発生しています」と述べました。
<ナレーション>
マイコプラズマ肺炎は「歩く肺炎」とも言われ、発熱や激しいせきを引き起こすといいます。中国メディアは「特に今年のマイコプラズマは薬剤耐性を持ち、薬が効きにくい可能性がある」としています。
国家衛生健康委員会・報道官は、「呼吸器系の疾患が同時発生」していると言っているのに、そのすぐ後のナレーションでは「薬剤耐性」の話につながっています。「今年のマイコプラズマが薬剤耐性を持ち、薬が効きにくい可能性がある」という話は、中国のどのメディアが伝えたかには振れていません。そのようなことを伝える中国メディアがあるのか少し探してみたのですが、見つけられませんでした。
前述の北京市衛生健康委員会のサイトには、「マイコプラズマ肺炎感染症は自然治癒する病気です」と書かれています。それなのにみんなが安易に薬を服用した結果、このような肺炎が流行したのかもしれません。
中国では、市販のアジスロマイシンを薬局などで買えるようです。ネットではマイコプラズマ肺炎用3点セット(アジスロマイシン、イブプロフェン、複合風邪薬)が流通しており、自己判断で服用しないように中国政府も注意喚起しています。
もし「薬剤耐性」を取り上げるなら、こういった背景にも触れながら、薬に頼りすぎないようにと伝えるべきだと思います。
どちらの番組も、「薬剤耐性」という言葉を無理矢理入れたように思えます。
アメリカのメディアには、「中国は抗生物質の効かない細菌に変化する事態を放置している可能性がある」と指摘する記事もあります(下記参照)。こちらは、中国がアメリカの10倍も抗生物質漬けであることなどにも触れながら薬剤耐性を大きく取り上げ、「多くが予想するような新型ウイルスではないかもしれないが、新たなパンデミックはもう到来しつつあるのだ」と締めくくっています。
一方、下記の記事では、感染症専門医William Schaffner氏が「直ちに警戒すべき理由はない」と語っています。また、感染症専門医Monica Gandhi氏は、「ほぼ3年間にわたるロックダウンによる他の病原体の回避を考慮すると、中国の免疫負債が他国よりも悪化し、それが今回の肺炎の波につながることはありえる」と述べています。
このように様々な意見があり、今得られる情報からは、今回中国で流行している肺炎がどのようなものかわかりません。テレビで報じていることだけを鵜呑みにせずに、自分でも調べて情報をチェックしていくことが必要になってくると思います。
「薬剤耐性」とパンデミック条約やIHRとの関係
「薬剤耐性」については、以前、下記の記事を書きましたが、パンデミック条約やIHR改正とも関連があります。
上記の記事で、2023年5月13日(土)~14日(日)に長崎で開催されたG7保健大臣会合に関する資料を取り上げました。
別紙2 G7長崎保健大臣宣言(抄訳)
キーワードとなっていたのが、「ワンヘルスアプローチ」と「AMR(薬剤耐性)対策」です。
※「WHO CA+」は、いわゆる「パンデミック条約」です。
18. WHO CA+が効果を発揮するためには、パンデミック PPR の全サイクルを適切な形でカバーする必要がある。このような背景から、我々は、強固な公衆衛生対策を促進するために、人や動物から発見された病原体や遺伝子配列データを、生物学的安全性の担保された方法で、かつ、責任ある方法で迅速に共有することの重要性を強調する。この仕組みにおいて、予防は重要な柱でなくてはならず、我々は、パンデミックの脅威を早期に検知し、パンデミック PPR に対するワンヘルス・アプローチを定着させるために、多分野との協力と連携の強化を通じて、システムと能力の強化にコミットしている。パンデミックを防ぐためこの取組は、効果的かつ効率的な方法で AMR 対策にも取り組むべきである。加えて、遺伝子配列データを含む公衆衛生に係る情報及びデータの迅速な共有を強化することは、リスクを伝え、エビデンスに基づくアプローチを発展させるために重要である。
ワンヘルス・アプローチについては、厚労省の広報誌『厚生労働』2023年11月号に説明があります。
動物からヒトへ、ヒトから動物へ伝播可能な感染症(人獣共通感染症)は、すべての感染症のうち約半数を占めています。また、抗菌薬の不適切な使用を背景としたヒト、動物、食品、環境等における薬剤耐性(AMR)を持つ細菌の出現が、国際社会で大きな課題となっています。
ワンヘルス・アプローチとは、こうしたヒト、動物、環境の健康(健全性)に関する分野横断的な課題に対して、関係者が協力し、その解決に向けて取り組むことを指します。この動きは世界的にも広がっています。
WHOは下記の記事で、「ワクチンにより抗菌薬耐性に関連する年間50万人の死亡を回避できる可能性がある」と言っています。
これまでメディアで触れられていなかった「薬剤耐性」という言葉が急に出てくるようになったことは、やはりこれらと関係しているのではないでしょうか。
IHR改正の検討状況
国際保健規則(IHR)(2005年)の改正の検討状況について、厚労省のサイトに資料がまとめられていました。私が確認したのは、「最終更新 令和5年11月28日」の情報です。
資料
(注1)IHR (2005):International Health Regulations
(注2)WGPR: Working Group on strengthening WHO preparedness and response to health emergencies
(注3)WHO CA+:WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (PPR)
(注4)パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書(いわゆる「パンデミック条約」)の交渉(外務省HP)
(注5)WHO執行理事会決定EB150(3)(英語)(PDF)
(注6)WGIHR: Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005)
(注7)WHO総会決定WHA75(9)(英語)(PDF)
(注8)WHO総会決議WHA75.12(英語)(PDF)
第59条等仮訳 (PDF[97KB])
2022年5月の第75回WHO総会において、「IHR改正の効力発生までの期間を24カ月から12カ月に短縮する第59条等の改正案を採択しました(注8)」と書かれています。
この拒否期限が11月末まででしたが、それについては触れられていませんでした。
衆議院・原口一博議員がIHR改正とパンデミック条約に関する質問主意書を提出しましたが、答弁にも具体的なことは書かれていません。
国際保健規則改正とパンデミック条約に関する質問主意書
質問(PDF) (HTML版)
答弁(PDF) (HTML版) ※後日公開
中国の肺炎など、パンデミックにつながりそうな情報は、これらの進捗も確認しつつ、チェックしていく必要があると思います。
