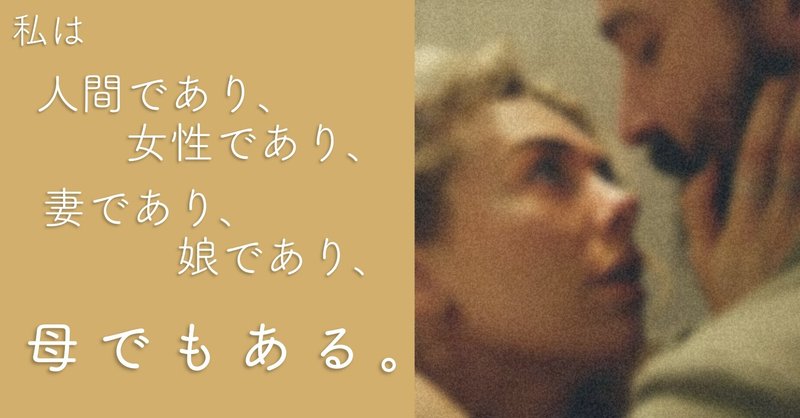
Netflix映画『私というパズル』(2020)を観て。
まずこの作品を観終えたときの第一印象は、「とことん人と人とが向き合う作品だなぁ」というものだった。登場人物らはもちろん、受け手の私たちもエネルギーが必要な作品だった。
それもそのはずで、これは一人の女性の出産からその生まれて間もない子の死、その悲しみと自己・他者の受け入れまで描かれているものだからだ。比較的そういった「家族」をテーマにした日本の有名映画は何作か鑑賞したこともあったが、洋画でこのような内容を扱ったものはあまり触れたことがなく、新鮮にも感じた。
【作品情報】
『私というパズル』(原題『Pieces of a Woman』)
監督:コルネル・ムンドルッツォ 脚本:カタ・ヴェーベル
カナダ・ハンガリー合作のドラマ映画。主演はヴァネッサ・カービーが務めた。本作での演技によって、カービーは第77回ヴェネツィア国際映画祭で女優賞を受賞。
【あらすじ】主人公マーサ(ヴァネッサ・カービー)は自身の子を自宅で出産する準備を整えていた。夫のショーンは不器用ながらも懸命にサポートしていたが、その甲斐もなく死産に。悲しみのどん底に突き落とされた2人だったが、思うように分かち合うことができず、夫婦の間に徐々に溝が生じ始める。そんなマーサに追い打ちをかけたのが母親のエリザベスだった。
マーサの悲しみだけではなく、夫や母親、助産師とも向き合いながら、彼女は自己を取り戻そうとしていく。
私自身、女性として歳を重ねるにつれて、「母親」というのは身近でありつつもなんだか得体のしれない存在だなぁと感じることも増えてきた。そのため、本作はそういった謎のベールに包まれている自分自身もなりえる存在である「母親」の側面をいくつか知ることができた気がする。作品のネタバレにならない範囲での感想と、ネタバレを含む感想に分けて、記録しておきたい。
映像としてのインパクト
この作品を語るうえで欠かせないのは、ワンカットのようにも見える出産シーンだろう。自宅出産というあまり馴染みのないものではあるものの、それがまさに目の前で繰り広げられるかのような臨場感を伴うことで、命の誕生というものを自分もその場で体験したような気分になった。
母・父・子・そして助産師の関わり合い方という部分から、なんだか道徳の時間に見るような、教育的な面でもかなりクオリティの高いものなんじゃないかーと思うほどで、映像作品というよりは資料という風に感じるほどだった。
死産を経た女性の視点のリアルな描写
そして、なによりも娘を亡くしてからの容赦ないマーサに対する現実についての描写というのは全く大袈裟な演出ではないのに実に酷かった。シンプルであるのにここまで訴求力のある映像というのは、経験したことがなかったかもしれない。本作品内の描写と近いような話を、Eテレの番組の『ねほりんぱほりん』で実際に不妊治療を経験した人たちの経験談として見聞きしたことがあったため、より主人公の心情というのを想像して苦しくなってしまった。
妻と旦那の対峙(ネタバレ有)
まず初めに子どもを亡くしたときの二人のリアクションの差というのがわかりやすく描かれていた。私は女性としての目線で見ることになるわけで、全員が全員そうとは思わないが、何か問題が起きた時に現実的で慎重なのは意外と女性で、理想論やロマンを語るのは男性というような描写にはかなり納得感があった。
産後間もない彼女が、産まれてくるはずだった子どもに向けて作っていた部屋を片付けるなど、冷静に過ごそうとする姿勢・強がっている様子から、自分でも自分が強がっていると気づいていないようにも見えて心が傷んだ。
彼女自身、二人姉妹の姉であり責任感が強く、母親に結婚後も金銭的に支援をしてもらっているという要素を見ても、「つらい」「かなしい」と感情を吐露することができなかったのだろうと思った。
子を亡くした直後、夫のある一言によって彼女は少しの不信感を夫に持ってしまったのだろうなという風にも思うし、もし感情を吐き出すことができていればまた違ったラストだったのかもと思える。
母と娘の対峙(ネタバレ有)
女性しか子どもを産むことができない以上、母親はその娘の親である以上に女性としての先輩である。
女性の幸せの定義はもちろん時代によって個人によって変わりゆくだろうけども、やはり先人としての想い、女性としての想いというのは娘を持つ母ならそれを共有しようとするのは無理もない、とこの作品を見て思った。
母親ではないが、年上の女性に「煙草を吸ったら妊娠とかに影響があるし…」と謎のお節介をかまされたことがあって、心底それを私は気持ち悪いと思ってしまったんだけど、この作品を通して、私たちが生まれてきたのは見えない命の連鎖を女性たちが繋ぎ止めてきたからだというのも事実だということに気づかされた。
この作品では、母親は自分の経験や周囲との繋がりの面からも訴訟という「エゴ」を娘に突きつけてきたわけだが、マーサもまた自然分娩・自宅出産にこだわるという一種の子に対するエゴを突きつけていたと考えることも可能かもしれない。
思いは目に見えないけど思いやりは目に見えるというコピーのCMが放送されていた時期があったのを思い出したのだが、
実際に形にしてしまうことで当事者を束縛してしまう”思い”もあるのだということを実感するとともに、自分もそうなっていないかというのを、これからパートナーや家族を持つかもしれない身として真摯に考えていきたい。
(ハワイ在住の元モデル?現モデル?が実践してる自然派にこだわりすぎて子どもを石鹸や化学的なもので洗わないで、沐浴も極力控えるみたいな育児を思い出した…。そのモデル自身もかなり母親に振り回されたと言っていたから余計に…。)
子と親の対峙(ネタバレ有)
年齢を考えても私はおそらく母親側の目線、これから子を持つ可能性のある女性としての目線で見るのが一般的とは思うけど、
私自身、難産で胎児のときに死にかけていたというエピソードがあるため、生まれてくるはずだった子どもという視点からも興味深いストーリーだった。もしかしたら私が産まれて死んでいたら、という世界線を見れたような感覚になったのは初めてだ。
ただ正直なところ、主人公夫婦が今までお互いが気づいていなかった個人の価値観の違いが出産と子の死を通して、初めて露呈されたのだと私は思った。
夫婦それぞれが育ってきた環境が違いすぎ(セロリ)ような気もしたので、考え方がこんなに違う両親のもとに生まれ、育てられるとしたら、子どもにとってなかなか大変な家庭環境になっていたんじゃないか、なんて思ってしまった部分はある。
両親のすれ違いや衝突の中で生きていく恐れも十分あったと思えたし、そういったストレスに巻き込まれなかったことだけが亡くなった娘さんにとって唯一幸せだったことかもしれない。
ストーリーの鍵となる「リンゴ」(ネタバレ有)
本作品では亡くなった娘と、母親であるマーサの娘に対する記憶が「匂い」によって結び付けられていくシーンがある。
映画『パラサイト 半地下の家族』がアカデミー賞を受賞した際に評価されていたように、”匂いは映像作品を通して伝えることができない”ということを逆手に取って受け手の想像力に依拠しながら話を広げていき、その匂いを誰もが想像できる馴染みのあるリンゴの香りという風に表現していくところでかなり想像力が刺激された。私は自分の子どもを持ったことがなければ、その子を亡くしたこともないが、生まれてすぐの尊い我が子というのを感覚的に想像することができ、その表現を通して、他人として鑑賞していたはずの映画の前半部分が自分の事のように感じられた。
アダムとイヴが食べることを禁じられた果実をリンゴという風に捉える見方もあり、メタファーとしても亡くした子(=リンゴ)を通して、夫と妻(=アダムとイヴ)が価値観の違いに気づくというのは秀逸であるとも感じる。
最後に
女性とは、パートナー(旦那)というピース、母親というピース、自分の産んだ子というピース等々が様々に繋がりあっているパズルのようなものだということなのかなぁ…と自分なりに嚙み砕いていた。
一方で、”Pieces of a Man”というのはどう描かれるのだろうという興味も沸いた。
ストーリーの鍵であった「リンゴ」の演出には心を掴まれたし、作品の終わり方も、様々な人と対峙したマーサのこれからの生き方というのを、受け手に委ねているようにも感じ、社会で生きていく女性として、母親にとっての娘として、子を亡くした母親として、希望も見れるような終わり方だった。個人的には、裁判の話が出た時に「きっと彼女ならこうしてくれるだろう」と信じて見ていたので、良くも悪くも裏切られなかったというのが少し残念だった点だ。
自分に降りかからなくとも、自分のパートナーや自分の友人に十分起こりえるような内容の設定であるからこそ、色々な人達に薦めたい作品だと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
