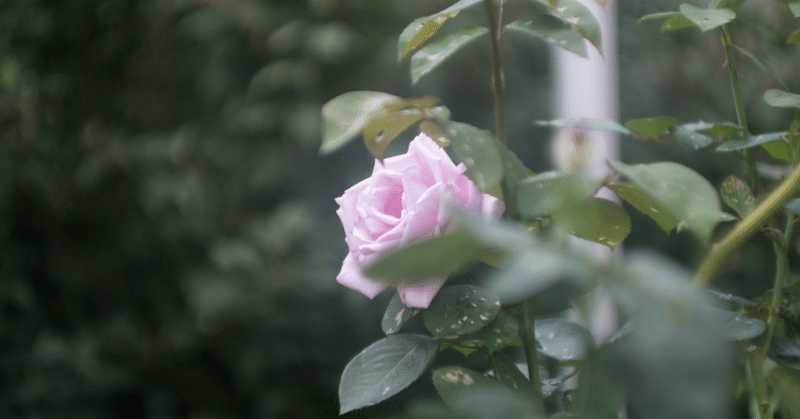「写真っていうのはねぇ。いい被写体が来たっ、て思ってからカメラ向けたらもう遅いんですよ。その場の空気に自分が溶け込めば、二、三秒前に来るのがわかるんですよ。その二、三秒のあいだに…
- 運営しているクリエイター
#詩
不可入性(2012年11月6日)
自分
感情
欲しい
好き
嫌い
明白
漠然
空想
現実
弁解
植物性
女の一生
取る
取るな
闘牛師
夫
夢
盲目
理窟
束縛
反省
別れる
ヒステリー
無縁の衆生
時間
音楽
空間
意志
浮気
空
壁
土
17であった早熟の詩人が行き当たった「壁」というのは「心と生(性)」そのものであったか。