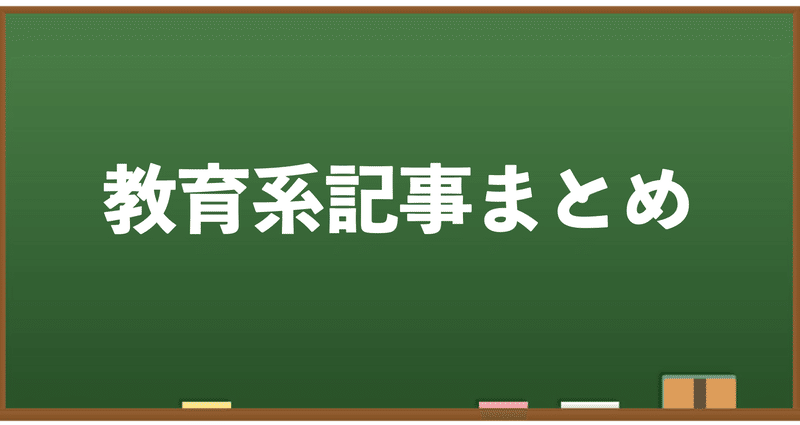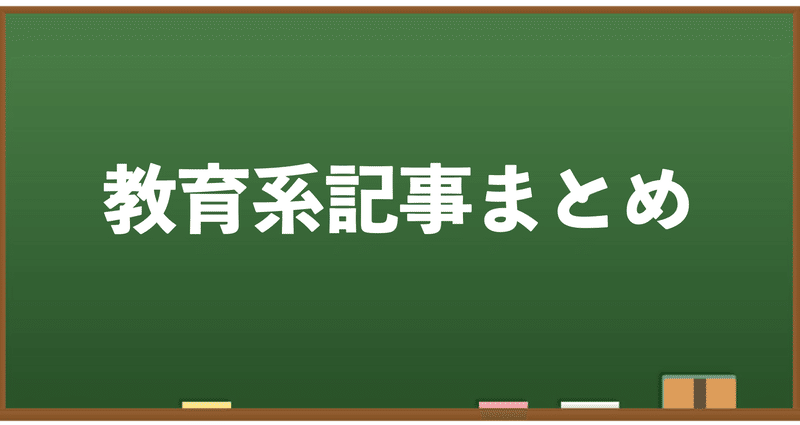「教育」を外側から見る(前編)
※一昨年度と昨年度の2年間、2002年10月に創刊したメールマガジン『ごかいの部屋~不登校・ひきこもりから社会へ~』のバックナンバーから厳選した100本の掲載文を転載してきました(字句や一文など小幅な修正をしている場合があります)。
※昨年度の最後にお伝えしたように、今年度からはメールマガジン(メルマガ)にかぎらず過去に書いた文章を毎月1本、時系列に転載することによって私の自称 “体験的不登校・ひきこもり論” の進展をたどりながら理解と対応の参考にしていただけるよう進めてい