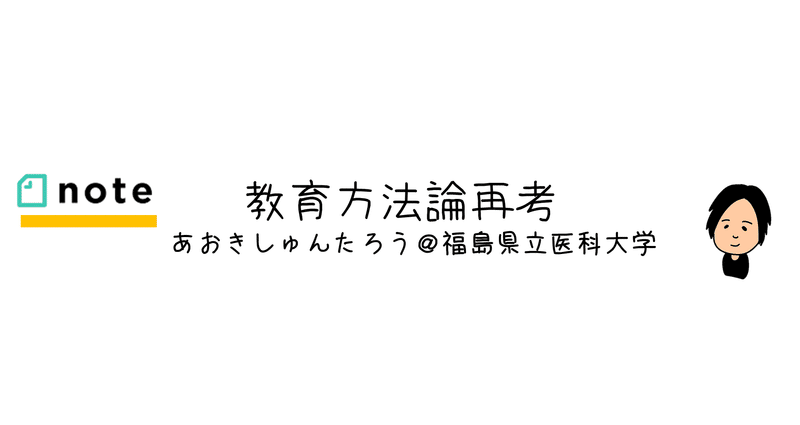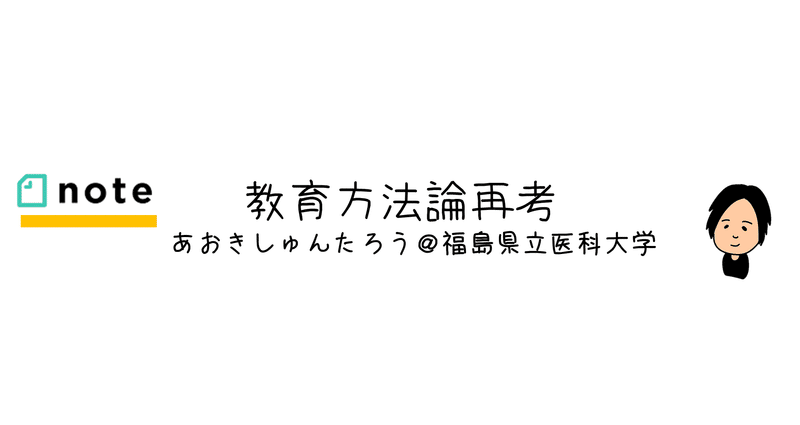アンプロフェッショナリズムの認識の学生と教員のずれ
こんちは、あおき(医学教育中)です。きょうは論文の抄読会でテーマとなった、アンプロ行動の学生と教員との間の認識のずれについてのメモです。論文は以下の論文です。(詳しい情報を知りたい方は、かならず論文を読んでください。)
プロフェッショナリズムというのは、医療従事者が専門家として社会にどうふるまうのがよいかについての態度、価値観、行動、および周囲との相互作用として定義されます(むずい)。なんか、ここは議論があるところで、定訳ってのがないんです。プロ意識くらいな感じかなあと認識