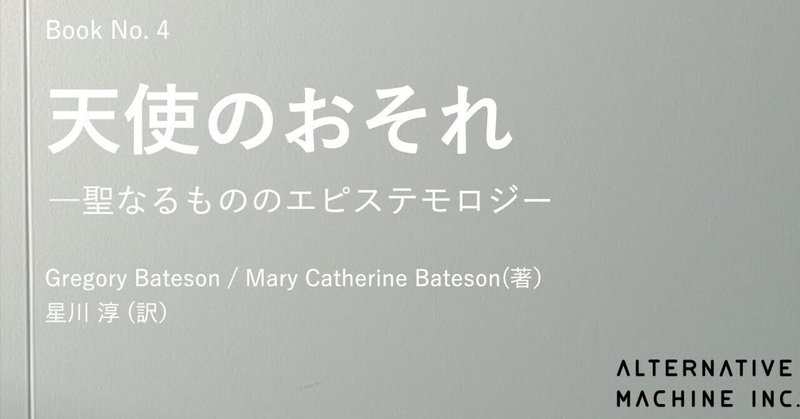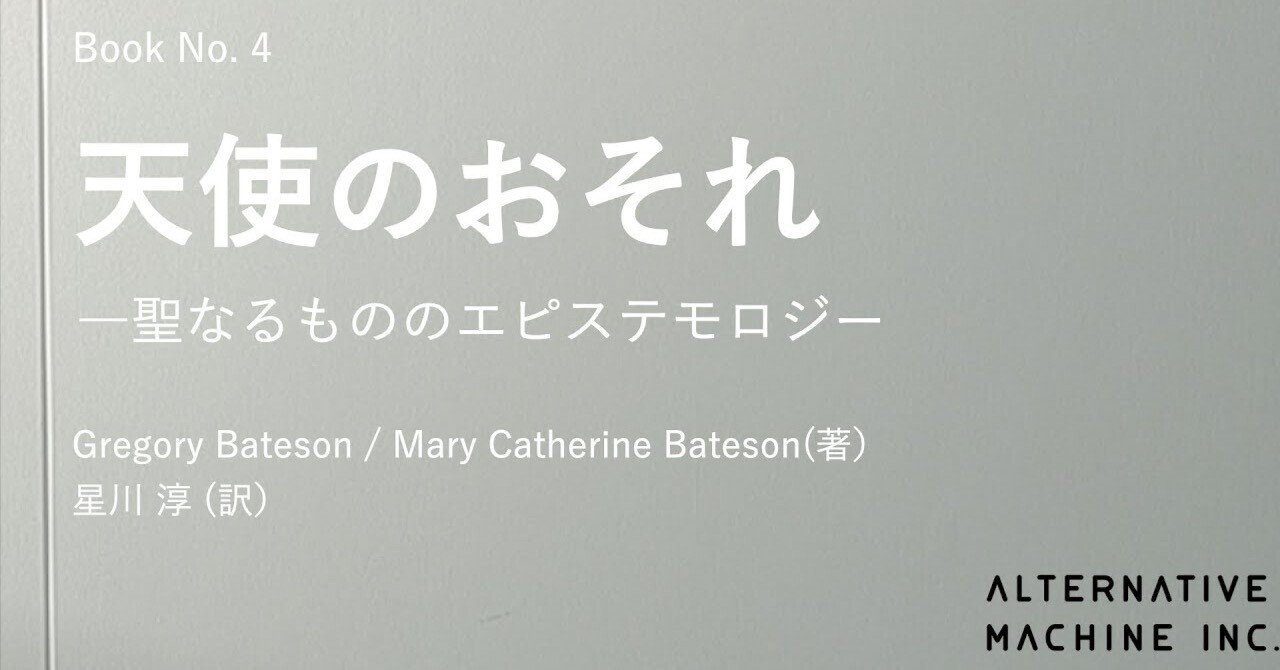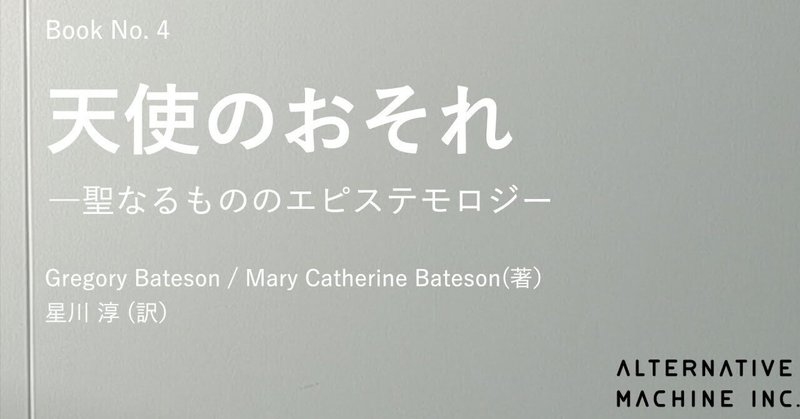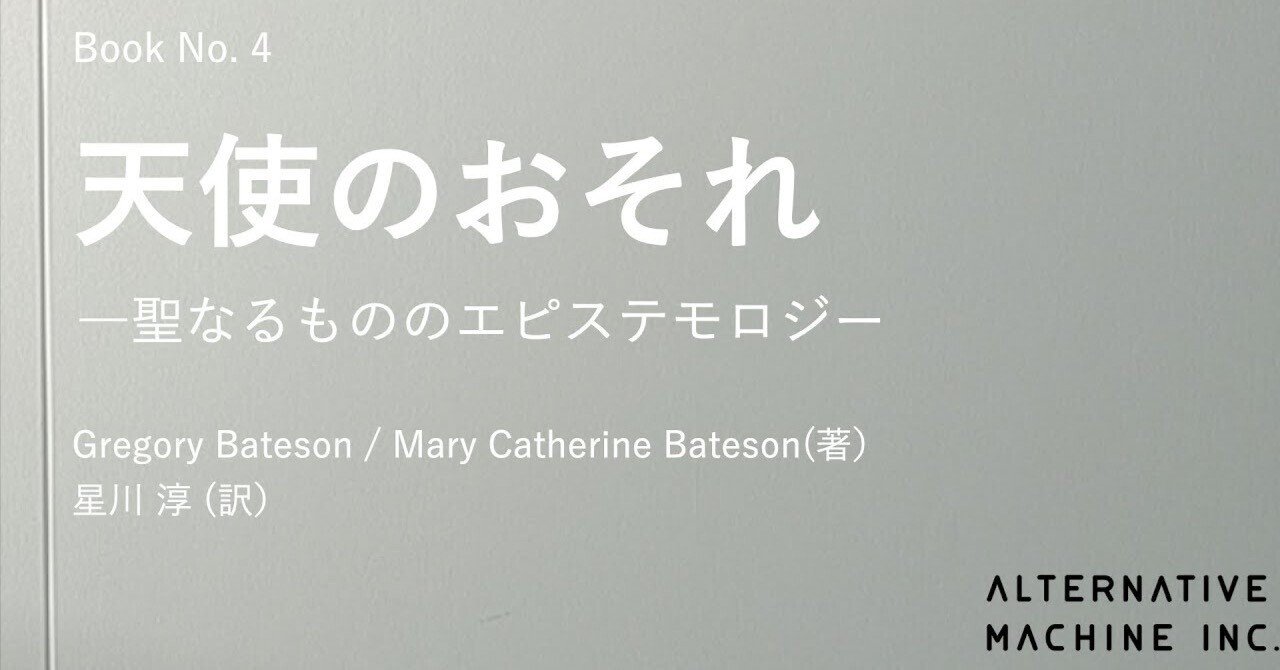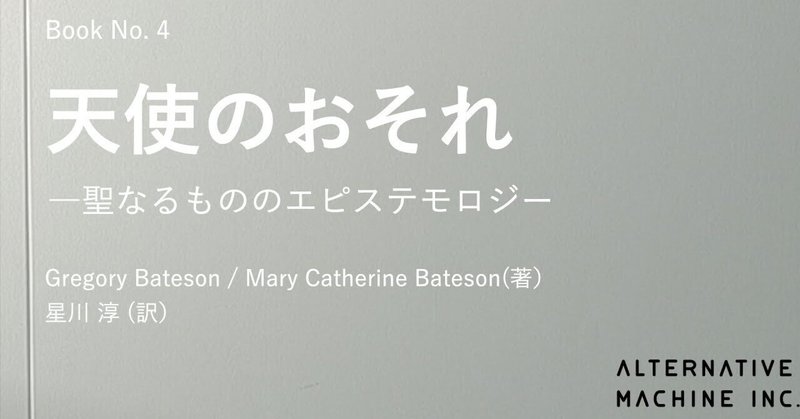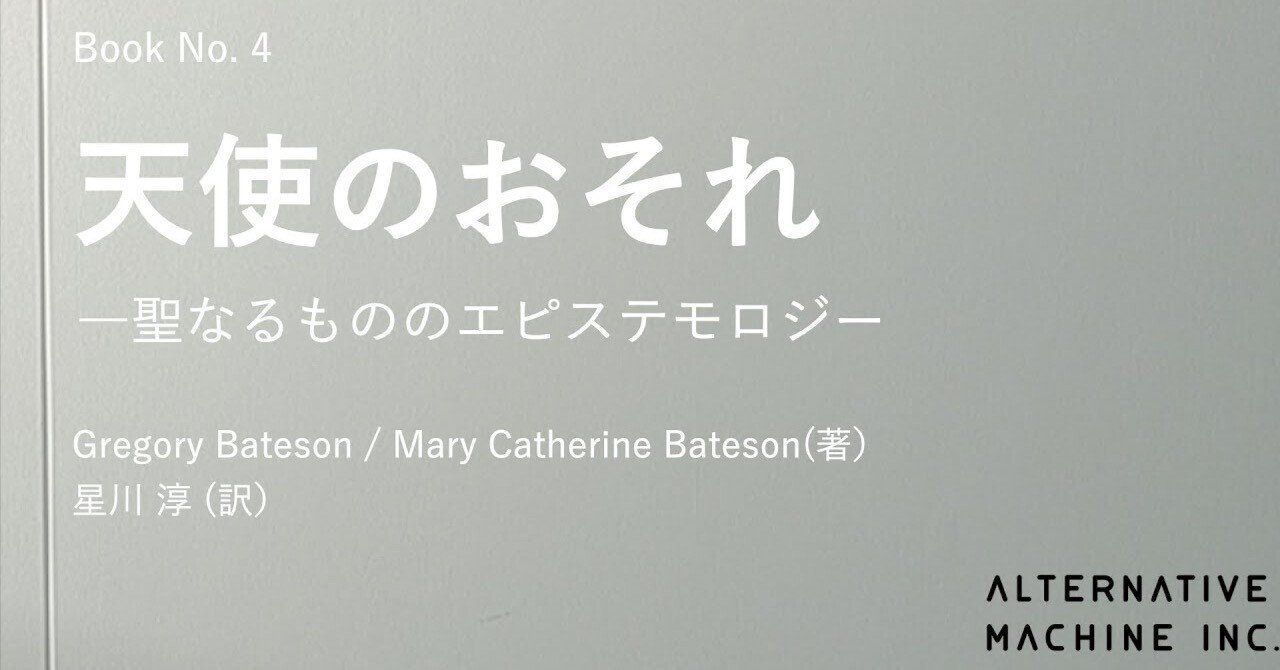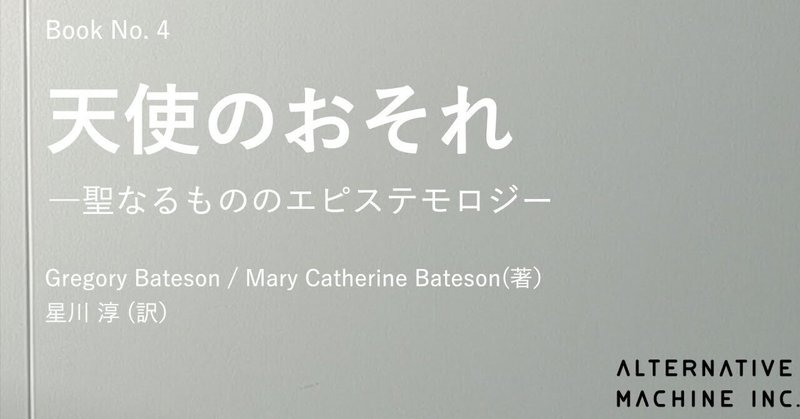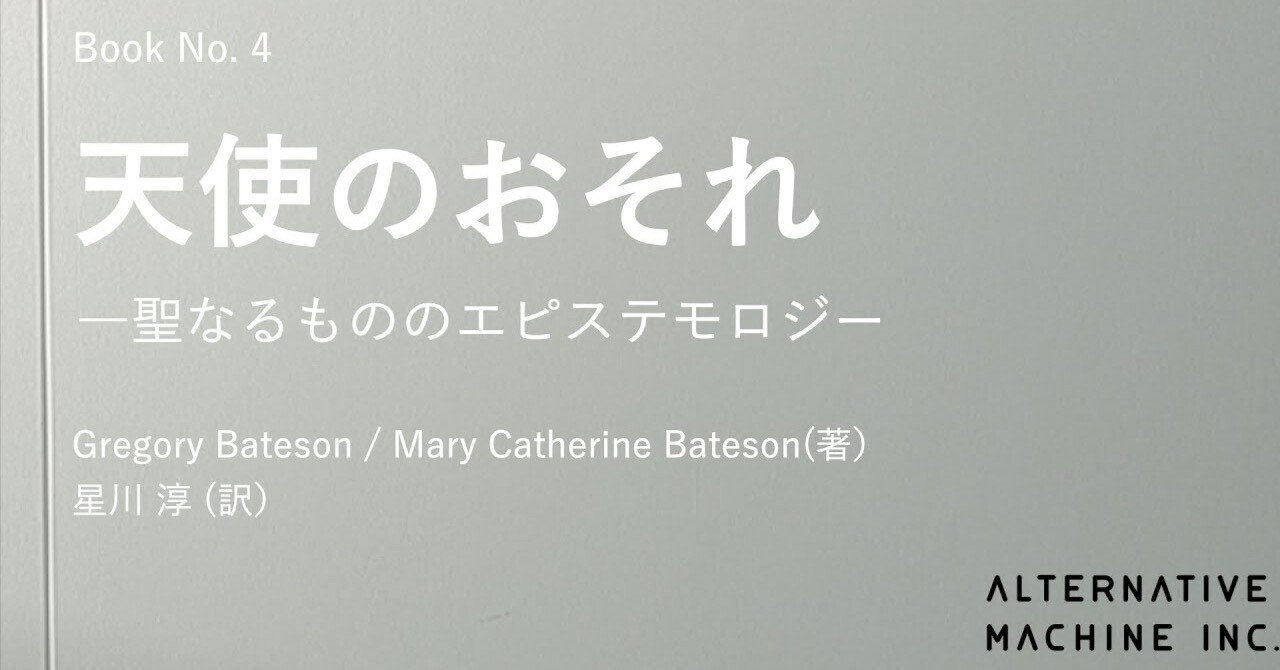最近の記事
機械では表せない生命そのもの:(M,R)システム 【Robert Rosen "Life Itself", ALife Book Club 6-5】
前回はローゼン流のメカニズムと機械の定義、そしてそこから導き出されるメカニズムの性質についてお話しました。 これをふまえて、ローゼンの「生命は機械であらわせない」という主張に迫っていきます。 機械としてあらわせないものこれを達成するためにローゼンはまず、機械を関係生物学的に記述するところから始めます。 まずはローゼンのいうところのメカニズムと機械についておさらいしておきます。 機械であるためには、数学的機械、すなわちチューリング機械(コンピューター)として表せる必要があ
シミュレーション可能性と機械 【Robert Rosen "Life Itself", ALife Book Club 6-4】
だいぶ準備ができてきたので、今回から「生命では機械としてモデル化できない」というローゼンの主張に迫っていこうと思います。 「シミュレーション可能」とはとはいえ、まだローゼンの言うところの「機械」の定義もまだでした。 このためにシミュレーション可能(simulability)という概念を導入します。 言葉としてはモデル化と近そうですが、ローゼンははっきりと使い分けしています。これまで見たように、モデル化とは自然システムを形式システムで再現することでした。 一方のシミュレー
関係生物学(Relational Biology)とはなにか? 【Robert Rosen "Life Itself", ALife Book Club 6-3】
前回は「生命そのもの」にせまるには基礎から考え直さないと、、ということで、「機械としてモデル化する」とはどういうことか、とくに「モデル化する」とはという部分を検討しました。 今回はモデル化部分を深掘りして、自然科学のモデルでよく見られる「状態と再帰」という考えと、それとは違ったパラダイムである「関係生物学」を見ていきます。 「状態と再帰」という描像モデル化とは、自然システム(因果的エンテイルメントで動作)を形式システム(推論的エンテイルメントで動作)で再現するということ、
生命は原理的にモデル化できない 【Robert Rosen "Life Itself", ALife Book Club 6-2】
「生命そのもの」の理論を扱う本、ロバート・ローゼン "Life Itself"の二回目です。 (この本やはりややこしくて、またもや一週休んでしまいました。すみません。) 今回から具体的な内容に入っていきます。 なんで生命がわからないのかさて、この本のターゲットは「生命そのもの」です。 物理が発展している今、ありとあらゆるものはすべて科学的に取り扱えるはずです。それは生命も例外ではなくて、構成要素である分子の振る舞いは物理法則で完全に記述できます。 それなのに、「生命とは
「生命そのもの」にせまる理論の探求 【Robert Rosen "Life Itself", ALife Book Club 6-1】
今回から取り上げる本は、「生命とはなにか」を考える人工生命の分野にとってかなり直球の本、その名も"Life Itself" (生命そのもの)です! アメリカの理論生物学者ロバート・ローゼンによって1991年に書かれた本書、和訳もされておらずマニアックな部類ではあります。それでも2500回くらい論文で引用されていておりけっこう影響力がある本なのです。 以前からとりあげようと思っていたもののなかなか難しくて渋っていた本書、頑張って解説していこうと思います。 (とはいえ、準備が
LLM全盛の今こそチューリングテストの原著を読んでみませんか? 【チューリング 『計算機械と知能』, ALife Book Club 番外編】
チューリングテスト、ご存知でしょうか? 機械が人らしく振る舞っているかどうかを判定するものとして天才アラン・チューリングが70年以上前に提案したテストです。 70年前というと、パソコンなんていうものはもちろんなく、バカでかい計算機がやっと出始めてきたそんな時期です。(未見の方は、まさにチューリングを扱っているこの映画を見てみると雰囲気がわかると思います。) LLMが発展しついに人工知能が完全にこのテストを完全に凌駕しそうになってきた今こそ、天才チューリングの洞察をよみなお
どこでもないところから「わたし」を探す 【ネーゲル 『どこでもないところからの眺め』, ALife Book Club 5-4】
前回からひきつづき、どうやって主観的なものを客観化していくかというお話です。 ネーゲルの3ステップまずはネーゲルのアプローチをおさらいしておきましょう。 前回はこの三つの問のうち最初の二つ(「頭の中で起きていることは客観的なのか?」、「頭の中の出来事と物理世界はどう関係するか?」)についてお話しました。 客観世界の中であっても「主観的な見方」というものを(ある程度)想定できて、なおかつそれと物理的な世界観は同じものの別の捉え方(二面論)となっているということでした。 今
主観を客観世界にいれるという厄介な話 【ネーゲル 『どこでもないところからの眺め』, ALife Book Club 5-3】
ネーゲル『どこでもないところからの眺め』も三回目になりました。 みんなが理解できるものに至るには、主観から客観に行くしかありません。でもその上で、主観を理解したいとなるとどうしようもないというのが前回までの話でした。 ぼくはふだんは、物理法則で記述できるものだけが世界に実在していてそれでぜんぶ基礎づけられる、そして、それで無理なものはあきらめるしかない、という立ち位置です。 でも、そんな生ぬるいことを許してくれないネーゲルがどう考えを進めていくのか紹介していこうと思いま
「コウモリである」ということを理解できるか? 【ネーゲル 『どこでもないところからの眺め』, ALife Book Club 5-2】
前回お話した通り、この本のテーマは主観と客観をどうつなぐかということです。 理解する主体が人である以上、かならず主観から始めるしかありません。一方で、それを超えてみんなが理解できるもの(客観)に至ろうとする営みがあり、その典型例が科学(とくに物理)なのでした。 (そうしないと、いつまでたっても「あなたの感想」にすぎないといわれてしまいます。) 基本的に科学者にとってはここで話は終わっています。この世界は究極的には物理法則で記述できるものであって、それで全て網羅し尽くせるは
何でも「あなたの感想ですよね」といえてしまう問題 【ネーゲル 『どこでもないところからの眺め』, ALife Book Club 5-1】
「それってあなたの感想ですよね」が小学生の間で流行り、親御さんが困っていると聞きました。 でもこの言葉は本当にすごくて、たいていのことはこれひとつで口答えできます。 「うなぎっておいしいよね」みたいな本当の感想だけでなく、「早起きは体にいい」とか「地球は太陽の周りをまわっている」みたいな一般的にうけいれられていることでもいけます。 これに、常識だからとか、そうに決まっているとか答えたら思う壺であって、本当にただの感想になってしまいます。 (常識は時代で違いますし、ご存知
ガイア理論とデイジーワールド、そしてシムアース 【ラヴロック 『ガイアの時代』, ALife Book Club 番外編】
前回はラヴロックのガイア仮説についてお話しました。 簡単におさらいすると、地球上の大気は生命にとってちょうどいい状態になっていて、しかも生物(生命圏)によって保たれている、ということです。 そして、この制御は地球規模なのになぜかうまくいっているということで、それを統べているなにかがあるのではとし、このなにかを「ガイア」と名付けたのがガイア仮説でした。 このなにかを科学で説明出来ないものに帰着させてしまうとオカルトになってしまいます。とはいえ、生物という地球にとってはちっぽけ