
うつ、不安、パーソナリティ(第二期:第5回③)
「うつ」に代表される気分に関わるもの、「パニック」や「PTSD」などの不安や恐怖が関与するもの、そして発達障害以前に注目されていた「パーソナリティ」の障害。
私たちが出会う可能性のある「精神疾患」は数多くあります。ここでは、「気分」、「不安と恐怖」、「人格」ということについて触れます。
1.「気分」とその障害
「気分の波(浮き沈み)が激しい」と他者のことを形容することがありますが、そこまででないとしても、私たちの「気分」は一日の中で、またそれよりも長い(短い)期間で上下しています。
何となく落ち込む(うつ)、高ぶっている(躁)状態のまさに「深さと長さの異常」が気分に関わる精神疾患です。
その「気分の波」が、激しく低下していれば「うつ」、激しい高低差で短時間に変われば「躁うつ」と言われるような状態かもしれません。ただし、気分の波が「あること」自体は何ら異常なことではありません。その波の「形」に異変が起き、それが普段の日常生活を難しくしてしまっているということです。
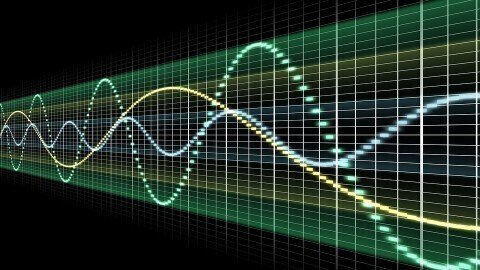
2.「不安」とその障害
「不安」や「恐怖」も、あること自体は正常で、特にこれらは危険回避のために生物(生命)として必要不可欠な働きです。関連する精神疾患は、ここでもその「深さと長さの異常」です。社会や対人関係には心的に傷つく恐れや危険が現実にあり、過去に傷ついた経験はその根拠となり、さらに強化します。

虐待やマルトリートメントとの関連は、これらについても指摘されています。不安や恐怖、依存(その対象が無いと不安になる)の対極に、「安心」や「自立」があると理解することはケースの理解に繋がります。解離性障害では、不安回避のためにトラウマに関連する記憶を切り離しています(水密区画化)。

3.「パーソナリティ」とその障害
「パーソナリティ障害」と言うときの「パーソナリティ(人格)」とは、個人の認知とそれ故の感情や行動を指し、その障害とは、ここでも「深さと長さの異常」です。大きく3つの群に分類され、さらに細分化されますが、統合失調症に関連する群もあり、発展可能性のある状態と理解することもできます。
「発達障害」との判別(鑑別)が難しいと言われていますが、幼少期のトラウマとの関連も古くから指摘されています(特に境界性パーソナリティ障害)。生育つまり虐待やマルトリートメントが関与しているならば、同様に発達障害と混同されやすい「愛着障害」に今後は統合されていくものかもしれません。
この「パーソナリティ」の変容が、本人の意志や遺伝でもなく、むしろ環境によるものであるならば、これは過酷な環境を生き延びてきた「虐待被害者」の証とも言えます。特に反社会的人格障害(先述)は犯罪加害のリスクとして知られていますが、彼らは加害者になる前に被害者であったと言えるはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
