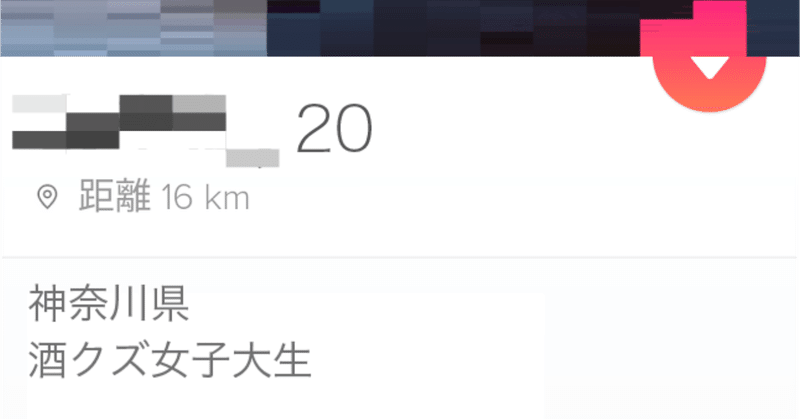
成人式をボイコットして、代わりにコスプレセックスした女の子 / Tinder文学 第4話
荒れた成人式のニュースを毎年楽しみにしている。
ひとたびは猿山から会社や社会に輸送され、高卒新入社員としてコキ使われたお猿さんたちが、当時の栄華を再び取り戻さんとして暴れに暴れる。日本を代表する一夜限りの奇祭ではないかと思う。過去数年分の成人式関連のニュースを改めてチェックして心を整えるなど、事前準備も抜かりない。
きちんとした大学を出て、きちんとした会社に勤めている皆さんは、自分の学生時代を思い出してほしい。
たいてい、お勉強はできるがリレーの選手に選ばれることはなく、バレンタインデーにチョコを得たり、卒業式に第二ボタンを失ったりする経験のない、なんというかー イケてない学生生活を送っていた方が多いのではないか。かく言う僕がその最も代表的なひとりだ。
そんなだから、僕たちの成人式は、だいたいこんな感じだ:
成人式でお猿さん(当時からスクールカーストの上の方にいて、今は地元で就職してヴェルファイアを乗り回している連中だ)が暴れる様を、東京からわざわざ帰省して式に参加した僕たちは、遠くから醒めた目で見る。そして、式が終わったら友達何人か(みんなそこそこ勉強はできたが、地元の国立大に進学した)とマックに行ってポテトを食べて、彼らが送る田舎での生活の慎ましさ/退屈さを感じて、早々に東京に戻ってしまう。そして、東海道新幹線で東京駅なり品川駅なりに降り立ったその瞬間の、息の詰まるような人混みや、ホームから見える高層ビル群を目にして、なんだか帰るべきところに帰ってきたような、そんな安心感を覚える。
皆さんの成人式は、こんな成人式ではありませんでしたか?
ところで、あるアンケート調査によると4割ほどの新成人が、成人式を欠席するそうだ。
仕事が忙しいとか、振袖を用意するのが面倒とか、理由は様々だが、その中に「会いたくない人がいるから」との理由を挙げた人が女性では1位(欠席理由の2割強)である点を見逃せない。
ふるさとは、全ての人にとって心安らぐ、また帰るべき場所ではない、ということだ。
今日は、成人式に行かず、代わりに東海道新幹線が見える部屋でコスプレセックスをした女の子の話をしようと思う。
前日の夜から上空を覆った強い寒気の影響で、成人の日の東京には、早朝から雪が舞っていたらしい。
昼前に目覚める。まだ昨日の酒が残っている感じがした。
マグカップに水を注ぎ、レンジで温める。ややぬるいその中にネスレの安いインスタントコーヒーを混ぜ入れる。酸っぱい。次はもっといいやつを買おう。
コーヒー片手に窓を開ける。刺すような冷たい風が部屋に雪崩込む。雪片のいくつかも部屋に舞い込んだが、常軌を逸した寒がりの僕は暖房を32度に設定していたから、舞い込むそばから溶けて消えていった。
渋谷区の空は一面のグレーで、幾分かぼんやりとした清掃工場の煙突と、その更に向こうには西新宿の高層ビル群の曖昧な輪郭が見える。テレビをつける。NHKのアナウンサーは、夜には都内でも数センチの積雪と、それに伴う鉄道交通網の麻痺が予見されると無機的に読み上げた。
窓を閉める。冷えた体に熱を取り戻そうと、更にぬるくなったコーヒーをレンジで再び温める。今度は熱くなりすぎたそれを番茶のようにすすりながら、毎朝(もう11時だが)恒例のTinderチェックを実施する。

20歳!今日は成人の日、君のための日だ。一升瓶でも贈りたいくらいだ。
成人式おめでとう、と思ったので、成人式おめでとう、と送った。
成人式は任意参加のイベントである。出ることもできるし、出ないこともできる。
気になってGoogleで調べてみたら、前述のアンケート結果を発見する。ほら、そんなもんだ。成人式に参加して退屈を覚えた先輩としても、成人式なんて出ても出なくてもいいイベントだよと優しく抱きしめてあげたい気持ちになった。
成人式感のないところに行こう、本当の成人の世界っちゅうもんを見せてあげようと、いつも女の子に提案するよりもちょっといいお店を提案してみた。白金高輪のシチリア料理屋。かっくい〜
しかし、彼女はその提案に乗ってこなかった。

鳥貴族はまだしも、自分の家の最寄りに来い、と年下に言われるのはやや癪だったが、この雪である。女の子を遠くに引っ張り出して帰れなくさせるのも可哀そうである、どうせ東横線で20分だし、と自分の心を整理して、彼女の家の近くの、安いがそれなりにうまい居酒屋を予約した。
「彼女の家の近くの、安いがそれなりにうまい居酒屋」をすんなり発案できたのには理由がある。彼女の住む、そして今回の事件の舞台となるその街・新丸子は、私が学生時代に4年間住んだ街だったから。やや時間は経ったが、当時通い慣れたその店はまだ健在であったのだ。
沿線の某私立大にほど近いその駅には、僕を含むその大学に通う学生たちがたくさん住んでいたから、もしかすると、彼女は大学の後輩かもしれない。懐かしい気持ちで、その日の18時、数年ぶりにその駅に降り立った。
約束の時間から15分ほど遅れてカウンター席に登場した彼女は、「さむーい」と言って手をこすり合わせながら、全く悪びれることなく隣席に座った。
まず目を引くのは、綺麗に巻いたツインテールの髪型。アイドルのような非日常的な雰囲気を滲ませるその髪型は、彼女の派手ではないがよく整った顔に、不思議とよく似合っていた。
そして、次に目を引いたのは、不安なほどに細く、そして気候にそぐわないほどに大胆に露出された彼女の二本の脚。転んだら折れてしまいそうな、そしてこの寒さの中にも関わらずストッキングにすら覆われていないその脚を、彼女は気前よくぶらぶらさせながら僕に問う。
「待ちました?何着るか悩んでたら遅くなっちゃって」
大学生とは思えないほど垢抜けたその顔。過剰ではなく、しかし自然な魅力を発するよう程よく施された巧妙なメイク。あざとさに溢れつつも、無邪気さを演出するかのように上品に覗く白い歯列。完成されたかわいらしさが、彼女の顔面にピタリと貼りついたように、全くブレることなく輝いている。
まとめるとすれば、間違いなく美人女子大生である。
しかし、不思議な違和感があった。美人女子大生として定義されるには、余りに幼さの主張が強すぎる髪型。研究熱心だ、と言われればそれまでだが、鏡の前で何時間も練習したような、余りによく出来すぎた無邪気な笑顔。
大人になりきれない子供のような、大人のふりをする子供のような。後から振り返ってみると、女子大生であるはずの彼女の中に、どこか幼さというか、かわいい女子高生めいたもの、またはそうありたいという執念のようなものを、私はそのとき感じたのかもしれない。
不思議な幼さとは裏腹に、よく飲む子だった。
「成人の日に乾杯」とビールを勢いよく飲んだと思ったら、次は初めて飲んだというホッピー、飲み慣れているというハイボール、ウーロンハイと、おじさんのようなお酒のチョイスを続け、そしてそれらを全て気持ちよく飲み干した。
「家の近所なのに、全然知らなかったー。なんでこんなお店知ってるの?」
「昔、この辺りに住んでたんだ。大学生の頃だけど。ほら、あの、ローソンが1階に入ってるマンション」
「えー、私の家の超近くだよ」
同じ街を共有しているということは、人の距離感をこうも縮めるものか、と感心した。
「大学は?」
と、3駅隣の日吉にある某大学に通っているのか(すなわち、僕の大学の後輩なのか)と尋ねてみた。
「違うよー、私は、」
と、駒場にある某大学の名前を彼女は口にした。
意図せぬ学歴の暴力にぶん殴られながらも、僕は問いを続ける。
「なんで新丸子に?井の頭線じゃなくて」
「うーん、大学からの上京組だから、地理とかよくわかんなかったし。家賃と、大学からの距離でスーモで調べたら、ほら、」
彼女は、食べかけの牛ハラミ串で駅の東の方角を指しながら、
「新幹線の高架があるあたりの、オートロックの新築マンションが出てきて。それで新丸子にした。安かったし。」
納得である。確かに、渋谷で乗り換えれば30分もかからないだろう。
「出身は?」
上京組、という発言を拾って、僕は更に質問を続ける。
彼女は、西日本のとある中堅都市の名を口にした。確か、「こだま」くらいは止まる街だっただろう。
「成人式は、特に地元に帰ったりとかはしなかったの?」
そのはずである。今日の昼からの彼女との距離はずっと十数キロだったから、おそらく成人の日の今日は、地元に帰るどころか、雪に閉じ込められて、ずっと新丸子にいたのだろう。
「うん、成人式、特に出たくなくて」
「賛成だ、僕は経験者だけど、あれは特に出るべき式でもない」
にべもなく答えた彼女に敬意を表して、僕は、成人式に対する屈折した自説を滔々と説いた。
彼女はそれを、随分と面白がってくれた。
こんなふうに肯定してくれた人は初めてである、大学の周りの友達も皆当たり前のように地元に帰っていくから、と、彼女は続けた。
そこから、急に警戒心が解けたかのように(元々フランクな雰囲気であったが)、彼女は更にホッピーを追加した。
あれだけ飲んだのに、会計は驚異的に安かった。やはり時代は新丸子である。
私も酔ったが、彼女はもっと酔っていた。
「送ってぇ」
と情けない声を上げて、僕の手を、その白くて小さくて、そして冷たい手でギュッと握りしめて、慣れた足取りで僕が住んでいたマンションにあるローソンへと飛び込んだ。
「まだ飲むよね?」
と、彼女は度数の高い缶チューハイ数本と紙パックのお茶、翌日飲む用に、とインスタント味噌汁をカゴに入れて、払ってくれ、とでも言わんばかりに笑顔で僕に押し付ける。
僕は黙って、そのカゴにコンドームを1箱追加した。
暗い灰色の空から、真っ白な雪のかけらがぱらぱらと落ちてくる。
歩道にも、車道にも、雪がうっすらと積もり始めている。駅から離れ、商店街を抜けて、多摩川が近づいてくるにつれて、人も車も通らなくなって、悲しいほどの静けさの中を、酔った彼女と、少し酔った僕だけがとぼとぼと歩いてゆく。彼女の着てきたコートの、首元と袖口についた真っ白なファーと、見ていて痛々しいほどに白く、細いその脚が、雪よりもずっと白く感じられた。
家についた彼女は、手慣れたように部屋に暖房をつけ、アイリスオーヤマの安い加湿器をつけ、ベッドにぽんと座って缶チューハイをごくごく飲み始めた。僕は床に置かれたピンクのかわいいクッションに座って、家主の意向を尊重する形で、同じように缶チューハイをちびちびと飲む。
窓の外を、一筋の光が、轟音と共に駆け抜けた。立ち上がり、カーテンの隙間から外を覗くと、長い長い東海道新幹線が走るのが見えた。
「この時間もまだ新幹線があるんだね。終電は何時なんだろう」
お酒のせいか、今この世の中で最も意味のない質問をなんとなく投げかけてしまう。
彼女は何も答えず、ベッドから降りてきて、僕の座っていたピンクのクッションにちょこんと座る。彼女の真っ黒い瞳が、アルコールのために幾分かとろんとしているものの、僕の小さな瞳をじっと覗き込んでいるのがわかった。
僕は彼女の横の、カーペットの上に座って、今すべきだと思ったことを彼女に実行した。彼女は拒まず、しかし何も言わず僕に応じた。
電気が消えた部屋に、暖房と加湿器の、煩わしい起動音だけが響く。数分に一度、東海道新幹線やその他の在来線が轟音を上げて走り、その度に彼女は、布団からちょこんと出した顔を少し上げて、それらの列車が発する眩しい光を、遮光性の低い遮光カーテンの隙間から、じっと見つめる。
彼女の細い首筋ー 骨が、筋が、全て透けて見えるような、やせっぽちのその首筋。床に転がった。思いの外セクシーなブラ。なんとなく気まずくて、僕は布団から手を伸ばして、ベッドに程近いテーブルに置いてある缶チューハイのぬるくなった残りをすする。彼女は僕からそれを取り上げて、同じようにすすって「ぬるいね」と言う。
「成人式ね、」と、彼女は布団に入り直して、天井を眺めながら言う。酔いはすっかり醒めたのか、今日聞いた中で、一番しっかりとした大人っぽい話ぶりに、僕の注意は全て彼女の口元に奪われた。
「行かなかったの。行きたくなくて。地元にいい思い出全然ないし、会いたい友達もいないし。」
思い直したように、彼女はテーブルの上の缶チューハイに手を伸ばす。届かなかったから、僕が代わりに取ってやって渡してやる。彼女は受け取ったそれをゴクリと飲んで、ありがとう、と小さく言って、僕にそれを返却する。
そこから彼女がぽつぽつと語ったことは、彼女の悲惨な過去についての話だった。
教育熱心な母の指導の元、部活に入ることもできず(本当はバレー部に入りたかった)、毎日のように塾に通わされたこと。そのストレスのせいか過食気味になり、塾で隠れて食べていたスナック菓子のせいか、元来細身であった彼女の体重は、10歳を超えるあたりから激増したこと。
見た目を理由にいじめられるようになったこと。小学6年生のクラス文集では、「かっこいい人/かわいい人」の項で、なぜか彼女が2位にランクインしたこと。それを仕組んだ一部の男子たちが、配布されたクラス文集を読む彼女をじろじろと、嘲るように眺めてきたこと。
中学でも高校でもいじめが続いたこと。不登校をやろうかと思ったが、世間体や内申点を気にする母がそんなことを許すはずもないから、時に希死念慮に襲われながらも学校に通い続けたこと。
そして、このような不浄の地から離れたいという思いから、猛勉強の末、結局は母の願った通り東京の国立大学に現役合格し、「こだま」に乗って上京してきたこと。
自分以外に、自分のことを知る人がいない街に引っ越してきてから、やっと彼女の命運は反転する。
彼女は故郷から遠く離れたこの地で、全く新しい自己と、全く新しい人生を手に入れた。
まずは、「ビリーズブートキャンプ」をやり込んで体重を落とした。服装やメイクも研究し、それらを思う存分買い込めるよう家庭教師のバイトに励んだ。
綺麗になった彼女を、世間は放っておかなかった。学内誌には「キャンパス美女」として特集されたし、それを見たお台場のテレビ局から声がかかり、ビートたけしが司会を務める学生クイズ番組にも数度登場したらしい。今でも彼女の名前で検索すれば、その時の彼女を見ることができる。
その日と同じように、かわいらしいというか、痛々しいほどに幼いツインテールで微笑む彼女の魂は、もしかすると彼女の失われた青春、あるいは、もしかすると存在したかもしれない、彼女の故郷での幸せな青春時代に取り残されているのかもしれない。
「ね、」重苦しい空気を破るように、彼女は努めて明るく私に呼びかける。
「クローゼットの中に、高校の制服があるんだけど。」
言われるがままにクローゼットを開けると、確かに端の方に制服が掛かっている。地方の公立高校のそれらしく、紺が主体の、飾りっ気のない冬服。
「制服ディズニーに使う、って実家から送ってもらったんだけど、」
それを着てセックスをしよう、というのが彼女の提案だった。
彼女の顔をじっと見る。
薄暗くてよく見えない。しかしきっと、居酒屋で見せてくれたような、あざとくて、無邪気で、硬直的で、完璧な笑顔をその顔に貼り付けているのだろう。
制服姿の20歳を、その制服が象徴するコミュニティを憎み、成人式をボイコットした20歳を、辛い過去を乗り越えるためか、あるいはそれをお互いの体液で毀損するためか、年不相応の髪型と制服を身に纏って性行為をする20歳を眺めながら、僕は無心でセックスを続ける。
窓の外では雪が降り続き、僕はニトリの安い木製ベットが軋む音の中で、本日最後の東海道新幹線が高架を走り抜けるのを確かに聞いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
