
銀河フェニックス物語 【恋愛編】 ジョーカーは切られた(まとめ読み版①)
休日にレイターと火星へやってきた。
二人でランチを食べた後、レイターは「新しいレーシングゲームを試してくる」と言って街のゲームセンターへ出かけて行った。
わたしはあの騒々しさが苦手だ。
フェニックス号に戻り、のんびりと読みかけの本を読んでいた。
一時間もしないうちに、レイターが真っ青な顔で船へ帰ってきた。
「どうしたの? 顔色が悪いわよ」
「気持ち悪りぃ。ゲーセンで突然めまいがして……その後どうやって帰ってきたか覚えてねぇ」

「ゲームセンターと言えば、ニュースでひどい事件を伝えてるわよ」
さっきからアナウンサーが臨時ニュースを伝えていた。二人で居間のモニターを見つめる。
「ゲームセンター『ジョーカー』で、何者かによってまかれた猛毒のために客や店員ら七人が心肺停止状態となっています。今、入ってきた情報によりますと、事件直後、この店から飛び出した若い男が目撃されており、警察では事件と関連があるものとみて、この男の行方を追っています。男は金髪で背が高く、白のシャツに紺色のズボンをはいていたということです」
「おいっ、これ、俺のことじゃねぇかよ」
「えっ」

「さっきまで、ここでゲームやってたんだ。新型のレース機が入ってたのはこのジョーカーって店だ」
きょうはプライベートだというのに、『厄病神』が発動した。
驚いていると、ピンポーン。船の呼び鈴がなった
* *
「警察です。レイター・フェニックスさんはおみえですか?」
僕が初めてレイターに会ったのは、ジョーカー事件でフェニックス号へ任意の聴取に出かけた時だった。
警察手帳を見せると、彼は明らかに嫌そうな顔をした。
「私は火星七番署刑事課のマーシー・ガーランドと言います。恐れ入りますが署まで御同行願いたい」

新米警察官の僕と同い年、と言う彼は確かに防犯カメラに映っていた人物だ。白いシャツにスラックス。服装も一致している。
「キャリアの警部補さんかよ」
面倒くさそうに答える彼に、僕の後ろからペアを組んでいるパリス警部が声をかけた。
「久しぶりだなレイター。大きくなったもんだ」
「げげげっ、あんた何でこんなところに」
レイターは嫌な人にあったといわんばかりの顔をした。
「お前『ジョーカー』で起きた事件のことは知っているな」

「今、ニュースで見た」
「話は早い。お前はあそこで何をしていた」
「何ってゲームさ。宇宙船レースの最新版が入ってたんだ」
「どうして事件発生直後に店から飛び出した?」
「どうしてって気分が悪くなったから。俺は被害者だぜ」
「『ジョーカー』とグレゴリー一家の関係を知っているだろ」
驚いたことに警部はいきなり事件の核心に触れた。
「は?」
レイターは目を見開き、びっくりした顔をしている。演技とは思えない。

「ジョーカーの奥にはグレゴリー一家の秘密の賭博場があったんだ。知らなかったとは言わせん」
事件現場となったゲームセンターは、我々が内偵調査に入っていた違法な賭博場だった。そしてその経営を行っていたのがマフィアのドン。『裏社会の帝王』ダグ・グレゴリーとそのファミリーだった。
「知らねぇよ。そんなもん。俺はゲームやってただけなんだから」
「とぼけるな」
「俺とダグの親父とは、もう何の関係もねぇんだぜ」
「今度こそお前のしっぽをつかんでやる。話は署でゆっくり聞こう」
*
取調室でパリス警部と僕は重要参考人であるレイター・フェニックスと向き合った。
椅子にだらりと腰掛けたレイターへの事情聴取は僕の指導員であるパリス警部がメインで行った。
いつもは僕が取り調べをするのを警部は横で見ているが今回は事案が大きいからか、経験豊富な警部が自らやると僕に言った。
「お前が毒ガスを撒いたのか?」

「なんで俺が撒くんだよ」
「毒を吸った客はほとんどが即死だった。どうしてお前だけ助かったんだ。事前に解毒剤を飲んでいたんじゃないのか」
「俺さあ、皇宮警備の予備官やってたんだよ」
皇宮警備は連邦軍のエリート集団だ。王族の暗殺を防ぐため毒物が効かないように訓練を積む。
「薬物耐性か。それを事件に利用したんだな。店内の防犯カメラ映像は電磁ウイルスで消去されていた。皇宮警備官ならできるプロの仕事だ。ダグへの恨みか」
警部はレイターを犯人と決めてかかっているようだった。良識派の警部にしては珍しい。こんなことは初めてだ。
僕は気になってレイター・フェニックスのプロフィールを検索したが前科も何もなかった。
職業は自称『銀河一の操縦士』S1にも出場した元レーサーだ。

宇宙船レースに興味のない僕でも知っている。
『無敗の貴公子』の引退レースで、あのエース・ギリアムに、あと一歩で土をつけるところまで迫ったレーサー、それが彼だった。
副業でボディーガードをやっている。
ボディーガード協会のランク3Aと腕前はトップクラス。彼が言う通り皇宮警備の予備官も務めていた。
家族はいないが後見人は連邦軍のジャック・トライムス将軍で身元もしっかりしている。

毒ガスを撒くという残忍な事件と結びつかない。
純正地球人である彼の出身は、過去にパリス警部が勤めていた地球の警察署の管内だった。警部が彼にこだわるのは過去に何かあったに違いない。
「だから、さっきから言ってるように、俺はジョーカーで三十分位ゲームをやってたんだ。そうしたらめまいがして、気分が悪くなったから外へ出た。それだけさ」
めんどくさそうに彼は答えた。
「この小さなポーチの中に時限式の毒ガス噴霧器が入っていたんだ。店のこのゲーム機の上に置かれていた。覚えているか?」
警部が現場の写真を見せながらレイターにたずねる。
「俺のもんじゃねぇ。他人のカバンのことなんて知るかよ」
「ちょうどお前の座っていた位置から見える場所にある。偶然とは思えん。 昔は置き引きしようと他人の鞄を狙っていただろうが」
「証拠があるなら逮捕してくださいって、あんたとモーリスに百万回は言ったぜ。『疑わしきは罰せず』だろ」
「そんなことばかりダグから覚えおって」
「ダグだけじゃねぇぜ。あんたもいろいろと教えてくれた。『加害者に理由あり、被害者に理由なし』ってな。俺は被害者だから聞くだけ時間の無駄さ」

二人の会話から想像すると、彼は警部が面倒を見ていた不良少年だったようだ。彼がグレゴリーファミリーと関係する不良グループに属していたとなれば、今回の事件とつながる。
それにしても、違和感がある。身元調査が厳しい皇宮警備官と不良は結びつかない。
のらりくらりと話すレイターは聴取に慣れていた。何も聞き出せないまま夜になった。任意ではこれ以上話を聴くことができない。彼を船に帰すことになった。
「事件の参考人であるお前に警護をつける」
「へぇ、ボディーガードに警護をつけるほど警察に金があるとは知らなかったぜ。監視の間違いじゃねぇの」
「よくわかってるじゃないか。マーシー、こいつから目を離すな」
「はい」

僕は、彼の警護という名の監視をすることになった。
*
「なあ、マーシー、頼むから船までエアカーを俺に運転させてくれ。その方があんた、警護しやすいだろ」
すっかり暗くなった警察署の駐車場でレイターが提案した。どうしたものかと迷ったが、彼が変な動きを見せたら公務執行妨害でその場で逮捕するだけだ。僕はマイカーの鍵を渡した。
「ったく、ティリーさんに心配かけちまったぜ。別れるとか言い出したら、機嫌取るのが大変なんだからな」
緑の髪に赤い瞳。僕たち警察の訪問に驚いていた彼女は順法意識の高いアンタレス人か。

運転席に座るレイターの横顔を見ながら、僕はついさっきパリス警部と二人で交わした会話を思い出し、緊張が高まるのを感じた。
警部の話は、僕の想像を越えたものだった。
*
「レイターの命が狙われる可能性があるから気をつけろ」
「何者なんですかあの男は。前科も無いようですけど、グレゴリーファミリーの下部組織構成員ですか?」
「あいつは、ダグ・グレゴリーの後釜候補だ」
僕は驚いた。そんな情報は初耳だ。
「ダグの後継はナンバーツーのスペンサー、というのが既定路線ですよね」

スペンサーはダグ・グレゴリーの右腕。姿を見せないダグの代わりにファミリーを仕切っている。
「表向きはな」
「ダグの跡を継ぐと言うことになると、グレゴリーファミリーの跡を継ぐだけでなく、次の『裏社会の帝王』という話になりますよ?」
警部は情報に自信があるようだが、簡単には納得がいかない。
「レイターは、昔ダグに、十億リルの懸賞金をかけられたんだ」
「十億の懸賞金?」
敵や裏切者に対しマフィアが懸賞金をかけることはあるが十億は高額すぎる。それと後釜という言葉は結びつかない。警部の話は矛盾している。
「お前も『緋の回状』は知ってるだろう」
「はい」
ダグ・グレゴリーが銀河中のマフィアに出すお触れのことだ。

「ダグは当時十二才のレイターの首を差し出せば十億リルを取らすと『緋の回状』を回したんだ」
「十二歳をですか?」
マフィアのドンが十二才の殺害命令に十億。尋常じゃない。警部は話を続けた。
「グレゴリー一家だけじゃない、銀河中のマフィアがなりふり構わずあいつを殺そうと追いかけた。そのせいで一般市民も巻き込まれて街中の治安がめちゃくちゃになった」
「それは、第三次裏社会抗争のことですか?」
警部はうなずいた。
十年以上前、警部が地球で勤務していた時に起きたマフィアの抗争だ。グレゴリーファミリーが一気に頂点に上り詰め、勢力図が一気に変わった。
「警察もレイターを保護できなかった」

「でも、彼は今も生きているじゃないですか?」
「裏社会抗争の時、あいつは爆発事故で死んだと思われていたんだ。レイターを狙っていた奴らが二十人も死んだという大事故で、『緋の回状』も取り下げられた。ところがあいつは生きのびていた」
「彼は今も命を狙われているわけですか?」
「いや、あいつが十六才でソラ系に戻ってきた時、その話は手打ちになっている。だが、とにかくあいつは注意人物なんだ。心していけ」
*
鼻歌を歌いながらエアカーを飛ばす彼のどこがそんなにすごいのだろうか。

腕につけた通信機が鳴った。警部からだ。声の調子があわてている。
「レイターはそこにいるか?」
「ええ、運転していますけど」
「すぐにやめさせろ」
「えっ?」
「いいから、すぐやめさせろ」
スピーカーをオンにして僕はレイターに言った。
「レイターさん、車を停めてください」
「大丈夫だよ。相変わらずパリスの親父は心配性だな。三分の一見えてりゃ運転に支障はねえよ」
言っている意味がよくわからない。
警部が通信機のスピーカーを通してレイターへ話しかけた。
「レイター、お前、自覚症状があるんだな。毒物を鑑定した医師から連絡があった。薬物耐性があっても視野狭窄が起きると。もうすぐお前の目は見えなくなる」
そんな人が運転する車には僕だって乗りたくはない。
「ええっ?! 僕が運転、変わります」

「俺は他人が運転する車は嫌ぇなんだよ。大体あんた、後ろの車に気付いてる? 目が開いてても見てなきゃ一緒だぜ」
そういうと彼はおもいっきりハンドルを切った。身体が傾く。
パンパンパンッ……
発砲音だ。振り向くと後ろの車から体を乗り出した男が銃で我々を狙っていた。
「なっ」
「つかまってろ」
レイターは素早いハンドルさばきで銃撃をかわしていく。
通信機のスピーカーからパリス警部がたずねる。
「何が起きてる?」
「銃撃を受けています」
レイターは一気に車を加速させた。カーチェイスだ。
プロのレーサーだったという彼は車と車の間を見事にすり抜けていく。僕が運転していたらあっという間に事故を起こすか、撃たれていただろう。
そもそも、この車、こんなにスピード出せたのか。
赤信号も突っ切った。今は非常事態だ。交通法規を守れとは言えない。
「安月給のサツが乗ってる車は、ほんとしょぼいな」

「悪かったな」
僕たちを追っている車は一台だけではなかった。
角という角から銃を持った車が次々と飛び出してくる。追われる立場は初めてだ。
物量作戦。こんなことができるのはグレゴリーファミリーに違いない。
前からも敵が攻めてきた。レイターが車を停めてつぶやいた。
「ちっ、しょうがねぇな。どうせいつかは挨拶にいかなきゃなんねぇんだ」
十台近い車のヘッドライトで照らされ囲まれた。
いくつもの銃口に狙われている。
僕たちは両手を挙げて車の外へ出た。
鷹のエンブレムがついた真っ白な高級車から、大柄な男がゆっくりと車から降りた。白いスーツに紫のサテンシャツ。
手配写真通りの吊り上がった目。ダグの右腕、スペンサーだ。グレゴリーファミリーのナンバーツー。
「久しぶりだなレイター。でかくなりやがって」
濁声が響いた。

「大幹部のあんたがわざわざ迎えにきてくれるとは、人手が足りてねぇのかよ」
「あとでぶん殴ってやる」
と言ってスペンサーはこぶしを振った。ブンっと風を切る音がする。銀色に光る金属の義手。スペンサーは元ボクサーだ。
グレゴリーファミリーの総本部は地球にある。ジョーカー事件への対応で幹部が火星へ来ているのだろう。通信機はオンになっている。パリス警部に聞こえているだろうか。
「所持品は預からせてもらうぜ。刑事さん、窃盗罪とか言いだすなよ」
手下が僕らの銃を抜き取る。警察手帳、手錠、通信機も取り上げられた。
さらに、手を縛られ、目隠しがされた。これは、窃盗に加え逮捕監禁罪の現行犯だ。時間と場所を記憶する。
「おとなしくついてこい。親父がお呼びだ」
スペンサーが親父と呼ぶのは一人しか考えられない。大変な局面に僕は立ち会おうとしている。
こういうケースの対処法は警察学校の授業でも習わなかった。僕がやるべき任務はなんだ。情報収集か。いや、重要参考人を守ることだ。
* *
ティリーはフェニックス号の居間でレイターの帰りを待っていた。
ジョーカー事件の続報をニュースが伝えている。
毒ガスで死亡したのは、グレゴリーファミリーの関係者がほとんどだった。店から飛び出した若い男を重要参考人として警察が聴取している、とアナウンサーが冷静に報じていた。
レイターは連邦軍の特命諜報部員だ。
これまでにも人を殺したことがある。けれど、無差別に毒ガスを店で撒くようなことをするはずがない。
車のライトが近づいてきた。船の外へ迎えに出る。警察の車に乗っていたのは年配のパリス警部だけだった。
「レイターが部下のマーシーとともに拉致された」

「拉致ですか?」
驚いたけれど、レイターは『厄病神』だ。彼と一緒にいると、いろんなことが起こる。ゲリラに拉致された時もレイターと一緒に脱出した。
気持ちはすぐに落ち着いてきた。
「グレゴリー一家に連れていかれた。こちらに連絡があるかも知れないから待たせていただきたい」
「わかりました」
パリス警部が不思議そうな顔でわたしを見た。
「あなたは心配じゃないのかね?」
「心配ですよ。でも、彼はボディーガード協会のランク3Aで、危険な状況にも慣れています。きっと大丈夫です」
「レイターは今、目が見えない」
「えっ? どういうことですか?」

思わず息を呑む。
目が見えないという話を聞くと同時に、レイターがめまいがすると言って帰ってきたことを思い出した。
* *
目隠しをされたまま、僕とレイターはビルの一室へと連れていかれた。
雰囲気から察するに、このビル全体がグレゴリーファミリーのアジトのようだ。
バスッツ。
横で鈍い音がする。人を殴る音。
「痛ってぇなあ」
レイターの声が聞こえた。
「安心しろ、ボディだけにしておいてやる」

スペンサーがあの金属の義手でレイターを殴ったということか。止めなくては。
「暴力はやめるんだ」
「威勢のいい、兄さんだな」
スペンサーの濁声が耳の近くで聞こえた。冷たい金属の指が髪を引っ張る。手も使えず目隠しされている。スペンサーを蹴ることはできるが、相手を逆上させるだけだ。殴られることに備える。
レイターの声がした。
「おい、スペンサー。あんた相変わらずバカだな。ジョーカー事件で大変な時に警察と揉めたら、ダグに叱られるぜ」
「くっ、生意気言いやがって」
スペンサーは僕の髪から手を離した。
「ここでしばらく待ってろ」
目隠しがはずされた。狭くて何もない部屋に鍵がかけられた。うっすらと血の匂いがする。監禁部屋だな。窓が塞いである。敵対勢力の突入に備えて、ビル全体に窓がないようだ。
「大丈夫かい? 君、スペンサーの義手で殴られたんだろ?」

「平気さ、ガキの頃は死ぬかと思ったけどな。相変わらずせこい奴だ。不意打ちだぜ」
しゃべっているレイターから違和感を感じる。目の焦点が合っていない。すっかり忘れていた。
「レイター、君、目は?」
「目隠ししてもしなくても同じだな。悪いけどマーシー。歩く時は、俺の半歩前を歩いてくれるとうれしいんだけど」
「ああ、わかった」
「あんたも貧乏くじを引いたもんだね。俺の監視なんてさ」

「大丈夫です。警部もきっと手を打ってくれていますから。警察を信じてください」
という僕を彼は笑った。
「俺は、十二年前もダグに追われてた。さて、警察は何をしてくれたでしょうか?」
挑発的な態度だった。
「あなたを保護できなかったとは聞いています」
「うまい言い方をするねぇ。正確に教えてやるよ。警察は俺が早く殺されるのを待ってたんだ」
「それは違う」
「パリスの親父に聞いてみな。警察は俺をダグの仲間とみてたから、殺されてもどうでもいいと思ってた。それどころかうまくいけば殺人容疑でダグをたたける、って連中は俺が殺されるのを今か今か待ってたんだ。ところが、俺が中々死なないもんだから、警察もあせって俺を探しはじめた」
「あなたを守ろうとしたんだ」
「違うね。俺を保護したら警察署ごと爆破されるって状況だぜ。ダグとの取り引きに使おうとしたのさ」
「デタラメを言うな!」
僕はまだ一年目のペーペーだが、警察官としての矜持がある。
僕は田舎の新興開拓星の出身だ。ギャングが暴れて荒れ放題だった僕たちの星に警察が秩序をもたらした。その正義に憧れて僕は警察官になった。
「ウソじゃねぇよ。今回のジョーカー事件だって、俺が犯人ってことでダグに殺されれば一件落着だ。ダグとぶつかって俺を助けたって、警察には何の得にもなりゃしねぇ。あんたは不運だったよな」
そんなことはない。と否定しようとした時、ドアが開きスペンサーが顔を出した。
「親父が到着した」
身体がブルっと反応した。これは武者震いだ。僕らは裏社会の帝王、ダグ・グレゴリーが待つ部屋へと案内された。
* *
フェニックス号の居間にティリーとパリス警部が座っていた。
「どうぞ」
コーヒーを勧めたわたしに警部は質問をしてきた。
「失礼ですがあなたとレイターの関係は?……恋人ですか?」

「え、ええ」
「それは、大変ですな」
ちょっとむっとした。大変なのは本当だけど、初対面の人からいきなり言われると不愉快。
「きょう、彼に変わった様子はありませんでしたか?」
「特にありません」
「食事の後、彼とは何と言って別れたんですか?」
「『新しいレーシングゲームを試してくる』と言ってました」
「あなたはどうして一緒に行かなかったのですか?」
「わたしはゲームセンターの騒々しさが好きではないので」
「それだけですか? レイターから来るなとか、何か言われたんじゃないですか?」
「何も言われてません」
嫌な感じだ。この人から、レイターに対する敵意みたいなものを感じる。
「一つうかがいたいんですけど刑事さんはレイターを毒物事件の犯人と疑っているんですか?」

「そうです」
そのはっきりとした口調に、わたしは驚いた。
「信じられない。レイターは被害者です。彼には事件の動機も何もないんですよ」
「動機はいくらでもある」
「?」
「私はレイターを子どもの頃から知っているが、奴は極悪人だ」
思わずわたしは机を叩いた。
「そんな言い方って失礼じゃないですか!」
わたしだってレイターがマフィアとつるんでインチキなお金儲けをしていたことは知ってる。でも、わたしとつきあうにあたって、やめたはずだ。
善人とは言えないけれど、極悪人は言い過ぎ。
昔からの知り合いだか何だか知らないけど、本当に腹が立ってきた。そんなわたしの怒りを見てか、刑事さんは突然話を変えてきた。
「あなたはダグ・グレゴリーのことを、知っているかね?」

レイターが連れていかれた、というマフィアのドン。
今回の事件現場がグレゴリーファミリーの賭博場とつながっていたとニュースでやっていたことを思い出す。
「裏社会の帝王って人ですよね」
前に、レイターの知り合いというマフィアからもらった自伝本に、その名前は何度も出てきた。
「レイターが、その跡取り候補だということは?」
「はっ? 何ですって? 冗談言わないで下さい」
びっくりして声が裏返った。
「冗談ではない。そのグレゴリーの店で事件は起きた。そして彼は今、ダグ・グレゴリーのもとにいる。知りませんでした、ではすまされない状況なんだよ、お嬢さん」
突然の警部の言葉に、頭が混乱してきた。
「私はあなたのためを思って言うけれども、あいつと付き合うのはやめなさい。あなたの知らないレイター・フェニックスは、平気で悪事を働く、とんでもない奴だ」
「失礼します」

それだけ言うとわたしは居間を離れた。
警部の顔を見たくなかった。
マフィアとつるむレイターの姿が容易に想像できてしまう。
レイターの過去にはわたしの知らないことがたくさんある。彼のことを「平気で悪事を働く、とんでもない奴」と言われて、否定できない自分が嫌だった。
* *
「親父が到着した」
監禁部屋のドアをスペンサーが開けた時、僕は武者震いをした。
僕はギャングもマフィアも恐れてはいない。だが、親父とは『裏社会の帝王』ダグ・グレゴリーのことだ。さすがにアドレナリンが出た。
レイターの前に出て歩く。
案内されたのは応接室だ。高級そうな調度品が目に付く。部屋に入ると、レイターは友だちに会ったような軽い挨拶をした。
「やあ、ダグ。久しぶり」
細身で長身の男が葉巻を吸いながら深々と一人掛けのソファーに腰かけていた。
レイターは見えていないはずなのに、ダグに向かって笑顔を見せた。葉巻のにおいを頼りにしているようだ。
ピントのぼけた古い写真でしかみたことのない『裏社会の帝王』ダグ・グレゴリー本人だ。

一目でわかる。威圧感がすごい。
さっきまで偉そうにしていたスペンサーが直立不動で身体を固めている。
張り詰めた空気の中、レイターのヘラヘラした態度が、違和感をもたらしていた。
ダグ・グレゴリーと僕の目が合った。
ギャングもマフィアも僕は嫌いだ。市民の平穏を脅かす。必要悪だと言っていた叔父はギャングに殺され、仲の良かった従兄弟も巻き添えで死んだ。
現在、ダグ・グレゴリー本人に出ている逮捕状はない。なんと声をかける。
『裏社会の帝王』は口の端をゆがめてニヤリと笑った。
金縛りにあったように身体が固まる。これまで対峙してきたギャングたちとまるで違う。
ダグの顔を見た者は生きては帰れない。という噂が頭によぎった。握る手に汗がにじみ出る。
僕は警察官だ。そのプライドが正気を保たせる。
「十二年ぶりか。レイター、大きくなったな」
ダグが口を開いた。低く腹の底に響くような声。
「ちっ、そればっかりだ」

レイターは口をとがらせ不貞腐れた顔で応じた。
「さっそくだが、お前に話が聞きたい」
「何も話すことはねえよ。あんたの息がかかってるとは知らねえで、たまたまゲーセンに入った善良な一般市民が、毒物事件に巻きこまれちまった。以上」
「善良な一般市民ねえ」
ダグは紫煙をくゆらせながら立ち上がり、レイターに近づいた。左手でレイターのあごをつかむ。
「レイター、お前、帰ってきて俺の跡を継げ」
ダグのその低い声で、部屋の空気が一気に凍り付いた。
入り口近くに立っているスペンサーの顔色が真っ青になる。

パリス警部が言っていた通りの話だ。
「言っただろ、俺は一般ピープルなのよ」
そう言ってダグの手を払いのけた。
「じゃあ、ビジネスで俺のボディーガードをする気はないか?」
「ボディーガード協会を通せよ。だけど、あんたにゃ用心棒のブレイドがいるだろが」
「ブレイドの後継者を探してるところなのさ。まあいい、奥の部屋で二人で話をしよう」
ダグはレイターを隣の部屋へと招いた。『裏社会の帝王』と重要参考人を二人きりにするわけにはいかない。
「私も、立ち会わせてくれ」
声を上げた僕をダグがじっと見て応えた。
「客人は、しばし待たれよ」
「……」
次の言葉が出なかった。ゆっくりとした口調なのに、一切の反論を許さない。
レイターは軽い足取りでダグの後ろを歩いていく。誰一人レイターの目が見えていないことに気付いていない。と思った時、ダグが口を開いた。
「レイター。そこは少し段になっているから気をつけろ」

「ご丁寧にどうも」
誰も気にとめない普通のやりとり。
僕だけが息を飲んだ。ダグは気が付いている。レイターの目が見えないことを。
バタン。
隣の部屋のドアが閉まった。
* *
グレゴリーファミリーのどのアジトにもダグのための小ぶりな執務室がある。ナンバーツーのスペンサーも入ることは許されない。二人が入っていった防音の部屋のドアをスペンサーは穴が開くほど凝視していた。
そこには、十二年前もレイターは入室できた。
「久しぶりの親子の対面だぞ、もっと素直に喜んだらどうだ。もっとも父親の顔が見えなくては実感がわかないか?」
ダグが低い声で笑った。
「よく言うぜ、殺害の『緋の回状』回しといて。あんたも出世したもんだよな。『裏社会の帝王』は表社会にも随分顔を利かせてるそうじゃん」
「半分はお前のお陰だ。感謝している」
「フン」
「お前も素直に跡を継ぐと言っていれば、もっといい暮らしができたぞ」
「俺は表で十分楽しい毎日を送ってんだ」
「そうだな、憧れの『銀河一の操縦士』にもなれたしな」

「いちいち、うっせぇんだよ。大体、俺が跡を継いだら、あんたの大好きな秩序が壊れるだろうが」
「俺が好きなのは秩序だけじゃない。もう一つを忘れたわけじゃないだろう?」
レイターはあきれたように肩をすくめた。
「ったく、秩序と狂気かよ。確かに十分、狂ってるぜ」
ダグは革張りの回転椅子に腰かけると葉巻の灰を灰皿に落とした。
「フフフ。本題に入ろう。今回の事件は我々にとって随分迷惑なものだった。被害者のほとんどがうちの関係者だ」
「そりゃ災難なこって。賭場ももう使えねぇんだろ。踏んだり蹴ったりだな。言っとくが俺じゃねぇからな、毒ガス撒いたのは」
「なぜ、お前はあの時間あそこにいた?」
「答えは簡単。ジョーカーに新型の宇宙船ゲームが入ってたからさ」
「真面目に答えろ。物事を茶化すのは昔からお前の悪い癖だ」
レイターが口をへの字に曲げた。
「俺はあんたのシマに近づかねぇように人生送ってんだ。あんたもわかってるだろ、俺の動きを見てれば」
「闇での噂はよく聞く。個人でやらせておくにはもったいない腕だと思っているよ」
「残念だが、足洗ったんだ」
「俺が聞きたいのはそんなことじゃない」
ダグはゆっくりとレイターに煙を吹きかけた。
「お前のもう一つの顔だ。将軍家直轄の特命諜報部隠密班」

「……」
レイターが黙った。
「特命諜報部は何を知っている? それが聞きたい。十二年間、俺との接触を避けてきたお前が、なぜ、今日あそこにいた?」
「偶然だ、っつうの」
「レイター、お前、素手で俺を殺せるんだろ」
「は? だったらなんだよ」
「ここでやってみろ、そうすればすぐに俺の跡が継げるぞ」

「あんたの、そのめんどくせぇ性格につきあう気はねぇ!」
* *
レイターとダグ・グレゴリーは二人だけで隣の部屋へと入っていった。
僕は、手下の一人に銃を突き付けられたまま立っていた。

何としてもレイターを救出して逃げ出さなくてはならない。部屋の状況を把握する。
スペンサーは動揺が収まらず鼻で荒い息をしている。彼自身はダグの跡目を継ぐつもりでいることがよくわかる。
手下たちは緊張を緩めることなく棒立ち状態だ。
ダグは僕を客人と呼んだ。レイターがスペンサーに言った通り、ダグは警察と揉めたくないのだろう。
普段は、警察とマフィアは対立している。
だが、ジョーカー事件でそのバランスが崩れている。今回、グレゴリーファミリーは被害者だ。一方で、これだけの騒ぎを起こし、賭博場が表に出たことで、我々は監視を強くすることもできる。マフィア側からすれば、事を荒立てないのが賢明だ。
そこを利用してここを出るしかない。だが、どうすればいい。興奮状態のスペンサーとはまともな交渉できる気がしない。
バタン。
突然、ドアが開いた。
「スペンサー!」
レイターが叫びながら飛び出してきた。そのままドアの前に立っていた見張りを蹴り倒すと、するりと手錠から手を抜き、銃を奪う。
「き、貴様、何をした?」
スペンサーがあわてている。レイターとダグとの間で一体何があったのか?

奥の部屋からダグの笑い声が聞こえる。
レイターは銃口を正確にスペンサーに向けた。目が見えない彼は、スペンサーに呼びかけることで位置を確認したのだろう。
「ブレイドがいなくて助かったぜ。スペンサー、俺の射的の腕前忘れたわけじゃねぇだろ」
「や、止めろ」
スペンサーはあわてて金属の義手で自分の急所をかばう。防弾か。
「さて、マーシー、行くぜ」
「ああ」
僕は声を出して返事をした。
レイターはスペンサーを銃で狙いながら僕の声に向かって近づいてきた。手下たちは動けないでいる。
レイターが片手で僕の服の端をつかんだ。僕は外へつながるドアに向かって、走り出した。レイターが後ろからついてくる。
「撃て、撃て、逃がすな!」
スペンサーの声が背後から聞こえる。
ビュンッ。
閃光と熱。レーザー弾が耳の横をかすめる。
レイターが振り向きながら銃を撃つ。人が倒れる音がする。本当に彼は目が見えていないのか。
目隠しをして連れてこられたが、僕は方向と歩数を数えて記憶していた。出口へ近づいているはずだが、ビル内の構造は増改築を繰り返したかのように複雑だ。
「次の角を右だ」
僕が迷うとレイターがすかさず指示した。
ドアの開くわずかな音も彼は聞き逃さなかった。前からの追っ手も撃ち倒していく。
ドドンッドドンドンドン。
ビル内に一斉放送がかかった。打楽器の音楽が流れだす。
「ちっ」
目と耳の両方の感覚を封じられてレイターが混乱したようだ。足が止まった。僕も立ち止まる。
突然、レイターは天井を最大出力で撃った。照明が落ちて真っ暗になる。打楽器の音もやんだ。エネルギー回路を切断したのか。
相撃ちを恐れたグレゴリー側の射撃も止まった。
レイターが僕を先導する。彼は暗闇の中、スピードを落とすことなく夜行性の動物のように走り抜けた。連邦軍の皇宮警備はどれほど高度な訓練を積むのか。
僕だって警察学校で突入訓練は経験している。だが、暗視カメラなしでは無理だ。彼に服を引っ張られ、何度もつまずきそうになりながら、必死に後についていった。
見張りを倒して外へ出る。夜が明けていた。目に陽の光がまぶしい。
「レイター!」
ビルの前で手を振る男がいた。見るからにチンピラという格好だ。

「おいらだよ。ジムっス。この車に乗れ」
「ジム」
敵か味方かわからないその男の車にレイターは素直に乗り込んだ。
「空港まで頼む」
「合点承知ッス」
レイターはシートに深く腰掛けて目を閉じた。
「マーシー。あとはまかせた」
そう言ってレイターは僕に銃を渡した。
「もう俺のできることはねぇから寝る。気持ち悪くて吐きそうなんだ」
レイターの身体が僕に寄りかかってきた。具合が悪いのか。
「大丈夫か?」
彼は寝息を立てて寝始めた。こんな状況で眠れる神経がよくわからない。
追っ手は来なかった。
「ジムさん。あなた、レイターとどういう関係なんですか?」
「幼なじみッスよ。おいら、グレゴリー一家の構成員ッス」
「え?」
ファミリーを裏切って助けてくれたということか。
きょう僕はレイターを警護したのか。それとも彼に警護されたのか。落ち着かないままジムから借りた携帯通信機でパリス警部に連絡をいれた。
* *
フェニックス号の前でティリーは待っていた。
間もなくレイターが到着するという連絡がパリス警部のもとに入ったのだ。
毒物の影響で、レイターの目が見えないという話を聞いて、わたしは居ても立っても居られなかった。ずっと寝ないで待っていた。
車が船に近づいてくる。
「レイター!」

車から降りてくるレイターを見てわたしは駆け寄った。
安心と不安が入り乱れて、涙がこぼれた。
「ただいまっ、ティリーさん」
レイターの声は明るいけれど、顔色はよくない。目をのぞき込むと焦点があっていない。
「大丈夫? あなた、目が見えないの?」
「ふむ、月のない真夜中みてぇだ。かわいいティリーさんのお顔が見えねぇのは残念だな」
彼はわたしの頬を両手で包みこむと、そっとわたしの涙をぬぐった。
熱があるのか手が熱い。

「泣くなよティリーさん。二、三日もすりゃ治るさ。目が見えなくてもキスにゃ困んねぇよ」
と言いながらレイターが唇を重ねてきた。
キスをしながらも、わたしの涙は止まらなかった。
レイターの目が心配なことに加えて、パリス警部が口にしたわたしの知らないレイターが不安を増幅させている。この人が『裏社会の帝王』の跡取り候補。
レイターはわたしの髪をくしゃくしゃとなでながら耳もとでささやいた。
「何かあったのか?」
いつもと変わらない声だった。わたしの知っているレイターだ。
「わたし、レイターのこと信じてるから」
顔を見上げてそう答えるのが精一杯だった。
レイターは笑顔を見せた。
「さては、パリスの親父に変なこと吹き込まれたんだろ。グレゴリー一家の大悪党とかなんとか」

どきっとしながら、小さくうなずいた。
「大悪党じゃなくて極悪人」
「ほんとバカだな」
そう言うとレイターはわたしを強く抱きしめた。
「ったくあの親父も一度でも俺を逮捕してから言え、ってんだ」
この人の中には、悪いことを躊躇なくできるレイターと、他人のために命を投げ出せるレイターが共存している。
わたしの知らない過去のレイターがたくさんいる。それでも、目の前にいるレイターはわたしの大好きな彼氏だ。
レイターの胸の鼓動がわたしの身体に響く。乱れた心の波動が整ってくる。
* *
フェニックス号の居間で警察官のマーシーは船内を見回した。
変わった船だ。操縦席が分離されていない。こんな船は初めて見る。パリス警部は部屋の外で本部と連絡を取っていた。
レイターの彼女だというティリーさんが僕たちにコーヒーをいれてくれた。
レイターは船の中で全く不自由なく歩き回っているから、つい目が見えないことを忘れてしまう。
机の上に置いたコーヒーカップを手で探すレイターを見て、隣に座る彼女があわてて手に持たせた。
幼なじみだったというジムが驚く。
「レイター、目が見えないんスか?」

「あんた、何、言ってんだ今ごろ」
「だって、走ってたじゃないスか。さっき」
「足が悪いんじゃねぇんだから走れるさ。とにかくジム、ありがとな」
「とんでもないッス」
「ジム、そのパシリみたいなしゃべり方やめろよ。昔はため口だったじゃねぇか」
「おいら、レイターについていくって決めたんスよ」
「はぁ?」
「おいらがグレゴリー一家にいるのは、レイターが跡を継ぐために帰ってくると思ったからで」
ティリーさんがビクッと反応した。
「ジム、俺の彼女が驚くだろが。変なこと言うな」
そう言ってレイターは正確にジムの頭をはたいた。
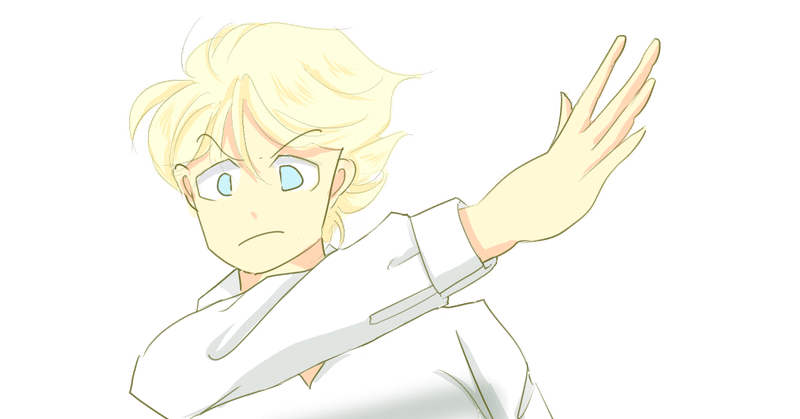
「痛てぇ」
「レイター、やめなさいよ」
ティリーさんが止める。
「さすが、おかみさんッス。レイターがナンバーツーのスペンサーなんかとは格が違うってことはみんな知ってるんスよ。ダグだってレイターに後を継いで欲しがってるし」
彼は間違いなくダグの後継候補だ。
「言っとくが、俺は一度だってファミリーに入ってたことはねぇんだからな。ティリーさんも刑事さんも勘違いしねぇように」 まとめ読み版② へ続く
裏話や雑談を掲載したツイッターはこちら
ティリー「サポートしていただけたらうれしいです」 レイター「船を維持するにゃ、カネがかかるんだよな」 ティリー「フェニックス号のためじゃないです。この世界を維持するためです」 レイター「なんか、すげぇな……」
