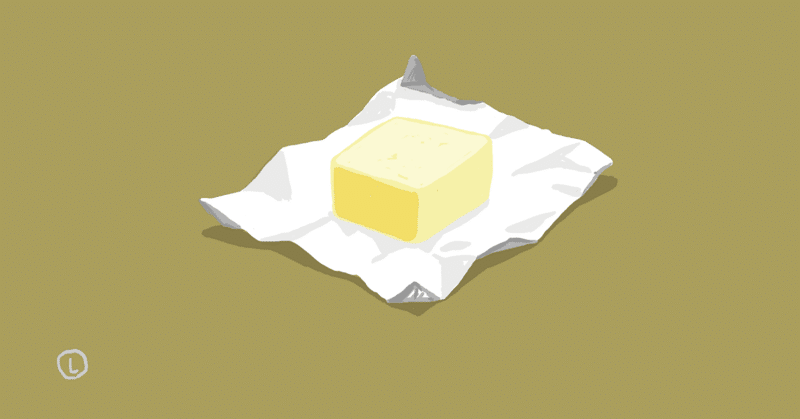
つめたいバターを舌に乗せ|柚木 麻子『BUTTER』からの連想
柚木 麻子『BUTTER』を読み返したら、冷蔵庫から出したてのバターをひとすくい、そのまま舌に乗せたくなった。
※小説の中の具体的なエピソードにはほぼ触れていませんが、結末についてハッピーエンドかそうじゃないか程度の言及をしているため、ネタバレタグをつけています。ご注意ください。
愛人業の果てに複数人の男たちの殺害容疑を掛けられた「若くも美しくもない」女――記憶に新しい実在の事件をモチーフにして、容疑者と週刊誌記者、その友人という三人の女を軸に物語が進んでいく。
作品の中で頻繁に引かれる『ちびくろさんぼ』の結末が示唆するとおり、この小説のキーワードは「変容」だ。にらみあった虎がぐるぐる回るように、女たちの関係性はめまぐるしく変わりゆき(支配と隷属、ケアするものとされるもの、戦友、共依存、敵同士……)、それと同時に人格までも変容していく(または、見えなかった面が立ち現れる)。輪になってぐるぐる回り続ける三人の女の周りには次々に、それぞれの感情と人生を抱えたたくさんのおんなたちが現れ、それがまたさらなる変容を促す。
白く固まったバターが溶けて流れて、あらゆるものに絡みつくがごとく、物語は一時も形を定めない。
そして、揺らぎ変容し続ける女たちと対象的に、まるでこの世の真理のごとく盤石なものとしてそこにあるのが、「食べること」の喜びである。
ひとりで欲望のままにとる、一個の動物としての喜びがあふれる食事(たとえば深夜のバター醤油ごはんやたらこスパゲティ、セックスのあとの塩バターラーメン)。友人や同僚とテーブルを囲む、日々の生活と営みの象徴のような食事(たとえば真冬の新潟で味わう、米や味噌や魚や野菜を使った素朴で滋味深い料理たち)。
食事のシーンが出てくるたび、そのページに目が釘付けになる。詩的な比喩と、リアルな身体感覚でもって豊かに描写される、世にもおいしそうな食物。それらを歓喜をもって噛み砕き、飲み下す女たちの様子を追っていると、なにか清冽な光を宿したものが、身体の中に入り込んでくるような錯覚を覚える。食べることは生きることだ、と、そんな紋切り型の言い回しが、なんの衒いもなく頭に浮かぶ。
そんな中でも、題名に冠されている「バター」はやっぱり特別。
食べるということそのものが持つ生命力とはまた別の次元で、この小説の中のバターは単なる食べものではなく、あらゆるものの象徴だ。飽食、肉欲、神秘、解放、依存、救済、ひかり、いのち、そして変容――登場するたびに、さまざまな単語が頭に浮かぶ。
カロリーやコレステロールといった概念がふだんこの食べ物に抱かせている、どちらかというと不健康で背徳的なイメージはいつのまにか完全になりをひそめ、物静かで神聖で、計り知れないほどの豊かさを湛えた物質としてのバターが、そこここで描かれる。
そういえばこの小説以外の本でも、バターが特別な食べ物として描かれる様子をなんどか見てきた。
子供のころ、家族でレストランにいくとき、私のいちばんの楽しみはバターだった。銀色の器にうやうやしく並んだ、まるいバター。私はそれを、バタナイフにつきさしてそのまま食べた。のどを滑るつめたさと、塩気のあとに感じるこってりとした甘み。
茹でたとうもろこしにバターをのせて、溶けて流れ出す直前を歯で食い止められたときのうれしいこと。口のなかに冷たいバターの固まりが残っていないとつまらない。だからとうもろこしを食べ始めると、バターの消費は急激な勢いとなる。
「(前略)美味しいバターを食べると、私、なにかこう、落ちる感じがするの」
「落ちる?」
「そう。ふわりと、舞い上がるのではなく、落ちる。エレベーターですっと一階下に落ちる感じ。舌先から身体が深く沈んでいくの」
バターの、人を魅了する力はどこに秘められているのだろう。たとえばオリーブオイルとか、同じ動物性油脂でもラードなどには到底宿らないような神話性のようなものが、文筆家たちを惹き付けているように思える。
読んでいる間ずっと渇望し続けた。バターが食べたい。それも、冷蔵庫から出したてのしんと冷え切ったバターをひとすくい、そのまま舌に乗せてみたい。そうしたら、もっとこの物語を理解できる気がする。
銀色のナイフで掬ったバターはきっと、ストイックに冷たく固く、それでいて舌に乗せた瞬間から、淡雪のようにすうっと融けはじめるだろう。私の身体の熱を奪ってとろりとした液体に変じたそれが孕んだ乳脂肪の甘さとコク、微かな塩気は、こよなく静かに、ひとしずく残らず味蕾へ染み込んで、私の身体の一部になるだろう。
ふだんは思い付きもしないそんな欲望が顔を出すのだから、物語の持つ力は計り知れない。
物語はくるくると変容しながら、救済へと進みゆく。静謐な光が差し込むようなラストシーンに心を奪われながら、原始的で暴力的で、そして不穏な食欲が胃の腑に巣食っていることを、私ははっきりと自覚する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

