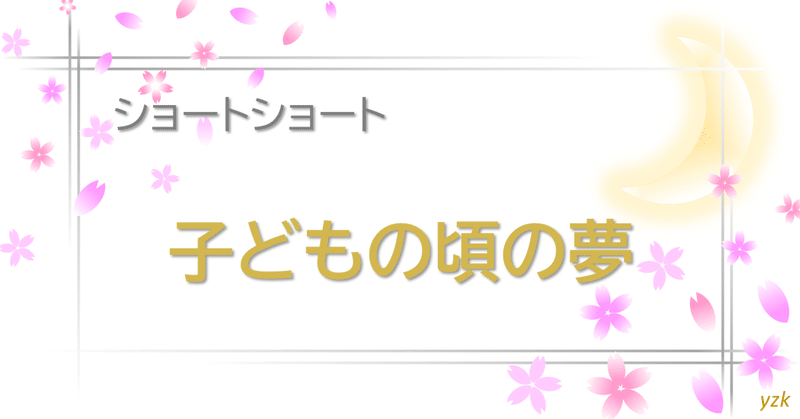
【ショートショート】子どもの頃の夢
「子どもの頃の夢って、何だった?」と、夫がタブレットから顔をあげて訊いた。ニュース動画で、小学生の夢ランキングなるものが紹介されていたようだ。
私は、ソファーに投げ出した足をマッサージしていた。一日じゅう車椅子に座っていると足の血行が悪くなるし、むくみもする。だから、車椅子に座ったまま足だけをソファーに乗せ、ストレッチやマッサージをする。たいていは、夕食と後片付けが終わったこの時間に。そして、たいていは、私の足のとなりに夫が座っている。結婚するときふたりで見つけた、オリーブ色のソファーに。
「子どもの頃の夢ねえ……そっちの夢ではないんだけど、トイレの夢をよく見てた」
ふくらはぎを横から軽く叩きながら、そう答えた。
「ああ、寝てるときに見る夢のほう」
「そうそう」
夫が訊いたのは大人になったら何になりたかったかの話だと分かっていたけれど、子どもの頃の夢というと、すぐに思い出すのはトイレの夢なのだ、どうしても。
人によっては、ある決まったシチュエーションで窮地に陥る夢をしょっちゅう見ることがあるらしい。
私の場合、決まったシチュエーションとは、トイレだった。
小学校に上がる前後から、何度も同じ夢を見た。夢の中で、私はトイレに座っている。でも、どんなに意識を集中しても、何も出ない。私は、いま出しておかなきゃいけないのにと、心の底から焦る。
この夢は、現実を色濃く反映している。
私は生まれつきの脳疾患で手足に障害があり、幼少期からずっと車椅子を使って生活している。人生の大半の期間、トイレで用を足すには全面的な介助が必要だった。車椅子から便座に乗り移ることも、下着の上げ下ろしも、用を足したあとトイレットペーパーで拭くことも、自力ではできない。
小さい頃から、トイレのことは心の片隅でいつも気にしていた。尿意がなくても、しばらくトイレに行けなくなるからと、粘って無理やり出すことがしばしばあった。しばらくトイレに行けなくなるのは、介助者が不在にするとか、出かけた先に車椅子で入れるトイレがないとか、そういう理由だ。
学校では、午前中の中休みと給食後にトイレに行くと決めていた。その時間に母が来てくれていた。それ以外の休み時間は、トイレに行かない。いや、行けない。介助者がいないからだ。私は通常学級に通っていたけれど、当時はまだ、障害のある生徒を学校内で介助する支援員の制度がなかった。
遠足や旅行のときは、トイレ休憩だからといって車椅子で入れるトイレがあるとは限らないので、使えるトイレがあるときに行くようにしていた。車椅子ユーザーがどこの公衆トイレでも使えるような社会ではなかったのだ。
家から一歩出たら、生理現象に従うというよりは、トイレをめぐる環境に体を合わせる。それが、私の子ども時代だった。
いざとなったら授業中でも先生にトイレを訴えたり、トイレ休憩のたびに用を足したりできる周りの子たちと、それが叶わない私とでは、一回のトイレチャンスの貴重さと、それを逃してはならない切迫感が、おそらくはまるで違うのだった。
トイレに自由に行けない毎日は、子ども心に結構なプレッシャーだった。次のトイレタイムの前におしっこしたくなったら困るのに、いま何も出なかったらどうしよう、と尿意のないトイレタイムにはいつも心配していた。
トイレに座っても何も出ない夢をしょっちゅう見るのは、そのプレッシャーの現れだったのだろう。
夢の中の私は、焦りを募らせる。焦れば焦るほど、本当に一滴たりとも何も出てこない。現実では、こんなに何も出ないならしばらく大丈夫だろうと思えることもあるのだけれど、夢の中では、そうはいかなかった。何が何でもここで用を足しておかないと、という強迫観念がせり上がってきて、どんどん追い詰められていく。
そんな夢を、何度も見た。小さな頃から、本当に何度も。
だから、子どもの頃の夢と聞くと、トイレに座って焦っていた夢を一番に思い出してしまう。歌手になりたいとかパン屋さんになりたいとか、そういった、将来へのキラキラした夢ではなくて。
「そうだったのか。子どもの頃、トイレのことをいつも気にしなくちゃならないことが、すごく重荷だったんだろうね」
私の話をひととおり聴き終えると、夫がいった。夫とは、恋人時代も含めると5年ほどの付き合いになるけれど、トイレの夢の話をしたことは一度もなかった。
重荷。それは、この上なく的確な言葉だった。私は、夫に話がきちんと伝わったと分かり、安堵した。
自分自身について他人に話すとき、本当に伝わるように話すことも、話の意味を本当に分かってもらうことも、なかなか容易なことではない。でも、私は夫と結婚して、自分自身の何事かを話しても本当には伝わらなかったときの埋めようのない孤独を、以前ほどには感じなくなった。
「そうだね。あの感じはまさに重荷だったんだと思う。子どもだから、なおさらかもしれない。トイレのことで失敗しちゃいけないって。大人なら、もう少し開き直れるのかもしれないけどね」
「いまはもう、そういう夢を見ることはない?」
「うん、何年も見てない」
「なら良かった」
夢から解放されたいまでも、夢の中で追い詰められていく恐怖や夢から覚めたときの疲労感をありありと思い出せるけれど、あの夢に怯えることは、たぶんもうない。
「トイレの話してたら、トイレ行きたくなっちゃった」
私がそういうと、夫は小さく笑って私の足をソファーから下ろし、車椅子のフットレストに乗せてくれた。
私はリビングの引き戸を開けて、廊下の隅で待機しているリベコルに声をかけた。
「リベコル」
《どうしましたか?》
音声と、顔の部分にある液晶画面の文字表示で、リベコルが訊く。
「トイレをお願い」
《わかりました》
リベコルは、人間並みに介助ができるAIロボットだ。「自由な体」を意味するラテン語を縮めて、名づけられたらしい。2030年に介護施設で導入され、そのあとすぐ介護保険や障害福祉サービスの給付品目になった。それで、私のように個人家庭でも使うことができる。
頭部に胴体、二本ずつの手足。丸みのある濃いグレーのボディで、待機中は70センチほどの身長しかないけれど、呼びかけて介助を頼むと胴体の部分が自動で上に伸びて、160センチくらいになる。
見た目を人間に近づけた機種もあるけれど、私はあえて、ロボット然としたタイプを選んだ。
感情のやり取りが発生したり、気兼ねしたりせずに済むのが、ロボットのよいところだ。介助者の都合を推し量ったり、推し量っていないふりをしたりする必要もない。日に何度も人に介助してもらわなければならない生活だと、人間同士の関わり合い特有のあれこれが、ときに煩わしくなる。せっかく介助ロボットを導入したのだから、外見や話し方から人間っぽさを感じさせないロボットでいてくれるほうが、気楽でいい。
リベコルを使い始めたことで、私は夫との結婚に踏み切ることができた。トイレや入浴や着替えや、その他もろもろをリベコルに頼れるから、いわゆる健常者である夫と対等な関係でいられる。
《持ち上げます》
「うん」
ちょうどリベコルに抱えられて車椅子からトイレに移るとき、ふいに気づいた。夫の最初の質問に、まだ全然答えていない。
子どもの頃の夢は、小説家になることと、好きな人と幸せに暮らすことだった。
大人になった私は、小説家ではないものの、エッセイの連載を持ち、エッセイ集を何冊か出している。文章を書く仕事というくくりなら、夢から大きくはずれてはいないだろう。
二番目の夢が叶ったことは、いうまでもない。
〈完〉
作品を気に入って下さったかたは、よろしければサポートをお願いします。創作の励みになります。
