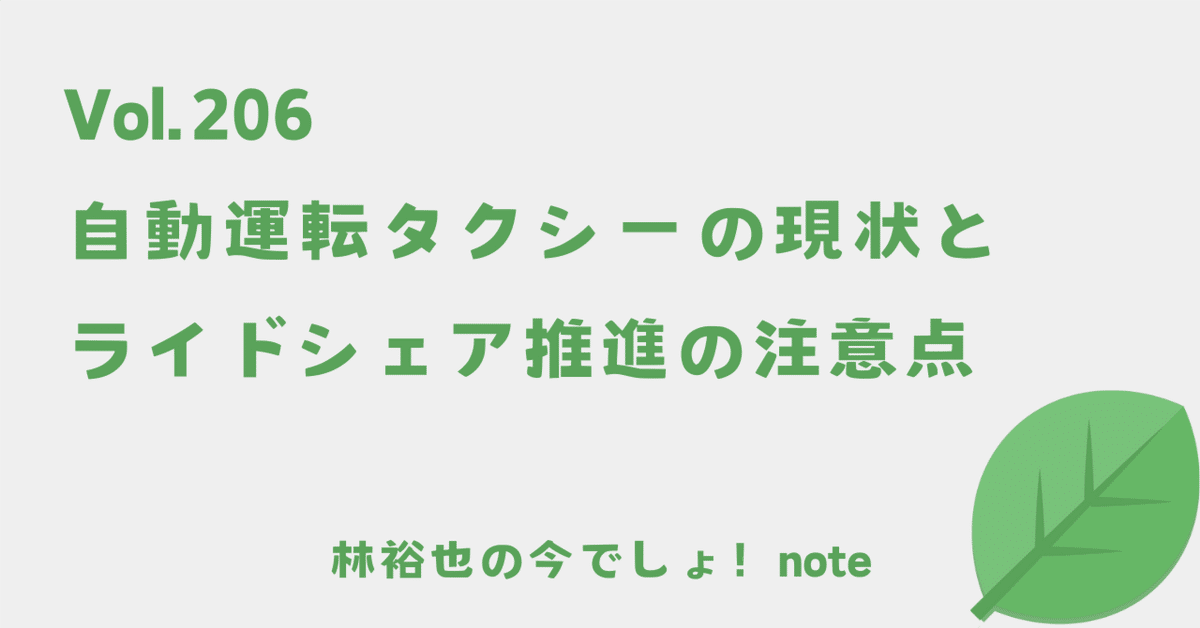
#206 自動運転タクシーの現状とライドシェア推進の注意点
いかがお過ごしでしょうか。林でございます。
今度、ライドシェアやモビリティをテーマに、3児移住ワーママさんにインタビューをさせてもらう予定なのですが、私がこれまであまりアンテナ高く張っていた分野ではなかったので、基本知識くらいは仕入れておこう!という趣旨の記事です。
前回は、実家は地方にあるけど今は東京で暮らす私にとって、自分事として感じられる地域交通の課題って何だろう?と思いを巡らせながら書いてみました。
今日は、前回の記事の最後にも色々と気になったところが出てきた、という趣旨の話をしていますが、その一つである「自動運転タクシー」の検討状況の現在地を概観を掴んでおこう!というのと、個人的には自動運転タクシーが一般的になってくるまでの繋ぎとして大活躍するであろうと考えているライドシェアを推進する時に、今後どのような論点を持って見ていかないといけないのか、という点をまとめておきます。
自動運転技術におけるステップ
国土交通省が「自動運転に関する取組進捗状況について」というレポートを出しているので、まずはそれを元に基本知識をまとめてみます。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001583988.pdf
自動運転技術におけるステップは、レベル1〜5として段階的に定義されており、各国の社会実装における段階論の指標もこの定義をもとに議論されています。
以前、カーニー日本法人会長の梅澤高明さんが自動運転のレベル1〜5についてお話されていたのを思い出して、国土交通省のレポートと梅澤さんの話をあわせて聞くことで、より理解を深められました。
レベル0が従来の自動車だとすると、レベル1は「一方向だけの運転支援」とあるように、アクセルとブレーキ操作による前後の加速減速か、ハンドル操作による左右の制御いずれかをシステムが支援するものです。
「衝突被害軽減ブレーキ」は2019年時点で9割を超える新車に搭載、とあるように、レベル1の車は割と一般的になっている印象です。
レベル2は、「縦・横方向の運転支援」とあるように、前後左右の動きを制御し「走る・曲がる・止まる」の機能を複合的にシステムが制御するレベルです。
日産が2019年に販売開始した「ProPILOT」、ホンダが2021年に販売開始した「Honda SENSING Elite」などがこれに該当します。私の実家の車もこれが搭載されていて、高速道路で「自動運転モード」をオンにすると、前の車を自動で追従したり、左右の位置の微調整といったハンドル操作を自動で行ってくれます。
レベル1と2では、ドライバーが常に運転状況を監視し、必要に応じて自分で操作することが求められます。
レベル3は、「特定条件下での自動運転」とあり、「走る・曲がる・止まる」を全てシステムが行うため、ここからが本当の自動運転と呼ばれます。しかし、条件外では、人が操作する必要があります。
レベル4は、「特定条件下での完全自動運転」とあり、高速などの特定状況のみ、あるいは大雨、大雪などの極限環境以外で「走る・曲がる・止まる」をシステムが全て行ってくれます。基本的にドライバーが操作する必要はありませんが、高速道路などの特定条件を離れたら人間の運転が必要です。
レベル5は、「完全自動運転」で、レベル4の極限環境も含めて、全てシステムが運転を行う完全な無人運転です。セーフティドライバーや人間の操作を全く求めません。
自動運転で先行する米中。日本は5年遅れ
米国では、Google系Alphabet傘下の自動運転車開発企業のウェイモ、GM子会社のGM Cruiseの二社が社会実装を牽引してきました。
ウェイモは、2018年に世界初の自動運転タクシーサービスをセーフティドライバー付きという条件でアリゾナ州郊外で開始し、2020年10月に完全無人の商用サービスに発展しています。GM Cruiseも深夜帯に限定したサービスから開始しました。
2023年8月、両社には、市内全域で有償サービスとして24時間の完全無人運行が認められています。しかし、2023年10月に、GM Cruiseが関与する人身事故が発生し、GM Cruiseは950台のロボタクシーを運行停止、CEOも辞任する事態となりました。
中国では、Baiduが先行し、2017年にアポロ計画と呼ばれる自動運転車の共同開発の企業連合プロジェクトを発足させています。
2018年7月には、世界初のレベル4の自動運転バス「アポロン」の量産を開始し、2022年に完全自動運転の商用ロボタクシーの試験運用を開始しています。
Auto X社は2021年1月、中国初のセーフティドライバーなしの無人ロボタクシーの商用サービスを深圳で開始させました。
日本では、2023年4月の道路交通法改正により、レベル4の自動運転が解禁。2023年5月より福井県永平寺町で日本初のレベル4での自動運転の実証実験が開始されています。これは、2つの停留所を結ぶ2Km区間で自動運転を実現するものです。
2023年10月には、ホンダとGM Cruise社が都内お台場での2026年初頭でのレベル4の自動運転タクシーサービスの開始を発表しましたが、その5日後に上述したCruise社の車両が関与する人身事故が発生しているため、この先の見通しは分かりません。
アメリカでは2020年、中国では2021年に無人ロボタクシーの商用運行を開始させていることから、日本は約5年の遅れと言えます。
自動タクシーより先に実現できそうなライドシェア
このように、日本で自動タクシーがより一般的になるには、もう少し時間を要する見込みです。
先日ご紹介した国土交通省のモビリティに関する最新レポート(2024年5月31日)においても、「2027年度に100ヶ所以上で無人自動運転サービスを実現」といっているくらいで、はじめはインバウンド政策と関連付けて観光地での導入が優先されるでしょうから、私の実家のように一般的な生活者でもある程度無人タクシーが使えるようになるのは、もう少し先になりそうです。
仮に2030年となれば、私の場合、父親70歳、母親67歳の年齢となっていて、免許返納を考え出しているあたりだと思います。この時、自動運転よりは先に一般化できそうなライドシェアがどのくらい普及できているかは、生活スタイルに直結するリアルな課題です。
ライドシェアが一般的となった場合の利用額は、運営コストを加味すると現在のタクシーの約10分の1程度との試算がいくつかの調査会社、大学の研究で公表されており、よりマイカー保有からシェアリングへとシフトする動きも加速するでしょう。
ただ、ライドシェアが国内で進むほど、国内自動車産業に与える影響が大きいのも事実です。自動車産業は、現在安定的に貿易黒字を叩き出せる唯一の産業で、2019年時点で12兆円の外貨獲得産業になっているとのこと。世界的なシェアリングの潮流を見ていると、この流れは不可避であると見ており、電気産業のような流れになるという強い危機感を抱いている人も多いはずです。
また、Uberのような外資ライドシェア事業者が一気になだれ込んでくれば、沖縄には観光客が多いのに外資ホテルばかりで地元に外貨が落ちないというのと同じ構造で、インバウンドで観光客は多くくるのに、観光客の移動にかかる消費は観光地に全く落ちず、地域経済が思うように活性化できないという状況にもなりそうです。
少なくとも、ライドシェアのような仕組みが発展して、観光客が移動しやすくなることで観光客が増加し、既存のタクシー事業者の稼ぎも増えるという面はあるでしょう。いきなり外資企業がなだれ込んでこないように、あえてブレーキを踏みながら、国内企業が稼げる仕組みで確実にライドシェアを浸透させていくのが、大方針としては適切なのだろうと考えているところです。
それでは、今日もよい1日をお過ごしください。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
この記事が参加している募集
もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!
