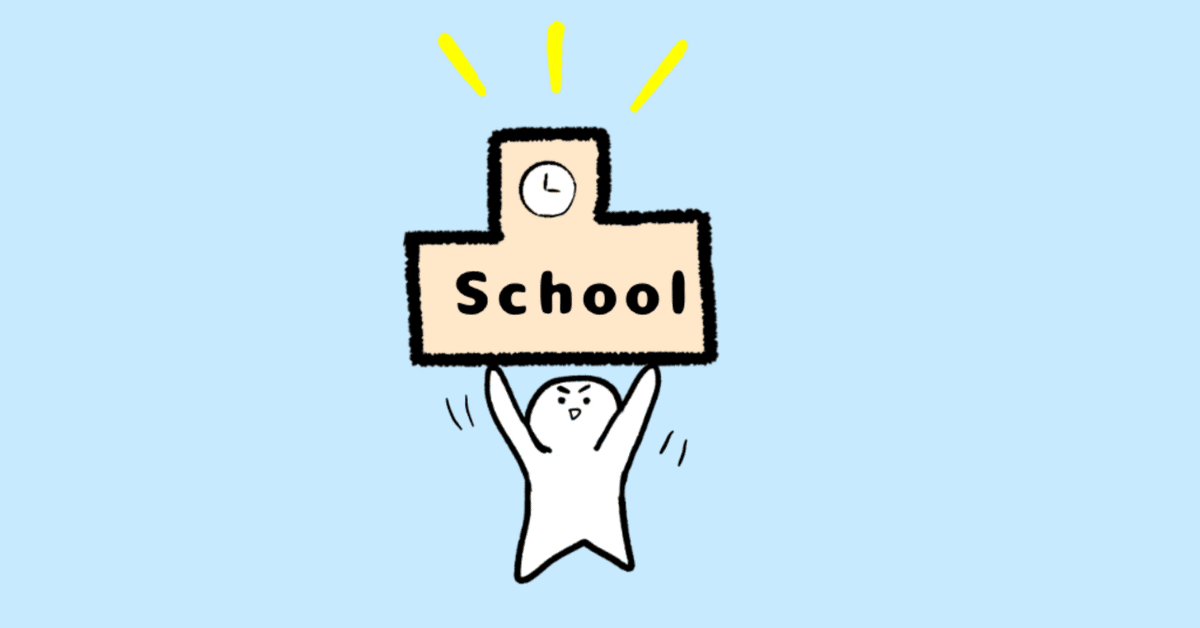
【今でしょ!note#56】 高校普通科の危機 (2/2)
いかがお過ごしでしょうか。林でございます。
前回は、昨年末に公表された文部科学省 国立教育政策研究所の義務教育終了段階の生徒が、実生活で活かせる知識や技能をどの程度身につけているかを測定するPISA調査のレポートから考えたことを整理しました。
https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2022/01_point_2.pdf
前回記事はこちらになりますが、日本の高校1年生段階の平均的な基礎学力は、世界的に見てもトップレベルであるにも関わらず、その後の大学ランキングでは欧米や中国の大学が上位を台頭し、また労働生産性もOECD 38カ国中30位(2023年)とその後の勢いに繋がっていかないのは何故だろうと考えるに至りました。
そして、今の社会でより求められるようになっている「何か他人よりずば抜けた専門性」や「自分の頭で考えて課題解決できる能力」のトレーニングが高校・大学くらいでできていないのでは?という1つの考えに辿り着きます。
まずはその入り口となる高等教育、特に何かに特化した技能というよりも、大学進学を主目的とした高校普通科の授業時間が大学受験対策のための時間に寄りすぎているのではないか?ということで、どのような機会を作っていけると良いのか、私なりに考えたことをご紹介します。
社会に出てから究極的に必要なスキル
AIなどに代表されるテクノロジーの加速度的な進展により、世の中の変化はこれまでよりも今後ますます速くなっていきます。
そうなると、何が今後の社会で必要とされるスキルなのか、自分が社会の中で重宝され、相対的に価値を引き上げて稼ぎに繋げていくために何を身につけておけば良いのか、ということについて、誰も予想ができなくなっています。
じゃあどうすればいいの?ということになるわけですが、私はそんな状況の中でも普遍的に変わらない本質的なスキルがあると考えています。
それは、「世の中がどのように変化しても、変化の内容に応じて、自分の頭で考えて、課題を解決していける能力=課題解決能力」と「世の中の流れを見て、自分はこちらを選ぶ、と自分で意思決定して行動していく能力」です。
おそらく、この2つさえ持ち合わせていれば、どんな世の中になっても人は生きていけます。実際に、今社会で活躍されている人は、皆余すことなく持ち合わせているスキルだと考えています。
これは、高校生や大学生だけでなく、大人にも共通して必要な能力ですし、何ならこれらを持ち合わせていない大人が結構多いように感じます。
そしてそれは、暗記型で1つの答えをできるだけ早く解くことばかりを反復練習して鍛錬する日本型教育が、なかなか変わってこないことに大きな要因があります。
学校教育現場のアップデートは遅い
学校教育現場のアップデートは遅いです。
全国どこでも一定の教育課程水準が保てるよう文部科学省が定めている学習指導実施要領は10年に1度しか改訂されません。
また、地域大学の教育学部の先生や、現職の小中高の先生方とお話する機会が多くあったのですが、「学校では、去年と同じ授業を教え続けていれば、基本的に困ることがないからアップデートされにくい」ということもおっしゃっていました。
定期的にインターネット接続して、ソフトウェア更新がされない脆弱性の高いパソコンのようなもので、社会の流れ(≒インターネット)に接続して、必要な能力を取捨選択していく(≒最新ソフトウェアへのアップデート)ことがなかなか起こりにくい環境であると自分なりに理解しています。
最新ソフトウェアにアップデートされていない状態が危険な状態であることを認識する機会が、そもそも少ない構造になってしまっているとも感じます。
高校の普通科にとって、まだまだ評価軸として見られやすいのは有名大学への進学率などで、世の中で真に必要とされるスキルを身につける経験をいかに提供してくれる学校なのか、という評価軸の重要性がまだまだ薄い側面もあるのでしょう。
しかし、世の中の変化の中で、価値基準が後者に置かれるタイミングは、遅くても必ず来ると確信しています。そうなると、早い段階からそういった機会を提供できる学校の魅力度が上がるので、早いうちから準備し仕込んでおいた学校が選ばれるようになってくるでしょう。
公立・私立問わず、少子化で子どもの数が減っていくに連れ、そこまで多くの学校は要らない、となってくるはずなので(大学の乱立など、現在もすでにそうなっていますが)、学校がある地域で競争力を持っていくことは、生存戦略にもかかってくると考えます。
2022年度から高校で開始された探究学習
2022年度、高校向けの学習指導実施要領が改訂され、「総合的な探究の時間」が教育課程に定められました。

「総合的な探究の時間」に改訂された
探究学習の目標として「課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身につける」「実社会や実生活と自己との関わりから問いを見出す」というような、私が社会で本質的に必要とされるスキルと述べたようなことがズバリ定められています。
そして学習指導実施要領に明記されたことの最大の意味は、「授業時数を確保することが明示されたこと」にあります。
1授業50分として、卒業までに必要な標準授業時数が示されたことで、各校で教科学習時間と調整して、探究授業の設定が実質的に求められるようになりました。
私としては、この機会を活用しない手はないと感じており、上述した「自分たちの環境がアップデートされていない状態が危険な状態であることを認識する」ための対策として、高校の時から社会と接続する機会を持たせることに尽きる」と考えます。
社会の企業活動でリアルに必要とされる能力が何なのか?自分の価値を上げていくために必要な考え方や課題解決能力、論理的思考などを身につけていくためのカリキュラムを提供できれば、かなり面白くなってくると感じています。
一方で、それを高校の現場の先生のみで企画・運営していくのは、ほぼ無理であると考えており、昨年度、そこをお手伝いする形で高校の探究授業のアドバイザー講師として、お仕事させていただいたこともあります。
実際に、探究授業の意義を頭では理解していながら、どのように企画・運営すれば良いのか戸惑っている学校も多いと聞きます。
だからこそ、高校にとってはチャンスであり、上述したような中長期で見たときの学校にとっての生き残り戦略の意味でも、うまく外部リソースを活用して企画実行し、小さく挑戦しながら企画内容を研ぎ澄ませていくことが大事です。
「教育現場と社会を接続することで、社会で必要なスキルを若いうちから身につけ、自分の生き方について、自分の頭で考え、行動する能力を身につける」
これが、私の考える探究授業の目標です。
個人的な関心からも、この分野はかなり面白いと感じているので、勝手に探究授業の企画を考えてみて、また記事にしていこうと思います!
それでは、今日もよい1日をお過ごしください。
フォローお願いします!
もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!
