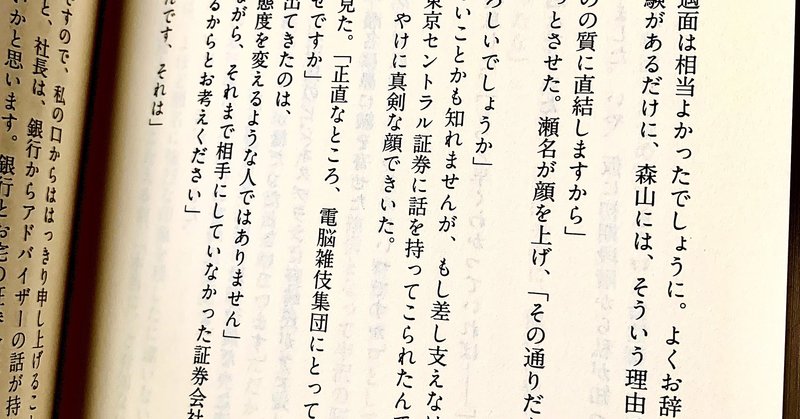
書評 #1|ロスジェネの逆襲
久しぶりにドラマ『半沢直樹』を眼にし、働く人々の共感を誘うストーリー展開に心を刺激された。「感情表現の強調」を歌舞伎の醍醐味の一つと捉えるならば、市川猿之助や尾上松也が登場する企業を舞台にした経済ドラマも歌舞伎にも似た、良質なエンターテインメントへと昇華される。第一話の余韻が残り、僕は六年前に読んだ原作『ロスジェネの逆襲』を再び手にした。この後の文中では『半沢直樹』『ロスジェネの逆襲』両作品の核心や結末が示唆されているため、気になる読者は読むのを避けてもらいたい。
この作品に限らず、著者である池井戸潤の作品に通底しているテーマは「信念の試練」である。主人公たちはマジョリティと戦う。そして、多くの苦難に行く手を遮られ、窮地に追い込まれながらも信念を貫く。最終的にはその行為自体が道を開く。現実の社会においてこうは順調に物事が運ばないまでも、それは成功を収める上での定石と言える。
『ロスジェネの逆襲』でも明暗は信念の強さにあると言っても過言ではない。「なぜ電脳雑技集団は東京セントラル証券にアドバイザリー契約を申し入れたのか」はその象徴的な問いである。消去法によって選ばれた道筋、私利私欲によって決められた選択、そのすべてが結果に直結しないとは思わない。しかし、そこには他者が共鳴するほどの熱量もなければ、物事の本質を捉えた力強さもない。本来は顧客のことを考えるべき場面で人事にばかり眼を向ける東京中央銀行の人間たちはその典型だ。作中で半沢は次のように述べる。
「銀行が政治決着しようと、我々は上っ面やご都合主義ではなく、本質を睨んだ戦略を選択したい。それこそが勝利の近道です」
後半から脚光を浴びるコペルニクスというフォックスの子会社はアマゾンをモデルにしていると想像する。言わずもがな、ビジネスの舞台は全世界的だ。この要素に注視すれば、著者は日本の封建的な企業風土にも一石を投じていると感じられる。
一方ですべての人間が半沢や森山、東京スパイラルの瀬名のように意志を示す力を持ち合わせていない。意志の有無。意志はあれど、それを表現する力や勇気。それらを持ち合わせていない人々にとって、マジョリティに迎合することは現実的な選択肢であり、成功への近道と捉えても違和感はない。伊佐山や諸田など、作中では出世欲を前面に出した登場人物たちは悪役として据えられる。しかし、先述した力を持ち合わせておらず、生活水準を維持する、家族を養っていく、社会的な格を保持することを求められた場合、否定ばかりするのも偏った視点と捉えることができる。より重要なのは、本質的な意志による議論が行われる場が増えていくことだろう。
「意志あるところに道は拓ける」
この言葉を残したのは、第十六代アメリカ合衆国大統領として歴史に名を残す、エイブラハム・リンカーンである。以前の上司から「意志を示さなければ、お前がいる意味はない」と言われた僕は、『ロスジェネの逆襲』を読み、この言葉が脳裏によみがえる。人格そのものが表現されるビジネスの場において、その奥深さを再認識させてくれる作品だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
