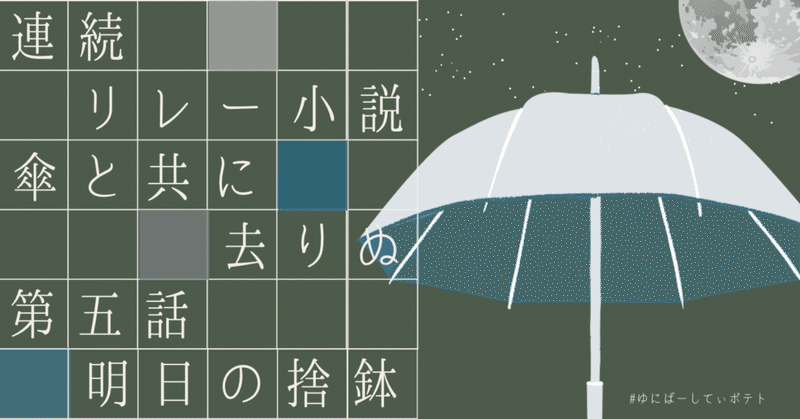
【小説】傘とともに去りぬ 第5話 明日の捨鉢【毎週20日更新!】
▼前回の第四話はこちらから
うれしさのあまり、死にたくなる。ビニール傘をやっとのことで手に入れた。ズボンの裾を濡らさないよう慎重に、川から出る。傘は、頼まれたとおりのボロさを誇っていた。早く、足を洗って稽古に戻らないと。オレは近くの公園の蛇口をひねり、泥臭い足に水をかける。その冷たさが、溜まった疲労を解きほぐしてくれているようで気持ちがいい。
爪の間に入った砂利を丹念に流していると、ほどよく汗をかいていることに気づく。一仕事終えた喜びを、オレはいつの間にか感じていた。
これはオレが夢見た、人生の形じゃない。
六月/芥見楽太郎
「なんでそういう解釈になんだよ! おつかいひとつ満足にできねぇのか、テメェわ! もう帰れ、役立たずが!」
スタジオに、監督の怒号が鳴り響く。稽古に打ち込む役者たちがなにごとかと振り返るも、「集中!」という掛け声によって、それは一瞬で他人事になった。この場にいるだれもが、人の心配してる余裕なんてない。楽太郎がまたなんかやってるよ。そんなささやきが、テレパシーのように聞こえてくる。
「いやでも、彼の生い立ちを考えると――」
「あのなぁ。オレが欲しかったのは、骨が折れてる、使えないボロボロの傘なわけ。台本読んだならわかれよ。普通に考えればわかるだろ。だいたいさ、本当に川で拾ってきたか? まさか楽しようと、その辺で拾ってきたんじゃないだろうな」
「違いますよ。言われた通り、裏通りの川で拾ってきました」
「あっそう。どこで拾ったかなんてどうでもいんだよ。頼むから、余計なことでオレをイラつかせないでくれ」
そう言って、監督は背を向ける。川で拾うことにこだわったのはほかの誰でもない、監督のはずだった。充実であればリアリティが増すと、雄弁に語る姿を今でもよく覚えている。今回やる舞台は、この地域で古くから語り継がれた伝承、”夢食い”をベースにしたものだった。
監督は近くにいた下っ端の役者を捕まえ、なにやら話を始めた。突如として、頭の中で鳴り響く警報。ヤバイ。このままだと、監督からもらった仕事が、アイツに渡ってしまう。手にしたビニール傘を強く握りしめながら、オレは自らを奮い立たせる。
「あのっ、監督のイメージを教えてくれませんか?」
監督はゆっくりと、頭だけをこちらに向けた。刺すような視線。イラつかせている自覚はあっても、剥き出しの感情を前に、どうしても足がすくむ。
「オマエさ、役者向いてないよ」
「あの、もう一度、チャンスを――」
すると突然、背後から肩を掴まれた。その手は、監督を追いかけようとするオレの意思を阻んだ。慌てて振り振り返ると、同期の朝井が小さな声でささやく。やめとけよ。ため息を多く含んだ、地を這うような声だった。動揺のあまり、身動きが取れなくなってしまう。
「監督、このシーンなんだけど」
さっきの一言が幻聴かと思えるくらい、朝井は朗らかに話しかける。
まるでこの場にいないみたいに扱われ、どうすることもできなかった。すみませんでした、という言葉ですら、筋違いと言わんばかりの空気。やるせなさを握った拳を、音もなく下ろす。
朝井の背中が大きい。
かたや看板役者、かたや役者兼美術スタッフお手伝い。同じタイミングに入団して、夢を語り合っていたはずが、いつからか圧倒的な差が生まれてしまった。アイツは顔が良いから、監督に気に入られている。朝井はもう、オレのことをあだ名で呼ばない。オレも人前では、朝井さん、って呼んでいる。
手に残っている、役割をなくした傘を見つめる。
監督の解釈とどう違ったのか、まだよくわかっていない。持つ位置を高くすると、柄の部分についた星形のチャームが揺れた。所有者がいたことを必死に訴えているみたいだ。その背景を想像して、なんだか切ない気持ちになる。
今日一日、舞台美術の手伝いをしながら、オレは傘の持ち主について考えていた。
アクリルのチャームは一見、女性らしいアイテムだが、傘のサイズからして持ち主は男性。身長は175センチオーバー。この小物選びの柔軟さは、おそらくは学生。大学生と言ったところか。もし彼に男兄弟がいるなら、からかわれるか、バカにされるかするはずだ。女兄弟なら、彼ではなく、兄弟に持ち主が移る可能性が高いから、ひとりっ子なんじゃないだろうか。恋人とおそろいという線もあるが、それにしてはかわいさが足りてない。なんにせよ、ビニール傘なんて使い捨てアイテムでも大事にできるその人に、会ってみたくなった。
◇
公演初日が迫っているせいで、仕事は夜遅くまで続いた。スマホの時計は、若い数字を示している。終電はとうに過ぎているから、歩いて帰るしかない。夜は、歩いているだけで開放的な気分になれる。狭まっていた意識が解れて、空腹具合が気になりだした。
「おい楽、ラーメン食いに行こうぜ!」
最寄りのコンビニに向かっていると、突然、首に腕を回された。かはっ、と声が漏れ出る。打ち上げ花火のようなエネルギッシュな声。つなぎの袖から、絵の具の匂いがした。瑞希は、頬に色を付けたまま、疲れを感じさせないにこやかさで笑う。
「びっくりした、殺されるかと思ったわ!」
「あっ、ちょっと待って、今からでも入れる保険があるはず」
「動機があからさますぎるだろ。つーか、オレの保険金なんて知れてるわ。もっとほかのやつ殺せ」
「ならオマエの奥さんを」
「いねぇし。いたとしてもやめろ」
「だれかをやらないと、次はオレの番なんだよ!」
「デスゲームにでも参加させられてんの? どうした、話聞こうか?」
「いやそんな、恋愛相談みたいなノリで来られましても」
「やめろ、急に冷めんな」
彼の小気味好い笑いに、重く圧しかかっていた疲労も軽くなる。おそらくオレたちは、この時間、世界でもっとも純粋な笑いを生み出していた。即興劇のような掛け合いも、いつものこと。彼の明るさにほだされて、つい全力で合わせにいってしまう。
瑞希はオレと違って、美術スタッフを志望して働いている。二年先輩だが、歳はひとつしか変わらない。役がもらえない時は、よく手伝いにいかされ、なんとなくお互いに顔を覚え、いつしか普通に話すようになっていた。瑞希は生粋の演劇オタクで、彼はいつも、架空のだれかを真似ているような、芝居がかったしゃべりかたをする。もし本気で舞台の道に進んでいたら、良い役者になっていたかもしれないなと、悔しいが思ってしまう。
行き先は駅前のチェーン店か、外観は汚いけどうまい店か。そんな究極の二択にあぁだこぉだ言いながら、オレたちは導かれるように後者を選んだ。
入口近くの券売機でチケットを買い、店員に渡すと、店の奥まで続く朱色の長テーブルに並んで座る。塩コショウやラー油を決まったポジションに並べたがる瑞希を横目に、オレはビニール傘の置く場所を探していた。
「そういやなんで傘なんて持ってんの? 雨降るっけ?」
「拾ったんだ。つーかさ、聞いてくれよ」
だらだらと愚痴を吐いていると、しばらくして店主のおじちゃんが、「はぁ、おろり」と言いながら、ラーメンが入った器を置く。たぶん、『はい、お待ち』と言っているんだろうけど、一度として正確に聞き取れたことはなかった。大量の背油が浮く豚骨ラーメンが目の前に現れ、口の中のよだれが騒ぐ。この背徳感がたまらない。どちらかが決めたわけではないが、オレたちはラーメンを目の前にする時だけ、言葉を交わさないことにしていた。最後の一滴まできれいに平らげる。
タバコは悪魔が持ってきたなんて言うが、だとしたら、ラーメンは神様からのご褒美だ。監督に怒られたことさえ、危うく忘れてしまいそうになる。
オレよりもすこし早く食べ終えた瑞希が、どんぶりの上に箸を置いた。なにか言いたそうな視線を感じ、どうかした? と尋ねる。眉をきりっと上げ、いつもの芝居がかった顔を作る。舞台は、薄暗い雰囲気のバーといったところか。
「楽、相談があるんだけど」
「なんだよ。急に改まって」
「これはかなり深刻な問題で、オレも話すべきなのか正直迷ってるんだ。オマエに迷惑をかけちまうかもしれねぇ」
「いいから話せよ。まどろっこしいな」
「替え玉が食べたいんだけど、金がないんだ。見ろよ。財布の中、五円玉パーリーだぜ」
財布の中身を見せる瑞希がおかしくて、つい吹き出してしまう。飲み込むはずだった麺が変なところに入った。慌てて箱ティッシュに手を伸ばす。
「嘘、嘘。替え玉ほしいけど、そうじゃなくて――」
瑞希はオレの背中を摩りながら、落ち着くのを待ってから続けた。
「じつはさ、先輩に別の劇団に誘われてんだよ」
言葉の意味は理解できた。ただ、どことなく感想を委ねるような言い回しに、なんて返したらいいのか迷ってしまう。良かったじゃん、なのか。寂しくなるな、なのか。それとも、なんだよ突然に、なのか。そのどれもがしっくりこなくて、ふと、このアドリブへの対応力がオレのダメなところなんだろうな、と別のことを考えはじめる。そもそも、その誘いが瑞希にとって、良いものなのか悪いものなのかもわからない。
箸を置く。なるべくフラットに、無感情に聞こえるように気をつけながら、尋ねる。
「行くの?」
「オレ、楽と一緒に行きてぇよ」
「行くって、どこに」
瑞希が答えた劇団は、役者を志す者ならだれもが知っているような、有名なところだった。もちろんオレも知っている。いや、知り過ぎていると言ってもよかった。
「なぁ、ここにいてもしょうがないだろ。顔で配役決めてるような営業劇団じゃ、いつまでたってもチャンスは回ってこねぇよ。楽だって、本当は大工仕事じゃなくて、芝居をしたいだろ。一緒にさ、そこ受けにいかないか?」
視線をラーメンに逃がす。すぐに返事ができなかった。瑞希が言う先輩にも心当たりがある。彼が劇団を抜けるという噂は、オレの耳にも届いていた。それくらい、今いる劇団にとって重要人物だ。
その先輩に誘われたら、行くしかない。瑞希の気持ちになれば、考えなくてもわかる。オレと一緒がいいと言ってくれることはもちろん嬉しかった。友人として、これ以上の喜びはない。だけど、オレは首を縦に振ることができなかった。
「ちょっと、考えさせてくれ」
オレの心を読むかのように、瑞希が言う。
「楽なら即答するかと思ってた。なんだよ、未練でもあるのか?」
「そうじゃない。誘ってくれたのはうれしいけど、今すぐに決めれない。すまん」
「わかった。じゃあ、今週の金曜まで待つよ」
そう言って、瑞希はテーブルに並んだ調味料を片づけはじめた。ほんのすこし、器の底に麺が残っていたが、かき集めて食べる気にはなれない。水を一気に飲み干すと、立ち上がり、傘を手繰り寄せる。あんなに濃かったラーメンの味も、思い出せなくなっていた。
なんとなく気まずくなり、「オレ、コンビニ寄ってから帰るわ」と嘘をつく。ひとりになりきりにたかった。どうしたら瑞希と鉢合わせないかを考えながら、ぐるぐると遠回りをする。辺りは静けさに包まれていた。公園の近くを歩くと、がさがさと物音がする。影に紛れた黒猫が一匹、様子をうかがっていた。なんとなく嫌な感じがして、速足で通り過ぎる。知っている場所のはずなのに、時間帯が違うだけで、町はオレに冷たく当たった。
瑞希がこれから行く劇団の名前をオレはよく知っている。
まだ夢を追うことに無垢でいられたころ、入団オーディションを受けたことがあった。中学、高校、大学の時期に、各一回ずつ。結果はすべて不合格。悔しかった。次こそはと思って、寝る間も惜しんで勉強した。一本の映画を一秒ずつ細かく観察したり、監督や役者のインタビュー記事を読み漁ったり、自分の演技を録画して研究したり。
親は、役者を目指していることに反対などしなかった。そもそも興味がないのだ。勉強も運動も、コミュニケーション面ですらパッとしなかったオレは、かわいがるには出来の悪い息子だったのかもしれない。
大学生になって入った劇団研究会は、芝居を趣味程度にしか考えていないメンツばかりで、居心地が悪かった。あきらかに浮いていたと思う。演技の話よりも、俳優の顔やドラマの視聴率ばかりに盛り上がる。そんな奴らを、オレは静かに見下していた。
いつかあの劇団に入って、実力をつけて、人の記憶に残る芝居をしたい。
ただ、肝心のオーディションは通らなかった。大学を出てからも受けたが、結果は変わらなかった。このまま舞台に立てないまま終わるのはもっと嫌だった。アルバイトをするかたわら、SNSで都内の劇団を探し回る。手当たり次第に受け、ようやく手にした居場所が今の劇団だった。
それが今じゃどうだ。どこにいたって、オレは芝居をさせてもらえない。
もう五年が経つ。オレはあれから、なにかひとつでも学べただろうか。成長できただろうか。
どうやらオレには芝居の才能がないらしい。
ずっとそのことに気づかないふりをして生きてきた。舞台美術の手伝いを買って出て、あたかも必要とされているみたいに振る舞っていた。瑞希の誘いがなければ、オレはたぶんこのまま、将来について深く考えることもせず、のうのうと過ごしてきただろう。
ようやく、夢を諦める決意がついた。
胸の奥が、じりじりと痛い。これまでもずっと、痛みはあるはずだったのに、その正体がわかった瞬間、楽になれたような気がする。オレは皓々と佇む、丸い月を見た。腹に力を据え、肺を夜の空気で満たし、一気に吐き出す。力が抜けていくのがわかる。これでいいんだと、今なら納得できそうだ。
白く照らされた道路をぼんやりと眺めながら、アパートへの帰路に入る。周りに音がないことを良いことに、オレは道路の道をふらふらと歩いた。辞めるタイミングをいつにしようか。あわよくば、監督の悪口でも言ってやろうか。そんなことと企てながら、上機嫌になる。
前から、足音がした。
それは靴音ではなく、ぞっ、ぞっ、と重たいものを引きずるような音だった。
顔を上げると、黒い影のような塊が道路の真ん中で立ち、不気味にオレを見ていた。いや、見ているのかどうかはわからない。塊には目がなかった。手と足と顔の輪郭がある。なで肩で、手足は短い。目を凝らすと、それは動物のバクの形に似ているような気もする。
「芳しい、自棄の香り。汝に宿いし落ちた心、我に食はせよ」
頭に直接語りかけているみたいに、不思議とはっきり聞こえてくる。排水溝の奥から込み上げてくるような低い声。影の塊は、街灯の光を受けても白む様子がない。右腕らしき部分を上げ、ゆったりと近づいてくる。
「食には対価が要。我の作法なり。汝の望みを言え。叶えてやらぬこともない」
酒は飲んでないから、酔ってるわけじゃない。働きすぎて幻覚を見てるのか? それか手の込んだドッキリ? 自棄の香り? 望みを言え? 意味がわからない。
関わらないほうが良さそうだ。オレは黙って踵を返すが、その先にも、同じ影の塊が、沈黙を浮かべながら佇んでいた。背後を振り返っても、そこは平凡な夜しかない。影はひとつだけ。じりじりと距離を詰めてくる。
逃げるしかない。そう思ったが、足が言うことをきかなかった。つまずくところなんてないのに、後退りしたオレは尻餅をついてしまう。
「望みを言え」
死ぬかもしれないと、本能が警鐘を鳴らす。オレは咄嗟にビニール傘を振り回した。やっとのことで、「来るな!」と声が出る。すると、傘の先がどこかに当たった。芋虫をつつくようなそれに似ていて、悪寒が走る。同時に、こんなわけのわからない状況で、なんでオレひとり死ななきゃいけないんだと腹が立った。
芝居を辞める、そう決意したばかりなのに、なんでコイツは、弱みにつけこむような真似ができる。オレをおちょくっているのか? どうせ、こいつ、人の足元見て、笑いたいんだろう。もし役者になりたいなんて願ったところで、なれるわけがない。バカにするな。オレのことも、芝居のことも、バカにすんな。
体中が熱い。オレは傘を両手で握り締め、影の首目掛けて勢いよく振りかぶった。直接触れていなくても、破れそうな肉の感覚が伝わってくる。ぶちぶち、ぶち。その音に、鳥肌が立つ。皮膚らしきものがひも状に伸び、地面に向かって、頭と首を繋ぎとめる。仰け反ったまま、影の塊は動きを止めた。切り裂いた断面が、うじが沸くみたいに脈打つ。
まだ、生きてる。
影は垂れ下がる頭を持ち上げ、首にくっつけた。そのまま、何事もなかったかのように歩き出す。足がすくんで動けそうない。
「くんなよ。あっち行けって」
声を張り上げるだけで精一杯だった。傘を構えたまま、逃げるチャンスをうかがう。決意を固め、足に力を込めたその時、影が傘の先を掴んだ。振り払おうとしても、力で負ける。オレは傘を手放し、全力で走った。酸素が、足りない。後ろを振り返る勇気もなく、歯を食いしばりながら、がむしゃらに走る。腕を無理やり振った。転びそうになりながら、ひとけの多そうな場所を目指した。
住宅地の角を曲がる。カーブミラーにはなにも写ってない。そのはずなのに、曲がりきると、目の前には影の塊が、悠然とこちらを見ていた。
足がこわばっている。力が抜けて、その場でへたり込む。
「最後だ。望みを言え」
夜の果てみたいに重たい声だった。影の背後には嫌になるほど丸い月があった。そのあまりの美しさに涙が出る。オレは、こんな人生のために、今までもがいてきたのか。
「だったら――」
恐怖心を払い除けようと、腹に力を入れる。
もうすべて、どうでもよかった。
「この世界から、演劇を消してくれ……」
影の動きが、ぴたりと止まった。
表情はあいかわらずわからないが、笑っているように思えた。
「すばらしい。これぞ至高の自棄。汝の願い、叶えてやろうぞ」
その声を最後に、オレの意識は途絶えた。
◆
「おい、起きろ。おいってば」
声がして、目を開ける。気がつくと朝だった。体中から腐敗臭がして飛び上がる。どうやらオレは、燃えるごみの袋を背に、眠っていたようだった。昨日の夜、酒でも飲んだのだろうか。思い出そうとしても、霧がかかったかのように思い出せない。手にはなぜかビニール傘があった。持ち手の部分には、星型のチャームがついている。
「なんだってんだ、一体」
ズボンについた生ごみを手で払い落す。口の中がやけに脂っこく、吐き気がした。そういえば、ひとりでラーメンを食べに行った気もする。
「なぁ、アンタ」
顔を上げると、若い男がいた。大学生だろうか。髪は短く、利発そうな顔をしている。背も高く、なぜだかわからないが、いいなぁ、という思いが込み上げてくる。さっきから、感情の出所がわからず、なんだか歯がゆい。
「起こしてくれたのか。ありがとう。」
体中が臭かった。早く家に帰って、シャワーでも浴びたい。立ち去ろうとすると、若い男がオレの腕を掴んだ。「なんで……」となにやら深刻な色を浮かべ、彼はつぶやく。
「アンタ、その傘、どこで拾った?」
(つづく)
第5話担当 飛由ユウヒ
次回の更新は7月20日です!
「記事を保存」を押していただくと、より続きが楽しめます!
ぜひよろしくお願いします!
6話はこちら▼
過去のリレー小説
▼2022年「そして誰もいなくならなかった」
▼2021年「すべてがIMOになる」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
