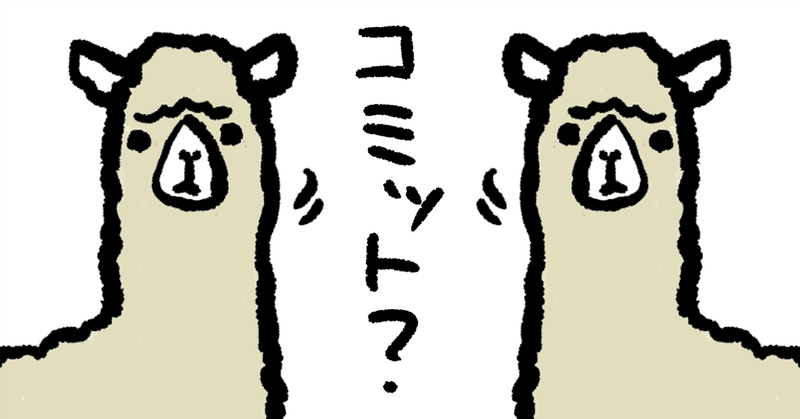
【論文】中小企業従業員における組織コミットメントの規定要因-組織コミットメントを高めるコツには経営者との接触頻度にあった!?-
組織コミットメント、という言葉を聞いたことはありますか?
ざっくり説明すると、組織と従業員の関わり合いに関して、メンバーがそこに居続ける、あるいはそこを去ることに影響する心理的な状態を捉えた概念のことを指します。
この論文は、大企業に比べて従業員離職率が明らかに高いと言われる中小企業の現状を背景に、中小企業で実際に働く従業員がいかにして組織に定着しているのかを、組織コ ミットメントの概念を用いた独自の調査結果に基づいて議論を深めています。
中小企業の人事の方や、上司の方、従業員の離職に頭を悩ませている方は何かのヒントになるかもしれません。こちらは論文のため、分析方法まで細かく明記していますが興味がない方は分析方法は読み飛ばしてください!
【論文名】
中小企業従業員における組織コミットメントの規定要因─経営者との一体感を醸成するには─/鈴木泰詩・浦坂純子
組織コミットメントとは?
定義として広く受け入れられてきたのが、Mowday,Strees,and Porter(1979)の定義といわれています。
「組織の価値や目標の共有、組織に残りたいという願望、組織の代表として努力したいという意欲などによって特徴づけられる、組織への情緒的な愛着」
また、組織コミットメントの構成要素として、マイヤーとアレンは以下の3つをあげています。
情緒的コミットメント:組織あるいは組織内のメンバーに対する感情的な愛着、組織に対する同一化、一体感
規範的コミットメント:組織に居続けることへの義務感、忠誠心、恩義
継続的コミットメント:組織を去ることによって失うデメリット、組織に居続けることのメリット、代替的な選択肢の欠如
マイヤーとアレンによれば、情緒的コミットメントは、メンバーが是非とも居続けたいと思うこと、規範的コミットメントはそうすべきと思うこと、継続的コミットメントはそうする必要があると思うことにそれぞれ関わっているといいます。
検証仮説
この論文では、検証仮説を「中小企業従業員の組織コミットメントの強弱を規定する要因は企業経営者との距離感にある」としています。
※ここで述べる距離感とは経営者と交わされる業務上のやり取りの頻度や、就業時間外におけるプライベートでの接触回数、あるいは会社のことや従業員自らのことについて経営者と語らう場など中小企業ゆえに生まれる経営者との接触頻度などを示す。
調査方法
企業規模を500名未満に限定した上で組織コミットメントの規定要因を探っている。
対象者:京都府と滋賀県に本社を持つ,従業員数 10~500 名までの企業(24 社)に勤める男女
期間:2011 年 8 月 8 日から 9 月 16 日
方法:調査票を直接配布、郵送回収による自記入式調査票調査
回収状況:780 サンプル中 504 サンプル。有効回答数 504 サンプル(回収率 64.6%)
分析方法
従属変数
推定の中心となる従属変数Ⅰは、情緒的コミットメント、規範的コミットメント、功利的コミットメント、及びこれら3つのコミットメントを包括する組織コミットメントに関する変数である。さらに組織コミットメントを独立変数Ⅱとした場合の従属変数Ⅱについては、定着意識に関する変数で構成する。
独立変数
独立変数については、5 つのカテゴリーで構成されている。A は調査対象者の年齢や性別などからなる従業員基本属性、B は従業員のキャリア志向性、C は経営者と従業員の日常業務共有、D は経営者と従業員のプライベート共有、E は経営者と従業員のキャリアビジョン共有である。
二項ロジスティック回帰分析
独立変数Ⅰが、従属変数Ⅰの組織コミットメントにどのような影響を及ぼすのかを、最小二乗法による線形回帰分析を適用して確認。従属変数Ⅱの定着意識に関しては、Aの従業員基本属性の全変数をコントロールした上で、独立変数に組織コミットメントのみを用いて二項ロジスティック回帰分析を適用する。

分析結果
分析結果は、以下のことがわかりました。
・中小企業において、従業員を組織にコミットさせるために必要な要因としては、日常業務における業務指示が経営者から直接的に一定の頻度で行われていること(日常業務共有接点)、従業員とプライベートでの接点を経営者が一定の頻度で持つこと(プライベート共有接点)、従業員の将来をしっかりと共有し理解する時間を設けること(キャリアビジョン共有接点)が明らかとなった。
・日常業務における経営者とのやり取りが「2 週間に1回以上」存在する従業員は、それ未満の接触頻度しか持たない従業員よりも、情緒的コミットメントが有意に強化されることが明らかになった。
・プライベートにおける経営者との接触頻度についても、「半年に 1 回以上」の頻度で経営者と何らかのプライベート接点を持つ従業員は、それ未満の接点しか持たない従業員より、情緒的コミットメントが強化されるということが 10% の有意水準ではあるが示された。
・従業員が経営者に対して自ら会社の中で取り組みたいこと、つまりキャリアビジョンを共有する頻度が「1 カ月に1 回以上」確保されていれば、それ未満の頻度でしか経営者と自らの将来について語ることができない従業員よりも、情緒的コミットメントが有意に強化されることが確認された。
その他にも、情緒的コミットメントを強化する要因として、経営者との接触頻度のみならず、職位に関係なく 機能するリレーションシップの重要性が新たに示唆されたこともわかったそうです。
経営者のスタンスを踏襲した上司や先輩に従業員が指導されることによって、間接的に情緒的コミットメントを強化し得るということを指します。
上司や先輩が従業員に下す指示内容、あるいはその背景に存在するスタンスを中心に、経営者とその周囲の管理職層との一貫性が組織の中でどれだけ担保されているのかが組織コミットメントを強化する重要な要因になり得るということもわかっています。
いかがだったでしょうか。経営者と従業員がコミュニケーションをできる限り取った方が良いことはなんとなく想像つきますが、経営者以外の上司や従業員も、経営者が持っているスタンスや一貫性を担保できるかどうかも、従業員の組織コミットメントに大きく影響することは、面白い発見でした。
考察や課題などはここでは割愛していますので、より詳細を知りたい方はぜひ論文を読んでみてください◎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
