
コーチングを受ける全ての方へ|変わるための脳の取り扱い方法
コーチングを受ける方がはじめに理解しておくべきこと

コーチングを受けていただく前に、コーチング用語と、マインドのカラクリについての知識をインプットし、理解を深めて頂くための記事です。マインドのカラクリを理解することによって、クライアントが自らの才能で、主体的に人生を生きていくことを共に目指します。
そのため、言葉をそのまま素直に受け取ってください。素直に受け取るとは、自分なりの解釈(過去の知識)を、そこに入れない、挟まないということです。
新しい理論を受け取るときに、過去の理論は邪魔になります。過去の成功体験が最大の盲点を生み出すからです。
また、わからないことは、かならず聞いてください。
世界はフォーカシング・イリュージョン(焦点錯覚)に満ちています。

全体を通してご覧になり、大まかな全体の概念理解(ゲシュタルト)を掴んでください。それが何においても大切になります。
コーチング用語を説明します

入力と出力の間にある、「内部モデル(人の心のようなものです)」に変更を促して、行動変容を促す。これが、コーチングのとても簡単な説明です。
ゴール設定の条件について

クリエイティビティを最大化するには、現状の外側(今の自分の脳では予想できなかった事象)のゴール設定が絶対条件です。
ゴール設定には、ゴール達成を含みません。なぜなら、ゴール達成を含んでいる時点で、それは現状の延長線上だからです。
ゴール設定には3つの条件(原則)があり、1つずつ説明します。
条件1|現状の外側のゴール設定であること

現状の外のゴールとは、どのようなものを言うのでしょうか。
自分の居心地のいい場所の外側である
想像すると怖くなりドキドキを伴う
達成手段・方法の想像がわからない
周囲の人たちが驚き、止めてくることがある
以上のようなことが想像されます。
現在の状態のままいけば、十分起こりうると予測されるゴール。無理すれば、頑張れば、なんとか達成できそうなゴールは、全て現状の延長線上であり、それを「理想の現状」と定義します。
ゴールがありありと、イメージできるというのも、現状の外側ではありません。現状の外のゴールは、社会的に置かれた状況によって変わります。
例えば、一度も社会で働いたことのない学生にとっては、社会に出てはじめて仕事をする、というだけでも現状の外側になり得ます。
しかし、会社でマーケティングの仕事をしていて、独立してフリーランスになり、マーケティングの仕事をするのは、現状の外側のゴールでもなんでもありません。
現状の延長(理想の現状)です。
また、ゴールは見つけるものではなく、設定し、「つくるもの」です。
設定した瞬間に、ワクワクしながらも、心がざわざわし、恐れを感じるものなのです。なぜなら、達成の方法がわからないのですから。私たちはわからないものに対して、恐れを抱きます。
これを認知不協和(にんちふきょうわ)と言います。
認知不協和が起こることが、現状の外側のゴール設定である証拠です。
条件2| want to であること。have to ではない。

want to(内的好因子が行動起因)と、have to(外的嫌因子が行動起因)についてです。
want to とは、すきなこと、日常的にやりたいことのなかに隠れたりしていますし、時には、自分が権威だと思っている人に逆らってでもやっちゃうことでもあります。
褒められたいからやったとか、他人や環境からの外圧を受けいれたものは、want to ではありません。
特にティーンエイジャーまでを振り返り、幼少期から、今現在まででの中でwant to を思い出してみてください。
その中で人生通底しているwant toが、あなたの根幹をなす「最高価値」です。
※ゴールが want to に結びつくのは、本音のゴールである必要があるからです。want toに結びつかないとしたら、それは単なる妄想(あこがれ)である可能性が高いです。
条件3|日常で入ってくる情報が変わる

ゴール設定をして、コンフォートゾーン(自分が居心地のいい場所)をゴール側に動かすと、今まで見えていなかった情報が、目に入るようになります。
これまでに目に入らなかった情報が入るために大切なことは、ゴールに対して臨場感を持つことです。
臨場感は「自分ごと」でないと持てませんから、本音のゴールである必要があります。
現状の外側のゴールへの道筋は、臨場感を持つことで、これまで入ってこなかった情報が入るようになり見えてきます。これが、クリエイティビティー(創造性)のカラクリです。
条件4|没頭・没入してしまう

want toでは、ご飯を食べるのも忘れて、寝るのも惜しんでやってしまう、
すごい集中力を発揮してしまう、ということがあります。
want toをやっている時は、無意識に、自分の臨場感世界に没入していますよね。これが、集中力のカラクリです。
集中力の深さ = 臨場感世界の没入度
なので、have toだと集中力を発揮できないのは、お分かりになるかと思います。
条件5|複数のゴールを持つ

オールライフ(人生全体)で考え、ゴール設定をしていきます。
オールライフで考える理由は、仕事だけのゴールを設定していると、
仕事ばかりをやり過ぎた時に、健康を害したり、家族関係が崩壊してしまうなどが考えられるからです。
結果的に、仕事のゴール達成の妨げになってしまうことがよくあります。ですから、オールライフでゴールを設定します。
オールライフのゴールを、それぞれでバランスよく持つことで、それぞれのゴールを全体を包括したゴールを、無意識が勝手に整合性をとります。
意識的ではなく、無意識がというところがポイントです。人間の脳の無意識の特性として、見たものに近づこうとする傾向があります。
これを、テレオロジカル(目的的志向)と言います。
条件6|ゴールに対する臨場感を持つ

使う言葉やイメージをどうやって持つかが大切です。
使う言葉を変えることは理解しやすいと思います。イメージをどうやって持つかの部分については、VAKを使うといいです。
V:Visual(視覚)
A:Auditory(聴覚)
K:Kinesthetic(体感覚)
沢山のゴールを持つと、たくさんのことに気がいって、集中できないんじゃないかと言う方がいます。
それは全く関係ありません。
それどころか、本音のゴールであれば、多くて構いません。
意識下でのゴールは、ひとつしか取れませんが、無意識下では複数を同時並行処理することができます。
無意識は勝手にゴールの整合性を取り、1つ抽象度の高いゴールを導き出してくれます。
ここで注意したいことは、計画に落とし込むことです。
そうすると、現状の中で判断を下し、それがやらなければならないこと(=have to)になってしまいます。
セルフエフィカシーについて

ゴール達成能力に対する自己評価を自己効力感といいます。
コーチの機能は、クライアントのエフィカシーを上げる役割である、と言えます。
なぜなら、エフィカシーは、ゴール達成のために最も必要なものだからです。
エフィカシーを簡単に言うと、手段や方法は明確でなくても、わからなくとも、「自分ならそのゴールを達成できる気がする」という謎の自信のことです。
誤解してほしくないのは、、過去にこんなことをやってきたから、私にはできそうな気がするという頭の中で計算できるから自信がある。のではないということです。
過去のからくる自信は、セルフエスティーム(自尊心感情)と言います。
セルフエスティームは、現在の「ポジションに対する自己評価」です。
現在のポジションがどうであれ、ゴールには関係ありません。
エフィカシーは、未来のゴールを達成できる能力があるかどうかを、「自分が評価する」ということです。
誰の意見も関係なく、自分がそう思い込んでいるということです。
皆さんも経験があると思います。なぜか、わたしだけはできるような気がするんだよな、という経験が。
コンフォートゾーンについて

パフォーマンスの限界を決めるものはなんでしょう。
私たちの体は、慣れ親しんだものを維持しようしたり、一定の安定した状態を維持する機能を持っています。それをコンフォートゾーンと言います。
生理学的には、ホメオスタシス(=生体恒常性維持機能)と言います。これは、誰にでも備わっている機能です。
コンフォートゾーンを離れると、ホメオスタシスのフィードバックがかかります。(フィードバック:現状に引き戻そうとする力)
ホメオスタシスのフィードバックについて、体温を例にして説明します。
夏でも冬でも気温の変化があっても、私たちの体温は、約 36〜37 度に維持されています。
約 36〜37 度という幅を持っており、コンフォートゾーンはゾーンなので、バッファ(遊び代)があります。
どんな環境に身を置いても、寒くても、暑くても、常にその範囲内を維持しようと、ホメオスタシスのフィードバックが働きますので、私たちの体温は、約 36〜37 度に維持されています。
体温が30度になったり、45度になったりはせず、約 36〜37 度を保持しようとする力、これがホメオスタシスのフィードバックです。
コンフォートゾーンは、自分にとって重要度の高いもの、高く評価するものだけが集まった空間です。
だから居心地がいい。
サッカーなどのスポーツチームが、ホームゲームだと勝率がいいのは、
コンフォートゾーンの中で、試合ができるからです。
パフォーマンスの限界を決めるのは、コンフォートゾーンの中にいるかどうか、なのです。
また、体温を36度と37度と、同時に2つ持てないことと同じように、コンフォートゾーン(ホメオスタシス)も、1つしか持てません。
現状の外側にゴール設定した場合、コンフォートゾーンが、現状とゴール側に2つできます。
ではどうすれば、ゴール側のコンフォートゾーンを選択することができるのでしょうか。
普通に考えれば、これまでの心地よい環境、現状へのフィードバック(ホメオスタシスのフィードバック)が、かかりそうですよね。
その答えは、決断です。
断つことを決めるということです。
決めて断つだけだと、スピリチュアルに聞こえるかもしれませんが、これが、認知科学的にも正しいと証明されています。
ゴール側がコンフォートゾーンになると、現状から、ゴールへ向かって、ホメオスタシスのフィードバックが働きます。
モチベーションの構造
このコンフォートゾーンに戻ろうとする力が、「モチベーション」です。
つまり、モチベーションは結果でしかありません。
ここで、一つ注意して欲しいことがあります。
理性(計算的思考)でゴールまでのプロセスを、導きださないということ、です。
理性で考えると、現状の中での答え合わせとなり、現状に引き戻されます。ゴールまでの道のりは無意識に任せてください。
ゴールまでの道筋が見える脳の構造

ここで大切な内容が、RASとスコトーマの関係です。
RAS について解説します。

RASとは、脳幹網様体不活系(のうかんもうようたいふかつけい)のことです。
RAS は脳幹にあり、農耕革命によって、人間が安定した睡眠を獲得できたことで発達しました。
狩猟採集⺠族の時は、いつ襲われるかわからない状況なので、安定した睡眠時間を取ることが、できなかったことで、RASは未発達でした。
農耕革命後、前頭前野が発達し、脳の大きさは大きくなったけれど、首から下は進化がみられず、脳の消費エネルギーを作ることが間に合わなくなります。
そこで、さらに睡眠で調節するという機能が発達しました。
そこで機能したのがRAS です。
RAS は、睡眠と覚醒のコントロールをしています。
生命維持のために、どこまでを覚醒させ、どこまでを睡眠にもっていくのかを判断し、切り替える機能があります。
ここまで一見、コーチングと関係ないようなお話をしてきたのですが、
「この睡眠に関わる RAS の機能が、脳の情報処理にまで、広がっているからです。」
日常で入ってくる情報全てを処理していては、脳はパンクしてしまいます。
RAS は生命維持のために、「今の私」にとって、「重要な情報」と「重要でない情報」を、判断しています。
RAS によって、「重要でない情報」がスコトーマ(心理的盲点)になります。
RAS は、自分にとって重要性の高い情報だけを入れ、自分にとって重要でない情報は、入れないというシステムです。
入れないということは、意識に上がってこない、認識できないということです。
全身麻酔で意識を失っている時には、RASの機能が落ちています。つまり、意識のカラクリはRASにあるのです。
入ってくる情報は自分で変えられます。
それを決めるのが、あなたの「ゴール設定」です。ゴール設定により、あなたの重要性が変わるからです。
RAS とスコトーマの例をあげてみましょう。

大勢の賑やかな場所にいても、好きな人の声は小さくても聞こえます。これも 、RAS とスコトーマによるものです。
自分に必要な情報だけを集めています。
赤ちゃんが産まれたら、街に赤ちゃんがこんなに居たんだと
気づきます。これも同様です。
欲しい車があると、街でその車に出会うことが多くなります。
今のあなたは、どこに RAS が発火しているのでしょうか?
もし現状なのであれば、
「現状を維持する」ことがゴール設定ですから、現状を強化する方向に RASで情報を収集し、その他の領域はスコトーマになっています。
新しい扉を開けるためには、現状の外にゴールを設定することです。
自分一人で、現状の外にゴールを設定するのは、非常に難しいのが、ご理解いただけたのではないかと思います。
そこを、サポートしていくために、私たちコーチが存在しているというわけです。
セルフトークについて
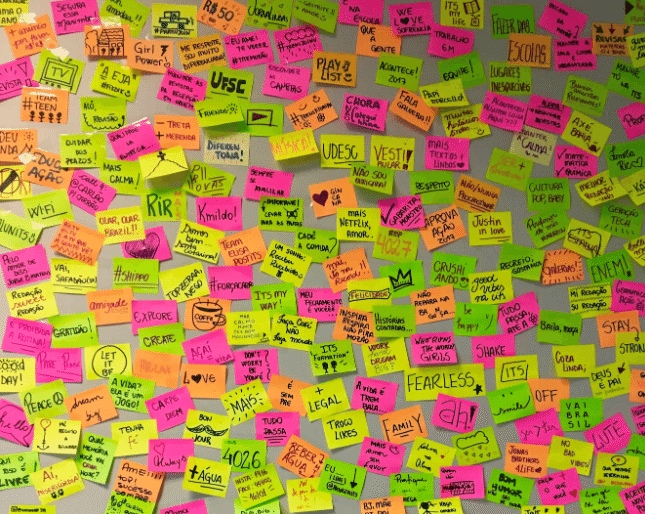
私たちは、意識していないものも含めて、1日数万回セルフトークをしています。(発語せずに、頭に浮かんだ言葉を含みます)
自分に語りかける言葉によって、映像が浮かび、情動が動いて、感情が誘発され、その感情の力によって、セルフイメージを形成します。
情動記憶は、言語により反復されます。
そのセルフイメージが、ビリーフシステム(=内部モデル)を作り上げます。
このビリーフシステムは、記憶のデータベースであり、マインドの最高価値と最低価値を含む、意思決定を選択させています。
ビリーフシステムの大きな集合の中に、コンフォートゾーンの部分集合があると認識してください。

人間の進化の系譜(生存戦略)により、失敗を基軸とした優先順位の体系となっているので、失敗の方が覚えています。
コンフォートゾーンを、ゴール側に置くためにも、セルフトークをコントロールして、ゴール側の臨場感を高めることが大切です。
私たちは現実を、臨場感で認識していますので、コンフォートゾーンは、臨場感がある方を選択します。(目的的志向=テレオロジカルにより)
情報は物理を包摂します。

なので、無自覚に言ってしまう、ネガティブセルフトークを、取り除いていきましょう。
ゴール設定した未来の自分から、ゴール世界の自分ならどんなことをしているのか、ゴール世界の自分ならこうする、などと話しかけるようにしましょう。
これが、アファメーションです。
アファメーションとは、ゴール側の臨場感を高め、ゴール側をコンフォートゾーンにする作業です。
特に、失敗した時のセルフトークは大切です。簡単なワードを持っておきましょう。
「自分らしくない、だったらどうする?」というようなもので良いと思います。臨場感はセルフトークの回数で決まります。
パスワードなどの文言にしたり、携帯の待ち受け画面にしたり、毎日目にするなど、ゴール世界のセルフトークで、いっぱいにしましょう。
そうすることで、自分のアイデンティティが更新されます。
セルフトークにより、自分の定義は更新されていきますから、セルフイメージをゴールに合わせて、更新していきましょう。
終わりに
ゴール設定するのに、過去の実績やリソースに、こだわる必要がないことがお分かりいただけたと思います。
ゴール達成に一番必要なのは、あなたの未来のゴールを達成できるという謎の自信、エフィカシーです。
ゴール設定により、コンフォートゾーンがずれて、スコトーマが外れ、RASが発火し、あなたに入ってくる情報が変わります。
脳が無意識にゴールへの道筋、プロセスを導き出すでしょう。
あえて、無意識に任せてください。
want toから、現状の外にゴール設定がされたとき、ゴール達成へのプロセスを、意識的に考える必要はありません。
ゴールへの臨場感が高まることで、ゴール側のコンフォートゾーンに向かって、ホメオスタシスのフィードバックがかかり、モチベーションの高まりを客観的に感じるでしょう。
これが、スティーブ・ジョブズが言うconnecting the dotsの心象風景であり、マインドのカラクリを使ったゴール達成の方法です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
