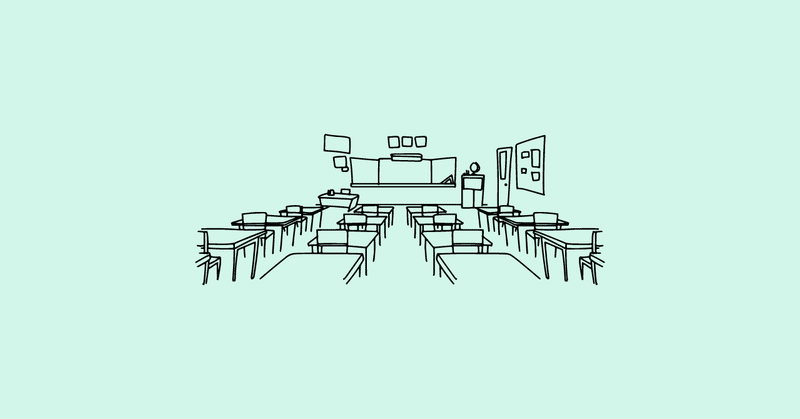
女王様の教室 #シロクマ文芸部
登場人物
K中
遠藤結奈 中3
一条杏里 中3
斉藤くん 中3 元野球部主将
N校文芸部
部長・・・・一条朱里 高2
冬の色は移りにけりないたずらに――
「いやそれ、違うからね」
鋭く、ぽつりと耳に言葉。
「〝花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに〟」
若干の音程をつけてさらりと杏里が言う。
「さすが。百人一首の女王」
少し茶化すと、杏里は嫌そうに顔をしかめた。
「やめて。女王はうちの姉」
杏里が姉に対して強いコンプレックスを抱いているのは、友達になってからずっと感じていた。杏里のお姉さんは、地区大会で準優勝したこともある本物の「百人一首の女王」だ。
放課後の教室には、弱い西日が差し込んでいる。冬なのにまるで春のような日差し。今年は夏が長すぎた、いつまでも暑い、冬が来ないと大人たちがぐずぐず言っていたけれど、部活が終わっている受験生にとってはすでに季節は移り替わっている。少なくとも私、遠藤結奈にとっては冬だ。人生の冬だ。
教室には、塾に行く前に自習している子が何人か残っているくらいで、ほとんどの子は重い鞄を抱えてすっとばすように出て行った。
自習組でも、必死に机に齧りついている子と、なんとなくぼんやりとしたりおしゃべりしている組に別れ、私と杏里は教室の隅でぼそぼそと話をしていた。12月に入っておしゃべりなんてしている場合じゃないのはわかっているけれど、どうせこの後、塾で追い込み特訓なのだ。たまには息抜きだってしたい。
「おうぃ、百人一首——じゃなくて一条」
急に隣で声がした。机の脇に立つ声の主を見上げる。野球部元主将、斉藤くん。結構いい線まで行ったのに、春の大会で敗退して関東大会に行けず、野球部を引退、受験生になった。髪を伸ばしてなんちゃってツーブロック。イケメン感が増している。私はちょっと、いやだいぶ、斉藤くんのことが気になっている――のだが、この斉藤くんが、目の前の杏里のことが好きなことは、とっくにお見通しだった。どうやらN高を受けるつもりらしい。杏里と同じ高校に行きたいのだろう。
杏里は杏里で、N高校より上のランクのF高でも判定Aだというのに、どういうわけかN高に固執していた。それには、お姉さんへの複雑な気持ちが関係しているんじゃないかと、私は思っている。
杏里はアイドルみたいに可愛いし、頭もいい。今だってさらっと百人一首を諳んじてしまう。とても太刀打ちできないことくらい、わかっていた。よくある話だ。漫画のように「華やかなタイプのあの子じゃなくて目立たないきみをずっと見てたよ」というわけはいかない。現実は厳しい。
小学校時代に「百人一首」がすべてそらで言えるからと言う理由でついた子供じみた渾名が大嫌いな杏里は、「ああン?」といった風情で下から舐めるように斉藤くんにガンを飛ばした。でも昭和のヤンキーを思わせるそういうところがまたキュートなんだよね、わかるわかる。昭和のヤンキーなんて知らんけど。ただのイメージだけど。
「お前さ、古典得意だろ?ちょっとこの問題教えてよ」
「は?なんであたしが。は?なんでお前呼ばわり」
けんもほろろに返す杏里に、斉藤くんはめげない。やっぱ運動部で主将までする子は厳しさへの耐性が半端ない。M体質なんじゃないだろうかと思う。だいたい、杏里を「百人一首」と呼ぶ時点で、もうオレは君が好き、感が溢れまくっている。どうしてそれで気を引けると思うのか。男子ってほんと子供だ。でも私は、斉藤くんのそんなところが好きだけどね。私もMか。
「俺、どうしても古文漢文がダメなんだよな」
「あんたのことなんて知らん」
「なあ。そう言わずに。助けると思って」
なんかちょっとうざくなってきたなと思いながら問答を眺めていたら、急に斉藤くんが私を見た。
「そんじゃ遠藤でもいいや」
「でもって何。ひどくない?」
「だって遠藤、国語得意だろ。現文とか寝てても答えるし」
今さっきの私と杏里の会話を聞いていたらとてもそんなことは言えないだろうに、と思う。「花の色は」を「冬の色は」だと思っていたくらいなのに。私は百人一首はさっぱりだ。でも現代文だったらそれなりに得意科目ではあった。そして確かに現国だけは、授業中たまに寝ていても、指名されたら答えは出せた。なんだ、意外と斉藤くん、私のこと見てたんだ――。
「私、古典はダメなんだよ」
「だよな!俺もほんと、これで点数がた落ちなんだよ」
斉藤くんは、意外と真面目に困っているらしい。真面目に困っている、というのは変だけれど、真剣になんとかしたい気持ちで声をかけて来たらしいことは分かった。
「杏里、教えてあげなよ」
杏里は無視だ。いつのまにか参考書を出して問題を解いている。
「ていうか、私も教えてほしい。なんなら古典だけと言わず、数学と物理も」
そう言うと、杏里はようやく振り返って、私をじっと見た。でっかい目だな、と思う。引き込まれそうな、猫みたいな目。
そして、静かに言った。お告げのように。
「N高に行って、文芸部に入るって言うなら」
文芸部!?と、斉藤くんが素っ頓狂な声を上げた。さっきからうるさいと思っていたのだろう、周辺の自習組がじろりとにらんだ。
「いや俺は、野球部——」
言いかけた斉藤くんを、杏里は視線でねじ伏せた。そういえば、N高は野球が強いのだった。なるほど。彼がN高校に行きたいのは、あながち、杏里についていきたいからというだけの理由でもないらしい。
「兼部できるから」
杏里はしれっと言う。私は杏里のその口調に、嘘をかぎ取った。長年のつきあいだ。そのくらいはわかる。
「きみたちは文芸部。わかったね?N高で、文芸部だよ」
杏里はまるで女王様のようにそう言った。
私と斉藤くんは、思わず生唾を飲み込んで顔を見合わせた。可愛い女子が凄みを聞かせると、なんだってこんなに迫力が出るんだろう。
いやあの、俺は野球ひとすじで全然文芸部とかだいたいなんで受験前から部活きまってるんだよそれにおまえが部活決めるとかおかしいだろ――
私は抗議する斉藤くんのブレザーの袖をちょっとだけ引っ張った。
杏里の機嫌を損ねていい結果になったためしはない。
園児の頃から彼女とつきあっている私には、わかる。
「まずは斉藤。お前とか、今後一切、言うなよ。それから結奈。親友だからって、情けはかけん」
杏里はスイッチが入った顔でそう言った。二人はまた、目を見合わせる。そしてそうしながら、こうやって斉藤くんと目配せするなんて超ラッキー、なんて思っていた。やばい。ずっとふたりで杏里に叱られていたい。これはなんだ。Mか。ふたりともドMか。
杏里は、そうと決まったらまずはこの掛詞だらけのすげぇ歌からだ、とキラリと目を光らせ、ニヤリと笑う。
ドSな女王様のお言葉に私たちは、受験生にはあるまじき変な喜びを感じつつ、ただただ無暗に笑いながら頷いていた。
花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
久しぶりに文芸部シリーズ。今回はそのスピンオフです。
舞台は中学校。文芸部シリーズの登場人物の妹さんが出てくる模様。
これまでのお話はこちらから。
全国の受験生諸君、頑張れ~!
小牧さん、今回もよろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
