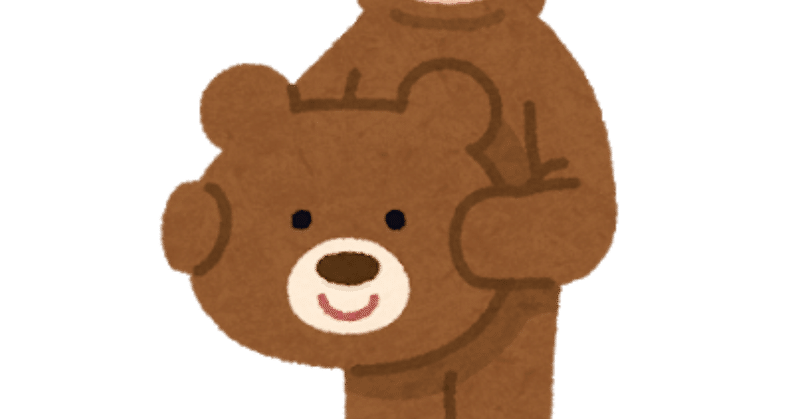
商学部卒、来週ディズニーランドに行くので、本気出すことにした
来週、ディズニーランドへ行くことになった。
私は基本、ディズニーに興味がない人間だ。でも、3-4年に一度くらいは誘われて行き、それなりに楽しんで帰ってくる。
自分じゃ行かない場所に連れてってくれる人は貴重だ。自分の世界広げてくれるからね。
さて、今回もそんなノリで行くのだが、ただ行くだけではつまらないなぁと思っていたところ、ふと、「これ、ディズニーの経営やホスピタリティ学ぶチャンスじゃね?」と思った。
そうだ。そうなんだ。そう決めた。(頑固)
今日時点では、ポップコーンや着ぐるみ(着ぐるみと呼ばないで)の原価とか、空間の作り方とか気になっているけど、どんな点に注目すれば『ディズニーらしさ』を体感できるのだろうか。

よし、事前にありったけのディズニー経営について学んでから、フィールドワークとして行こう!
▼やり方
・ディズニーの経営やマインドに関する本3冊を通して、情報を叩き込む
・サイトやIRを読み込む
・そして実際に行って肌で感じる!!それが全て!!!
本は早速Amazonで1冊届いたので昨日から読んでいるのだけど、めちゃ面白い。行き帰りの電車で本の虫になっている。
現時点の感想は、伝統継承&文化の徹底ってすごい力発揮するんだなということ。逆にマニュアルであの世界観はできっこない。
もう少し掘り下げると、『積極的にフレンドリー』という伝統があり、『細部までこだわる』『歩み寄り・語りかける』文化がある。
それを示す例として、こんなエピソードが挙げられていた。
ディズニーでは全員が名札をつけることを必須としているが、本部からの視察団がそれを忘れてパーク内を歩いていた。
するとパークキャストが近づいてきて、『名札をつけていませんよ』と注意した。それを言われて、本部の人間はすぐに名札をつけたと同時に、嬉しくなったという。
そのキャストは『細部までこだわる』からこそ、名札がついていないことに気がついたし、『歩み寄り・語りかける』を徹底したからこそ、本部の人間にしっかりと名札のことを注意できたのだ。
これは結構重要だ。
少なくとも、『細部までこだわらない』→『細部までこだわるけど言わない』→『細部までこだわるし、語りかける』のように三つ先の意識がないとできないことだし、ただ言うだけとか怒るとかではなく、『歩み寄り・語りかける』の形で相手に届けたのである。
ディズニーは、『従業員』を『キャスト』と呼ぶなど、言葉の選び方を徹底しているが、文中では、経営陣も含めて『キャスト』であると語られていた。顧客満足度を最大化する目的、いや、文化の中では誰もがキャストであり、ゲストを楽しませるために全力を尽くすのである。
この章の前には、『パークには清掃スタッフが4万5千人いる』という言葉も出てくる。冷静に考えて多くないだろうか。
この数は当時のフロリダの話だが、日本に置き換えてみよう。
公式サイトを見ると、
従業員数
社員 3,411名
準社員 19,697名
(2019年4月1日現在)
とある。
合計で、23,108人だ。
すると、つまり、日本のディズニーの清掃スタッフは23,108人ということになる。
なるのだ。
カバー取って見えた英語タイトルが『Inside The magic Kingdom』なのが良い。フロリダのディズニーにあるThe magic Kingdomのエリアを指している。『7つの法則』って書いた方が日本人ウケいい&ビジネス書っぽくなるのだろうけど、ちょっともったいないなぁと思った。

こんな感じでディズニー本番に向けて着々と準備している。
なんかもう全然テキトーでもいいので、本気出すぞ!(どっち)
考えてたら緊張してきた!!!
しかも午前予定あるから、15時-22時の7時間しか居れない!
5人くらいで行くからあんまり勝手なことできない!
最初の1時間はシングルライダーしてみようかな!
あ、一緒に行く人が読んでたら。
多分頭の中で「この着ぐるみ何回着まわすんだろう」とか色々考えてるけど、口には出さないので安心してね()
何にも得られなかったらウケるし、キャラクター、乗り物、ショーなど個人的な感情で「これが見たい!」というのはないけど、とりあえず当日7時間の密度を上げて楽しむために、この一週間は本気を出そうと思っているところであります。
おわり
生きる。 解釈が交わる世界で、手を取り合いましょう。
